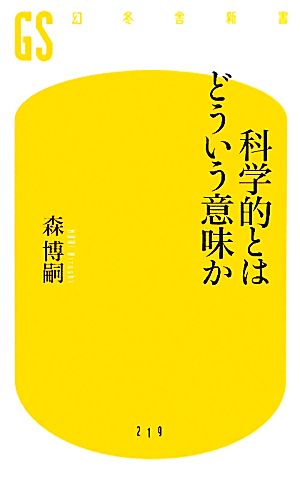科学的とはどういう意味か の商品レビュー
"科学的"と言う言葉をキーに、著者の持論が展開されている。文系・理系の分類など、世間的に理系と言われる側から見た意見には、肯くばかり。
Posted by
『科学とは、民主的にみんなで確認をするシステム、つまり、他者と共有できることが基本となる』 タイトルにあるように、『科学的』とは何を意味するのかということを、色眼鏡をかけずにかつわかりやすく語りかけてくれる。
Posted by
「数学が得意であること」と「数字で量を見積もれること」と「科学的であること」というのは少し違うことであるような気もしてわたしにはちょっと理解しにくい本でした。数学のもう一つの面である「論理整合性」をあまり考えていなくて、「文系」だから「数学が苦手」という話で進めてしまったのはちょ...
「数学が得意であること」と「数字で量を見積もれること」と「科学的であること」というのは少し違うことであるような気もしてわたしにはちょっと理解しにくい本でした。数学のもう一つの面である「論理整合性」をあまり考えていなくて、「文系」だから「数学が苦手」という話で進めてしまったのはちょっともやもやします。理系の私からすると最も「文系」的な分野の一つである「法学」こそが数学との親和性が高いと感じているのでちょっと残念な本でした。
Posted by
本のタイトルで損しているな感じました。この本で語られていることはタイトルよりも深いです。(著者がタイトルに悩んだことを書いていましたが) 以下の内容が強く印象に残りました。 ⑴科目で学ぶことは「データ(情報)」、「メソッド(方法)」の2種類。数学や物理は主にメソッド中心。 ⑵...
本のタイトルで損しているな感じました。この本で語られていることはタイトルよりも深いです。(著者がタイトルに悩んだことを書いていましたが) 以下の内容が強く印象に残りました。 ⑴科目で学ぶことは「データ(情報)」、「メソッド(方法)」の2種類。数学や物理は主にメソッド中心。 ⑵科学を敬遠するのは、自分で考えること、感じることが面倒でしたくないからである。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
”科学の存在理由、科学の目標とは、人間の幸せである。” ということを前提に、”科学的”といっているのは、どういう意味でいっているのかという、見方について、書かれた本.”理系”、”文系”にこだわっている人は一度読むとよいかもしれない.
Posted by
前半はかなり納得。 「科学」という言葉にほとんどの人が拒否反応をしていると思う。 ただ普通になぜ?どうして?を気にして、理解するだけなのに。と思ってしまうのは、私が理系だからなのでしようか。 後半に関しては、超能力や占いを完全否定しているように感じ、科学が一番大事であり、超能力や...
前半はかなり納得。 「科学」という言葉にほとんどの人が拒否反応をしていると思う。 ただ普通になぜ?どうして?を気にして、理解するだけなのに。と思ってしまうのは、私が理系だからなのでしようか。 後半に関しては、超能力や占いを完全否定しているように感じ、科学が一番大事であり、超能力やういの基である「精神」や「心理」は不要というふうに受けとりました。(一応、両方大事とは記載されてますが、個人的に受けとりました) 科学が社会や経済に間違った使われ方をしているのに似て、「精神」や「心理」といった分野を異なった使い方をしているだけでは。(使い方が間違っているかどうかはおいといて)
Posted by
これだけ科学技術が発展した現代において、科学離れ(科学的無知、無関心)が顕著になっている。 特に文系と称される人々は、数学が苦手だからといった些細なことで自ら考えることを放棄している。 科学とは、自ら理性的に考えることであり、また現代に生きるには必要不可欠なものである。 是非と...
これだけ科学技術が発展した現代において、科学離れ(科学的無知、無関心)が顕著になっている。 特に文系と称される人々は、数学が苦手だからといった些細なことで自ら考えることを放棄している。 科学とは、自ら理性的に考えることであり、また現代に生きるには必要不可欠なものである。 是非とも自称文系の人々にこの本を読んでもらいたい。 僕自身文系学部に属しているが、自分はより理系的な人間だと自負しているし、数学等を切り捨てて文系に進んだ人を哀れに思ったりもする。 そんな視点からこの本を読ませていだだくと、すごく納得できました。 しかし、こういうタイトルの本を手に取らないのもまた文系人間の特徴だとも思う。 森さんは理系、文系と二つに分類すること自体に否定的であるようですがねw 現代日本はお上(特にマスコミ)の言うがままに生きる人が多いように思う。 常に正しく必要なことだけが報道されていると思い込み、自ら考えることを放棄している。 その方が楽だし、他人との協調性も取れるのだろうけど、果たしてそれが正しいことなのだろうか? そもそも何が正しいなんていう普遍的な心理は存在しない、ならば自分が思うように、ある意味自己中心的に生きることが人生において大事なのでは無いだろうか。 もちろん社会で生きていく上で自己中心的であってはまずいが、だからと言ってイエスマンよろしく何でもかんでも鵜呑みにして従うのは間違っている。 我思う故に我ありとは良く言ったもので、考えることこそが人生だと思う。 理性的に考えることを放棄した時点で、人生をやめたに等しいといっても過言ではない。 思考しない人生はそういうのが得意な機械に任せておけばいい。僕は人間らしく生きる。
Posted by
科学を理解していてかつ表現力も傑出している こういう本が増えれば擬似科学も減っていくのではないかと思う
Posted by
科学的であるとはどういうことか(第三者によって再現できる、数字で測定できる、など)、科学的な思考をすると(しなかったときと比べて)どのようなメリットがあるのか、科学的な思考を生活の中でどのように役立てればいいのか、などなど。 それなりに面白かったです。 想定読者は科学にアレルギの...
科学的であるとはどういうことか(第三者によって再現できる、数字で測定できる、など)、科学的な思考をすると(しなかったときと比べて)どのようなメリットがあるのか、科学的な思考を生活の中でどのように役立てればいいのか、などなど。 それなりに面白かったです。 想定読者は科学にアレルギのある文系なんだろうけど、そういうひとはそもそもこの本を読まないんじゃないかという噂。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「科学を無闇矢鱈に否定して目を背けるのは、あなたにとって不利益ですよ」というのが一番言いたいことだそうだ。すごく良く解る。 でもこの本では、いわゆる「文系」が「理系」科目に対して反発することが多い、という内容が扱われていたけれど、逆も然りだよね。理系は文系科目に対してそう苦手意識を持っている訳ではない、と書いてあったけれど、少なくともわたしの身の回りではそうではないな。 理系というか、研究もそんなに力を入れてやる訳でもない薬系だからそう感じるのかも?必要ないから英語はやらない、本も読まない、歴史なんて興味ない、というひとがすごーく多いように感じるんだよなあ。それってとても勿体ない。 まあ結論を言うと、自分にこれは必要ないとか、こんなものは信じられないって妄信的に切り捨ててしまうのではなく、自分が生きて行く上で何が必要になるのか、何がプラスになるのかを冷静に、自分だけの物差しで計るべきっていう、ごく単純なことになってしまうのだろうけど。
Posted by