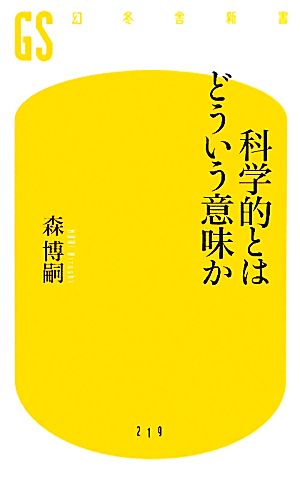科学的とはどういう意味か の商品レビュー
物事は単純化しないと処理しきれないからそんなに悪い事でもないとは思うが、その度が過ぎると事実と異なる思い込みや偏見になるわけで、ある程度は論理的や数字で考える事の必要性を説いている。言葉は使いようである。 但し、定義もよくわからないし文系とか理系とかはあまり意味ある分類だとは思わ...
物事は単純化しないと処理しきれないからそんなに悪い事でもないとは思うが、その度が過ぎると事実と異なる思い込みや偏見になるわけで、ある程度は論理的や数字で考える事の必要性を説いている。言葉は使いようである。 但し、定義もよくわからないし文系とか理系とかはあまり意味ある分類だとは思わない。著者はこの辺に非科学的な比較を持ち込み、言葉による単純化をしている気はする。なら各試験科目の偏差値という数字で比較した方がスッキリするだろう。東大の文系とFランの理系ではどちらが論理的に数字で考えるかは明らかである。 著者は原発賛成派のようであり、本書も311後の日本を意識して書かれているが、結構批判されたようだ。人間は感情の生き物である。そこを見誤り、科学・論理に突き進むと結局自分の身が守れなくなるというのもまた事実ではある。 「科学とは方法であり、その方法は他者によって再現できる事が条件である」は311後よりも再現できないコピペ論文で話題になった昨今こそ響くフレーズではある。
Posted by
理系か文系かと聞かれれば、私の場合、理系ということになるのでしょうか。よく妻と話していても、数字にこだわりすぎるところがあるようで、はっきり言っていやがられます。しかし、世の中、数字で考えた方が分かりやすいことの方が多いように思うのですが。 この本の著者は、もともと科学的に...
理系か文系かと聞かれれば、私の場合、理系ということになるのでしょうか。よく妻と話していても、数字にこだわりすぎるところがあるようで、はっきり言っていやがられます。しかし、世の中、数字で考えた方が分かりやすいことの方が多いように思うのですが。 この本の著者は、もともと科学的に考えることの大切さ、あるいは非科学的に考えることの危うさについて、機会あるごとに主張してきたようです。この本を書こうとしているとき、あの大震災が起こり、原発事故が日々報道されるのを見て、さらにその思いを強くしたのではないでしょうか。 さて、この本は大きく4つの章に分かれています。第1章「何故、科学から逃げようとするのか」では、現代人が、科学的なものの見方を避けようとしていることを指摘しています。それどころか、科学的に考えようとすると、具体的には数字で表現しようとすると、数字じゃ分からん、数字なんてものは当てにならんとまで言われる始末です。 第2章、第3章では、「科学的というのはどういう方法か」「科学的であるにはどうすれば良いのか」が、分かりやすい例を交えながら紹介されます。p.121では、科学的に答えてみよう、「鳥はどうして飛ぶことができるのか?」という話題が展開します。確かに、こんな身近なことも私はよく知らないんだなあと反省させられました。 p.89のある技術者の返答も考えさせられました。「AとBはだいたい比例していると考えて良いか?」という質問に対して、技術者らしい実直な回答をします。なるほど、こういう姿勢が大切なのだなと思いました。 第4章では、「科学とともにあるという認識の大切さ」になります。ここでは、子供に対して、大人がどう接するべきかが書かれています。その中で私が引っかかったのは、p.184「僕たちが科学少年だった時代のように、これからの子供が科学に魅了されることは、おそくら無理だろう。」という部分です。なぜかというのが、どこにも詳しく書いてないように思うのですが、本当だったらさびしいですね。私の息子にも、いろいろなことに好奇心を持ってもらいたいです。
Posted by
同じ理系にいた人間として、共感できる部分がとても多いなと感じる作家です。 今回も、自分ではうまく言葉にできないことをうまく表現してくれていると感じる部分もあって、読後感はよい。 ただ、この長さが必要かというとそうでもない。 もっと、短く端的にできる気がいたしました。
Posted by
本書の目的については著者が明確に記載しているので理解できたが、ではその目的を果たしているのかどうか、ということには少し疑問。非科学的なものを鵜呑みにしてしまうことの危うさは充分理解できるけれど、では科学的とは、という命題に対しては答えきれていないのではないか、と感じた。勿論、書い...
本書の目的については著者が明確に記載しているので理解できたが、ではその目的を果たしているのかどうか、ということには少し疑問。非科学的なものを鵜呑みにしてしまうことの危うさは充分理解できるけれど、では科学的とは、という命題に対しては答えきれていないのではないか、と感じた。勿論、書いてあることは正しいと思うのだが、人が何故非科学的なものに惹かれていくのかということへの考察がもう少し必要なのではないかと思う。例えば、あの某宗教団体へ何故理系人間が多く参画してしまったのか、等々。この辺への言及があれば説得力があがると思うのだが。
Posted by
学会で,理論と実践や研究のあり方が議論となり,その直後にお勧めがあって手に取った。 「誰かが考えたことを大勢で吟味し,そしてその効用を共有する仕組みが,科学の基本である。(p.91)」 「まず,科学というのは『方法』である。そして,その方法とは,『他者によって再現できる』ことを条...
学会で,理論と実践や研究のあり方が議論となり,その直後にお勧めがあって手に取った。 「誰かが考えたことを大勢で吟味し,そしてその効用を共有する仕組みが,科学の基本である。(p.91)」 「まず,科学というのは『方法』である。そして,その方法とは,『他者によって再現できる』ことを条件として,組み上げていくシステムのことだ。他者に再現してもらうためには,数を用いた精確なコミュニケーションが重要となる。また,再現の一つの方法として実験がある。ただ,数や実験があるから科学というわけではない。 個人ではなく,みんなで築き上げていく,その方法ことが科学そのものといって良い。(p.107)」 人を対象として研究する場合(教育,言語習得),難しいと思いつつ,この基本については忘れてはならないな,と。
Posted by
目次 第1章 何故、科学から逃げようとするのか(いつから避けるようになったのか 向いていないと思い込む ほか) 第2章 科学的というのはどういう方法か(科学と非科学 非科学的な習慣 ほか) 第3章 科学的であるにはどうすれば良いのか(「割り切り」という単純化 科学は常に安全を求め...
目次 第1章 何故、科学から逃げようとするのか(いつから避けるようになったのか 向いていないと思い込む ほか) 第2章 科学的というのはどういう方法か(科学と非科学 非科学的な習慣 ほか) 第3章 科学的であるにはどうすれば良いのか(「割り切り」という単純化 科学は常に安全を求める ほか) 第4章 科学とともにあるという認識の大切さ(ごく普通に接すれば良い 数字にもう少し目を留めてみよう ほか) 本の内容 科学—誰もが知る言葉だが、それが何かを明確に答えられる人は少ない。しばしば「自然の猛威の前で人間は無力だ」という。これは油断への訓誡としては正しい。しかし自然の猛威から生命を守ることは可能だし、それができるのは科学や技術しかない。また「発展しすぎた科学が環境を破壊し、人間は真の幸せを見失った」ともいう。だが環境破壊の原因は科学でなく経済である。俗説や占い、オカルトなど非科学が横行し、理数離れが進む中、もはや科学は好き嫌いでは語れない。個人レベルの「身を守る力」としての科学的な知識や考え方と何か—。
Posted by
前に本屋で見かけて気になっていたものの、そのときは買わず。最近になって購入。 工学博士たる著者が『科学的』とはどういう状態を表すのか、科学的に考える思考力は発想力がないと、どのような問題が発生するのか、といったことを書いたもの。 僕自身も、工学修士を持っているので、科学的とい...
前に本屋で見かけて気になっていたものの、そのときは買わず。最近になって購入。 工学博士たる著者が『科学的』とはどういう状態を表すのか、科学的に考える思考力は発想力がないと、どのような問題が発生するのか、といったことを書いたもの。 僕自身も、工学修士を持っているので、科学的という考え方はそれなりに持っていると思っている。『科学的』ってのは一言で言うと『再現性があるかどうか』ということにつきる。 もう少し言うと、同じ条件下で誰が行っても同じ結果が得られるかどうか、というところがポイントで、それを満たさない限り科学的ではない、という判断になると考えている。 おおよそ、著者とは同じような考えだったな、と思う。まあ当たり前の話と言えばそうだ。理系学部で勉強をした人間にしてみれば、知らなきゃおかしいレベルだよなぁ、と思う。 そういう意味で、本書ではそれほど目新しい話があったわけじゃない。だけど改めて自分の日々の考えを見直すのには、とても有用だったと思う。 そもそも、文系と理系、と区別すること自体が、(著者も近しいことを書いているが)ナンセンスだと僕は思っている。人は誰も文系的な要素と理系的な要素を持っていて、どちらかと言うと強いほうがある「かもしれない」けど、おおよそは変わらなくて、どっちの勉強をしたか、どっちに興味を持ったか、というだけでしかないと思ってんだよね。 だから世の中の文系理系議論には、僕は興味ないし、どーでもいいじゃん、と思う。そんな所で自分自身を貶めなくてもいいよね、とも思うし。苦手、と思った時点で苦手になるからねぇ。 秀逸だったのは、最初の方に書かれていた以下の文章。 「文系には、数学や物理から逃避するという特徴(あるいは傾向)があるけれど、理系にはそういった特徴は顕著ではない。理系の人間は、特に国語や社会から逃避しているわけではない。ここを、文系の多くはたぶん誤解しているだろう」 これはそうだと思う。というか、サンプルが殆ど無いのであくまで僕自身のことで考えざるを得ないが、僕はまさにそうだった。正確には、国語も社会も得意だった。地理や漢字みたいに「覚えるしかない」ものは苦手だったけど、読解問題であるとか、個人的に好きだった歴史などは全然得意だった。そんなもんである。 それを文系(と自分を定義している)の人たちは、「お前らは文系学科が苦手、俺達は理系学科が苦手、おあいこでしょ」と平気でおっしゃいますが、じゃああなた方は理系と言われている人たちが理解している物理程度に古文を理解しているのでしょうかね、と質問もしたくなる。 おっと、話がそれてしまった。 ともあれ、本書は『文系と理系』と分けることの無意味さ、科学的に考えることの重要性、科学的に考える方法論、といったことがわかりやすく親切に書かれている。科学が苦手だ、数字は難しい、なんて考えている人は、ぜひ手にとって読んでみるべきだと思う。 と書いたが、そういう人はまず間違いなくタイトルで敬遠するんだよな。。もったいない。。
Posted by
「文系」を自認する人に。数字や論理に基づく説明を敬遠し,結論だけを求めることの不利を説く。こんこんと。さすが小説家だけあってさらさら読める。独特の外来語表記にはちょっと違和感も。
Posted by
すごくしっくりときた。日常的に感じる「なんか違うなー」が形になったような感じ。 私自身、科学的な感覚の一番肝要な部分は、大学でそれなりの訓練を受けて身につけたという経緯があるから、これを読んで、その感覚がない人がどこまでついてこられるかは若干疑問。
Posted by
【動機】森博嗣なので。 【内容】「観測された数字を自分で解釈すること」や「詩的・包括的な言葉で思考停止せずに原理を問いつづけること」で落ち着いて判断することの重要性を説いている。 【感想】ちゃんと考えることは、めんどくささと向き合うつらさを負う一方で、好奇心をじゃましないという前...
【動機】森博嗣なので。 【内容】「観測された数字を自分で解釈すること」や「詩的・包括的な言葉で思考停止せずに原理を問いつづけること」で落ち着いて判断することの重要性を説いている。 【感想】ちゃんと考えることは、めんどくささと向き合うつらさを負う一方で、好奇心をじゃましないという前向きな面も見出せることに気づいた。
Posted by