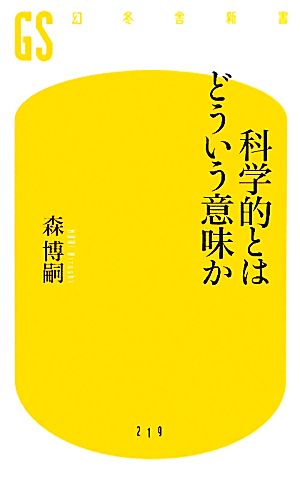科学的とはどういう意味か の商品レビュー
近頃はネットで色々と見るものが増えたけど、 その大半は誰かの「感想」だったりする。 感想の洪水に飲み込まれて無難な腺で落ち着いたり、 不特定多数のみんなと同じであることに無意識に安心していたり。 本当、気をつけなきゃいけないな。 あと、「数値をイメージする」ってのは確かにそのと...
近頃はネットで色々と見るものが増えたけど、 その大半は誰かの「感想」だったりする。 感想の洪水に飲み込まれて無難な腺で落ち着いたり、 不特定多数のみんなと同じであることに無意識に安心していたり。 本当、気をつけなきゃいけないな。 あと、「数値をイメージする」ってのは確かにそのとおりで。 桁が多くなるとすぐ諦めてしまうのは自覚があっただけに胸が痛い。 少しずつ気をつけていきたいと思います。
Posted by
科学とは第三者による再現性のあるものであり、そうなるようにするたための態度が科学的な態度という。著者の危惧するように今の日本人は過度にそして意識的に非科学的な態度をとっているように思えてならない。
Posted by
2011/7/9読了。 科学的ということをもっと深い部分(哲学の範疇に属するような)で考察する内容を期待していただけに、"文系"(文中では理系科目を毛嫌いする人の意)の人に対して理系的な物の見方を説明する議論の中に新鮮味は感じられなかった。 しかし、理系の人...
2011/7/9読了。 科学的ということをもっと深い部分(哲学の範疇に属するような)で考察する内容を期待していただけに、"文系"(文中では理系科目を毛嫌いする人の意)の人に対して理系的な物の見方を説明する議論の中に新鮮味は感じられなかった。 しかし、理系の人間であれば大概の人が感じている(であろう)ことを、イメージしやすい例えと言葉で伝えられるということから、著者が文系に近い理系であるという言葉は的を得ているのであろうと感じた。
Posted by
数学が苦手でも、物理が苦手でも、ただ自覚的であれば問題は無い。 「言葉」のイメージだけでわかったような気になってしまう「文系」の弱点を思い切り指摘されて、痛い痛い。科学とは「方法」であるという説明がとても腑に落ちた。
Posted by
いつもの森先生の話。文系、理系だとか。 震災、というより、それに対する在り方についての言及を含んでいるのが意外でした。時事問題を減らしてより抽象的・一般的な記述にするかと想像していたため。 ある質問に関する、技術者の誠実な回答に関するエピソードが印象的。性急に答えを求めてしまうこ...
いつもの森先生の話。文系、理系だとか。 震災、というより、それに対する在り方についての言及を含んでいるのが意外でした。時事問題を減らしてより抽象的・一般的な記述にするかと想像していたため。 ある質問に関する、技術者の誠実な回答に関するエピソードが印象的。性急に答えを求めてしまうことへの戒めとして、心に刻もう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
科学とは、普遍性を維持するための仕組みである。そのため、誰にでも再現ができ、誰もが観察できるものである。 科学を通じて、一般的に理系と呼ばれる人と、文系と呼ばれる人の事象に対する反応について述べている。 また、東日本大震災が生じたときの人々の反応から、人々の科学に対しての無知を憂いている、ように書いている。 http://unreconstructed.dtiblog.com/blog-entry-18.html
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
要するにもっと数字を意識せんといかんってことと、自分で考えろってことを言っとります。主観と感情先行の報道は改めて、客観的な数値を示せとも。震災中に書かれたみたいだからよりイメージしやすい。小説家だけあって比較的読みやすい。ノベライズの一角でよく見るから名前は知ってたけど小説は読んだことない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
久々に森先生の本を読んで、懐かしかった。 現代社会の複雑さに目をそむけて、楽をするために状況を鵜呑みにすることの危険さ。森先生は昔からそういうことを書かれていたなあと思い出しました。 津波のエピソードにものすごく納得しました。 波というとサーフィンとか、すぐに引いていくような印象だけど、超高潮になると、引かないイメージがする。 言葉・名詞によって思考が制限されてしまうんですよね。 毎日少しでも、自分の頭で考える時間を持ちたいなと思いました。
Posted by
森先生、新書をもっと書いていただきたいなと思ったけれど、そう思うことがもう考えるのを面倒がっているのだろうな。とりあえず、どうして携帯電話で通話ができるのか、自分で調べて理解したいと思います。
Posted by