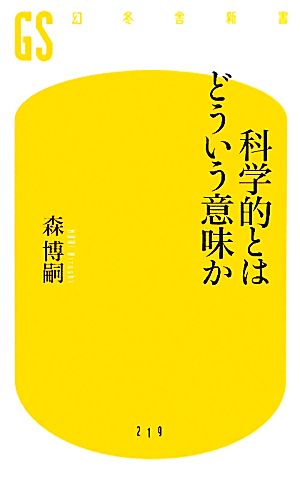科学的とはどういう意味か の商品レビュー
***** 題名の通りの内容。 人生の中で一度でも「科学とは何か」を考える機会を持てたことをとても嬉しく思った。先生に感謝。 ***** 数字に向き合うスタンスを考える上でもとても示唆に富んでいる。 人は難しいことはなるべく考えたくない生き物である。 ファスト&スローで言っていた...
***** 題名の通りの内容。 人生の中で一度でも「科学とは何か」を考える機会を持てたことをとても嬉しく思った。先生に感謝。 ***** 数字に向き合うスタンスを考える上でもとても示唆に富んでいる。 人は難しいことはなるべく考えたくない生き物である。 ファスト&スローで言っていたシステム2(合理的な思考)は怠惰で怠け癖があるので考えることは避けるし、システム1(直感的な思考)は手元にある情報から最も確からしいものをばさっとつかむ。いずれにせよ、相当に意識しない限りは目の前のことに対して熟考するような「めんどくさいこと」はしない。 *****
Posted by
英語を調べると文系は Humanities、理系は Science なのか。学問分野としてはもちろん別だが、それを学ぶ人にとって二律背反ではないはず。この本での描き方だと、ともすれば「理系はエリート、文系はバカ」みたいなステレオタイプな思い込みを増長させやしないか。日本人はただ...
英語を調べると文系は Humanities、理系は Science なのか。学問分野としてはもちろん別だが、それを学ぶ人にとって二律背反ではないはず。この本での描き方だと、ともすれば「理系はエリート、文系はバカ」みたいなステレオタイプな思い込みを増長させやしないか。日本人はただでさえカテゴライズ化が大好きだ。昭和生まれ平成生まれ・血液型・長男次男・関東関西…。年代・地域・個人特性についてどこの国でも多かれ少なかれそんな遊び(?)はあるだろうが、少なくとも自分は文系だ理系だと主張しあうのは日本だけじゃないのかな。 (続きはブログで)http://syousanokioku.at.webry.info/201212/article_17.html
Posted by
科学や数学とか、もちろん他のものにたいしても安直な思考停止はよくないなと、思う。 そして協調することがよいとはいけませんよ、といつものことが書かれている。 頭のなかのことをそのまま文字にしたような本。わかりやすくてよかった。 科学的に考えようとは言わないけれど、科学的に考え...
科学や数学とか、もちろん他のものにたいしても安直な思考停止はよくないなと、思う。 そして協調することがよいとはいけませんよ、といつものことが書かれている。 頭のなかのことをそのまま文字にしたような本。わかりやすくてよかった。 科学的に考えようとは言わないけれど、科学的に考えないと損をする、だってさ。
Posted by
選挙前のこのタイミングで読んだのが最適だったような気がする書籍。 工学博士にして小説家、エッセイストである森博嗣さんが、東日本大震災の直後に、「科学的に思考しなければ損をする」という視点で、科学から自ら離れてしまっている一般人のために記した一冊です。 非常に分かりやすく書かれて...
選挙前のこのタイミングで読んだのが最適だったような気がする書籍。 工学博士にして小説家、エッセイストである森博嗣さんが、東日本大震災の直後に、「科学的に思考しなければ損をする」という視点で、科学から自ら離れてしまっている一般人のために記した一冊です。 非常に分かりやすく書かれてありますが、科学を絶賛するというものではありません。自身自身が科学的に考えて行動するためのきっかけにできるのではないかと思います。 "カリスマ的な指導者の発言が国民を動かしたりするようなことは、科学にはない。また、科学は、一部の特権階級にだけ、その恩恵をもたらすものでもない。科学は、経済のように暴走しないし、利益追求にも走らない。自然環境を破壊しているのは、科学ではなく、経済ではないのか。" という言葉が私が今感じている気持ち悪さの説明として一番腑に落ちます。 政治家が作ったマニフェストや公約集、経済学者が記した著作、TVや新聞の解説を読む前に、まずこの一冊を読んで普段の生活から「理由もなく直感的な印象だけで判断しない」ようにしたいものです。
Posted by
科学を好きになって欲しい、ではなく、科学的に思考しなければ損をする、という点から書かれている。科学が宗教・呪文になっている、という指摘。個人的には、科学は結果ではなく、コミュニケーションで作り上げていくプロセス、というのが興味深かった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
天文学者と物理学者と数学者の3人が、スコットランドで鉄道に乗っていた。すると、窓から草原にいる1匹の黒い羊が見えた。 天文学者がこう呟く。「スコットランドの羊は黒いのか」 それを聞いて、物理学者が言った。「スコットランドには、少なくても1匹の黒い羊がいる」 すると、数学者がこう言った。「スコットランドには、少なくとも羊がいて、その羊は少なくとも片面は黒い」 僕なら、ここに、子供を1人登場させ、最後にこう言わせたいところだ。 子供「あれは本当に羊なの?」 人間は単純化を無意識に好むものであり、概念に名前をつけ、言葉によって理解したつもりになる。 つるかめ算という名前を知っていることで、オームの法則という名前を覚えたことで、それが理解できたと思い込んでしまえる。 つまり、「神」という言葉を信じれば、人間のこと、社会のこと、自然のことを理解したつもりになれる。 少し変な例を挙げてみよう。 駐車場の9番に車を駐めたら係員が駆けつけてきて、「そこに駐めちゃ駄目だ!」と怒られた。どうしてかと尋ねると、「車はキュウにとまれない」と答える。そのジョークはわかる。だから、笑っていると、「とにかくすぐに車を退けてくれ」と要求された。貴方はどう思うだろう? 腹が立たないだろうか?駄洒落という「言葉遊び」と、現実のルールを混同してはいけない、という常識的な理屈がたぶん貴方にあるはずだ。面白さは認めるが、やはり「理不尽だな」と感じるのではないか。 けれども、神を信じ、神に支配されていた時代には、これと同レベルのことが罷り通っていた。現代の日本でも、「縁起が悪い」といって大勢が反対するようなものがある。 自分だけのことならば勝手であるけれど、ときどき摩擦が起こるだろう。
Posted by
工学博士で小説家の著者が「科学的とはどうい意味か」に答える本 文系への偏見や非合理的な物事の意味を軽んじている部分は多少あったけど、「科学的」であることはどういうことがは分かりやすく説明されていたと思う 以下抜粋 「学科で教わることは…『データ(情報)』と『メソッド(方法)...
工学博士で小説家の著者が「科学的とはどうい意味か」に答える本 文系への偏見や非合理的な物事の意味を軽んじている部分は多少あったけど、「科学的」であることはどういうことがは分かりやすく説明されていたと思う 以下抜粋 「学科で教わることは…『データ(情報)』と『メソッド(方法)』だ」(p35) 「『10メートルの津波が来る」という情報がもたらされたとき、…今自分がいる場所と、自分の体力と、周囲の状況から、『自分にとって危険か安全か』を判断すること…それが『科学』なのである」(p45) 「マスコミが…真の情報を伝えない理由は、大衆が…ドラマ(物語)を求めているからにほかならない。どうして、そういったものを求めるのかというと、それは、自分では考えたくないからだ」(p56) 「科学とは『誰にでも再現ができるもの』である。また、この誰にでも再現できるというステップを踏むシステムこそが『科学的』という意味だ」(p71) 「どうして人間は、その『再現性のある科学』というものを発展させてきたのだろう。それは、再現される事象を見極めれば、これから起こること、つまり未来が予測できるからだ」(p84) 「数というのは『順番』という上限関係だけでなく、『量』というものを示す性質を持っている」(p93) 「科学というのは『方法』である。そして、その方法とは、『他者によって再現できる』ことを条件として、組み上げていくシステムのことだ。他者に再現してもらうためには、数を用いた精確なコミュニケーションが重要となる。また、再現の一つの方法として実験がある」(p107) 「『新幹線が速いのは何故か』という問いに対して、『ひかり号だからでしょう』というのが、単純化による言葉だけの理解である」(p132)
Posted by
ミステリやスカイ・クロラを書いた人という認識だったけど、工学博士。こっちの科学本のほうが本職に近い。 科学者だけど、科学嫌いの文系人間の心理をよくわかっていらっしゃるw かなりわかりやすく的確に、普通の人(非理系)が科学にどう対処すべきかを書いた本。 なぜか2012年度高校入試...
ミステリやスカイ・クロラを書いた人という認識だったけど、工学博士。こっちの科学本のほうが本職に近い。 科学者だけど、科学嫌いの文系人間の心理をよくわかっていらっしゃるw かなりわかりやすく的確に、普通の人(非理系)が科学にどう対処すべきかを書いた本。 なぜか2012年度高校入試で森博嗣は大人気で、この本以外に「自分探し…」や「自由をつくる…」からも引用あり。森さんは試験問題としての引用をどう思ってるんだろ……気になる。
Posted by
科学について、科学に興味のあるない関係なしにすべての人に向けて書かれている。 少し深く考える、疑問を持つだけで変わるところは多い。 科学の嫌いな人(主に文系)に伝えていきたい内容である。
Posted by
森博嗣の本はたくさんあるけど、初の新書。 理系を敬遠することがどれだけ自分のマイナスになるのか、というテーマから、氏の独特の口調で社会問題へ切り込んでいく。 人は楽をしたい。 だから結果だけを求めて、感情や感想までも相手に求めてしまう。 自分の思考を停止してしまう。 少しだ...
森博嗣の本はたくさんあるけど、初の新書。 理系を敬遠することがどれだけ自分のマイナスになるのか、というテーマから、氏の独特の口調で社会問題へ切り込んでいく。 人は楽をしたい。 だから結果だけを求めて、感情や感想までも相手に求めてしまう。 自分の思考を停止してしまう。 少しだけ考えてみる。 自分の中に量的な基準を持つ。 イメージする。 これだけで社会をうまく乗りこなせる。 少しだけ村上龍と通じることがある。 要するに日本人はバカで、未来はかなり絶望的でもっとしっかりしろ!ということ。
Posted by