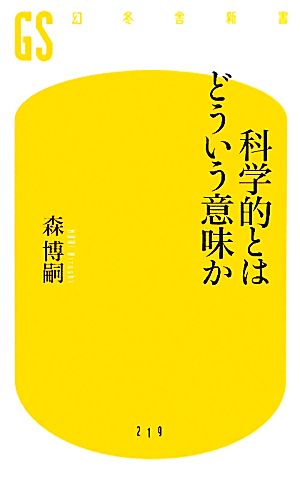科学的とはどういう意味か の商品レビュー
驚く程読みやすくてびっくりしました。文系と理系のくだりに納得しすぎて気付けば読了していました。うん、今まで勉強しなかった分、勉強しよう……。
Posted by
あとがきによればこの本は12時間で書き上げられたものらしい。東日本大震災の直後に擱筆したようで、災後の緊張感がところどころに表れている。いやむしろ、あの放射能汚染をめぐる報道の混乱の中で本書の方向性が決まったのではないかと思われる。 世の中に多く存在する科学嫌いを筆者は思考停...
あとがきによればこの本は12時間で書き上げられたものらしい。東日本大震災の直後に擱筆したようで、災後の緊張感がところどころに表れている。いやむしろ、あの放射能汚染をめぐる報道の混乱の中で本書の方向性が決まったのではないかと思われる。 世の中に多く存在する科学嫌いを筆者は思考停止と考え、その不利益を述べていく。表層的な印象や、個人的な感想を中心に報道するメディアや、それを鵜呑みして自分で判断することなく結論だけを求めようとする多くの人々を痛烈に批判している。 正直言って文系と理系に人を大別したり、人間の行動を図式的に捉えすぎている感がしないではない。結論を急ぐあまりに詳細を省略した感がある。また、多少内容的重複が気になる。それは新書という器にしては仕方ないのかもしれない。 学習が「情報」の多さに偏重せず、「方法」の獲得に力点を置くべきだという考え方は、新しい学力観とも関係する注目点である。科学論を考える前の準備として読んでおくべきだろう。
Posted by
世間でいわれる理系人への誤解を解く。 3.11関連の記載はここに書かれていたのか。 理系にすすみ周りにも理系人が多かったが、世間的にみたら理系はマイナーであることに最近気がついた。
Posted by
図書館で借りた。 タイトル通りの内容を述べている。3.11直後に執筆されたらしく震災の例が多い。 文系・理系と分けることは相対的なもので、理系と呼ばれる分野の中でも互いに、あちらは文系よりだ、理系よりだと話をすることがあるようだった。 著者が問題だと感じていることに、理屈は...
図書館で借りた。 タイトル通りの内容を述べている。3.11直後に執筆されたらしく震災の例が多い。 文系・理系と分けることは相対的なもので、理系と呼ばれる分野の中でも互いに、あちらは文系よりだ、理系よりだと話をすることがあるようだった。 著者が問題だと感じていることに、理屈はいいから結論だけ教えてくれ、という態度があった。現象を理解して、対策を自分で考えるのではなく、危険かどうかだけをしらされて避難するかどうかを指示してもらう態度は非常に危ないと同意できた。正直、そのような態度を取る人間はどうして相手をそこまで信用できるのか理解に苦しむ。 著者のスタンスとして、科学の楽しさとか、科学に興味を持って欲しい、のではなく、知らないと不利益を被ることを伝えようとしている。 よくスポーツの楽しさとか読書の楽しさとか、自分のやっていることを相手にも押し付けようとする人たちがいるけれど、楽しさは個々人で異なるのだから大きなお世話だと思っている。むしろ知らないといけないこと、困ることを何とか身につけさせるようにする方が大切な態度だと考えるため著者のスタンスに共感する。
Posted by
「感情的」なニュースに辟易している最中、この本を手にした。科学のことだけでなく、マスコミの流す情報に対する意見も書いてあり、同感だと思うことが多々。 「物語ではなく、情報や意見により耳を傾けるべきである」とのこと。小説が大半を占める私には耳が痛い。 鵜呑みにするのではなく、疑うこ...
「感情的」なニュースに辟易している最中、この本を手にした。科学のことだけでなく、マスコミの流す情報に対する意見も書いてあり、同感だと思うことが多々。 「物語ではなく、情報や意見により耳を傾けるべきである」とのこと。小説が大半を占める私には耳が痛い。 鵜呑みにするのではなく、疑うことや厳密性の追求、白黒はっきりつけようとしないこと(しかも何となくで)。 今さら科学者になれる訳ではないが、少しでも科学的であるスタンスでいたい(生きにくそうだけど)
Posted by
理系を毛嫌いするのはなぜか?分からないものを避ける。科学は分からないものを分かろうとする手段であり,絶対的なものではない。そのために他者による再現性を重視しており,他者でも扱えるように他者と共通認識をもてるように数量化したり,制限をつけた記述をしたりする。感覚的に表現するメリット...
理系を毛嫌いするのはなぜか?分からないものを避ける。科学は分からないものを分かろうとする手段であり,絶対的なものではない。そのために他者による再現性を重視しており,他者でも扱えるように他者と共通認識をもてるように数量化したり,制限をつけた記述をしたりする。感覚的に表現するメリットはあるが,他者と事実を共有するには感覚はあまりにも主観的すぎる。その感覚をいかに数値化するかがまた科学であったりする。
Posted by
文字通り科学について書いてあって、「科学離れ」について触れている。すでにタイトルで科学嫌いにとってはハードルになってるんだけど、読んでみたら人にとっても科学者にとっても優しい言葉が書かれてあった。 科学は人をしあわせにするためにある、という言葉は響きがもうしあわせだった。科学は...
文字通り科学について書いてあって、「科学離れ」について触れている。すでにタイトルで科学嫌いにとってはハードルになってるんだけど、読んでみたら人にとっても科学者にとっても優しい言葉が書かれてあった。 科学は人をしあわせにするためにある、という言葉は響きがもうしあわせだった。科学は慎重に時間をかけて実証していくことだというのも優しさを感じる。 「実験をすれば科学的だと勘違いしている人がかなりいる」と書かれててそこにも興味がわいた。何度も再現性を確かめて、「正しい」と思える状態に近づくプロセスが科学なんだって言われてちょっとわくわくした。 「科学を遠ざけることは損だし危険すらあるのだから、もう嫌いと言っていられる状況ではない」という主張も、今まで誰からも言われたことなかったことで素直に聞き入れてみたくなった。おとなってすぐ「科学って面白いよ」って科学実験ショーなんか見せて子供を喜ばせることばかり考えるんだけど、そういう科学が見たいわけじゃなかったぼくは損得とか言われたほうが面白かった。 科学って聞くと数式とか思い浮かべて降参しちゃうんだけど、考えたら社会科学も科学のうちだし。社会や人間はより複雑な気がするけどそっちの科学には興味がないわけじゃなかったわけで、結局科学嫌いというより数式についていけないと思ってただけなんだろなって思った。 科学が嫌いって自分で思い込んでたところあるけど、別にそんな「思い込み」にこだわることもないんだなって思えた。 難しい数式はわからないけど、日々の人とのやりとりを数字に置き換えて計測したことがある。いつ会ったとか、何日ごとにメールを書いたとかだけど、それだけでも、やってみたら、目の前の出来事が少しだけ以前より理解できた(気がする)。それだけでも科学に寄り添ってるということかもしれない。
Posted by
前書きに書かれているとおり、本書の主張は次の2つ。科学から目を背けることは自分自身にとって不利益、そういう人が多いことは社会にとって不利益。主張も内容も明確でわかりやすいがそれ以上の興味深さはない。
Posted by
141p。"一般の人たちが目にする...「○○発見!」のようなニュースは、ほとんど眉唾状態のもの...であると理解して良いだろう。" 完全にSTAP細胞問題のことを予言しているとしか思えなかった。
Posted by
本書は「科学的とはどういう意味か?」というタイトルではあるが、この点を深く追及するというよりは、この問いを起点として水平的に問いをずらして展開し、「文系と理系」「科学と非科学」と言った具合に対立構造を強調しつつ、科学の優位性を強調する仕上がりとなっている。 「科学的とはどういう...
本書は「科学的とはどういう意味か?」というタイトルではあるが、この点を深く追及するというよりは、この問いを起点として水平的に問いをずらして展開し、「文系と理系」「科学と非科学」と言った具合に対立構造を強調しつつ、科学の優位性を強調する仕上がりとなっている。 「科学的とはどういう意味か」という問いについては、その結論もその過程もこの本の数分の一程度のボリュームで済むと思われる扱いになっており、タイトルを見直した方が良いと感じる。中身も重複している部分があったり、順序がバラバラだったりで、体系的にまとまっているとは言えない。正直言って書きあがったエッセイがあまり編集されることなくそのまま書籍化された印象すら受けてしまったのは残念だ。事実筆者自身が後書きにて「本書は3日間、計12時間で執筆した」と認めている。 その他具体的に疑問に思われた点は幾つもあったが、例えば、 1.理系と文系というように二項対立で捉えることの非科学性を指摘しながら、理系が文系より如何に優位であるかにかなりのページが割かれている。(理系は文系を避けないが、文系は理系を理解できないため理系の人を「人間としての心が欠けている」と批判する、文系は理系に醜いコンプレックを抱えている、など) 2.科学の優位性、万能性を強調しすぎているきらいがある。非科学の例として、「神を信じている人」を挙げ、科学は「神の支配からの卒業」と捉えている。発展途上国ならともかく、科学の普及した先進国でさえ神を信じている人が多いことに疑問を呈している。しかし、そもそも科学と宗教はどちらを信じるかといった二項対立的なものではないはずである。筆者の論理でいけば、神を信じるという非科学的な思考をもつ人が多い国ほど、国家レベルでは科学の進歩は停滞し、個人レベルでは不利益を被り、最悪の場合生命の危機に脅かされるはずである。しかし、現在最も科学技術研究の先端をいく国はどこなのか?宗教のような非科学的なものを信じている国は困窮しているのか?神の存在を信じている、有能な科学者の存在はどう捉えればよいのか? つまりは「科学」と「非科学」という2つのカテゴリで括ってこれらの問題を捉えようとすることに無理があると思うのだ。 科学は、「印象や直感をできるだけ排除し、可能な限り客観的に現実を捉えようとする」。その厳格さが「他者による再現」を可能とし、その信頼性を担保する。 だが、あくまで個人的な意見ではあるが、その厳格さによりそぎ落とされたもの、定量化できないもの、印象や直感、その部分にこそ今後の時代を生き抜く上での重要なファクターがあると個人的には思える。科学的な考え方はもちろん重要だが、だからといって厳格な科学的思考にそぐわない考えを「非科学的」とみなし、それを見下して軽視してしまうようでは、それこそ狭量で危険な考え方なのではないか。 今回は思想的な部分での主張が強く、なかなか腑に落ちない所が多かったため、かなり辛口の批評となった。しかし、何かと考えさせられた一冊でもあるし、得たところも非常に多かった。森さんの今後の著作にも期待したい。
Posted by