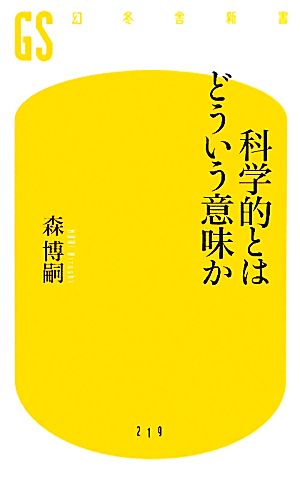科学的とはどういう意味か の商品レビュー
人はどのようにして冷静でいられるのか 人は得てして間違った判断を行う事がある。それは、人と人との事であれば、ホルモンの異常分泌などで説明が付くのかもしれないが(最近の科学ではどうもその点も解明されそうであるが)、適切な情報を収集せずに判断をする事がある。 それが、一生懸命に集...
人はどのようにして冷静でいられるのか 人は得てして間違った判断を行う事がある。それは、人と人との事であれば、ホルモンの異常分泌などで説明が付くのかもしれないが(最近の科学ではどうもその点も解明されそうであるが)、適切な情報を収集せずに判断をする事がある。 それが、一生懸命に集めた情報が判断に足りなかったというのであれば、残念ということであろうが、十分な情報ではない事を知っていながら、それ以上の情報は何故か不要と判断して、間違った判断をしてしまう。 そんな光景を、ここ数年よく目にするようになってきていた(そのような仮説を持つようになってきたためでしょう)ので、日本人はこの先大丈夫なのだろうか?とまで思ってしまっていたときに、このタイトルに出会った。 内容は非常に分かりやすい。 目に見えないものについて、人は判断を間違えやすいが、実は目に見えないものは数多く有り、子供の頃から慣れ親しんでいるものであれば、判断を間違えない。 理系と、文系と分けてしまっているが、文系に進んだ人は理系科目の試験が時間内に回答できなかっただけで、不得手であると認識してしまった可能性があるのでは?逆に私は、文系科目については、全くお手上げで、記憶についてはコンピューターに任せれば大丈夫と高をくくってしまった。従って、文学の繊細さについてはさっぱり分からず、本を読むのが凄く遅くて、未だに困っている。 文系、理系を問わず、科学的に考えることとはどういうことか。 実は、そこに世界をフラットにする考えがあるのではないかと考えている。 科学者は単に探究心にあふれている人が多く、自分の発見を世界に広め、人類の幸せのために使ってもらおうと思っている人が多いと考えている。ただ、それでは飯が食えないので、飯を食える仕組みを考えるパートナーと一緒に仕事をするか、自分で飯が食えるようにしていく事になる。 ただ、その中でその技術の使い道を誤った方向に使ってしまうことが有り、それが大きな事故を発生させることがあるのである。 科学とは再現が可能であるわけだから、Aさんが考えた技術は、Bさん、Cさんも再現できなければならない。となると、世界中であっという間に複製されるのである。 はさみは使いよう。とはよく言ったものである。 殺人を意図した毒物を除けば、ダイナマイト、自動車も有用な利用を考えて作られた技術であるが、それでも時代の中で大きな犠牲を伴ったことも事実である。 最近見た映画で、第二次世界大戦中にドイツ軍が使っていた暗号機エニグマを解読したイギリス人数学者を描いた、イミテーション・ゲームでも描かれていたが、大枠を数字から判断することは極めて重要だと考えている。 もちろん、数字には人の機微は描かれていないことは知っている。 http://imitationgame.gaga.ne.jp/ http://amzn.to/2lHV9qe
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2011年刊行。「科学的」の意味内容を功利主義的視点から解明し、非科学的な言動を止める処方箋を提示。「科学的」の意味内容は至極真っ当で何ら異論を挟むものではなく、著者の「非科学的態度は損だよ」との指摘も頷くところ大。ただ、非科学的言動を止めさせたいとする著者の意図が、本書で成功するかは??。①著者が真にターゲットとすべき相手は、本書を読まないような人々だし、②「非科学的言動は妄想」的な著者の叙述は、指摘として正しく(個人的には著者と同感)とも、読者が感情的に本書を忌避し、説得行動としては上手くないからだ。 善意から生じ、かつ正確なことを言えば相手に必ず伝わると考えておられるのだろうが、まさに理系の弱点を図らずも露呈してしまった感がある。ともかく、簡明な文章だし、内容は正鵠を射た正しいものなので、本書は長女には読ませてみたい。
Posted by
さすが、元理系大学(建築系)の助教授をされていた方らしく、科学的思考について述べられています。 ご本人曰く、”理系の中では非常に文系より”(p.8)とのことで、小説家でもありますので科学的思考に関しては、きわめて伝わりやすい文章で説明されている印象を受けました。 最近、放射線、感...
さすが、元理系大学(建築系)の助教授をされていた方らしく、科学的思考について述べられています。 ご本人曰く、”理系の中では非常に文系より”(p.8)とのことで、小説家でもありますので科学的思考に関しては、きわめて伝わりやすい文章で説明されている印象を受けました。 最近、放射線、感染症、ワクチンなどに関するセンセーショナルな報道を目にする機会が多いですが、それらを適切に読み解き冷静に理解するためのきっかけを得ることができる一冊だと感じました。 いわゆる情報リテラシーを向上させるには適した一冊です。 付箋は13枚付きました。
Posted by
気になっていてやっと読めた一冊。新書も高いから。電書で割引されていたので購入(*´∀`)俺も理系だけど科学って何と言われても科学とは論理的に考えられ、それが当てはまるもの的な認識しかなかった。タイトルが気になる人は是非どうぞ。
Posted by
「言葉とは単純化であり、ディテールを損ないかねない」という主張が、自分が最近考えていたこととピッタリ一致していた。 テーマがはっきりしていて、すんなり理解できた。 森博嗣はものの見方が鋭いというか、まさに科学的だなあ。
Posted by
数字を拒否しがちという点において、典型的「文系」のわたしには耳が痛い。ものの仕組みや道理がなぜ重要なのか、著者の意見が平易に綴られていて受け入れやすかった。 合理的であること、即ち冷静であること。
Posted by
スカイクロラの森博嗣による科学的とはという根本的なものを、東日本大震災の影響ですが考え直すべきという主旨の本。科学的にとはを考えることで、事象を感想やイメージだけで捉える危険を感じさせてくれる。 科学を敬遠する人は自分で考えることから逃げる人だ。科学とは、だれでも再現ができるもの...
スカイクロラの森博嗣による科学的とはという根本的なものを、東日本大震災の影響ですが考え直すべきという主旨の本。科学的にとはを考えることで、事象を感想やイメージだけで捉える危険を感じさせてくれる。 科学を敬遠する人は自分で考えることから逃げる人だ。科学とは、だれでも再現ができるものである。実験が科学では無い。数字や実験により、再現可能なものに近くなるということ。知ってるか知らないかは大したことはない。 文系と理系の違い。省略、ジャンプで結論にいきたくなるが、それが気持ち悪くて、一つ一つ確認するのが理系、科学的であるということ。鳥はどうして飛ぶことができるのか?翼があるから。しかし、翼があっても飛べない動物もいる。 科学は、神とか信じること、単純にすることでわかった気にすることができる。支配しやすい。科学は、理論によって、人間味のあるものを排除できる。思い込みから脱却し、慎重に事実を確認すべきだと。 津波は5メートル。これは高さであり、5メートルの堤防があれば防げる。これは間違い。波が押し寄せることで、力量は5メートル以上。波は押し上げられ、より高くなる。感情ではない、確認が必要だ。 科学の存在意義は、人を幸せにすること。祈ってますではなく、それはそれで人を救うけど、科学で本当に救うことも大切だ。理系の人にとって、世界はこんな風に見えている。
Posted by
科学の大切さについて、なるべくニュートラルな立場でわかりやすく説明してくれる内容。 ●文系と理系と二つにすっぱりと自分を分けてしまうのはもったいない。 ●科学を敬遠することは、他の分野に比べて日本人が日本語を知らないくらいに致命的なこと。 ●学生の時に学んだ学問のほとんどは暗記...
科学の大切さについて、なるべくニュートラルな立場でわかりやすく説明してくれる内容。 ●文系と理系と二つにすっぱりと自分を分けてしまうのはもったいない。 ●科学を敬遠することは、他の分野に比べて日本人が日本語を知らないくらいに致命的なこと。 ●学生の時に学んだ学問のほとんどは暗記ができれば良いが、数学はメソッド(方法)を学ぶので、他の学問とは少し違う。 ●幽霊はなぜ、壁をすり抜けたり宙に浮けるのか。つまり空気と同じ質量だから、風に飛ばされもするし、拡散もする。空気は密閉されていればガラスなどもすり抜けることはできない。であるとすれば一体何なのか? ●身近にある物の数字を知ることが大事。質量なども。 ●科学のおかげで宇宙にある法則は地球に即した法則で想定できる。今の所、あてはまらない法則はない。 ●科学とは誰がやっても再現できること。 などなど、とても為になりました。 それにしても、知らないことばかり…。
Posted by
科学を楽しいと感じるかどうかは人それぞれだけど、科学は人を幸せにするためにあるのだし、危険から身を守るのは科学だし、科学を毛嫌いして耳を塞ぐといろいろ損をするので、聞く耳を持つことを推奨するような本。
Posted by
科学は楽しいよ,面白いよ,といっても押しつけにしかなんなくて,楽しいとか面白いとかでなく知ってないと損するから,ていう言い方は非常に端的だと思う。そういう言い方だと脅迫っぽくなるし欠如モデル的に見える(知らなきゃだめよみたいな)から科学コミュニケーション界隈ではあんまり声を大にし...
科学は楽しいよ,面白いよ,といっても押しつけにしかなんなくて,楽しいとか面白いとかでなく知ってないと損するから,ていう言い方は非常に端的だと思う。そういう言い方だと脅迫っぽくなるし欠如モデル的に見える(知らなきゃだめよみたいな)から科学コミュニケーション界隈ではあんまり声を大にしては言ってないような印象があるけど(リテラシーの涵養とかは言ってるけど),もうちょっとこういう言い方出してもいいような気もしなくはない。ただ,じゃあどこまでが最低限知っておくべきリテラシーかというと,提案されているものはあるものの,どうなのだろうなあ。
Posted by