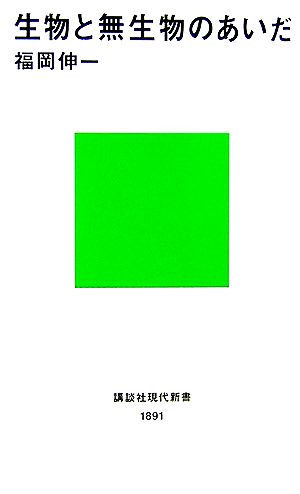生物と無生物のあいだ の商品レビュー
この本はすごくアカデミックな内容ですが、とても人間味溢れた表現で魅了します。 本当は生物と無生物の境界はここなんでは無いかと言う議論が白熱するのかと期待していましたが DNAからの生物の原理の探求の話がメインです。しかし、ニンゲンの体は常に変化を繰り返している とか原始と分子の間...
この本はすごくアカデミックな内容ですが、とても人間味溢れた表現で魅了します。 本当は生物と無生物の境界はここなんでは無いかと言う議論が白熱するのかと期待していましたが DNAからの生物の原理の探求の話がメインです。しかし、ニンゲンの体は常に変化を繰り返している とか原始と分子の間はなんでこんなに大きさが異なるのかなど、疑問に思っている事をズバッと回答して くれます。とてもすばらしうい。ぜひ続編を出してもらいたいものです。
Posted by
科学者でありながら詩的で文学的なセンスの光る文章。 生物というものは動的均衡、動的な秩序を持つ。生命を、静的で機械的なシステムとみて解き明かすことはできず、絶えず時間と流れの中の変化がそこにあることを見落としてはならない。 DNAのことや、科学者の発見の舞台裏などの記述は興味深か...
科学者でありながら詩的で文学的なセンスの光る文章。 生物というものは動的均衡、動的な秩序を持つ。生命を、静的で機械的なシステムとみて解き明かすことはできず、絶えず時間と流れの中の変化がそこにあることを見落としてはならない。 DNAのことや、科学者の発見の舞台裏などの記述は興味深かったし、科学に関する知識が著しく少ない私のような人間でも読みやすい表現で書かれていたが、やはり言葉の説明だけでは理解しきれない専門性や、関心のずれ(普通に暮らしていたら体感できるはずもないミクロなものへどんどんとむかっていくこと、原理を突き詰めていくことへの抵抗感が私にはある。)で、集中して読めない部分も多かった。 どこまで生命の神秘に迫っていくことができるのか、そして倫理的にそれがどこまで許されるのか、という著者の葛藤は、エピローグのとかげの卵の話の部分で、最も真に迫った表現で描かれていた。 このような生命科学の研究があるからこそ、撲滅できる病があったり、救われる命はある。しかし、作者も含め科学者たち自身は、根源的には、単に「生命とはなにか」という好奇心から研究を進めている。 否定できない科学的根拠に基づく証拠によって、それが説明されてしまったら、もうそこに神秘性はなくなるように私には思われる。
Posted by
生命の探究というテーマを主軸に、DNAの発見をめぐる研究者たちの人間模様も描かれています。発見だけでなく、それを発見した背景が語られているので読み物としても面白いですね。‘動的平衡’という考え方にはスピリチュアルなものも感じました。図書館予約数は99(08/04/26現在)です。
Posted by
視点は面白いが、そもそも自分はこの分野にあまり興味がなかったらしい。途中で飽きてしまいました。興味のある人にとっては、とっつきやすい本だと思います。
Posted by
生物の知識を持ち合わせていた方が読みやすいかもしれませんが、無くても どんどん読めます。 上手く表現できないのですが、ドキドキハラハラの展開でした。 生物と無生物の違いを比較していくのかと思っていましたが、 「生物とは何とダイナミックなものか」を描いていたように思います。 読みや...
生物の知識を持ち合わせていた方が読みやすいかもしれませんが、無くても どんどん読めます。 上手く表現できないのですが、ドキドキハラハラの展開でした。 生物と無生物の違いを比較していくのかと思っていましたが、 「生物とは何とダイナミックなものか」を描いていたように思います。 読みやすい文章です
Posted by
”生命とは何か?それは、自己複製を行うシステムである” ”よく私たちは「お変わりありませんね」などとあいさつを交わすが、 半年、あるいは1年ほど会わずにいれば、 分子のレベルでは我々はすっかり入れ替わっていて、 お変わりありまくりなのである” 研究内容への説明はわかりや...
”生命とは何か?それは、自己複製を行うシステムである” ”よく私たちは「お変わりありませんね」などとあいさつを交わすが、 半年、あるいは1年ほど会わずにいれば、 分子のレベルでは我々はすっかり入れ替わっていて、 お変わりありまくりなのである” 研究内容への説明はわかりやすいだけでなく、感覚的に迫るところがある。 文章がきれい。 文系の人間には、理系の世界をのぞいたようなわくわく感があった。
Posted by
これは面白い!「本」に連載時にちらりと読んで「面白い」と思ったものであったことが判明。(たしかロザリンド・フランクリンの回。)文学的な表現・分かりやすく語る方法・もちろん専門知識がきちんと揃って成り立つ技。 20080414
Posted by
2007年度の第二回駿台全国模試の国語の問題に出て、面白そうっ!って思ったらそれはなんとあとがきだったのです。タイトルあまり関係ないじゃん、と思った。岩波新書のウイルスについて書かれた『生物と無生物の間』という本のほうが的確な書名でしょ。
Posted by
まず、面白い。 しかし、生物と無生物のあいだ、という疑問に答えが与えられているかは疑問である。結論からいうと、動的平衡が生物の証、と言いたいのであろうが、川の流れに動的平衡がないのかと言ったら、あると思うし、今後動的平衡状態を脱した(生命体のある過程を切りとって冷凍して変化させて...
まず、面白い。 しかし、生物と無生物のあいだ、という疑問に答えが与えられているかは疑問である。結論からいうと、動的平衡が生物の証、と言いたいのであろうが、川の流れに動的平衡がないのかと言ったら、あると思うし、今後動的平衡状態を脱した(生命体のある過程を切りとって冷凍して変化させて戻す)といった実験過程も考えられる。
Posted by
DNAの説明がとっても解りやすく面白かったです。 全体的に読みやすくてテンポ良く読めましたが、最後の方が少し説明がくどくなってきて眠くなってしまいました。 でもここは最後まで読まなくてはいけません。 なぜなら、一番最後のあたりが、この著者が言いたい所の様だからです。 もちろん第2...
DNAの説明がとっても解りやすく面白かったです。 全体的に読みやすくてテンポ良く読めましたが、最後の方が少し説明がくどくなってきて眠くなってしまいました。 でもここは最後まで読まなくてはいけません。 なぜなら、一番最後のあたりが、この著者が言いたい所の様だからです。 もちろん第2章で問われているウイルスは生物か?の答えはこの一番最後に含まれている著者の思いの中に含まれているからです。 こう書くとこの書籍は生物か否かの区別の仕方を書いている様に思えるかも知れませんが、けっしてそう言う訳では有りません。 生物という計り知れない素晴らしい物をここまで説明したがまだ足りないそんな著者の気持ちがかかれている気がしました。
Posted by