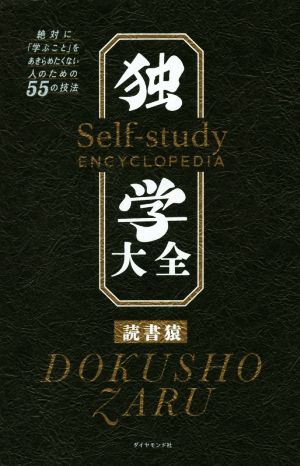独学大全 の商品レビュー
著者は、独学についてひたすら試行錯誤したのだろう。学びに躓いた時の答えがちりばめられている手引き書のような形になっている。多分何巻かにわけたら著者の懐も潤っただろうに、全部一冊にまとめて、かつ、3000円以下。ほんとに学びたい人のこと想って書いたことが伝わる、熱すぎる。中は、私も...
著者は、独学についてひたすら試行錯誤したのだろう。学びに躓いた時の答えがちりばめられている手引き書のような形になっている。多分何巻かにわけたら著者の懐も潤っただろうに、全部一冊にまとめて、かつ、3000円以下。ほんとに学びたい人のこと想って書いたことが伝わる、熱すぎる。中は、私もやってる!ってものから、これは参考にしたい!ってものまで色々。 内容は中高生や受験生にも参考になるものばかりで、学びたい人には老若男女、誰にでも勧めたい。 「この本はあまり賢くなく、すぐに飽きて諦めてしまう人に対して書いた」という。←わ、わたしです
Posted by
こういう「自己啓発系」の本って読んでもほとんど活用できないんだよなあと思いつつ、話題本ということなので試しに読んでみた。結論からいうとやはり自分にはあまりプラスにならなかった。 独学するためのいろんなテクニックが、「概念」のレベルで丁寧に書かれているのだけど、とにかく文章が冗長...
こういう「自己啓発系」の本って読んでもほとんど活用できないんだよなあと思いつつ、話題本ということなので試しに読んでみた。結論からいうとやはり自分にはあまりプラスにならなかった。 独学するためのいろんなテクニックが、「概念」のレベルで丁寧に書かれているのだけど、とにかく文章が冗長で読みにくい。話の途中に哲学者についての説明があったりとノイズが多すぎてぜんぜん集中できなかった。たぶんほとんどの人が僕と同じように、「分厚い本を読んだんだぜ」という自信が得られるだけで、現実世界では本書の教えを活用できていないのではないだろうか。 あと多くの人が「読みやすかった」「分かりやすかった」という高評価をしているが、本当だろうか? ※以下、本文より 『NDCトラバースは、一つのトピックを複数の視点/分野から眺めて、多角的に捉えるために図書館分類を利用する技法である』 ↑は、「独学したいけど何を勉強したらいいか分からないよね。そんなときのためのテクニックとしてNDCトラバースというのがあるんだ…」という流れで出てくる文章なのだけど、はっきりいって何を言ってるのか分かりづらい。読んですぐに「要約して」と言われて反応できる人は少ないのではないだろうか。本書ではこんな感じの文章が頻出するので、文章を理解するだけでもなかなかにキツイと思う。 いろいろ文句を書いたけど、本書のおすすめの読み方としては、二人で一緒にこの本を読んで、読み終わったあとに内容について議論してみるといいと思う。 「ぜんぜん理解していない」ということが理解できるから。笑
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ざっと流し読み。継続できるか否かがポイント、多くの人は、学習効果が低減してくる中程度の学習状況に達した段階で成長実感が薄れて挫折するとの考えに納得。 その他は、当たり前のことを当たり前にやれるかが重要か? ・動機明確化、目標設定、課題細分化(1/100にしてみる等) ・毎日の予定と実績をトラックして、認知バイアスを回避して客観的に現状把握する ・ポモドーロテクニックを習慣化する ・とにかく2分でいいから毎日何かする 等
Posted by
大全というタイトル通りの分厚さに読むのを躊躇してしまうが、中身は読みやすく、厚みの割に比較的短時間で内容が把握できた。 タメになったこと • シネクドキ検索→〇〇とは何の一種?と調べる。 • 点読→一冊読む前後にやってみる。 • 興味のある分野で自分の知っていること、知らないこと...
大全というタイトル通りの分厚さに読むのを躊躇してしまうが、中身は読みやすく、厚みの割に比較的短時間で内容が把握できた。 タメになったこと • シネクドキ検索→〇〇とは何の一種?と調べる。 • 点読→一冊読む前後にやってみる。 • 興味のある分野で自分の知っていること、知らないことを整理 • wiki simple English を毎日読む、コピペして記録する。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
やっと読み終わった。752頁にも渡る、この辞書のような本を通読し終えるのに何日かかったか。しかしこれは終わりではなく始まり。そう、自分の独学の始まりです。 ・・・ 本作は独学、換言すれば誰からも強制されない学び、をより良い形で続けていくための手引きであります。 収録された55のテクニックは表層的なものにとどまらず、なぜ学びたいのかといった自己分析を行うものや、知りたいことのレベルを測るシネクドキの技法など多く役に立つものがありました。 ・・・ 少し私事を。 私は本を読むことや日記を書くことが好きですし、上の子の高校受験を機にスタディサプリで世界史とかも勉強したりしてましたが、自分が本当に何を勉強したいのかはよくわかっていませんでした。でも、この本を読みつつ、カルテ・クセジュという技法でブレインダンプ的なことをしているうちに、自分が学びたいこと・知りたいことが分かった気がします。 ちなみに私が知りたいのは「人間性(humanity)とは何か」ということです。他の動物と異なる人間の特徴を改めて知りたい。理性だったり感情だったり、それがために秩序だった本能の営みから逸脱しイレギュラーな行為が生まれる本性。科学全盛の時代には哲学的アプローチをすると空虚になりがちだが、脳科学や行動経済学なども併せて学びたい。そこでは無慈悲なアイヒマンも生まれ、また友や仲間を守るために自己犠牲を厭わない多くの無名のヒーロー・ヒロインも生まれる。この悲しくも素晴らしい人間という種の本性を改めて学びたい。…ちなみに卒論でも修論でも類似のテーマで挑んだものの射程が広すぎて破綻した感がありましたが笑 ・・・ もう一つ本作で感銘を受けたのが技法28の目次マトリックスをはじめとした知識の鳥瞰のための技法です。筆者はこれを「点の読書から面の読書」と呼んでいますが、言い得て妙かと。 今まで私がしてきたのはある作者の本を読み、ちょっと面白そうだと参考文献をみて感覚で次を選ぶという、いわば運だよりの読書でした。しかし膨大な情報があふれる昨今、その波に飲み込まれることなく効率的に航海図を描くことも必要になります。本技法は類似書籍の目次をマトリクス(表)にすることで現在学会で盛り上がっているトピックや中心的話題やトレンドなど学問の概観が可能になり、またある作品で言っていることが他でどのように評されているかなどの比較にも使用できます。こうした整理をしたうえで読書を始めることで、外れを引くことも少なくなりますし、より精緻な読書ができると考えます。 もちろんジャケ買いやタイトル買いのロマンも捨て難いし否定する気はさらさらありませんが、既に人生の折り返しを優に過ぎた自分、残された時間がいかほどかわからないのならば、合理で包括的なアプローチを採用するほうが自分の知的好奇心に適うと考えました。 ・・・ おそらく今年一番感銘を受けた本だと思います。 技法ではありませんが、「巨人の肩にのる」というアイディアはとても感動しました。曰く、人間の知的営為はどれも最前線はすべて独学以外にあり得ず(誰も研究していないから)、そうした文化遺産を拝借して我々も遠い地平を眺めるというものです。つまり私たちの独学もどこかで知の巨人とつながっているというものです。 本作、自己向上・自己研鑽に挑む人にはすべての方にお勧めできると思います。ただしこれを読んでも何も変わらず、ここからどう進めてゆくかは当然の事ながら読者自身に委ねられています。
Posted by
全てを熟読したわけではなく、ざっと目を通しながら必要なところはしっかりと読むという感じで通読した。学びの途中で困った時は、またこの本に戻ってこようと思う。
Posted by
分厚いと聞いていたので図書館で読みました 全部読まず自分の読みたい箇所だけでも、ためになると思います 文章事態はそんなややこしくなく読みやすかったです
Posted by
特に印象に残った章は、 第一章 学ぶという欲求に応える為に、「中級の壁」が立ち塞がる。学び方を変えたり、学ぶことを変えたり、新しいことに目移りするのも、学んでいる欲求を満たす為であるが、結局、身についていない。 壁を越える為には、続ける習慣をシステムとして作ることが肝要である。 ...
特に印象に残った章は、 第一章 学ぶという欲求に応える為に、「中級の壁」が立ち塞がる。学び方を変えたり、学ぶことを変えたり、新しいことに目移りするのも、学んでいる欲求を満たす為であるが、結局、身についていない。 壁を越える為には、続ける習慣をシステムとして作ることが肝要である。 行動デザインシートでは、行動を分析する事で、ライバル行動を減らし、ターゲット行動を増やす。 まず4つの視点で、行動を分析する。 1.行動のきっかけの多少 2.ハードルの高低 3.ライバル行動の有無 4.褒美がすぐえられるか 例えば、ライバル行動=スマホみる時間 ターゲット行動=読書時間 で分析すると、 1.スマホ多い、読書少ない 2.スマホ少ない、読書中くらい 3.スマホ少ない、読書多い 4.スマホ速い、読書遅い 1.スマホで読書記録する。(今までの記録を見直すきっかけ) 2.一部の投稿や、オーディオブックの感想で○ 3.他のアプリを消す。ネットの制限をかける。 4.ブログで、公開する。スマホのスケジュール管理で減ったら、ご褒美にするなど。
Posted by
分厚くてびっくり。 第1章を流し目でパラパラと読む。 独学の計画を立てるのにも挫折しそうだ〜 おもしろそうなのだけ取り入れれればいいかな
Posted by
750ページもあるが、比較的平易な言葉で書かれているので、思ったほど時間を取られることはなかった。 自分はこの通りやるかどうかは別として、独力で何かを学ぼうとする人には、参考になるだろうと感じた。 第一部 なぜ学ぶのかに立ち返ろう ここでは独学を進めるにあたってのモチベーション...
750ページもあるが、比較的平易な言葉で書かれているので、思ったほど時間を取られることはなかった。 自分はこの通りやるかどうかは別として、独力で何かを学ぼうとする人には、参考になるだろうと感じた。 第一部 なぜ学ぶのかに立ち返ろう ここでは独学を進めるにあたってのモチベーション作りのことが書かれている。 志と目標を立て、くじけないように動機付けを高める。時間を確保して学びを継続する。その為の環境作りの参考も記載されている。 第二部 何を学べばよいかを見つけよう ここではまず何を知りたいのかを明確にした上で、資料の探し方、その使い方、集めた文献等の情報の整理の仕方、そしてそれを吟味する方法が書かれている。 第三部 どのように学べばよいかを知ろう 色々な読み方の紹介、記憶の仕方、分からないことに出くわした時の克服方法、そして自分自身の独学法を生み出そうた言うアドバイス。 第四部 独学の「土台」を作ろう ここでは、国語、英語(外国語)、数学の独学の骨法が書いてあり、それぞれ独学者がどうしたかと言う例が載っている。 個人的には記憶に関することに興味があり、その中には「理解は最高の記憶法であり、記憶は理解のよき助力者だ」「記憶の最善方法はプランニングだ」「一度に覚えるより分けて覚える方が効果が高く、長く続く。そして学習を分散するとしても、その間隔を次第、広げる方が効果ぎある」「人は自分の考えを声に出す時の方が、声に出さずに学んでいる時よりも素早く深く学ぶ」と言うことが書かれてあり、印象に残った。 しかし英語独学の骨法には、①文字と発音をチェック ②文法の前に単語を眺める ③テキストの会話や基本文を全部読む ④文法解説をきちんと読みながらテキストをもう一度読む ⑤一通り覚え理解してから、1章ごとに10回音読、3回筆写 ⑥これを1冊につき3周する とあるが、そりゃそれしかやることがない人にとっては効果があるんだろうけど………
Posted by