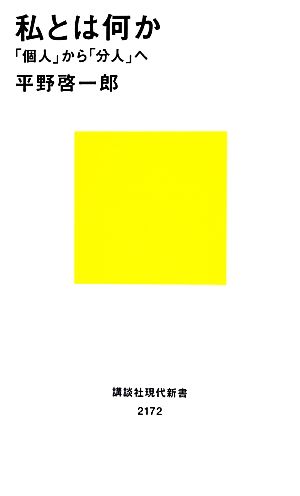私とは何か の商品レビュー
---------------- 125 人は、なかなか自分の全部が好きだとは言えない。しかし、誰それといるときの自分(分人)は好きだとは、意外と言えるのではないだろうか? 逆に別の誰それといる時の自分は嫌いだとも。そうして、もし、好きな分人が一つでも二つでもあれば、そこを足場...
---------------- 125 人は、なかなか自分の全部が好きだとは言えない。しかし、誰それといるときの自分(分人)は好きだとは、意外と言えるのではないだろうか? 逆に別の誰それといる時の自分は嫌いだとも。そうして、もし、好きな分人が一つでも二つでもあれば、そこを足場に生きていけばいい。 それは生きた人間でなくてもかまわない。 私はボードレールの詩を読んだり、森鴎外の小説を読んだりしている時の自分は嫌いじゃなかった。 人生について深く考えられたし、美しい言葉に導かれて、自分がより広い世界と繋がっているように感じられた。 そこが、自分を肯定するための入口だった。 ---------------- 感想 いやーおもしろかったし、何より救われた。 ずーっと読みたかった本、ようやく時間ができたので読めました!! けっこう自分は人間関係考えすぎて悩んでしまうタイプなので、本書の各所でわかる!と膝を打っておりました笑 中でも印象的だったのが冒頭の言葉。 これには本当に救われた。 自分はなかなか自信を持って自分のことを好きだとは言えない。 でも本を読んで感情が動いたり、人生について考えたりしている時の自分は悪くないと思える。 なんとなく感覚としてはあったけど、それを言語化してもらえたのが大きかったです 歴史への造詣も深く、個人の概念の変遷などは世界史とリンクする部分もあり非常に興味深かったです。 もう12年前の著作なのがびっくり。 ぜひ最新の平野さんの思考も学んでみたいです。 今後、『ドーン』と『空白を満たしなさい』を読んでみたいと思います。 一旦朝井さんの『生殖記』挟んでから。 ぜひ人間関係に悩んでいる人は読んでみてほしい、10代の頃に出会いたかった本でした ---------------- 印象に残ったところ↓ 40 結局、教育現場で「個性の尊重」が叫ばれるのは、将来的に、個性と職業とを結びつけなさいという意味である。 94 学校でいじめられている人は、自分が本質的にいじめられる人間だなどと考える必要はない。それはあくまで、いじめる人間との関係の問題だ。放課後、サッカーチームで練習したり、自宅で両親と過ごしたりしている時には、快活で、楽しい自分になれると感じるなら、その分人こそ足場として、生きる道を考えるべきである。 106 コミュニケーションは、極力シンプルな方がいい。お互いに色々と気を回さずに、思ったことをそのまま言い合うのが理想だ。 分人という単位で考えるなら、あなたが語りかけることができるのは、相手の「あなた向けの分人」だけである。 その一方で、あなたの言葉は、相手の「他の様々な人向けの分人」に常に曝されている。 相手との関係性の中で、あなたが悪意を持って何かを相手に信じさせたとしても、その言葉は、相手の中の別の友人との分人や両親との分人などを通じて吟味される。 109 私は精神科医でもカウンセラーでもないが、この話を聞いて考えたのは、かつては個人を単位として発症していたウツが、今は分人単位で起きているのではないかということだ。 不幸な分人を抱え込んでいる時には、一種のリセット願望が芽生えてくる。しかし、この時こそ、私たちは慎重に、消えてしまいたい、生きるのを止めたいのは、複数ある分人の中の一つの不幸な分人だと、意識しなければならない。 138 愛とは、相手の存在が、あなた自身を愛させてくれることだ。そして同時に、あなたの存在によって、相手が自らを愛せるようになることだ。その人と一緒にいる時の分人が好きで、もっとその分人を生きたいと思う。 144 その意味では、パートナーはよく似た分人のバランスを持っている人が理想的なのかもしれない。 148 愛する人が存在しなくなったことは、もちろん、悲しい。同時に、もう愛する人との分人を生きられないことが悲しい。 訃報の悲しみはしばしば遅れてやってくる。 誰かが死んだという知らせを受けて、その瞬間に涙を流す人は、実はそれほど多くないだろう。ショックは受けるが、実感はすぐに湧いてこないこともある。 183 「個人」は、ようやく近大になってから、言葉と共に、その存在を見出されるに至った。もちろん、それまでの西洋人も、自分と他人との区別がつかなかったなどということはない。しかし、個人が明確に意識され、議論され、価値づけられていくためには、やはり言葉が必要だった。
Posted by
新書は半信半疑の状態から読み始める事が多いですが、この本は納得してしまう面が多く、読み終えた頃には著者の考えが私自身に浸透しきってしまう感覚がありました。
Posted by
静かに、久しぶりに、ドカンと来た。 人は他者との相互作用の中でアイデンティファイされるというのは元々考えていたことだけど、そこに分人という概念を導入することで一見一貫性がないような振る舞いや性質もより柔軟に説明できるような気がした。 僕自身、例に漏れずポストモダン的な考え方(...
静かに、久しぶりに、ドカンと来た。 人は他者との相互作用の中でアイデンティファイされるというのは元々考えていたことだけど、そこに分人という概念を導入することで一見一貫性がないような振る舞いや性質もより柔軟に説明できるような気がした。 僕自身、例に漏れずポストモダン的な考え方(主体は存在しない!)にハマっている時期があったけど、分人的な考え方は自分の中でその次に来るものになりそう。 自分が心地よいと思える分人を足場にして生きていこうと思う。 また、自分が誰かと対峙するときに、あくまでその人も自分に対する分人として対峙しているということに配慮していきたい。
Posted by
分人という考え方はなかったですが、 なるほど納得!という感じでした。 どんな自分も自分であるということにとても 共感しました。
Posted by
【どう】良い 分人という概念は考えたことがなかった。 著者の考え方が表善されているだろう小説を読みたいと思った。 【学び、備忘録】 81 八方美人は分人の巧みな人ではない。むしろ逆。パーティならパーティという場に分人化しても、個人へは蔑ろにしている。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「貴重な資産を分散投資してリスクヘッジするように、私たちは、自分という人間を、複数の分人の同時進行のプロジェクトのように考えるべきだ」 辛く苦しい状態も、自分を構成するたくさんの分人の一つが経験しているものにすぎず、その状態自体もその分人を共有する相手・環境に半分は責任がある。それならば、心地よく楽しく過ごせる分人を足場にして生きる道を考えればよい、というのはなるほど、非常に心が軽くなる考え方だわ、と思う一方、やはり現実逃避感がぬぐえない…。 でも、そもそもそのマイナスイメージこそ、個人主義(※↓)的であり、それでは、様々な対人関係、人間の行動を論理的に説明することができないから、筆者が新たに分人主義を唱えたわけで。矛盾をはらむ個人主義的思考をベースにした感覚もまた、論理的ではない!現実逃避だなんて思わなくていいのだ! …と考えてよいのか。 ※個人は分割することの出来ない一人の人間であり、その中心には、たった一つの「本当の自分」が存在し、さまざまな仮面(ペルソナ)を使い分けて、社会生活を営む、という考え方。 「分人主義」公式サイトより dividualism.k-hirano.com
Posted by
「分人」自体の実感は誰しもが持っている気がするが、その分人の発生が「他者との関わりでできる」というところを言語化してくれたところが刺さった。そしてその分人でいることを好きでいられるか、というのは、自分の過去の振る舞いや感情と照らし合わせてると、なかなか有意義な分析ができそうだ。 ...
「分人」自体の実感は誰しもが持っている気がするが、その分人の発生が「他者との関わりでできる」というところを言語化してくれたところが刺さった。そしてその分人でいることを好きでいられるか、というのは、自分の過去の振る舞いや感情と照らし合わせてると、なかなか有意義な分析ができそうだ。 読んでいる間、そうは言っても「核みたいなもの(ゆずれないもの)、つまりどの分人にも共通する信念」みたいなものが「本当の自分」なのではないかと思ったが、この辺は遺伝とか教育とかにかなり依存したものなのかなあと思ったり、強烈な環境変化で変わることがあったりしそうだとも思ったり。 その辺も、構成比率の高い分人経由でアップデートされ、融合していくものなのか。するとやはり、「本当の自分」というものに拘らず、あくまで「その分人が好きかどうか」という価値判断で生きていくのは、人生の方針というか、幸せな生き方の道標になるような気がする。 『ドーン』読んでみよう。
Posted by
これまで漠然と感じていたことを、「分人」という言葉で分かりやすく言語化しており、新しい価値観が得られる一冊だった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
各々が社会で生き、色々な人と出会い、自分も色んな顔を持っている。 家族や恋人、会社にみせる自分は必ずしも一緒ではない。 それは個別化と捉えることもできるけれど、 それは「本当の自分」という核なるものがあってそこから相手に合わせて変容させているのか? 偽りの自分を許容しながら人と接しているのか?というところを出発点に、個人の認識の仕方を提示した本です。 人と関わり合う中で様々な面を持った分人ができていき、その集合体が個人なんじゃないか?という衝撃的な内容でした。 私自身、会社の同期でもある友人には会社とプライベートの印象が違うよねとよく言われ、 自分ってなんなんだろう。どっちか正解なんだろうかとよく悶々としていました。 それに答えを、認識の仕方の問題ではと気づかせてくれ、心を救ってくれた本でした。 人間関係に悶々とした時に読み直したい一冊です。
Posted by
平野啓一郎氏の著書のテーマとも呼べる「分人」という考え方を、本人の生い立ちを含めて詳しく解説。 全ての人は、「個人」(分母)の中に数えきれないほどの「分人」(分子)が存在していると提唱している。 確かに、「親の前での私」「学校での私」「会社での私」「友達の前での私」「夫の前での...
平野啓一郎氏の著書のテーマとも呼べる「分人」という考え方を、本人の生い立ちを含めて詳しく解説。 全ての人は、「個人」(分母)の中に数えきれないほどの「分人」(分子)が存在していると提唱している。 確かに、「親の前での私」「学校での私」「会社での私」「友達の前での私」「夫の前での私」などなど、色んな「私」が存在しているし、それぞれに振る舞いも違う。 歴代の彼氏の前での私の振る舞いも、それぞれに全然違う。 そして、同じように全て知った気になっている夫も同じように分人は存在して、「私の知らない夫」は必ず存在する。 実は、小学生の時代から知っている夫(結婚25年目)に浮気された事がある。 そこで、「私の知らない夫」を知った。 長ーい付き合いと周りとの付き合いから、夫は嘘をつかない人間だと思い込んでいたけれど、実際、平気で嘘をつく人間だった。 ショックで人間不信に陥り鬱病になったけれど、何年共に過ごそうと、きっともっと知らない部分もあるはずである。 全部知り得る事はないのだし、人によって態度が違うのも仕方のないことなのだ。 とすっと腑に落ちた。
Posted by