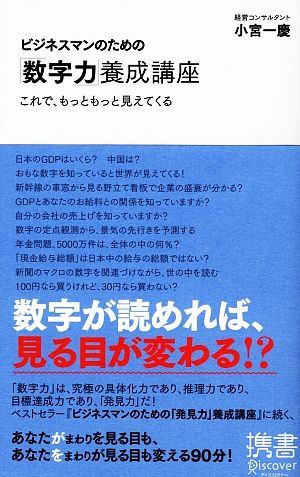ビジネスマンのための「数字力」養成講座 の商品レビュー
いつだったか書店で見つけて、読まなきゃと思っていた本です。 数字を読む仕事ですが、 小学生のときから理系が苦手だったくらいに苦手意識があるので 読んでみました。 ★GDP=Gross Domestic Product=売上-仕入 500兆円 ★労働分配率(GDPに占める人件費の割...
いつだったか書店で見つけて、読まなきゃと思っていた本です。 数字を読む仕事ですが、 小学生のときから理系が苦手だったくらいに苦手意識があるので 読んでみました。 ★GDP=Gross Domestic Product=売上-仕入 500兆円 ★労働分配率(GDPに占める人件費の割合)=大体60% ★付加価値率(小売でいう粗利益。日本は大体30%) などなど。 他に、本当に何事にも数字をもってくると信ぴょう性が高まるのと、 目標に近づきやすいことがわかりました。 しかし、本の最後の付録の専門用語 ・・・といっても著者は最低限これだけは分かってください、 と言っていましたが・・・ は、既に難しかったです。 自分の仕事の範囲のことやニュースでの数字には、 これから少しづつ興味を持って、実感していこうと思います。
Posted by
2年前に読んだが、まだまだ社会人として基本的な数字力を身につけていないことを痛感し、復習のために再読。読んでよかった。2年前読んで「よし、実践しよう!」と思ったことを半分もしていなかったことが分かった。。。特にこの本のいいと思った点は、読んだ人にしっかり「数字力」をつけさせるため...
2年前に読んだが、まだまだ社会人として基本的な数字力を身につけていないことを痛感し、復習のために再読。読んでよかった。2年前読んで「よし、実践しよう!」と思ったことを半分もしていなかったことが分かった。。。特にこの本のいいと思った点は、読んだ人にしっかり「数字力」をつけさせるために、随所に具体的な演習や習慣化を勧める数字力養成方法が載っていること。日本の労働人口や日本の平均給与を実際に知っている数字で推論してみる営みは、本腰入れてやってみると結構面白い。数字はそれ単体だけで見ても本質が分からないので、覚えるのにかなり苦労するし、すぐ忘れる。それが、比較したり他の数字と関連付けたりすることで初めて「実際にはこういう事を意味しているんだ」と実感できる。演習をやって、それが少し味わえたのが良かった。頭の体操として、演習で出てきたことを習慣化すると、すごい為になると思う。今度は実践できるように、手帳に書いておこう。。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ここに書かれていることは仕事で見たら当然と言えば当然のことのようだが、私生活でも常に数字を意識し、また具体的に数値に落とし込めるときは落とし込み、目標を具体化し逆算するというのは非常に大事だと思った。新聞に載ってる数値や、街中で見かける建物を高いと見るのではなく、何階かで見るなど常に数字を意識していこうと思う。普段数字を無機質なものとして見ているのは、その事柄に関心がないからであり、興味を持つことによって数字が有機的なものに見えるようになる。 数値化によって具体性が生まれ、それによって比較することができる。また比較する時、縦軸(過去ー現在)、横軸(他社、他国など)でそれぞれ比較することも大事だ。 数字自体は客観的だが、その数字の解釈にはバイアスがかかり主観的になる。そのことから、常にバイアスがかかった状態で見ているという意識が大事でもある。 様々な数値を関連させ、その数値のバックグラウンドを読みとくことや、日経株価の定点観測などできることを少しづつ行っていきたいと思う。
Posted by
ビジネスマンのための、というよりも、ビジネスマンになる前の学生のためのという感じ。 頭でっかちなビジネスマンにはなりたくない。
Posted by
GDPとは、国内総生産(Gross Domestic Product) 一定期間に国内で生み出された付加価値の総額 日本のGDPは、約500兆円 GDPが上がらないと、給料も上がらない。 ―― あなたは、中国で造られたものを、安い!と喜んで買っていませんか? その製品を製造するた...
GDPとは、国内総生産(Gross Domestic Product) 一定期間に国内で生み出された付加価値の総額 日本のGDPは、約500兆円 GDPが上がらないと、給料も上がらない。 ―― あなたは、中国で造られたものを、安い!と喜んで買っていませんか? その製品を製造するために必要な原材料費、人件費などの経費は、 中国に落ちるわけです。つまり、あなたが支払ったお金の何割かは、 中国に行くわけです。でも、日本で作ったものだったら、原材料は、 海外から輸入したものかもしれないけど、人件費などの経費は、 日本に落ちるわけですから、日本のGDPが上がるわけです。
Posted by
小宮一慶のビジネスマンのための「数学力養成講座」を読みました。 フェルミ推定関連の内容となっています。 本当?っといったところでは、GDPと日本人の平均年収 Amazonの書評にも記載されていましたが、 日本のGDPはおよそ500兆円といわれていて、そのうちの人件費は約6割...
小宮一慶のビジネスマンのための「数学力養成講座」を読みました。 フェルミ推定関連の内容となっています。 本当?っといったところでは、GDPと日本人の平均年収 Amazonの書評にも記載されていましたが、 日本のGDPはおよそ500兆円といわれていて、そのうちの人件費は約6割なので、人件費、つまり、私たちの給料に相当する額は300兆円 日本の人口が1.3億人で、働いているのはその半分で6000万人。 だから、6000万人で割ると、500万円が私たちの給料相当額。 ほんとか?てネットで調べてみたいところですが、それをやらないずぼらな私。 また、勉強になる点として、数字の見方の基本 (1)全体の数字をつかむ (2)大きな数字を間違わない (3)ビッグフィギュアをみる (4)大切な小さい数字にはこだわる (5)定義を正確に知る (6)時系列でみる (7)他と比較する でした。 どうも、数字って弱いんだよね。覚えられない。会話の中で具体的な数字をあげて会話できる人って格好いいですよね。 ということで、数学力養成講座でした。しかし、まずは、なによりも、関心を持つことが重要だそうです。 あと、日本経済新聞の数字の見方も解説されています。 なるほど、日経ってそうやって見るのかって思っちゃいました(^^;;
Posted by
数字の大切は普段の仕事から身にしみており、改めて痛感。 仕事以外でも経済の指標はざっくりとわかっているようになりたい
Posted by
他の著書「発見力」と内容が被っているところが多いように感じられた。 しかも、詳しくはそちらをどうぞ的だったりする。
Posted by
「発見力」に続き、購読。冒頭の「はじめに」で、本書の主題を簡潔に説明してくれているお陰で、以降の章は必要だと思う箇所だけ丁寧に読み進めば、短時間で効率的に情報が吸上げられると思う。著者の配慮を感じた。 また、本書で言う『数字が説得力を持たせる』という意味は、「数値により具体化...
「発見力」に続き、購読。冒頭の「はじめに」で、本書の主題を簡潔に説明してくれているお陰で、以降の章は必要だと思う箇所だけ丁寧に読み進めば、短時間で効率的に情報が吸上げられると思う。著者の配慮を感じた。 また、本書で言う『数字が説得力を持たせる』という意味は、「数値により具体化させることで、目標への距離(ギャップ)精度を高め、目標達成への具体的なプロセスを逆算し、具体化し易くなる」という点もそうだが、「数字を作ることで、自身の目標達成へのコミットメント(責任)を高めている」というも一因だと思う。 数字の見方に関しては、「数字自体は、何らかの比較を伴わないと、それが本質的にどう意味を持つものなのか判断できない」ので、時系列や他との比較を行うことや、数字の定義を正しく理解することが重要。また、定点観測などで数字の感覚を養い、自分の基準を持つことで、社会全体の動きが理解し易くなるとのこと。 最後に、章末の演習だが、著者の言う数字の見方のコツが体感でき、参考になった。
Posted by
押さえておくべき数字がコンパクトに纏まっていて素晴らしい。 ・うまくいっている会社の社長さんというのは、数字に強い、というか、数字の間違いにいち早く気づく ・日本のGDPは約500兆円 ・付加価値に占める人件費の割合(労働分配率)は半分強、60%=300兆円。 ・日本の就業者数...
押さえておくべき数字がコンパクトに纏まっていて素晴らしい。 ・うまくいっている会社の社長さんというのは、数字に強い、というか、数字の間違いにいち早く気づく ・日本のGDPは約500兆円 ・付加価値に占める人件費の割合(労働分配率)は半分強、60%=300兆円。 ・日本の就業者数はざっくり6000万人⇒一人当たりの平均給与は約500万人となる。 (実際は給与所得者が約4500万人で、その給与総計は200兆円弱。⇒450万円/人) ・日本の平均付加価値率(付加価値÷売上高)は0.3。 ・アメリカのGDPと人口は日本の約3倍(GDPは13兆ドル、人口は約3億人) ・世界全体のGDPは、約50兆ドル(日本とアメリカで約3割) ・総人口の21%が65歳以上の高齢者。最近生まれた子供は120万人。団塊ジュニアは200万人。
Posted by