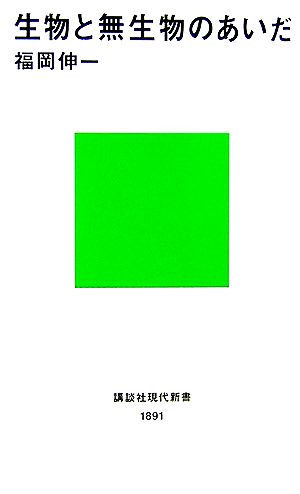生物と無生物のあいだ の商品レビュー
PCR検査の理屈が分かりました! 生物が原子に対してなぜこんなに大きいのか、や、エントロピー最大=死、それを食い止めるための代謝による絶え間ない動的平衡などの説明は大変面白かったです。 細胞膜という丈夫なバリアで守られた細胞が、作ったタンパク質をどのように外部に分泌するメカニズム...
PCR検査の理屈が分かりました! 生物が原子に対してなぜこんなに大きいのか、や、エントロピー最大=死、それを食い止めるための代謝による絶え間ない動的平衡などの説明は大変面白かったです。 細胞膜という丈夫なバリアで守られた細胞が、作ったタンパク質をどのように外部に分泌するメカニズムにも感心させられました。 こう言うことを明らかにするまでの研究者たちの情熱と努力に脱帽です。 野口英世の評価についてやポスドクなど日本の研究者が抱える問題にも触れているのも面白いと思う。 いろいろな研究者の生き方の紹介も興味深い。
Posted by
ブルーバックスでないのは、野口英世などの挿話があるからでしょうか、でしたら、表題に沿った内容を本旨として以下にまとめます。 生命とは何か?それは自己複製を行うシステムである。20世紀の生命科学が到達したひとつの答えがこれだった DNAを強い酸の中で熱すると、ネックレスの重なりが...
ブルーバックスでないのは、野口英世などの挿話があるからでしょうか、でしたら、表題に沿った内容を本旨として以下にまとめます。 生命とは何か?それは自己複製を行うシステムである。20世紀の生命科学が到達したひとつの答えがこれだった DNAを強い酸の中で熱すると、ネックレスの重なりが切断され、バラバラになる 構成しているのは4つ、アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T) 生命科学を研究するうえで、最も厄介な陥穽は、純度のジレンマという問題である。生物試料はどんなに努力を行って純化しても、100%純粋ではありえない。生物試料にはどのような場合であっても、常に、微量の混入物がつきまとう。これがコンタミネーションだ。 DNAこそが遺伝情報を担う物質である DNAは単なる文字列ではなく、必ず、対構造をとって存在している その対構造は、A-T,C-G という対応ルールに従う DNAは2本でペアリングしながららせん状に巻かれて存在している。今重要なのは、らせん構造そのものよりも、DNAがペアリングして存在しているという事実のほうである PCR ポリメラーゼ・チェイン・リアクション 任意の遺伝子を試験管の中で自由自在に複製する技術。もう大腸菌の力を借りることはない。分子生物学に本当の革命がおこったのだ。 2つの鎖を、センス鎖、アンチセンス鎖という ヒトのゲノムは、30億個の文字から成り立っています。1頁1000文字を印刷して、1巻1000頁としても、全3000巻を要する一大叢書となる。 遺伝子研究では、この中から特定の文字列を探し出さなければならない。 PCRとは、DNAの二重らせんでできていることを利用して、ソーティングとコピーを同時に実現するテクノロジーである DNAこそが、遺伝物質であるということがようやく広く認めるようになっていた。そうなれば、次のターゲットは、おのずと、DNA自体の構造を解くということになる。 DNAの結晶構造は、C2空間群という。2つの構成単位が互いに逆方向をとって点対称に配置された形をいう 摂取された脂肪のほとんどすべては燃焼され、ごくわずかだけが体内に蓄えられる、と我々は予想した。 ところが、非常に驚くべきことに、動物は体重が減少しているときでさえ、消化・吸収された脂肪の大部分を体内に蓄積したのである 生物が生きているかぎり、栄養学的要求とは無関係に、生体高分子も低分子代謝物質もともに変化して止まない。生命とは代謝の持続的変化であり、この変化こそが生命の真の姿である。 新しい生命観誕生の瞬間だった。 生命とは何か、それは自己複製するシステムである 秩序は守られるために絶え間なく壊されなければならない 生命とは動的平衡である流れである 細胞生物学とは、一言でいえば、「トポロジー」の科学である。トポロジーとは、一言でいえば、「物事を立体的に考えるセンス」ということである 細胞膜の薄さはたった7ナノメートルである プリオンタンパク質を完全に欠損したマウスは異常にならない。ところが、頭から3分の1を失った不完全なプリオンタンパク質、すなわち部分的な欠落をもつジグゾーパズルはマウスに致命的な異常をもたらしてしまった。 これをドミナント・ネガティブ現象という。タンパク質分子の部分的な欠落や局所的な改変なほうが、分子全体の欠落よりも、より優位に害作用を与える 目次 プロローグ 第1章 ヨークアベニュー、66丁目、ニューヨーク 第2章 アンサング・ヒーロー 第3章 フォー・レター・ワード 第4章 シャルガフのパズル 第5章 サーファー・ゲッツ・ノーベルプライズ 第6章 ダークサイド・オブ・DNA 第7章 チャンスは、準備された心に降り立つ 第8章 原子が秩序を生み出すとき 第9章 動的平衡(ダイナミック・イクイリブリアム)とは何か 第10章 タンパク質のかすかな口づけ 第11章 内部の内部は外部である 第12章 細胞膜のダイナミズム エピローグ ISBN:9784061498914 出版社:講談社 判型:新書 ページ数:285ページ 定価:880円(本体) 発行年月日:2007年05月20日第1刷発行 発行年月日:2007年09月25日第10刷発行
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
生物と無生物のあいだはなんなのか。 自己複製するもの。それが生き物の定義なら、脳細胞は一定数に達した後は増殖はしないようだ。 本書によると生物とは、動的平衡に流れるもの。 海辺の砂浜のように、常に砂は入れ替わるが、砂辺自体は同じ形で変化しない。 このように、細胞のタンパク質は常に入れ替わり続けるが、全体を見て人の形は変わらない。 なぜこのような事がおこるのか。それは、エラーが起こる前につねに細胞を取り換え続けることが リスクヘッジになるということ。 また、原子はなぜ、集まって人のような大きな個体となる必要があるのか。 それは、エントロピー増大の法則によってバラバラになるのを極力防ぐために、より数が集まった方がいいらしい?この辺は難しくてよくわからなかった。 そして、ウイルスは生き物なのか。これのはっきりした答えは書かれていなかった気がするが、 生物が動的平衡に流れるものであるなら、RNAを一本だけ持ち、核酸のかたまりであるウイルスは無生物ということなのか。 これを定義することに意味があるのかはよくわからない。ただ、自分は生き物であり、生き物とは何かを知ることは、自分とは何かを知ることになる。 人間が第一に存在するのではなく、細胞がより生きやすくなるために大きくまとまって人となったとわかれば、なんだか自我から少し解放されたような気分になる。 動的平衡の部分がイマイチ理解できてない気がするから、次の本も読んでみたい。
Posted by
こどものころ、「世にあるものは、空気も含めて全て原子からできている」「宇宙にある原子の数は不変」ということを何かで知ったとき、自分の体が原子でできていることが不思議でならなかった。当時は原子に粒粒のイメージを持っていて、粒粒がナゼ自分の形に留まっているのか、不思議だった。バラバラ...
こどものころ、「世にあるものは、空気も含めて全て原子からできている」「宇宙にある原子の数は不変」ということを何かで知ったとき、自分の体が原子でできていることが不思議でならなかった。当時は原子に粒粒のイメージを持っていて、粒粒がナゼ自分の形に留まっているのか、不思議だった。バラバラにならないの?って。 そして、自分の身体は原子からできているかもしれないが、自分の意識は何からできてるんだ?と、それも不思議だった。 意識についての不思議は未だに完全に不思議のまま。 身体についての不思議は、こども時代よりは腑に落ちた部分もある一方、理解した!わかった!とは全く言えない。 本書の動的平衡の話は、その身体の不思議に寄り添ってくれる話だった。私にとっては難解な箇所も多々あって理解しきれてはいないのだが。 引用交えての感想は読書メモ欄へ。 2023/8/26
Posted by
生物を生物と認識する要素は何か、を突き詰めた本。 遺伝子の二重螺旋構造やウイルスの発見時の経緯などが記載されていた。
Posted by
生物とは何かという疑問に一旦解答を与えてくれる一冊。 しかもいわゆる知識をただただ積み上げるだけではなく、やたらエモい描写で科学史や著者の実体験を交えながら「生き生きと」語られる。 読む前は「DNAが入っていれば生物でしょ?」みたいな雑な答えしかもっていなかったが、最後まで読めば...
生物とは何かという疑問に一旦解答を与えてくれる一冊。 しかもいわゆる知識をただただ積み上げるだけではなく、やたらエモい描写で科学史や著者の実体験を交えながら「生き生きと」語られる。 読む前は「DNAが入っていれば生物でしょ?」みたいな雑な答えしかもっていなかったが、最後まで読めば生物というもののダイナミズムがちゃんと「腑に落ちる」こと間違いなしだろう。
Posted by
とにかく文章が美しい。学術書なのかと思って読み始めましたが、エッセイに近い。日々の情景だけでなく研究や細胞の様子の描写もなんだか詩的で、言葉選びがとても素敵でした。 内容も難しすぎることはなく、中高生の理科で習った範囲で理解できます。やっぱり勉強ってしとくもんやね…。 個人的には...
とにかく文章が美しい。学術書なのかと思って読み始めましたが、エッセイに近い。日々の情景だけでなく研究や細胞の様子の描写もなんだか詩的で、言葉選びがとても素敵でした。 内容も難しすぎることはなく、中高生の理科で習った範囲で理解できます。やっぱり勉強ってしとくもんやね…。 個人的には、原子はなぜそんなに小さいか?の部分が納得感が強くて好きです。 あと、本の一番最後に書かれている「講談社現代新書」の刊行にあたって はとても良い文章ですね。背筋が伸びます。
Posted by
名著でした。 生命科学についての本で、 15章あるのですが基本的に、 ・エッセイ ・エッセイの流れを汲んだ生命科学の歴史的発見の話 という流れになっています。 エッセイの文章自体が本当に美しくて、作者は分子生物学の権威である福岡 伸一さん(坂本龍一さんの親友で『音楽と生命』...
名著でした。 生命科学についての本で、 15章あるのですが基本的に、 ・エッセイ ・エッセイの流れを汲んだ生命科学の歴史的発見の話 という流れになっています。 エッセイの文章自体が本当に美しくて、作者は分子生物学の権威である福岡 伸一さん(坂本龍一さんの親友で『音楽と生命』という共著も出せれています)なのですが、学者さんとは思えない文章です。 特に僕はDNAの螺旋を解き明かしていく話のあたりが面白かったです。 スタートからして、実は野口英世(現在の1000円札)の実績はほぼすべて過ちで現在は否定されているという話から始まります。 非常に専門的な話を書いているんですが、そのエッセイの入口のおかげで頭に入っていきやすくなっていて、どんな人にもオススメです。 今まで読んできた本の中でTOP10に入るほどの名作中の名作でした。 https://amzn.asia/d/11vTi9Y
Posted by
生物の構造についての説明と、それを解明するアカデミックな世界での研究者の奮闘が描かれた本でした。 本書を手に取ったのは、生物の構造に興味があったからで、研究者の奮闘部分は読み飛ばしましたが、それでも十分楽しめました。生物の定義で、 •自己複製を繰り返すことができる •動的平衡...
生物の構造についての説明と、それを解明するアカデミックな世界での研究者の奮闘が描かれた本でした。 本書を手に取ったのは、生物の構造に興味があったからで、研究者の奮闘部分は読み飛ばしましたが、それでも十分楽しめました。生物の定義で、 •自己複製を繰り返すことができる •動的平衡を保っている この2点があげられていましたが、特にこの動的平衡が興味深かったです。生物を構成する分子は常に入れ替わっており、確固たる「個体」がそこにあるのではなく、流動的な分子の滞留が形を成しているという「現象」に近いのが生物なのだと理解しました。DNAの話も面白くて、刊行当時は一般的な認知度は少なかったと思いますが、コロナ禍を経た2023年現在では一般的に認知されているPCRやRNAの説明も勉強になりました。
Posted by
情報のやり取りをしているわけではない(?)のに、研究者たちのなかでは色々な実験が同時並行で行われてるって不思議だなあ
Posted by