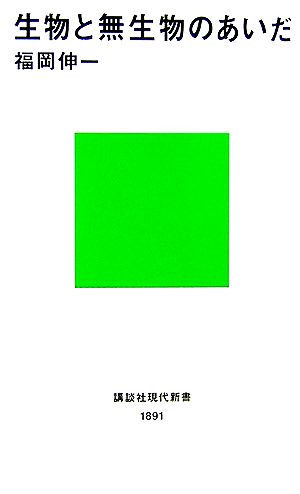生物と無生物のあいだ の商品レビュー
分子生物学の歴史を辿りつつ、筆者の語る動的平衡について生物がもつその神秘性に触れられる良書。学生時代にこういうものに触れていたらきっと進む先ちがっていたのかな。。なんて思うけど今からでも遅くはないか?
Posted by
先日読んだ「最後の講義」がとても面白かったので、2007年に出てしかもよく読まれたという当書を読みたくて♪ 生物学にとんと疎い私にも分かり易くて、挿話されている小さな逸話も興味深いものばかりでした。 とりわけ野口英世の評価が日米で天と地の差があるのにはびっくりでした。 なんとも奥...
先日読んだ「最後の講義」がとても面白かったので、2007年に出てしかもよく読まれたという当書を読みたくて♪ 生物学にとんと疎い私にも分かり易くて、挿話されている小さな逸話も興味深いものばかりでした。 とりわけ野口英世の評価が日米で天と地の差があるのにはびっくりでした。 なんとも奥深い生物学の世界ではあるけど、ここまで噛み砕いて貰えるととても面白く楽しく読むことが出来ますね。 そして人類よ謙虚であれ!との著者からのメッセージも伝わってきました。
Posted by
本を読むのそれほど時間はかからなかった。しかし、ノートを作ろうと思ったところからが、大変だった。結局、ブクログの本人だけが見えますページにたくさん気になった文を書き取った。それでも、私ができたのは、本の半ばまでだ。実をいうと、この本は二つぐらいに分かれている。ひとつは、生命とは...
本を読むのそれほど時間はかからなかった。しかし、ノートを作ろうと思ったところからが、大変だった。結局、ブクログの本人だけが見えますページにたくさん気になった文を書き取った。それでも、私ができたのは、本の半ばまでだ。実をいうと、この本は二つぐらいに分かれている。ひとつは、生命とは何か、あとひとつは、その生命はどう維持されるか。前のひとつは、たぶん量子生物学のようなものと、密接にこれから関わっていくのだろう。エントロピーゼロの死の世界が成長の最終地点なのだろうか? 誘導し、誘導される分子レベルの流れは、意味的にもっと上位の流れに連なっているのだろうか。すのままの目で自然をある程度の期間眺めた経験があると、物の環と、生命の環が交錯する姿を見るのは珍しくない。命が分子の流れの淀みのようなものだとするとそれが終わっても過程となる。不思議な話がたくさんある。太っているからといっても、細胞は入れ替わる。なら、最初にもどって痩せてもいいはずだがそうはならない。だとすれば、何がそれを覚えているのだろうか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
■ひとことで言うと? 生命とは、動的平衡にある系(システム)である ■キーポイント - 動的平衡 - 局所局所では破壊と再構築を繰り返しつつ、系(システム)全体としての秩序が維持されている状態 - 生命は負のエントロピーを食べて生きている(自然的な崩壊スピード < 意図的な破壊・再構築スピード を維持することで、エントロピー増大の法則に抗っている) - タンパク質の相補性 - タンパク質は柔らかな相補性を持つ - 外的な状況変化の即時把握(即応性) - 状況に応じた柔軟な挙動(柔軟性) - 異常状態での機能補完(代替性)
Posted by
「生命とは自己複製を行うシステムである。」1953年ジェームス・ワトソンとフランク・クリックの二人による1000語(1ページ)の論文が「ネイチャー」に発表され、ノーベル賞を受賞する。DNAが互いに逆方向に結びついた2本のリボンからなっているモデルで二重ラセンの対構造が直ちに自己複...
「生命とは自己複製を行うシステムである。」1953年ジェームス・ワトソンとフランク・クリックの二人による1000語(1ページ)の論文が「ネイチャー」に発表され、ノーベル賞を受賞する。DNAが互いに逆方向に結びついた2本のリボンからなっているモデルで二重ラセンの対構造が直ちに自己複製機構を示唆する‥‥このような発見とそれにまつわる生命探究の歴史がその時々に活躍した研究者に添って紹介される。特に華々しい栄誉に浴した人の陰で実質的で決定的な寄与にもかかわらず運悪く受賞できなかった人々(アンサングヒーロー)の話も丁寧に紡がれ、土台を築いた人々への賛歌が印象的である。 そうした観点からすると、筆者の野口英世の評価は相当ネガティブである。日本人が観光バス仕立てで群がるロックフェラー大学の胸像はいつもは注目されず埃をかぶっている。「単なる錯誤だったのか、故意に研究データを捏造したものなのか、自己欺瞞によって何が本当なのか見極められなくなった果てのものなのか、それは今となっては確かめるすべがない。恩師フレクスナーへの恩義に過剰反応し冷遇した日本アカデミズムを見返す過大な気負いが要因であり、典型的な日本人であった」と筆者は言う。 生涯かけて誠実に凄まじい努力をした世界の科学者達の偉業を紹介する前段で「典型的な日本人」野口のことを語るのは、生命科学の真理を発見する競争で、ルールと人間性の重要さを先ずおさえておくという筆者の強い意志を感じる。 筆者自身の研究も本音で丹念に語られることによって、世界トップクラスの生命科学の開発競争実態がリアルに伝わり、哲学的で示唆に富む描写は本物の科学者の人間的深さを感じさせる。 DNAのことはこれを手がかりにもっと知っていきたい。
Posted by
福岡先生の思い出と生物学の歴史の交わりが自然に書かれていてよい。 『生物進化の物理法則』をまた読み返したくなった。
Posted by
生物についての知識はあまりないけれど、生命の不思議さ、精巧なつくり、動的な平衡など、初めて知ったことが多く、興味深かった。著者の文章表現も良かった。
Posted by
読み終わって不思議な感じになった。村上春樹さんの本を読み終わった時と同じく、世界がクリアに見え、音が良く聞こえる感覚。生命の不思議が科学的に、ある時は詩的に語られる。ニューヨークやボストンの情景を絡めDNA、タンパク質、そして生命の持つ力が直接的に心に響き渡った。GP2蛋白の精製...
読み終わって不思議な感じになった。村上春樹さんの本を読み終わった時と同じく、世界がクリアに見え、音が良く聞こえる感覚。生命の不思議が科学的に、ある時は詩的に語られる。ニューヨークやボストンの情景を絡めDNA、タンパク質、そして生命の持つ力が直接的に心に響き渡った。GP2蛋白の精製に胸が躍り、ノックアウトマウスに驚愕する。自然や生命の尊さを実感できる良書であることは間違いない。大好き度❤️❤️❤️
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
生命とは何か?といった根元的な問いに対し、二十世紀の生命科学が到達したひとつの答えである「自己複製を行うシステムである」から「生命とは動的平衡にある流れである」と再定義した本書。 すべての物理現象に押し寄せるエントロピー増大の法則に抗う唯一の方法は、やがては崩壊する構成成分をあえて先回りして分解し、乱雑さが蓄積する速度よりも早く、常に再構築を行うとは、なんと私たちの生命は神秘的かと改めて感じた。 前半部のPCR発明やDNA二重らせん構造発見のストーリーは非常にスリリングで、著者特有の詩的な文章表現も相まって最も知的興奮を覚えた個人的なハイライトとなった。 後半部はやや専門性が増し難解なため、ついていくのに必死で前半ほど楽しめなかったが、著者の研究内容や研究者としての生活を垣間見れることができ興味深く読めた。
Posted by
グラント クレジット ピア・レビュー dynamic equilibrium 形の相補性 ルドルフ・シェーンハイマー ロザリンド・フランクリン 野口英世
Posted by