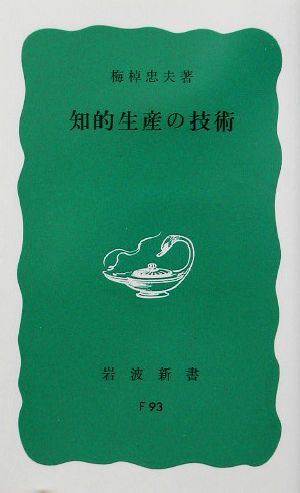知的生産の技術 の商品レビュー
明和電気のオススメで読んでみました。 カード利用の話は、なかなかいいな。 40年前位に書かれた本だとは、驚き。今でも十分に利用できる部分がある。ちょっと採用してみよう、と。
Posted by
本のタイトルは当然知ってました。1969年の出版とかなり以前の作品のために敬遠してましたが…今さまざま出ている知的生産の整理や発想の原点であり、しかも思いのほかわかりやすい。川喜田二郎さんと交流があったことも本書で知りました。 ツールの進化はあれども、情報整理の方法は変わっていな...
本のタイトルは当然知ってました。1969年の出版とかなり以前の作品のために敬遠してましたが…今さまざま出ている知的生産の整理や発想の原点であり、しかも思いのほかわかりやすい。川喜田二郎さんと交流があったことも本書で知りました。 ツールの進化はあれども、情報整理の方法は変わっていないとわかりました。人間の性質はそう簡単には変えられそうにないのと同じデスね(^ ^)
Posted by
情報の記録、整理、構築の点では学ぶことが少なくなかった。 発見の手帳:発見や自分の着想をきちんとした文章で書く。 索引をつくる。そのために標題をつけておく。情報の整理、情報間の相互連関を見つけることもできる。 カードの分類を決めない。決めると思想に枠を設けることになる。 こざね...
情報の記録、整理、構築の点では学ぶことが少なくなかった。 発見の手帳:発見や自分の着想をきちんとした文章で書く。 索引をつくる。そのために標題をつけておく。情報の整理、情報間の相互連関を見つけることもできる。 カードの分類を決めない。決めると思想に枠を設けることになる。 こざね法:B8判の紙切れに書き出して、つながりのあるものを並べ、ホッチキスでとめる。こざねの列を並べて文章の構成を考える。 学生時代に読まなったため読む機会を逃した感を持っていたが、遅すぎることはなかった。 <関心をもった本> 私の読書法(大内 兵衛)
Posted by
ほぼ日で紹介されてるのを見て読み始めた。 昔の本だけど、今でも応用できる考え方がたくさん。 この本を読んで、EVERNOTE使うようになった。 情報をどう整理してどう活用するのか?を考えるようになった。
Posted by
ある有名なブログで触れられていたので気になって読んでみたけれど、目からウロコ。40年も前に書かれた本とは思えない新鮮さ。書類整理などの具体的な方法は古さも感じるけれどこの「知的生産の技術」は著者も述べている通り発展途上のシステムなのであり、現在の技術の進歩、個人の状況に合わせて柔...
ある有名なブログで触れられていたので気になって読んでみたけれど、目からウロコ。40年も前に書かれた本とは思えない新鮮さ。書類整理などの具体的な方法は古さも感じるけれどこの「知的生産の技術」は著者も述べている通り発展途上のシステムなのであり、現在の技術の進歩、個人の状況に合わせて柔軟に変えていけばいいのだと思う。
Posted by
ブログに書きました。 http://t-katagiri.blogspot.com/2011/05/blog-post_23.html
Posted by
すばらしい。目からウロコ。 40年前か。学生運動くらいか。 よみやすい。 そんな昔に書いたように感じない。 当時のアヴァンギャルドが現代に受け入れられてるってことか。
Posted by
この本に出てくるカードの代替品として、evernote等のツールを活用すれば、この本の時代(1969年)の数倍から十倍の効率で知的生産は進むと思う。 また、この本の読書法は最近の同様の本のテクニックの源になっている気がする。
Posted by
カードをつかった情報の記録や、整理法、読書法など参考になる点が多い。 1969年に書かれていることもあり、「今」とは合わない部分や、すでに解決済みな問題の提起なんかもあるが、梅棹忠夫という人は物事の本質と将来のあり方を正確に見れる人だと思った。
Posted by
ダ・ヴィンチがメモ魔であった話からノート術、カードの使い方などが書かれている。一時期、流行ったカードの運用などは、この本が元祖だ。 版を重ねている古典的な名著に★2つとは失礼と言われるかもしれない。★2つは現代(2011年)に通用する実用書としての価値であり、1969年当時の知...
ダ・ヴィンチがメモ魔であった話からノート術、カードの使い方などが書かれている。一時期、流行ったカードの運用などは、この本が元祖だ。 版を重ねている古典的な名著に★2つとは失礼と言われるかもしれない。★2つは現代(2011年)に通用する実用書としての価値であり、1969年当時の知識人と呼ばれる人々がどのように情報処理や知的活動を行ってきたかを知るための歴史的な資料としては一級のものとは思う。 この本を読むと、この40年間、いかに情報化が進んだことが分かる。昔は情報を整理することに大きな意味があったわけですが、今や整理する必要すらない。 デジタル化して、最初にタグ管理さえ行えば、検索するだけで事が足りる。ということで、同書はアナログ時代の記念碑的な著書であっても、そのまま通用する部分はあまり多くない。 読書論も当時の雰囲気を伝えるものがあって、それはそれで興味深いのだが、実用には向いていない(少なくとも、私には)。 梅棹さんは「本というものは、はじめからおわりまでよむものである」と書く。それが著者の考えを正確に理解する方法だというわけだが、ちょっと待って欲しい。私たち読者は著者のために読んでいるわけではない。目的は自分の知識欲や情報を仕入れるためだ。読者には「全部読まない権利」もある。 70年代は全部読みが主流であり、それだけ時間もあったのだろう。それはそれで、うらやましい。
Posted by