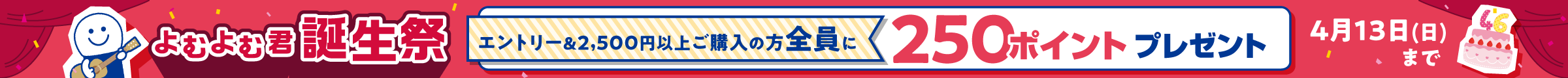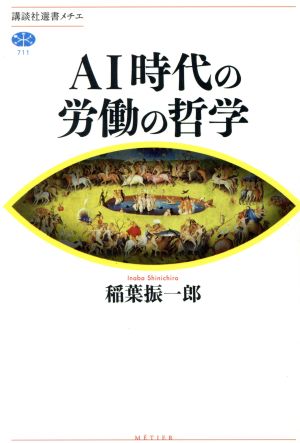- 書籍
- 書籍
AI時代の労働の哲学
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
AI時代の労働の哲学
¥1,760
在庫あり
商品レビュー
4
6件のお客様レビュー
経済の構造について述べた本。理系の書というよりは文系に内容が寄った書である。 AIが導入されることで結局世の中ってどのように変わるの?という点をマルクスなどを引用しつつ考察していく。マルクスのいう資本に知識を当てはめたり、機械化をAIに当てはめるなどの応用をしていくさまが見ていて...
経済の構造について述べた本。理系の書というよりは文系に内容が寄った書である。 AIが導入されることで結局世の中ってどのように変わるの?という点をマルクスなどを引用しつつ考察していく。マルクスのいう資本に知識を当てはめたり、機械化をAIに当てはめるなどの応用をしていくさまが見ていて楽しかった。 AIが発展していっても、結局その影響としては産業革命による機械化のときの影響の延長線上であるという点が自分にはない発想であった。結局のところ、AIが導入されることで生じることは、AIによる雇用減とAIによる生産性増大のみである。後者の影響が前者を上回れば問題としては生じないというスタンス。ただ、後者の利益が平等に配分されるような社会システムでないと不平等が蔓延してしまうという点には自覚的でなければならない。 他に、人-物の図式の中にAIが収まればいいが、人にも物にもAIが収まらず、その中間に位置し始めると身分制の再来が危惧されるという点が興味深いと感じた。AIよりも能力が上である人間と、能力が下である人間の両方が生じてしまうような状況下では、身分制が起こってしまうのは必至であろう。不平等を拡大させるという性質がAIにあるのだろうということに気づいた。すると、AIが人口に膾炙している現在・そして広く流布していく将来において、社会主義的思考が必要なのかもしれない。ただ、社会主義ではイノベーションは生まれにくい。従って、国民一人一人が不平等を是正する姿勢を見せることが大切なのかもしれない。 AIは、我々の善性を確かめる試金石となるのかもしれないと感じた。
Posted by 
「AIが…」と特殊に語られるけれども、基本を眺めなければ煽られるだけで理解ができないもの。AIに興奮したい人向けではないけれど、僕には必要な理解になった。 ただどううなのだろう。経済や社会、労働などのほかに、文化やそれを捉える人々のスロー回路の変化など。(風土性があるとは思う)...
「AIが…」と特殊に語られるけれども、基本を眺めなければ煽られるだけで理解ができないもの。AIに興奮したい人向けではないけれど、僕には必要な理解になった。 ただどううなのだろう。経済や社会、労働などのほかに、文化やそれを捉える人々のスロー回路の変化など。(風土性があるとは思う) 僕の興味の軸はおそらくこちらになるのだろうなと思った。しかし社会の本流は経済的なことなのだろうから、一度ゆっくりと読んでみたのはよかった。
Posted by 
人工知能の発達によって人間の仕事がうばわれるのではないかという問いかけがなされる現在において、あらためて労働をめぐる経済学や社会哲学における議論の蓄積のなかから、この問題について考えるための手がかりをとりあげなおし、人工知能がわれわれにもたらすインパクトの本質について考察をおこな...
人工知能の発達によって人間の仕事がうばわれるのではないかという問いかけがなされる現在において、あらためて労働をめぐる経済学や社会哲学における議論の蓄積のなかから、この問題について考えるための手がかりをとりあげなおし、人工知能がわれわれにもたらすインパクトの本質について考察をおこなっている本です。 著者は、ロックやスミス、ヘーゲル、マルクスなどの思想を渉猟し、資本主義における労働や疎外について彼らがいったいどのような思索を展開してきたのかということをたどっていきます。そうした枠組みを踏まえたとき、人工知能が人間の仕事をうばうという問題は、それが管理業務のようなものにまでおよぶことになるかもしれないとはいえ、従来の社会哲学において議論の対象となってきた枠組みのなかに収まるのではないかという見通しが示されます。 他方で、人工知能が道具以上の存在になって、人間の「内面」や「意識」にあたるものをそなえるようになったとすれば、現実には人びとに大きな葛藤をもたらすことになるとはいえ、それは人工知能を人間社会のメンバーに迎え入れることに対する抵抗感にもとづくものであり、本質的にあたらしい問題が生じるわけではないとされています。そのうえで、むしろ人間の「心」をもたないような人工知能にわれわれがかかわっていく場面において、人と物の二分法という枠組みそのものが問いなおされるという新たな問題が生じるのではないかという展望が示され、倫理学的な問題にまで踏み込んで考察がなされています。 人工知能についての問いを切り口にした、労働の思想史という印象です。
Posted by