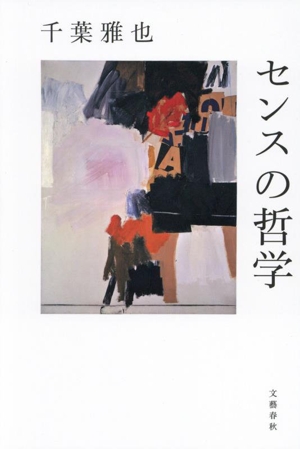
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1215-02-00
センスの哲学
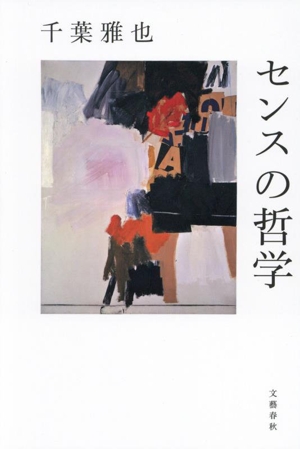
定価 ¥1,760
1,375円 定価より385円(21%)おトク
獲得ポイント12P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:1/14(水)~1/19(月)
店舗到着予定:1/14(水)~1/19(月)
店舗受取目安:1/14(水)~1/19(月)
店舗到着予定
1/14(水)~1/19

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
1/14(水)~1/19(月)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 文藝春秋 |
| 発売年月日 | 2024/04/05 |
| JAN | 9784163918273 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
1/14(水)~1/19(月)
- 書籍
- 書籍
センスの哲学
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
センスの哲学
¥1,375
在庫あり
商品レビュー
3.7
196件のお客様レビュー
センスの〈良さ〉は、ものごとを『意味的(何かのモデル=意味を目指す)』にどうするかではなく、『リズム(凸と凹)』の問題として「どう並べているか」という意識でものに関わり始めることが最初の一歩になる、と。 私たちはどうしてものごとの『意味』を追求してしまいますが、先ずはものごとの『...
センスの〈良さ〉は、ものごとを『意味的(何かのモデル=意味を目指す)』にどうするかではなく、『リズム(凸と凹)』の問題として「どう並べているか」という意識でものに関わり始めることが最初の一歩になる、と。 私たちはどうしてものごとの『意味』を追求してしまいますが、先ずはものごとの『動き(リズム)』に集中してみたら、ということでしょうか 本の表紙の絵画、アメリカの美術家ウラシェンバーグの『Summer Rental +1』を眺めて感じてみてはどうでしょうか。分かるような分からないような…
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
センスとは上手よりヘタウマ。モデルの再現から降りる。強度=リズム=デコボコ。意味から離れてモノをリズムとして見る。ビートとうねり。生物は安定を求めるが、わざと不安定、緊張の状態を作り出して、それを反復するのを楽しむ。目的達成を遅延し、余計なサスペンスを楽しむこと=丁寧に生活を楽しむこと。意味や目的からリズムへ、リズム=うねりとビートに乗る。意味のリズム=距離のデコボコ。予測誤差の最小化。リズム=「反復の予測と予測誤差という差異」のパターン認識。フレームの拡大→外れの経験をリズムにして平気になる。他方、平穏以上の刺激を求める。抽象化。客観性はなく、繋がるかどうかは設定次第。偶然への向き合い方の多様性→リズムの多様性→個性的なセンス。人生の途中のとりあえずの手持ちの技術と、自分から湧いてくる偶然性で何ができるか、と考える。「まず動こう」=リズム形成。途中でブラブラする、途中で視線を散歩させるような余裕の時間が芸術鑑賞の本質。人間は反作用が多様→遅延→行動の多様性。芸術は多様性、相対性も教えてくれて、人生のリズムもいろいろでいいじゃないか、ということになる。人間の生活は、目的達成と途中の宙づり状態を味わう不安混じりの享楽。個性とは何らかの反復=身体の癖。反復と差異のバランスという意味でのセンスの良さvs宿命的に何かに取り憑かれてしまうアンチセンス。センスの良し悪しとアンチセンスが拮抗するところが日常。アンチセンスという陰影を浴びてこそ真のセンス。
Posted by 
書いてあることは理解できるし共感もできるが、不完全燃焼な感じがしてしまう。 自分が美術に触れているからかも知れないが自分が普段制作する上で感じていることと筆者の考えの間に少しズレが生じてしまい全てに理解、共感は出来なかった。
Posted by 


