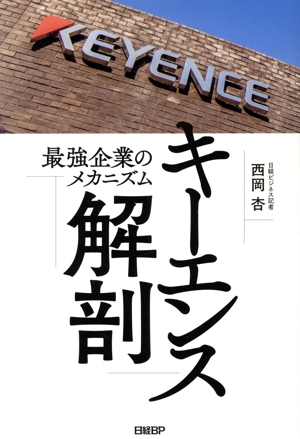キーエンス解剖 最強企業のメカニズム の商品レビュー
最強企業キーエンスの内情に迫る著書。性弱説に基き仕組みで打ち取る。軍隊のような営業スタイルかと思っていたが、仕組みやインセンティブを工夫し、徹底的にお客様のためにという風土を醸成している。そりゃ従業員は成長するでしょう…
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
転職斡旋をしている方々から、マネージャー・課長以上の管理職という役割での応募があった場合、キーエンスの人であれば係長・主任レベルの人からの応募でも会っておくという趣旨のコメントを読んだことがあります。キーエンスとはどんな会社なのだろう?と興味を持ちました。そして手にしたのが、高収益をあげており、従業員の給料も高額である会社、キーエンスを知ることができそうな本書です。 工業用の機器を販売している会社です。製造業の中ではトヨタカンバン方式という手法が広く認知されており、できるだけ在庫を抱えず適正な稼働を生み出すことが良いとされています。しかしながら、このキーエンスという会社は、在庫を持たないという発想ではなく、完成品の在庫をある程度抱えることで、注文から即納品することができています。商談の時には、デモで操作性の簡易さを実演して、顧客が望んでいる以上の商品提供ができています。 営業部門向け情報システム(SFA)が盤石に機能していることも本書を読むとわかりますし、営業マンが日々先輩社員とともに切磋琢磨しているロールプレイという仕組みを通して、販売力向上に常に取り組んでいたり、数値化と仕組みをきっちりと構築してビジネスを進めている素晴らしい企業だと理解しました。 真似できるところは、すぐにでも真似して良いと思うのですが、簡単にはいかないでしょう。自社の指標を個人の行動にまできちんと落とし込むことが必要です。その行動が、きちんと業績にプラスの影響が与えられるものかを確認できて良い循環が生まれます。私の中でキーエンスブームがしばらく続きそうです。
Posted by
平均年収が約2000万と世の中に最強の企業として知られているキーエンスであるが、なぜ最強なのか。 これから就活を始める読書としては、キーエンス独自の風土がキーエンスを最強たらしめている理由であると思う。ロープレに対するこだわりや営業の数など最強には最強の所以があった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
収益トップ企業の中身を知りたく読破。 交渉履歴の共有。誰に会うか、何が不足しそうか、他にお困りの方はいませんか?〜とにかく幅広にあっている。分単位での日誌、面談後5分以内に記録する文化。 18時からロープレを10分から15分開始。顧客側もさまざまな設定。年齢は関係なく改善点を言い合う。KPIがプロセス評価〜どれだけ実演したか。電話の件数。ロープレには台本がある。より細かな具体的な回答。分析シート〜累積取引社数、取引に関わった人数、商談に関わった人数、訪問者数、飛び込み回数、電話の発受信数、、、3人以上が打率が高い。ハッピーコール〜部下の提案がどうだったか上司が確認する。補足することが目的。電話も上司が横で聞く。営業がどこまでその先を知ってるか。現場からのニーズカード。何件から聞いたのか。即日回答! やっていることはシンプルだがその精度や徹底ぶりが凄かった。モチベーションも維持されており理想的な企業運営。学びが多く初の星5つ。
Posted by
普通かもしれないことを徹底的にやり切ると果てしなく遠くに行けることがよくよくわかる一冊。普通を徹底すると普通ではなくなりますね。すごい組織哲学だと思います
Posted by
粗利益8割。そこだけを切り取って見ていてはキーエンスの本質はわからない。 「企業は人なり」がふさわしい会社だ。
Posted by
キーエンスがなぜ高付加価値なのかが分かる一冊 他社でも取り入れられる取り組みや考え方が多く、勉強になった
Posted by
大きな利益を生み出し、社員が多くの報酬を得ることで有名なキーエンス。 その利益を生み出しているのは、商品ではなく人だった。 僕が知っているキーエンスの特徴は、この程度だった。 利益率の低い事業はしない。 オーダーメイドの商品は作らない。 どんなものも翌日納品。 こういう仕組み...
大きな利益を生み出し、社員が多くの報酬を得ることで有名なキーエンス。 その利益を生み出しているのは、商品ではなく人だった。 僕が知っているキーエンスの特徴は、この程度だった。 利益率の低い事業はしない。 オーダーメイドの商品は作らない。 どんなものも翌日納品。 こういう仕組みをつくれば、誰でも利益を生み出せると、浅はかに考えていた。 しかし、 これらの意思決定や行動をするのは、紛れもなく社員である。 では、仕組みさえ作っておけば、社員は忠実に動いてくれるのだろうか。 キーエンスでは、そうは考えていない。 人はすぐに怠けるし、意志の力だけで自分の行動を完全にコントロールすることはできない。 人は生まれながらにして弱い“性弱説”を根底に、それでも人が行動し、成果を出す仕組みを作っている。 たとえばセールスについて、うまくいかなかったらフィードバックを受けて反省すべき、と分かっていても、実際に実践している人がどれだけいるだろう。 しかも、大事なのは「“反省”をどう活かすか」だ。 キーエンスの営業は、毎日、セールストークのロープレを繰り返し練習することが義務付けられている。 ロープレでは上司が顧客役となり、様々なタイプの顧客を演じ、ロープレ後にはフィードバックをする。 これを毎日繰り返していれば、うまくならないわけがない。 また外出報告書という、とても面倒くさそうな制度もある。 外回りの営業は、事前に訪問予定を報告する。時間と相手先だけでなく、どのような目的で何を提案しにいくのかまで報告する。当然帰社後には、実践を報告する。しかも1分単位で。 この外出報告書は、上司が部下の行動を監視するためにあるわけではない。 外出報告書を作成する段階で、営業員は訪問先で何をするのか事前準備をすることになる。事前準備の有無により、営業成果が変わることを知っているからこそ、事前準備を“外出報告書”という形で仕組みがしたのだ。 実際に働いている社員はどう感じているのだろう。 「監視されている」と窮屈さを感じていないのだろうか。 どうやら、そうではないらしい。 キーエンスの仕組みに則って仕事をすることで、誰でも成果を上げることができ、顧客が満足し、会社は発展し、自身の報酬も増える。この大きなサイクルを理解しているために、むしろ活き活きと活力ある職場になっているらしい。 つまり、全体最適こそ、自分の利益だという考えが浸透している。 本書は最強企業を作っているキーエンスの人事の仕組みを紐解く良書だった。 経営者はもちろん人事担当者や部門責任者には、参考になる部分がたくさんあるだろう。 最後に、調べたわけではないが、この本には「モチベーション」に関する記述はなかったように記憶している。 マネジャーたちが日々上げようとしている“社員のモチベーション”。実は経営には直接関係ないのかもしれない。
Posted by
目標を明確にし、その進捗を数値化して徹底的に見える化することの重要さを感じた。日々の仕事で目の前の仕事に追われ、目的・目標が見えなくなってしまうことは多々あるので、改めて目的・目標を掲げ、それに向けた行動を取りたいと感じた。 その成果の見える化は、自分の仕事の中では何をパラメータ...
目標を明確にし、その進捗を数値化して徹底的に見える化することの重要さを感じた。日々の仕事で目の前の仕事に追われ、目的・目標が見えなくなってしまうことは多々あるので、改めて目的・目標を掲げ、それに向けた行動を取りたいと感じた。 その成果の見える化は、自分の仕事の中では何をパラメータとして設定するか難しいが、何か数値で示せるものを掲げ、日々のモチベーションアップに繋げたいと思う。これは管理する側としても周囲を動かす原動力に成りうると感じた。
Posted by
キーエンスの文化と概念を知ることができた。 経営者の強い意志で組織が構造化され、目標、評価基準、仕事の役割分担が明示されているからこそ、各々の能力を発揮することに注力できるのだとも思った。ただ、日本の大企業が全てそうかと言われると疑問であり、この働き方を模写する為には、経営判断が...
キーエンスの文化と概念を知ることができた。 経営者の強い意志で組織が構造化され、目標、評価基準、仕事の役割分担が明示されているからこそ、各々の能力を発揮することに注力できるのだとも思った。ただ、日本の大企業が全てそうかと言われると疑問であり、この働き方を模写する為には、経営判断ができる立場の人から取り組まないと無理だと思う。実際そうなったとしても、上司、先輩、同僚に染み込んだ古い体質のマインドはそう簡単に変わらない。 顧客対応のロープレは比較的取り入れ易そう。
Posted by