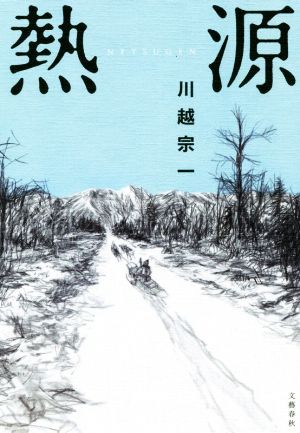熱源 の商品レビュー
最初の方はどことなく コメディチックで 楽しく読めていたけど 次第に昨今の世界情勢のことも 考えてしまったりして 重い何かを投げかけられた 読後感になった いつの時代も犠牲になるのは 辺境や弱い立場の人々で 彼らが戦争を望んだ訳でもないのに アイデンティティを奪われ 従わざるを...
最初の方はどことなく コメディチックで 楽しく読めていたけど 次第に昨今の世界情勢のことも 考えてしまったりして 重い何かを投げかけられた 読後感になった いつの時代も犠牲になるのは 辺境や弱い立場の人々で 彼らが戦争を望んだ訳でもないのに アイデンティティを奪われ 従わざるをえないように コントロールされていくだなと 思うと苦しくなった 過去に読んできた本や漫画と 気になって手に取った本の世界が 重なっていて 単独で読むより 重奏的に楽しめた時 読書してきて良かったなぁと思う ブックオフにて購入
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
アイヌのことが知りたくて読みましたが、直木賞作品とは知りませんでした。けっこう壮大なスケールです。 ロシア人、日本人、ポーランド人、リトアニア人といろんな人種が出てくるけれど、アイヌこそ誇り高き民族だと感じます。 「どうして誰もこの島を放っておけないのだ。人が住んでいる。ただそれだけではどうしていけないのだ。どうしてこんな嵐が吹き荒れるのか」砲弾の飛び交う中で叫ぶアイヌの女性。今も世界のあちらこちらで起きている戦争の愚かさ、はかなさを思います。 登場人物の容赦ない死別には悲しみが募ります。自分の妻子を捨てて祖国へと向かったブロニスワフには生きて再びサハリンに戻って欲しかった。
Posted by
アイヌの歴史史実を元にした作品。勉強にもなるし、途中に出てくるアイヌ料理の泥を使った料理の件で思わず笑ってしまうユーモアもあるが、トータルでは突出したものとは感じなかった。ただ、読了後に登場人物を調べると本当に史実だったのだとびっくりもして、そこを掘り起こしたのはすごいなと思う。...
アイヌの歴史史実を元にした作品。勉強にもなるし、途中に出てくるアイヌ料理の泥を使った料理の件で思わず笑ってしまうユーモアもあるが、トータルでは突出したものとは感じなかった。ただ、読了後に登場人物を調べると本当に史実だったのだとびっくりもして、そこを掘り起こしたのはすごいなと思う。直木賞。
Posted by
読了するのに時間がかかってしまったが、とても大切なメッセージが含まれている作品だった。 今まで、アイヌ民族のことはあまりよく知らなかったが、彼らの民族としての葛藤と誇りを知ることができた。 「アイヌって言葉は、人って意味なんですよ」 強いも弱いも、優れるもの劣るもない。生まれた...
読了するのに時間がかかってしまったが、とても大切なメッセージが含まれている作品だった。 今まで、アイヌ民族のことはあまりよく知らなかったが、彼らの民族としての葛藤と誇りを知ることができた。 「アイヌって言葉は、人って意味なんですよ」 強いも弱いも、優れるもの劣るもない。生まれたから、生きていくのだ。すべてを引き受け、あるいは補いあって。生まれたのだから、生きていいはずだ。(p375) アイヌ民族に限らず、すべての民族を超えた普遍的なメッセージだ。
Posted by
時代は明治維新から戦後まで。 場所は樺太。 北海道に行ったことはあるものの アイヌの人たちの生活など見たこともないし 文献など読んだ事もないので どういうものなのだろうと 友人らの紹介もあって 読んでみました。 まず最初に くじけそうになったのは アイヌの人の名前。。。 一度...
時代は明治維新から戦後まで。 場所は樺太。 北海道に行ったことはあるものの アイヌの人たちの生活など見たこともないし 文献など読んだ事もないので どういうものなのだろうと 友人らの紹介もあって 読んでみました。 まず最初に くじけそうになったのは アイヌの人の名前。。。 一度では覚えられない。 けど この本では主人公の他 皆さん個性的な名前なので なんとなく オッケーでしたが 外国人の名前が・・・ あれ、誰だっけと 初めの登場人物のリストをめくりつつ読みました。 アイヌの人達が最初に故郷を追われて でも 和人(日本人)と 共存をしていったけど その後 戦争で その土地も奪われていく。 人はどうして 他の人を虐げてまで 自分の土地を増やそうとするんだろう。 それが 結局は大きな争いになって 戦争になって 土地どころか 命を失う事になる。 この本では その命だけではなく 言語というか 文化までも奪われていく様子がわかる。 日本だけではなく アメリカや オーストラリアも 先住民の人たちを見下して 自分たちの言語を押し付けて 従来の文化や生活習慣は 野蛮だと決めつけて 自分たちと同じ生活様式を強いる。 なんか しみじみ 人のエゴというか 嫌だなぁって 思う本でした。 段々と 文化.芸能が すたれていってしまうような傾向になっているので 改めて 残しておかねばって 思える本でした。
Posted by
✓国を失い滅びると囁かれたアイヌの歴史小説 戦争で国を失った人が数多く居た。それはアイヌだけではない 人は国を失ったから滅びるのではない。人に殺される。だけど、その逆も可能だ。人によって生かされる 私にも熱はあるのだろうか
Posted by
2019年直木賞受賞作。史実を元にした傑作。 1880年以降から太平洋戦争までの樺太を舞台にした群像劇。これはそのまま この時代にこの地で生きた人々の歴史だ。 メッセージはひとつひとつが重く、彼らの叫びのごとく胸に迫る。人間とは何だ!と。 特に...
2019年直木賞受賞作。史実を元にした傑作。 1880年以降から太平洋戦争までの樺太を舞台にした群像劇。これはそのまま この時代にこの地で生きた人々の歴史だ。 メッセージはひとつひとつが重く、彼らの叫びのごとく胸に迫る。人間とは何だ!と。 特に大隈重信との問答は、人間世界の本質を問うものだと感じた。 文章は非常に淡々としているにも関わらず、私の裡側にも ふつふつと「熱」を生んでいく。 歴史に翻弄された結末を、教科書で我々みなが知っている。しかし、彼らは全力で自分たちの運命と闘っていた。 あの時代を生き抜いた彼らの「熱」は何だったのか。それを知っていただきたい。 ————— 大好きな漫画『ゴールデンカムイ』のおかげで、情景がありありと浮かんで、楽しかった。 やはり歴史に残る最高の漫画だ。
Posted by
樺太の地を題材にした歴史小説。故郷や文化を追われているアイヌたちの、千島樺太交換条約〜太平洋戦争終了ごろまで。
Posted by
まず、個人的にはゴールデンカムイと『同志少女よ 敵を討て』を読んでいないと時代背景つかめなかったなと。 この2作がとても大好きで時代背景を学び直しながら読んだ経験から今作に興味を持ったと言っても過言ではないです 第一章と第二章は、例のごとく二人の生い立ちと世界史を学び直すつも...
まず、個人的にはゴールデンカムイと『同志少女よ 敵を討て』を読んでいないと時代背景つかめなかったなと。 この2作がとても大好きで時代背景を学び直しながら読んだ経験から今作に興味を持ったと言っても過言ではないです 第一章と第二章は、例のごとく二人の生い立ちと世界史を学び直すつもりで調べながら読む これぞ醍醐味 おそらく史実かと思いますが 対雁の学校でサイゴー・ポロ・ニシパ(西郷隆盛)を崇拝する教師に出会ったこと、 “ヤヨマネクフの“ㇷ“の音が、日本語の音韻で育った人に聞こえないらしい”、だから対雁の学校では無理やり「八夜招(やよまねく)」と当てられていたこと、 アイヌの言葉と和人の言葉が異なること、同じ和人でも東北のお国の言葉と薩摩言葉が全く異なること、北海道の対雁で東北の言葉と薩摩の言葉とアイヌの言葉が入り乱れた場面等々 に面白みを感じました。 文字が滑る、というか目を滑らせて読むのがもったいない、一文字一文字、大切に読み進めたくなってしまいいつもより読むのに時間がかかった 1行たりともさらっと読み進めたくないと思いながら読みました ポーランドのこと改めて学びました。本当に勉強になりました。 「そこには支配されるべき民などいませんでした。ただヒトが、そこにいました」というブロニスワフの演説の言葉にみる サハリンとポーランドの対比。興味深くて面白いけどどこかしんどい気持ち。 第三章 録(しる)されたもの では、序章にあったトンコリや歌や言葉を残していくシーンに言わずもがな感動した 金カムのアシㇼパが残したいとやっていたのは決してギャグシーンではないんだよ… 第四章〜 ブロニシが新橋で長谷川辰之助(二葉亭四迷)に出会い早稲田で桜吹雪に ”視界は薄桃色の霧に塞がれた” ”なぜが胸が締め付けられるような郷愁を感じ”と。 桜のことや正座のこと(”両膝を揃えて曲げ、脛で床に接する姿勢で座っている”)とブロニシ目線で日本の文化を描写しています。 そう考えるとここまでも、歴史的事実をハッキリと現代に伝わる名称で書いてなかった。 日露戦争、ポーツマス条約やニコライ二世皇太子時代の大津事件など。 あくまでも当事者の目線で世界情勢を描写しています。 また、二葉亭四迷の人柄の描写はとても興味深い。 大隈重信とブロニスワフの会合は痺れたなぁ 大隈卿の「デアルンデアル」の口癖は笑いました 金田一京助の登場でいよいよ感が増しました。 金田一京助の口から石川啄木の話が出てきたところで吹いた。啄木…こいつ…と。 山辺が南極行きを決意した理由が切ないというか終盤にきてここでもこれかと辛い そして最終章を読むと同時に序章を読み返す 序章読んだときから思っていたが、「終わりの翌日」って本当に涙が出そうになるサブタイトルだと思いませんか… 全体を通して登場人物目線で書いていることには触れたが、改めて序章でロシア兵のクルニコワ伍長目線で露日戦争と書いていることに気が付いた。 じっくり読んでいるつもりでも、日本人の自分には今までの教育やら社会生活でのバイアスがかかっているなと実感した 最終章に登場する源田というオロッコ(ウィルタ)の日本兵の存在、言動については ここまで読み進めて最後の最後になんだか複雑な思いがむくむく湧きました 考えさせられる レコードのくだりはどの程度フィクションなんでしょうか。 本当に胸にくる。。。
Posted by
明治維新後から太平洋戦争終結までの、樺太アイヌの話し。途中から史実を元にしていると気付く。 差別とはこういう事で、一言で言い表せる様なものでは無く、わかったような気に成るのも良くない。 現代でもジェンダー差別とかは同じ様な心の苦しさがあるのだろうとおもう。 自分に出来る事は、...
明治維新後から太平洋戦争終結までの、樺太アイヌの話し。途中から史実を元にしていると気付く。 差別とはこういう事で、一言で言い表せる様なものでは無く、わかったような気に成るのも良くない。 現代でもジェンダー差別とかは同じ様な心の苦しさがあるのだろうとおもう。 自分に出来る事は、理解しようとする事と代弁する事だろう。 良本でした。
Posted by