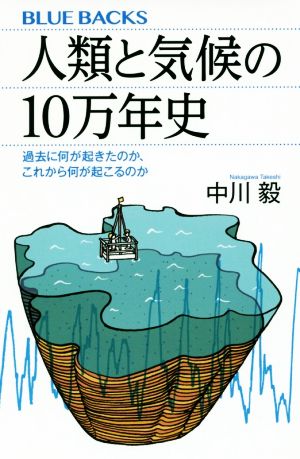人類と気候の10万年史 の商品レビュー
気候論争をする前に読むべき入門書。ファクトの大切さがよく分かる 恒常性バイアスが人類の繁栄を支えたがゲームチェンジは起こり得る 学び9 実用性8 視点の新しさ8 読みやすさ6 再読7 合計38/50
Posted by
福井県の水月湖行ってみたいと思った。年縞を明らかにするための苦労が伝わってきた。これからの気候変動を予測することの困難さがよくわかった。
Posted by
10万年スケールでの気候変動について、そして筆者が長年携わってきた水月湖の年縞堆積物の研究成果について、それぞれバランスよく語られており、変動を繰り返してきた地球の気候だけでなく、基礎研究の地道さや効用の大きさを学ぶことができた。 以下印象に残ったこと。 ・公転軌道の10万年...
10万年スケールでの気候変動について、そして筆者が長年携わってきた水月湖の年縞堆積物の研究成果について、それぞれバランスよく語られており、変動を繰り返してきた地球の気候だけでなく、基礎研究の地道さや効用の大きさを学ぶことができた。 以下印象に残ったこと。 ・公転軌道の10万年サイクルと地球気温(ミランコヴィッチ理論) 地球の公転軌道は、楕円と真円を往復するように繰り返しており、楕円から次の楕円になるまでの期間が10万年である。この10万年サイクルで、地球の氷期、間氷期も入れ替わっている。つまり、公転軌道が地球の気温に影響を与えているのだ。楕円軌道では地球がより太陽に近づくため、エネルギーを多く受けとり温暖な気候に、真円に近い時は相対的に地球が受け取るエネルギー量が少ないため、氷期となりやすい。現在は真円に近いものの例外的に温暖な気候を保っている。 ・地軸の歳差運動。2.3万年のサイクル。 地軸は止まりかけのコマのように、傾きを保ちつつゆっくりと回転している。この歳差運動は、公転軌道の10万年サイクルのように、2.3万年という高い周波数で地球の気候変動に影響を及ぼしている。 具体的には、主に季節ごとの気温変動に影響を与えている。公転軌道が楕円であるときを考える。(地球は太陽を楕円の焦点の一つとする楕円軌道をとる。)地軸が太陽側に倒れるとき、すなわち北半球における夏のとき、地球が太陽側の焦点周りを回っていれば地球と太陽の距離が近くなり、熱い夏となる。太陽側でない焦点近くを回っているときは地球と太陽の距離は遠くなり冷夏となる。同様の理屈で、寒い冬、暖冬が起こる。 冬は夏の残存熱量により一定の気温が保たれるので、地球の年平均気温は、夏にどれだけ気温が上昇するかの影響が大きい。すなわち、熱い夏になりやすい太陽近くで北半球の夏を迎えるときに年平均気温が上がりやすい。(ほんとに?これだと南半球は冷夏になっちゃう気がする。。。) ・気温変動のポジティブフィードバックとネガティブフィードバック。 気温が上昇すると、植生が発達し光合成が盛んになる、結果大気中の二酸化炭素濃度が下がり、気温を下げる方向に作用する。つまり、どこかで気温上昇に対してネガティブフィードバックがかかる。 気温が減少すると、気温を上げる方向に働く要因がなく??、凍結が進むと、太陽から受け取る熱を蓄えることができず?、気温を保てなくなる。よって更に温度が下降していくポジティブフィードバックがかかる。 ・水月湖の年縞堆積物の功績。 福井県にある水月湖は、湖面と湖底での水の入れ替わりが起こらない、湖底を掘り起こすような生物が生息していない、土砂が直接流れ込まない、など奇跡的な条件が重なって、砂が毎年少しずつ堆積することで形成される、一年ごとの縞模様が特徴である年縞堆積物を形成している。これは世界的にも貴重な湖である。 7万年分もの連続した年縞を取得したことで、その範囲であれば、一年単位で堆積したものの年代が特定できる。どの年代どういう砂が堆積したかによって、その当時を気候を読み解くことに繋がるのだが、中でも炭素14年代測定法の精度向上に大きく寄与した。この年代測定法とは、生物や植物が死滅した年代を特定する方法で、放射性崩壊して窒素14に変化する炭素14が、どれだけ体内に残っているかで死後何千年、何万年が経過したのかを特定する手法である。体内の炭素14の初期濃度は大気中と同じと考えることができるのだが、この大気中の炭素14濃度は年代ごとにバラつきがあるという問題点があった。その問題点を解決したのが水月湖の年縞堆積物であり、年縞中に堆積していた植物の葉から炭素14の崩壊量を測定し、年縞によりその植物が死滅した正確な年代を把握することで、各年代の大気中の炭素14濃度を特定することに成功した。これは、炭素14測定法の換算表(イントカル)に採用された。 ・なぜ人類は氷期に農耕を行わなかったのか?
Posted by
福井県・水月湖の湖底には約7万年分の「年縞」と呼ばれる地層が静かに刻まれている。一本一本の縞模様は過去の気候変動を克明に記録する「地球の年輪」だ。 この年縞を読み解くことで人類がどのように寒冷化や温暖化に適応し生き延びてきたかが見えてくる。食料の確保に苦しんだ時代もあれば気候...
福井県・水月湖の湖底には約7万年分の「年縞」と呼ばれる地層が静かに刻まれている。一本一本の縞模様は過去の気候変動を克明に記録する「地球の年輪」だ。 この年縞を読み解くことで人類がどのように寒冷化や温暖化に適応し生き延びてきたかが見えてくる。食料の確保に苦しんだ時代もあれば気候の安定によって文明が栄えた時期もあった。 今の気候変動は過去の激変とは異なる。人類自身がその要因となっているのだ。化石燃料の使用や森林破壊が未曾有の温暖化を引き起こしている。 年縞の知見を活かし気候変動にどう適応するかを考えることが現代の私たちに求められている。
Posted by
気候変動問題は昨今注目を集めているが、古代の気候変動を知るとそのスケールの違いに驚かされる。現代は氷河期の間にある温暖で安定した間氷期に当たり、非常に落ち着いている。気候は線形に変化するものではなく、不安定な変化が内在するシステムである。また、地球の公転自転運動の影響を受けて変化...
気候変動問題は昨今注目を集めているが、古代の気候変動を知るとそのスケールの違いに驚かされる。現代は氷河期の間にある温暖で安定した間氷期に当たり、非常に落ち着いている。気候は線形に変化するものではなく、不安定な変化が内在するシステムである。また、地球の公転自転運動の影響を受けて変化するダイナミックなシステムである。 筆者の専門は花粉の古代の地質に含まれる花粉をもとに過去の気候を分析することが専門らしい。福井県にある水月湖の年縞特定のエピソードも非常に興味深かった。
Posted by
気候変動を語る際に我々の暗黙の前提として、これまでの有史以来気候が安定していたというバイアスがある。つまりこれから起こり得る気温上昇はイレギュラーな事態であり、人類の歴史上未曾有の危機が訪れるといった気候危機論が言われるのは、標準となる安定的な気候があってこそである。 しかし本...
気候変動を語る際に我々の暗黙の前提として、これまでの有史以来気候が安定していたというバイアスがある。つまりこれから起こり得る気温上昇はイレギュラーな事態であり、人類の歴史上未曾有の危機が訪れるといった気候危機論が言われるのは、標準となる安定的な気候があってこそである。 しかし本来は、地球の気候は安定していない。とくに10万年というスケールで捉えると、実はたった数年で7℃も気温が上昇した時もあれば、今よりも10℃以上低い時代もあり、海面は±100mも上下していた。そんな過去の気候の積み重ねを調査する年縞と呼ばれる地質調査上の標準が、実は日本国内にある。 福井県三方五湖の一つ水月湖には、湖底に45m・実に7万年分もの年縞が堆積しており、その堆積物を調べることで気温や降水量、植生といった様々な情報を得られる。そこからはダイナミックに気候を変動させ、それに合わせて大幅に生物相を変化させてきた歴史が垣間見える。恐竜のいた温暖な時代も、日本が大陸と地続きになっていた寒冷期も、年縞によって特定できるのだ。 そして現在は、温暖期が終わり氷期に向かっていると考えられるが、8000年前の農耕が始まった頃から寒冷化の傾向はストップしている。つまり、人類活動の影響が産業革命以前より始まっていることが指摘されている。まだまだブラックボックスが多く気候変動の行方も分からない点は多々ある。それでもその基準となる年縞が日本国内にあるという事実は、日本人にとって責任感を思い起こさせるには十分であろう。
Posted by
古気候学・地質年代学の導入として,主に水月湖に堆積する年縞の研究について説明される。ミランコビッチ理論との関連も面白い。
Posted by
堅いタイトルであんま読む気にならないなーと思ってたけど中身は面白い。 十万年ごとに氷期と温暖期を繰り返すとか、1970年にはどんどんさむくなっていくと学者は考えていたとか。 研究に対しての情熱も熱い。 著者自身は過去を知るために、そのことが楽しいからやっている。
Posted by
人の一生からは想像できない時間軸・自然を相手にした謎解きを読んでいるようで面白かった. 地球はこれまでどのような気候であったか.それを踏まえ未来,人類はどのような気候に相対することになるのか. この複雑で難解な問いを紐解いていくにはまず,過去の地球・地域の気候を明らかにしていく...
人の一生からは想像できない時間軸・自然を相手にした謎解きを読んでいるようで面白かった. 地球はこれまでどのような気候であったか.それを踏まえ未来,人類はどのような気候に相対することになるのか. この複雑で難解な問いを紐解いていくにはまず,過去の地球・地域の気候を明らかにしていく必要がある. 長い年月をかけて蓄積した福井県の水月湖の湖底に眠る年縞は,この難解な問いに対して世界で認められた正確で緻密な物差しを与えてくれている. この年縞は現代から遡って約7万年という長い期間に対する非常に正確で緻密な史料を提供してくれており,本書ではその例として放射性炭素年代測定におけるキャリブレーションの提供,年縞に積もった花粉の分析による年代ごとの植生の推定,その他各年代ごとの雨量や気温の推定といった成果が説明されている. そのほか,地球の気候変動の規則性を推し量る理論であるミランコビッチ理論などが紹介されており,地球の気候史の概観が与えられている. 当然であるが地球の気候は非常に複雑な系の一つであり,単純な線形変化や周期変化だけでは説明ができないカオス性がありつつも,年縞をはじめとして徐々に解像度が高まっている過去から現代に続く気候史を俯瞰することで,現代の気候が置かれた現在位置や,一つの可能性として伺えるシナリオ,現代の人類が気候に影響を与えているかどうかに対して示唆を与えている. 人間の経済活動がもたらす気候変動の懸念に関する意見を耳にすると,気候変動にはさも人間だけが影響を及ぼしており,人間の活動が自粛されれば,過去の姿,期待する姿に戻るかのような錯覚を覚えるが,実態は全く異なっていることが改めて理解できる.人間の活動が環境に影響を与えていること自体は否定し得ないが,それがさも気候変動の主原因であり,人間の努力でなんとかできる・すべきであるという考えは,人間中心主義的な傲慢さの表れれはないかと改めて感じる. 一方で気候変動がもたらす経済や生活への影響は現実問題として無視できない.気候の変動性に対する”反脆弱さ”が求められていると思う. 水月湖には年縞をテーマとした博物館があるらしい.是非行ってみたい. =================================== “自然科学は善悪の判断には本質的に無力である” 古気候学:有史以前の気候が研究対象.地質学の一分野 年縞:1年に1枚ずつ堆積する薄い堆積物 福井県の水月湖:最も長く連続した年縞体積が見られる世界でも有数の場所.いわば地質学の定規「年代の目盛り」 地層に残された遺物→「何が」はわかったとて「いつ」がわからなかった.例:恐竜が反映していた時代の推定には人間にとって永遠とも言える数万年もの誤差がある 「気候変動」という言葉は80年代.ほとんどのメディアで取り上げられていなかった森林伐採や水質汚染がトレンドだった. ★10年後,20年後「温暖化は一過性の環境活動ブームネタに過ぎなかった」と行っているかもしれない.そのときは別の問題を話題にしながら. ★思い返せば「オゾンホール」という話を全然聞かなくなったな. ★負い目を感じさせてその罪滅ぼしとして商品を買わせる。企業のプロパガンダのレトリック 放射性炭素年代測定 ・炭素は同位体により3種類存在。 ・そのうち一つ(C14)だけが放射能を持ち時間の経過とともに減少する ・この減少する炭素を、減少しない炭素の量を比較することで経過時間(年代)を推定する ・c14は5万年でなくなってしまう。5万年しか計れない ・誤差がどうしても発生。標準時計にはなり得ない 物差し=c14年代を正確な年代に読み替えるための換算表 ケッペンの気候区分 →気候を区分けする分かりやすい目安が気温と雨量 →ケッペンはこれに景観(植生)を持ち込んだ →腹落ち感があり、今なおその根幹が活きる気候区分 ミランコビッチ理論 地球の公転軌道の離心率の周期的変化、自転軸の傾きの周期的変化、自転軸の歳差運動という3つの要因により、日射量が変動する周期
Posted by
あつかうテーマの壮大さ、面白さ、さらに読みやすさから、全ての人にお勧めしたい2017年発行のブルーバックスの1冊です。 本書があつかうのは古気候学。有史以前の気候変動を解明する研究で、基本的には地質学の一分野。解明する手段としては、放射性炭素法、花粉分析、年輪年代学などがありま...
あつかうテーマの壮大さ、面白さ、さらに読みやすさから、全ての人にお勧めしたい2017年発行のブルーバックスの1冊です。 本書があつかうのは古気候学。有史以前の気候変動を解明する研究で、基本的には地質学の一分野。解明する手段としては、放射性炭素法、花粉分析、年輪年代学などがありますが、本書が主題とするのは福井県にある水月湖の「年縞」です。 年縞とは、湖底などの堆積物によってできた縞模様のこと。 水月湖の底には、7万年以上の歳月をかけて積み重なった年縞があり、いくつかの奇跡が重なってできた世界的に珍しい貴重なもので、考古学や地質学における年代測定の「世界標準」になっています。 縞模様は季節ごとに異なるものが堆積することにより形成され、春から秋にかけては土やプランクトンの死がいなどの有機物による暗い層が、晩秋から冬にかけては、湖水からでる鉄分や大陸からの黄砂などの粘土鉱物等によりできた明るい層が1年をかけ平均0.7mmの厚さで形成されます。したがい、年縞に含まれる花粉の化石を調べれば、当時の植物分布がわかるし、現在の表層花粉と比較分析すれば当時の気温も推定できることになります。 著者の中川毅さんは立命館大学古気候学研究センター長。水月湖底の年縞を世界標準にしたプロジェクトのリーダーであり、「時を刻む湖」(岩波科学ライブラリー)の著書もあります。 地球は365.25日かけて公転しますが、その軌道はおよそ10万年の時間をかけて、円くなったり長細くなったりを繰り返します。一方、南極の氷に含まれる酸素と水素の同位体比から復元した、過去80万年の気候変動を見ると氷期と温暖期は10万年ごとにリズミカルに繰り返しています。大雑把に言えば、公転が円い時期は氷期であり、細長い時期は温暖期となります。 しかし、水月湖の湖底から見える風景はもっと複雑です。 ○氷期と間氷期が繰り返す中、人類誕生以来、その歴史の大半は氷期だった。 ○現代の温暖化予想は100年で最大5℃の上昇だが、今から1万1600年前、わずか数年で7℃にも及ぶ温暖化が起きていた。 ○東京がモスクワになるような、今より10℃も気温が低下した寒冷化の時代が繰り返し訪れていた。 ○温暖化と寒冷化のあいだで、海面水位は100メートル以上も変動した。 ○縄文時代の始まりは日本における温暖期の開始時期 ○平均気温が毎年激しく変わるほどの異常気象が何百年も続く時代があった。 ○氷期の終わりは世界的な農耕の拡大時期 ○夏の日射量が、中緯度の気候を左右する決定的な要因のひとつ。日射量は23,000年で一巡する歳差運動に影響する。夏の日射量が多い年は温暖となる さらに、「氷期が終わって気候が安定してから、今まですでに1万1600年もの年月が流れている。古気候学の知見によれば、過去3回の温暖な時代はいずれも、長くても数千年しか持続せずに終わりを迎えた。つまり今の温暖期は、すでに例外的に長く続いているのである」という恐ろしい見解もあります。 そして著者は「不測の事態を生き延びる知恵とは、時間をかけて『想定』し『対策』することではない。(中略)必要なのは、個人のレベルでは想定を超えて応用のきく柔軟な知恵とオリジナリティーであり、社会のレベルでは思いがけない才能をいつでも活躍させることのできる多様性と包容力である」と断言します。 とにかく面白いブルーバックスの科学読み物。老若男女全ての人にお勧めしたい本です。
Posted by