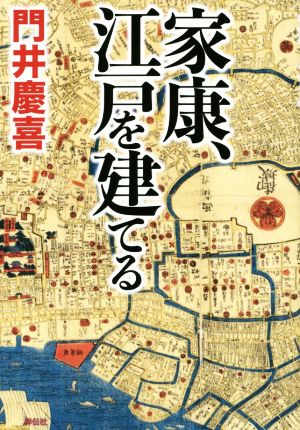家康、江戸を建てる の商品レビュー
徳川江戸都市計画・・・史料的には読んでいましたが、 利根川も江戸の町も別々に、でした。 が、小説化してつなげてくれるとは! 他にも、治水・財政・土地改良・・・まさに、 江戸という都市を作る! それに従事した人々の困難への挑戦! まってました!な感です♪
Posted by
「家康、江戸を建てる」というタイトルだが、家康はほとんど出てこない。 家康がいかに将来を見据えていたか、それとその家臣がそれぞれの事業にかかわる人選に秀でていたか、それに尽きる。 家康が築いて来た江戸が、現在の日本の生活に多大な影響を与えている。生活する為の飲み水を確保したり、貨...
「家康、江戸を建てる」というタイトルだが、家康はほとんど出てこない。 家康がいかに将来を見据えていたか、それとその家臣がそれぞれの事業にかかわる人選に秀でていたか、それに尽きる。 家康が築いて来た江戸が、現在の日本の生活に多大な影響を与えている。生活する為の飲み水を確保したり、貨幣を流通させたり、今の生活に根付いていることの原点を見た気がする。 そこが現在の日本銀行本店や井の頭公園である、と聞くとなんだか鳥肌が立つ思いだった。 川の流れを変えるなんて、計画が壮大過ぎる‼︎ 44
Posted by
★SIST読書マラソン2017推薦図書★ 【所在・貸出状況を見る】 http://sistlb.sist.ac.jp/mylimedio/search/search.do?target=local&mode=comp&materialid=11630258
Posted by
江戸が完成されるまでをお金、水(川の流れ)、天守、石垣の面から描かれた本です。 直木賞の候補作なので読んでみました。 私は大阪に住んでいて東京にはゆかりがないため地理の面では全くわかりません。 でも歴史が好きなこともあり街をつくるということはそれだけで本当に無数の命でできている...
江戸が完成されるまでをお金、水(川の流れ)、天守、石垣の面から描かれた本です。 直木賞の候補作なので読んでみました。 私は大阪に住んでいて東京にはゆかりがないため地理の面では全くわかりません。 でも歴史が好きなこともあり街をつくるということはそれだけで本当に無数の命でできているプロジェクトなのだな、と楽しめました。 直木賞・芥川賞を実況・解説するニコ生で言っていた通りぜひブラタモリで本を片手にまわって欲しいです。 それにこの大阪編も読んでみたいなあ。
Posted by
「関八州を差し上げよう」 秀吉は“ありがたい良い話”のように言うが、父祖の代からの三河をはじめとする現在の領地と引き換えである。 猿におにぎり取り上げられて柿の種をもらった蟹みたいである。 家臣たちは猛反対するが、家康は関東の「伸びしろ」に賭けたようだ。 そう、柿の種はやがて育ち...
「関八州を差し上げよう」 秀吉は“ありがたい良い話”のように言うが、父祖の代からの三河をはじめとする現在の領地と引き換えである。 猿におにぎり取り上げられて柿の種をもらった蟹みたいである。 家臣たちは猛反対するが、家康は関東の「伸びしろ」に賭けたようだ。 そう、柿の種はやがて育ち、多くの実をつけるようになる。 しかし、さすがに水浸しの大平原とボロ城を前に、家康絶句。“ぽーん”という擬音が聞こえてきそう。 しかし、切り替えは早い。 江戸そのものの地ならしに取り掛かる。 時系列どおりの小説ではなく、各プロジェクトごとに現場が描かれる。 まだ戦乱は続いていたが、収束に向かいつつあった。 ここではすでに戦国武将は主役ではない。 そこここに、時代の変わり目に置いていかれそうな人物も描かれている。 文官と技術者の時代がやってくるのだ。 亡くなる前年まで、家康は武将として豊臣を押さえてきた。 軍事と民政の二足のわらじを履き、もちろん忙しい。 人材を集め、各プロジェクトごとに専門家に任せる、そういう人使いの巧みさも、家康の江戸作り成功の秘訣だろう。 第一話 流れを変える 関東平野を水害から救い、米の収穫量を上げるために、利根川の川筋を変えるという大事業。 時代の流れを変える、という意味も含むだろう。 伊奈三代の仕事。 第二話 金貨(きん)を延べる 貨幣を流通させて、経済の天下統一を目指す。 伝統ある彫金氏の家、後藤家につかえる庄三郎の野心が家康とシンクロ! 第三話 飲み水を引く 治水事業により水害は減り、交通網としての河川は整えられつつあるが、良質な飲み水を手に入れなくては生活の質は上がらない。 質プラス量。 驚くべき技術開発で、水道を引く。 第四話 石垣を積む 城の土台となる石垣。 石の摂理を読み、良質な石を切り出す吾平と、石の重さの偏りをはかり安全かつ堅牢に積み上げる方向を決める喜三太、二人の「見えすき」と、神になった石。 第五話 天守を起こす 最後の戦国武将として、家康がどうしても打ち立てておきたかったのが天守ではなかったか。 時代はすでに次世代のものであるが、本当に天守が必要なくなるのはもう少し後である。 江戸は一日にして成らず。 そして永遠に普請中であり発展中。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ヴィジュアルと、江戸・東京のお散歩のガイドをお求めの方にはこちらもお勧め! 詳伝社新書「江戸城を歩く」黒田涼/著 ISBN978-4-396-11161-8
Posted by
秀吉の小田原攻めの時に、秀吉より三河・駿河から関東移封を命じられた徳川家康。 当時の秀吉の絶対的な権力に逆らえないのは理解できるが、関東に下った家康の居城は、小田原ではなく、何故寒村と言われた江戸だったのか? その答えは、本著にはない。 調べてみると、江戸は中世あるいはそれ以前か...
秀吉の小田原攻めの時に、秀吉より三河・駿河から関東移封を命じられた徳川家康。 当時の秀吉の絶対的な権力に逆らえないのは理解できるが、関東に下った家康の居城は、小田原ではなく、何故寒村と言われた江戸だったのか? その答えは、本著にはない。 調べてみると、江戸は中世あるいはそれ以前から水運で栄えた交易都市で、しかも後北条氏の重要な軍事拠点だったという説が近年浮上しているそうです。 冒頭から脇道にそれましたが、本題に戻ります。 江戸に下った家康が、というより家康の部下が行った今日の東京の基礎を築いた話です。特に現在の東京の拡大の基礎が、このように計画・実行されたのかと、知識欲が大いに満たされる。 1.流れを変える・・・伊奈氏3代に渡って成し遂げた、利根川東遷 2.金貨を延べる・・・秀吉の大判に対抗した金小判の鋳造 3.飲み水を引く・・・江戸に飲料水を供給した神田上水 4.石垣を積む・・・・江戸城の石垣を積む 5.天守を起こす・・・江戸城の天守閣を巡る家康と秀忠の対立 特に興味を惹いたのは、「2.金貨を延べる」 秀吉の天正大判というのは、流通する貨幣ではなく、石高を増やしたり領国を与える代わりの褒賞の意味を持っていた。日本統一を果たした秀吉には、国内に余った土地などなかった。その窮余策が金の大判だったのだ。これに対抗して家康は流通できる金の小判の鋳造を行い大判の駆逐を目論む。今日的な観点からすると非常に画期的な事業といえる。 また江戸城の石垣にしても、天守閣にしても、こういう意味があったのかと改めて驚くことが多かった。 天守閣は安土城にしても大坂城にしても、漆を塗り込んだり、金を使ったりして黒いものだった。漆喰で塗り固めた純白の天守閣は江戸城が初めてだという。 近年改修工事の終わった姫路・白鷺城が、やたら白すぎると評判になっているが、江戸城も白鷺城のようだったのか・・・ 今度江戸城(皇居)へ行った時には、そういう知識を噛みしめながら眺めてみたいと思う。 【追記】 小説としては、人物描写がやや甘い。この点が直木賞選考の際に、本書の欠陥とするどく指摘され、直木賞を逃したのは残念であった。 やはり選考委員のプロは、その弱点を鋭く抉り取っている。そのことを端的に捉えたのが、高村薫の以下のコメントである。 ※直木賞選考を終えた時の高村薫のコメント 「職人たちにはそれぞれ人生の物語もあるが、いずれも江戸時代のインフラや技術を楽しく紹介するための道具立ての域を出ない。老婆心ながら、小説は面白いアイデアとは別の次元で成立している何ものか、である」
Posted by
17/08/19読了 登場人物が真田丸キャストで再生される笑 淡々と、江戸設立時のエピソードを楽しめた。
Posted by
面白い・・・面白いけど、小説を読んでる感じはしなかったなぁ~。 もっと小説っぽいと、もっと面白いだろうになぁ~。。。 個人的には「石垣を積む」が面白かったかな。
Posted by
おととし東京都現代美術館でオスカーニーマイヤーの建築を振り返る展覧会がありました。彼の作り上げたブラジリアという人工都市のスケールに度肝を抜かれました。でも「家康、江戸を建てる」を読みながら、家康の江戸にあってブラジリアにないものもなんとなくわかりました。そこに暮らす人の生活です...
おととし東京都現代美術館でオスカーニーマイヤーの建築を振り返る展覧会がありました。彼の作り上げたブラジリアという人工都市のスケールに度肝を抜かれました。でも「家康、江戸を建てる」を読みながら、家康の江戸にあってブラジリアにないものもなんとなくわかりました。そこに暮らす人の生活です。人生です。江戸を建てるということは江戸城を建築するということではなくて新田を開発して生産力を上げるだし、上水をひいてインフラを整えるだし、貨幣を鋳造して商業システムを作るだ、と思い知りました。ビジョンとしての都市とリアルの積み重ねとしてのと都市の違い?治水の伊奈忠次、鋳造の後藤庄三郎、水道の大久保藤五郎、六次郎、春日与右衛門、石切りの見えすき吾平、見えすき喜三太、そして新概念の天守閣を作った徳川秀忠、平和の時代に必要なマニアックなスペシャリストたちの総合芸術がその後百万都市になる江戸なのでした。いやいやすべてを包含する総合プロデューサー家康のビジョンが凄いのかも。2020に向けて槌音高らかな江戸の進化形,TOKYO。そこにはどんなビジョンが示されているのか、いまだに見えてきていません。
Posted by
家康が江戸をつくるお話。上水の話とか、地元の話はもちろん、鹿島の話も出て来て興味深かった。古地図持って散歩したくなった。 1.流れを変える 2.金貨を延べる 3.飲み水を引く 4.石垣を積む 5.天守を起こす
Posted by