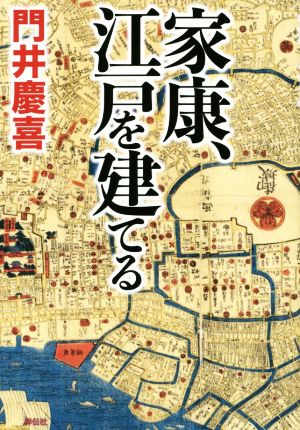家康、江戸を建てる の商品レビュー
良かった良かった。 こうやって江戸は作られたんだ。 知識のインプットだけでなく、 読み物としても面白かったです!
Posted by
江戸の水問題の解決に向けた取り組み、江戸城築城の問題等、小説風に書かれていて楽しく読めた。江戸時代の土木工事の技術も侮れないなと感心した。
Posted by
豊臣から家康の時代移変り時に家康が江戸を領土として開拓する内容、利根川、渡良瀬川の開拓や、慶長小判発行までのくだらない話でうんざりする内容
Posted by
家康は戦下手だが、街づくりの能力があった。 だから戦国の世は、彼には不向きだった。 そんな推測をしていたところに、この本に出会い 読んでみて、それが正しかったとの意を強めることが 出来た。 これからも家康の街づくりの能力をもっと 知ってみたい。 そんな本を探していきたい。
Posted by
家康が江戸を建てるまで。利根川東遷、貨幣鋳造、天守閣など、商都江戸を築くまでの話が技術者目線から語られており興味を惹かれる。 (1)庄三郎。へりくだる人間は仕事もへりくだる。おのれをたのめ。 (2)江戸というのは水を排し、同時に水を給しなけらば使い物にならぬ土地なのだ。 (3)人...
家康が江戸を建てるまで。利根川東遷、貨幣鋳造、天守閣など、商都江戸を築くまでの話が技術者目線から語られており興味を惹かれる。 (1)庄三郎。へりくだる人間は仕事もへりくだる。おのれをたのめ。 (2)江戸というのは水を排し、同時に水を給しなけらば使い物にならぬ土地なのだ。 (3)人格というのは業績と無関係なようでいて、案外後世の評価に直結するものらしい。 (4)この世で本当に大事な事は議論では決まらない。数字や脅迫や詐術や根回しで決まる。そんな政治のリアリズムが骨まで染み込んでしまつまっている。そのくせ人間評価の尺度は誠意なのだ。
Posted by
▶︎購入2016/05/17 ▶︎2016/05/29-06/01 ▶︎「江戸」の町をつくり育てたプロ集団の内情。 中世における世界最大の都市はこのようにつくられた。読み応えのある作品。
Posted by
こうやって江戸は出来たんだね。 今やってる大河「真田丸」ともシンクロしていて 興味深く読めました。 第155回直木賞候補。結果は・・・「残念」 第153回時にも「東京帝大叡古教授」で候補となったいたが それよりもこちらの作品の方が良いな。 因みに、153回直木賞は「流」
Posted by
新聞で広告を読んで…すぐ買ってくれた~秀吉から関東八州を貰った家康は利根川の河口が湿地となるのを見て,川筋を東に曲げる作事を伊奈忠次に命じた。渡良瀬川に繋げて元の川は隅田川となったが,期待の長男・熊蔵は大坂攻めで気を悪くして早死にし,次男が忠治として完成させた。赤堀川へと繋げて鹿...
新聞で広告を読んで…すぐ買ってくれた~秀吉から関東八州を貰った家康は利根川の河口が湿地となるのを見て,川筋を東に曲げる作事を伊奈忠次に命じた。渡良瀬川に繋げて元の川は隅田川となったが,期待の長男・熊蔵は大坂攻めで気を悪くして早死にし,次男が忠治として完成させた。赤堀川へと繋げて鹿島灘へ河口を向けるのは忠克の時代だった。後藤長乗の従者として江戸に下った庄三郎は長乗が寒さを嫌って江戸を去った後,本領を発揮して京で造られている大判をそっくり真似て作り上げたが,家康が命じたのは小判の製造。後藤家が家康の元地元・駿府で造った小判を見た庄三郎は,品位の高い小判を造るに当たっては後藤の名が欲しいと家康に申し入れ,京へ上って養子にしてもらうべく参るが,無理難題を押し付けられ,貰った地位は猶子だった。それが逆転したのは,関ヶ原。戦勝を知った庄三郎は,京の三条大橋に高札を建て,後藤家の本筋は庄三郎の方に移り,小判は徐々に浸透していった。飲み水を引くのは菓子司の大久保藤五郎に命じられ,13年後に鷹狩りに出かけた森で七井の池を見つけ,在の内田六次郎という百姓が普請役に任じられた。野方堀で進められ,外濠と交わるところは水道橋が架けられた。町中は暗渠とされ徳川上級家臣の若党・春日与右衛門が補佐と云うより,実際を担っていた。目白の堰を切ると水圧のせいであちこちで大噴出したが,十余年の歳月が流れ,洗堰の工夫で改良した。大久保長安に召し出された伊豆の石切吾平は石の節理を読める見えすきの才能を持っていた。江戸に城を構える石垣の石材を切り出す仕事が与えられたが,大仕事がしたいと,西伊豆に向かい,山頂の巨石を切り出したが資金が底を突き,伊達藩に委ねて江戸に出た。江戸には石積みの喜三太がいて,浅野家から伊達家に鞍替えし,大手門周辺を担当しながら,北詰の山内家の普請場まで面倒を見ている。吾平が切り出した巨石は用いられず,隅石に用いたらと云う提案も斥けられた。喜三太が伊達家に掛け合って江戸に運び込まれたが,用途は大手門の鏡石,しかも巨石は二つに割られていた。家康が天守に固執するのを秀忠は冷静に見ていたが,天守建築は始められ,漆喰で塗ることが決まった。漆喰は青梅で見つかったが,何故白い天守なのか,秀忠は納得いかない。平和の色であると共に,江戸に幕府を開くための犠牲になった死者の色でもあったのだ~まぁ,面白くてすらすら読めるんだけど,連作以外に方法はなかったのだろう。でも,もうすこし工夫することもできたと思うのが残念
Posted by
ブラタモリ好きならおススメ。家康が隅から隅まで江戸を設計した訳ではなく、人事にすぐれた経営トップであったということか。古地図を眺めてみたい。
Posted by
秀吉から、関東移封を命じられた家康が、 ほとんど不毛と言えた当時の江戸の地に、 江戸城および城下町を整備していく様を、 治水、上水、石垣、天守、貨幣、といぅ、 5つのテーマ、視点で描いた短編集です。 例えば…、NHKの「ブラタモリ」では、 訪れた土地々々の城づくり、街づくりを、...
秀吉から、関東移封を命じられた家康が、 ほとんど不毛と言えた当時の江戸の地に、 江戸城および城下町を整備していく様を、 治水、上水、石垣、天守、貨幣、といぅ、 5つのテーマ、視点で描いた短編集です。 例えば…、NHKの「ブラタモリ」では、 訪れた土地々々の城づくり、街づくりを、 遺構と併せ、様々な視点で考察しており、 元土木技術者としては、 毎回、興味深く視聴しておりまして…、 本作品の主題である、 江戸の城づくり、街づくりは、文字通り、 現代に至る日本の首都の礎づくりであり、 ゆえに、 本作品も、とても興味深く読みました…。 まず…、 当時の難工事の様子と、完成した施設が、 適宜、様相を変えた現在の様子も交えて、 主に、現場の視点から描かれており、 全体的には、とても面白かったです。 一方で、 何となくですが、史跡の説明板の内容を、 肉付けした程度の内容でもあったので…、 小説としては、もぅ少し練り込んだ上で、 ドラマチックな内容でもよかったかな~?
Posted by