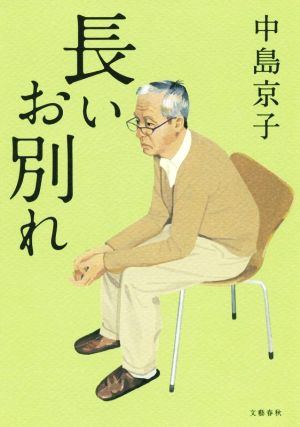長いお別れ の商品レビュー
認知症の夫を自宅介護する妻。 離れて暮らす3人の娘とその家族。 大変、不幸、なんてイメージばかりだけど、それが日常になっていくと、当然クスリと笑える場面があったり、幸せを感じることもある、淡々とした文体で描かれた穏やかな話。 なんで私がこんな目に、という思いを持たずに介護をし...
認知症の夫を自宅介護する妻。 離れて暮らす3人の娘とその家族。 大変、不幸、なんてイメージばかりだけど、それが日常になっていくと、当然クスリと笑える場面があったり、幸せを感じることもある、淡々とした文体で描かれた穏やかな話。 なんで私がこんな目に、という思いを持たずに介護をし続けることは難しいのかな、この本に書かれていることは綺麗事なんだろうか? 私にはわからない。
Posted by
実際の介護はこんなものじゃないんだと思う。オイラにその覚悟はあるかなぁ?嫁にその覚悟はあるかなぁ?ないよなぁ、きっと。オイラはカラダが丈夫なだけ、嫌がられそうだ。嫁が認知症になったら、夫婦ではなくて一からお互いを知っていく関係になると考えた方が精神的にいいかもしれない、長い間付き...
実際の介護はこんなものじゃないんだと思う。オイラにその覚悟はあるかなぁ?嫁にその覚悟はあるかなぁ?ないよなぁ、きっと。オイラはカラダが丈夫なだけ、嫌がられそうだ。嫁が認知症になったら、夫婦ではなくて一からお互いを知っていく関係になると考えた方が精神的にいいかもしれない、長い間付き添ってきた関係を信じて。 でもオイラ、先生が亡くなった場面でホッとしたんだ。悲しいけど、それとは違う感情のほうが大きかった。オイラには介護の経験はないけど、実際に直面したらきっとホッとしちゃうんじゃないかな。 ”ときおり、意のままにならないことにいら立って、人を突き飛ばしたり大きな声を出したりすることはあるけれど、そこにはいつも何らかの理由があるし、笑顔が消え失せたわけではない。この人が何かを忘れてしまったからと言って、この人以外の何者かに変わってしまったわけではない。” こんなふうに考えられる自信がない。曜子は昇平のそばにいたいという想いが強いから、耐えるという感情をあまり抱くことなく介護できたんだと思う。あと昇平の笑顔。笑顔のチカラをオイラは信じる。すごいパワーにもなるし、癒してもくれる。そういえば、嫁の笑顔見てないな。
Posted by
映画公開に備えて読む。この著者は「小さいおうち」以来久方だがなんとか作家を続けていたんだ、最近賞を取っても消えていく人が多いので文筆業も楽ではなさそうである。この手の小説を読むのは有吉佐和子の「恍惚の人」以来のような気がするが、介護保険制度が出来ても結局犠牲を強いられるのは家族で...
映画公開に備えて読む。この著者は「小さいおうち」以来久方だがなんとか作家を続けていたんだ、最近賞を取っても消えていく人が多いので文筆業も楽ではなさそうである。この手の小説を読むのは有吉佐和子の「恍惚の人」以来のような気がするが、介護保険制度が出来ても結局犠牲を強いられるのは家族でそのことは昔と一切変わっていないようである。排泄物を並べるという描写があったが、「恍惚の人」では投げていたのではなかったっけ、こういう物語を読むと老いに恐怖を感じる。この家族がQOLを重視し延命治療は行わかったのは賢明だと言える。
Posted by
某所読書会課題図書.短編が8つ、元高校の校長でアルツハイマー型認知症を患っている東昇平と介護している妻曜子の物語だが、複雑な読後感を覚える.長女の茉莉は夫の都合でサンフランシスコ在住、次女の菜奈は少し離れたところに住んでいる.三女の芙美は独身で料理に関する仕事をしており、それぞれ...
某所読書会課題図書.短編が8つ、元高校の校長でアルツハイマー型認知症を患っている東昇平と介護している妻曜子の物語だが、複雑な読後感を覚える.長女の茉莉は夫の都合でサンフランシスコ在住、次女の菜奈は少し離れたところに住んでいる.三女の芙美は独身で料理に関する仕事をしており、それぞれ両親の様子をうかがっている.ドタバタ劇のようなエピソードが連続するが、曜子の奮闘は特筆すべきものだと思う.娘たちはそれぞれの生活があり、介護に本気で向き合うことができないが、曜子が網膜剥離で入院した際、昇平の介護を菜奈と芙美が実際に行って、ぐったりきた「うつぶせ」の場面は実感がこもっていると感じた.
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
誰もが認知症になるのだろうか?きっと...なると思う 娘三人が父親に対する気持ちとして以外とクールだなと感じた。母親は最後まで自宅で介護したいという希望があり老老介護でありながらもかなり頑張っている。 記憶が徐々になくなっていく身近な大切なひと... 悲しみや失う寂しさ...日々の介護の中にそういうものが入り混じっていることを忘れてはいけない。と感じる。 介護を支えるものって愛情ってことなのかもしれない...
Posted by
決して綺麗事ではなく丁寧に認知症の事が書かれていて好感が持てました。 思わず笑ってしまう様なシーンがあったり、文体がリズム良いのでさらりと入ってくるのも良かったです。 でもやはり徐々に認知症が進行していく描写は怖くて悲しくて、 最後の3話は読むのが本当に辛かったです。
Posted by
主人公ともいえるおじいちゃんをあえて主人公にはせず、群像劇の中に登場するサブ的な役割にした点が素晴らしい。
Posted by
文句無しに星5つです♪ まさに今風の「恍惚の人」ですね。元中学校長や公立図書館長まで務めた東昇平氏を縦糸にして、徐々に認知症が進行して行く10年間が支え続ける妻や3人の娘や周りの人々の様子を横糸に語られていく、しかも全体にユーモアをまぶしながら。両親の介護体験がある私には何度も頷...
文句無しに星5つです♪ まさに今風の「恍惚の人」ですね。元中学校長や公立図書館長まで務めた東昇平氏を縦糸にして、徐々に認知症が進行して行く10年間が支え続ける妻や3人の娘や周りの人々の様子を横糸に語られていく、しかも全体にユーモアをまぶしながら。両親の介護体験がある私には何度も頷きながら時に反省しながら読み進めることができました♪ 長いお別れをこんな風に軽く深刻にならずに著していてとても良かったです。介護等が分かる人 通じる人にはオススメの本でした。
Posted by
「少しずつ記憶をなくし、ゆっくりゆっくり遠ざかっていく」認知症を、アメリカでは「ロング・グッドバイ」と表現するそうだ。 中島さんのお父様との「長いお別れ」を基に書かれていたことが納得できる、優しさに包まれた文章だった。
Posted by
誰にも来る長いお別れ、私にはいつ来るのだろうか?最近経験した身内のとの長いお別れは、母とだった。舌ガンと分かったのが春先の事、その後は自分のしたい事をして、別れを告げたのは翌年の正月3日だった。母は肉体を脱ぎ捨て軽やかにあの世に返って行った。と、知り合いの人が言っていた。そうかも...
誰にも来る長いお別れ、私にはいつ来るのだろうか?最近経験した身内のとの長いお別れは、母とだった。舌ガンと分かったのが春先の事、その後は自分のしたい事をして、別れを告げたのは翌年の正月3日だった。母は肉体を脱ぎ捨て軽やかにあの世に返って行った。と、知り合いの人が言っていた。そうかもしれない。実はお別れを告げる、2-3時間前に、母に十分頑張ったからもういいよ、と私は母に告げた。その言葉を聞き母は安心した。とも知り合いの人は言っていたからだ。 長いお別れは誰にもやって来る。でもそれは、永遠の別れではないように思う。なぜか分からないが、そんな気がする。だから、自分にやって来るであろう長いお別れは、悲しいものとは思わない。 何故なら、長いお別れは同時に、懐かしい人との再会を意味するからだ。
Posted by