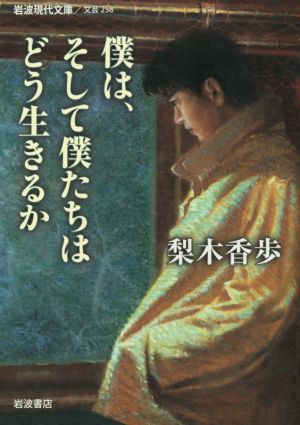僕は、そして僕たちはどう生きるか の商品レビュー
子どもは子どもなりにたくさん考えて、疑問があったり、意見がある。大人がそれを出せなくしているのではないか。 「普通」という概念を押し付け、「集団」の圧力を大きくしているのは大人なのではないか。 大人の私はそれが怖い。 人はひとりでは生きていけない。 だから、意見を“相手に”伝え...
子どもは子どもなりにたくさん考えて、疑問があったり、意見がある。大人がそれを出せなくしているのではないか。 「普通」という概念を押し付け、「集団」の圧力を大きくしているのは大人なのではないか。 大人の私はそれが怖い。 人はひとりでは生きていけない。 だから、意見を“相手に”伝える力が必要で、相手の考えを“知りたい”と思って聞く力が必要になる。 伝わらないことも、相手を理解できないこともあると思うけど、それで伝えることや聞くことをやめてしまうとそこで世界は閉ざされてしまう。 人との関わりに疲れてしまったとしても、自分の居場所があれば、生きていける。 その場所を見つけるためには傷つきながらも人との関わりを持たなければならない。 悩み、苦しみ、辛いことも少なくない。 だから、ひとりが楽。 その気持ちもとてもよくわかる。 だけど、人を信じて、どこかに自分の居場所があると、そう信じて生きていきたい。
Posted by
まさしくコペルくんの考えそうなことを著者は見事に再現したと思う。しかも、ユージンとニワトリの話には胸を締め付けられ、そしてコペルくんが自分の内面に気付くくだりはぞわぞわする。恐ろしい、そしてそういうことなんだ。
Posted by
========================= 僕にはもう自信がなかった。 自分が、いざとなったら親友さえ裏切って大勢の側につく人間なんだと思うと。 ========================= 胸を深く突かれた。 これは、自分だ、と思った。 自分は、「群れ」が...
========================= 僕にはもう自信がなかった。 自分が、いざとなったら親友さえ裏切って大勢の側につく人間なんだと思うと。 ========================= 胸を深く突かれた。 これは、自分だ、と思った。 自分は、「群れ」が怖くてしようがない。 「群れ」そのものも、「群れ」に飲み込まれたあとの自分も。 自分は、自分が思う自分でありたい、と願い続けている。 だから出来る限り、「群れ」には近づかないという方針を採用した。 そうして、15年以上の年月がすぎた。 これは、とても卑怯な行為なのだと思う。 「群れ」に立ち向かうことをせず、「群れ」を率いることもしない。 その「群れ」が間違っていたとしても、自分はそれを止めようとはしない。 ただ、その「群れ」に気付かれないように、飲み込まれないように願うだろう。 それはもう必死で。死に物狂いで逃げ回るのだろう。 本作は、著者の作品らしく、静謐な雰囲気のままに展開していく。 様々な物語があり、しかし、それらは深くは語られない。 そこには、読者へと判断を委ねる、想像の余地が残されている。 だからこそ、物語の一つ一つが、深く胸へと刻み込まれる。 梨木香歩という作家が書いた作品たちを、自分は心から好きだと思える。 冒頭で引用した一文は、この作品が終盤に差し掛かったところで示される。 思わず頁を繰る手が止まり、ひゅっと息を呑んだ。 そして本書は、最後にこんな言葉を残して幕を閉じる。 ============================== そう、人が生きるために、群れは必要だ。強制や糾弾のない、許し合える、ゆるやかで温かい絆の群れが。人が一人になることも了解してくれる、離れていくことも認めてくれる、けど、いつでも迎えてくれる、そんな「いい加減」の群れ。 ============================== やあ。 よかったら、ここにおいでよ。 気に入ったら、 ここが君の席だよ。 ============================== これは、救済、なのだと思う。
Posted by
吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』(岩波文庫)は、近年マンガ化されてふたたび大きな反響を呼んでいますが、児童文学などを執筆している著者のオマージュ作である本書も、吉野の本に劣らず読者に向けて深い問いかけがおこなわれています。 吉野の著書の登場人物にちなんで「コペル」というあだ...
吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』(岩波文庫)は、近年マンガ化されてふたたび大きな反響を呼んでいますが、児童文学などを執筆している著者のオマージュ作である本書も、吉野の本に劣らず読者に向けて深い問いかけがおこなわれています。 吉野の著書の登場人物にちなんで「コペル」というあだ名で呼ばれる14歳の多感な少年が、学校へ行くことをやめたユージンのもとを訪れ、叔父で染織家のノボちゃんやユージンの従姉のショウコ、オーストラリア人のマークらとの対話のなかで、タイトルになっている「僕は、そして僕たちはどう生きるか」とみずからに問いかけていきます。 ユージンの家には、彼の大叔父の集めた多くの本があり、それらの本をめぐるエピソードを通じて、戦争の時代を生きた日本人の姿と、身近な人びととの人間関係に苦しむ彼らの自身の姿がかさねられ、コペル少年はみずからのうちにも集団に同調して身近なひとの苦しみを見すごしてしまう弱さが存在していることに気づきます。しかし、そこから離れたところに身を置くことで、「僕はどう生きるか」という問いに向きあい、そしてふたたび「僕たちはどう生きるか」という問いに、もう一度出会うことになります。 ヒトラー・ユーゲントのことをきっかけに、「ボーイスカウトと軍隊」が地続きになっていることを本書のなかで指摘している著者だけに、いくつかの問題についてはもう少し慎重な取り扱いが必要だったのではないか、と不満を抱いてしまいます。たとえば、本書に登場する「インジャ」に関するエピソードは、批判が容易なところに読者の目を向けさせており、かえって危惧をおぼえます。「ボーイスカウトと軍隊」が地続きであるのとおなじように、バクシーシ山下の仕事と二村ヒトシの仕事は地続きになっています。そしてこの問題は、インジャのエピソードについて「自分が男だってことにまで、罪悪感をもってしまうほどだ」と語るコペル少年の「罪悪感」のなかにまで、無自覚のままにするすると入り込んでしまっているように思われます。 14歳の少年にそこまでの自覚を求めるのはむずかしいでしょうが、本書の提出している問いの鋭さを、いささか減じてしまっているように感じられました。
Posted by
14歳で1人暮らしをしている少年のわずか1日の物語ではあるけれど、これからの生き方を考えさせる。自分探しではなく、友人ひとりひとりの居場所を用意することが大事だと著者は訴えているようだ。そこは居心地がいい場所というのではなく、ふさわしい場所とでも言えばいい場所だ。 自分のことだけ...
14歳で1人暮らしをしている少年のわずか1日の物語ではあるけれど、これからの生き方を考えさせる。自分探しではなく、友人ひとりひとりの居場所を用意することが大事だと著者は訴えているようだ。そこは居心地がいい場所というのではなく、ふさわしい場所とでも言えばいい場所だ。 自分のことだけを考えていたら世界はだめになっていく。それって今の世界じゃない?
Posted by
自然の一部であることを謙虚に受け入れること。 世界のありようから目を離さないこと。 自分の頭で考え、自分の足で立つこと。 ああ、これは全く梨木香歩の作品だ。 主人公のコペルは、家庭の事情でひとり暮らしをしている。 もう3年も学校に出てこない元親友のユージンの家に、叔父のノボちゃ...
自然の一部であることを謙虚に受け入れること。 世界のありようから目を離さないこと。 自分の頭で考え、自分の足で立つこと。 ああ、これは全く梨木香歩の作品だ。 主人公のコペルは、家庭の事情でひとり暮らしをしている。 もう3年も学校に出てこない元親友のユージンの家に、叔父のノボちゃんを連れていくことになり、久しぶりに顔を合わせるコペルとユージン。 ユージンもうっそうと茂った森のような庭を持つ家に、ひとりで暮らしていた。 そこにユージンの従姉のショウコや、インジャや、オーストラリア人のマークが加わり、コペルたちは世界や自分と向かい合う。 ユージンが学校に行かなくなった理由は、コペルには思い当たらなかった。 「なぜ?」と問いただしても、何も言わないユージンを気にしながらも、いつかコペルはユージンと本音で話すことのできない距離を感じてしまっていた。 けれど、ユージンが学校に行かなくなった理由に自分が関与しているなんて微塵も思っていなかった。 きっかけは小学校教師の行動だった。 ユージンが卵から返して可愛がっていたニワトリのコッコを、学校で飼ってもらおうと連れて行ったら、命の教育の一環としてサバいて食べるという。 ユージンはもちろん、コペルだって、その必然性のない殺戮は変だと思った。 けれど言えなかった。 命を守ってあげることが出来なかった。 考え続けるユージン。 忘れていたコペル。 “「何かがおかしい」って、「違和感」を覚える力、「引っ掛かり」に意識のスポットライトを当てる力が、なかったんだ。「正論風」にとうとうと述べられると、途中で判断能力が麻痺してしまう癖もあった。” “あのとき、僕らが「つぶした」のは、単なるニワトリ一羽だけじゃない。ユージンの「心」も一緒に「つぶした」” 教室の中でも、地域の中でも、国の問題でも、多数決で解決しきれないことはいくらでもある。 白か黒か。ゼロか百か。 世のなかはそんなに単純じゃないはず。 “一人の個性を無理やり大人数に合わせようとする。数をかさにきて、一人の個性をつぶそうとする。しかも表向き、みんなになじませようとしているんだ、という親切を装って、 こういうのって、つまり、全体主義の「初めの一歩」なんだろう。” 自分が簡単に親友を裏切って大勢の側に立てる人間だったことを知り、衝撃を受けるコペル。 “……泣いたら、だめだ。考え続けられなくなるから” 梨木香歩の書く文章はとてもやわらかいのに、書いていることはとても厳しい。 ユージンの従姉のショウコは、心も体も大きくて強い。 “黙ってた方が、何か、プライドが保てる気がするんだ。こんなことに傷ついていない、何とも思ってないっていう方が、人間の器が大きいような気がするんだ。でも、それは違う。大事なことがとりこぼれていく。人間は傷つきやすくて壊れやすいものだってことが。傷ついていないふりをするのは格好いいことでも強いことでもないよ。あんたが踏んでんのは私の足で、痛いんだ、早く外してくれ、っていわなきゃ” そして “正面からぶつかって、玉砕するよりも、もっと、現実的に多くの人を助ける方法。とにかく生き延びて次世代のために尽くす、とか” 私も最近、正解より最適解について考えることが多い。 どうすることが、結果的に一番良であるのか。 “そう、人が生きるために、群れは必要だ。強制や糾弾のない、許し合える、ゆるやかで温かい絆の群れが。人が一人になることも了解してくれる、離れていくことも認めてくれる、けど、いつでも迎えてくれる、そんな「いい加減」の群れ” そんな「群れの体温」みたいなものを必要としている人に、コペルはこの言葉を言う力を自分につけるために、考え続けて生きていく。 “やあ。 よかったら、ここにおいでよ。 気に入ったら、 ここが君の席だよ。” 閉塞感が募る今の日本で、この本は若者だけではなく、大人にも読んでほしいと思う。
Posted by
尋常じゃなく大人びた中学生たちが タイトルの通り現代で自分たちが「どう生きるか」について それぞれに背負った苦痛や経験を元に考え、 分かち合い、許し合う物語。 凄く小難しいテーマを (非現実的ではあるけれども) 非常に理解しやすく身近な問題に置き換えて描いている。 読んでいて、...
尋常じゃなく大人びた中学生たちが タイトルの通り現代で自分たちが「どう生きるか」について それぞれに背負った苦痛や経験を元に考え、 分かち合い、許し合う物語。 凄く小難しいテーマを (非現実的ではあるけれども) 非常に理解しやすく身近な問題に置き換えて描いている。 読んでいて、つっかかるところは殆どない。 手に取った瞬間の表紙の厚みから その変のありふれた文庫本とは違う これは特別な本なんだ、という感触があった。 著者をはじめ、出版に関わった人々の熱意が感じられる良本。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「君たちはどう生きるか」を読み終え、この本を思い出した。再読。 あちらのスピンオフかと思ったら全然別物。 この本の凄さを改めて認識し、それに付け加え内容の濃さと自然との共存というテ-マのひとつを再認識。若い女の子にもぜひ読んでいただきたい。 世の中にはこんなにも若い人向けの本が充実しているのになかなか手元に届かない。どうしたら、届けられるのだろうというジレンマにまた当分悩まされそう。 機会があれば紹介したい本の一冊に!
Posted by
前書き 群れが大きく激しく動く その一瞬前にも 自分を保っているために 澤地久枝氏の解説より 日本はこの前の戦争終結以来、一人の戦死者も出していない。一人の外国人も殺していない。世界に誇っていい記録だ。それでも、政治は戦争の方向へ動いてゆく。あやういかなの時相である。
Posted by
なぜこの表紙なのか、なぜこのタイトルなのか、と思いながら読み始めた。小説の文章はとても読みやすい現代文。主人公の少年コペル君の話し言葉だ。だが、読み進めていくにつれ話題が深化していく。小学校で不登校になった親友ユージンに何が起きたのか、そのときコペル君自身が何をしたのか。偶然出会...
なぜこの表紙なのか、なぜこのタイトルなのか、と思いながら読み始めた。小説の文章はとても読みやすい現代文。主人公の少年コペル君の話し言葉だ。だが、読み進めていくにつれ話題が深化していく。小学校で不登校になった親友ユージンに何が起きたのか、そのときコペル君自身が何をしたのか。偶然出会った傷心の少女インジャに何をしてあげられるのか。戦前に徴兵拒否した青年の話題と現代のコペルたちの悩みが重なっていく。この表紙とタイトルは時代を超えた守るべき共通の価値観を考える象徴だった。
Posted by