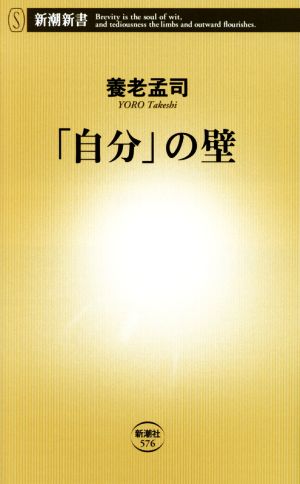「自分」の壁 の商品レビュー
バカの壁を読んだ後、自分の理解力、読解力不足に凹んだ。こちらの本は自己嫌悪に陥いることなく?読み、納得する部分が多かった。個人的に社会性の中で生きていくことに充足感を感じていた理由が自身の中で腑に落ち、自己理解に繋がった。
Posted by
この著者は、「医学」・「昆虫」・「独自の推論」が受けているのがわかるが、「経済」に関してだけは、あまり語らない方がよいと思います。
Posted by
確固たる「自分」というものはいるのか。 そんなのはいないのではないか。 というのが筆者の主張です。(養老氏は他の書籍でも同様のことを述べています) 「自分」なんてない。自分は他者と社会と他の生物と地球と繋がっているし、変化しているんだ。 大事なのは「人といかに違う...
確固たる「自分」というものはいるのか。 そんなのはいないのではないか。 というのが筆者の主張です。(養老氏は他の書籍でも同様のことを述べています) 「自分」なんてない。自分は他者と社会と他の生物と地球と繋がっているし、変化しているんだ。 大事なのは「人といかに違うか」ではなく、人と同じところを探すこと。世間と折り合いをつけて生きること。 しかし、戦後、「私」「個性」「独創性」ということを求められてきてからおかしくなってきた。 そのことを、世間との関わり、生物学としての面、江戸時代の日本などから説明しています。 その他、 政治に関わらない、世の中を変えようとしない話 意識は信用できない、言葉と現実は別ものの話 あふれる情報、情報過多に左右されないための話 人生は、ゴツゴツしたものである話 など、全体を通して、筆者の「人間はあくまでも自然の中の1つ」という考えが書かれています。 養老氏の切り口は「ゆったり」とした考え方、姿勢を与えてくれます。 よろしければ。
Posted by
彼によれば、個性や、自己の確立というものは、西洋世界から来たものであって、根本的に日本人の性質になじむものではないと、彼は、主張している。さらに、もともと日本人は、「自己」とか「個性」をさほど大切なものだとは考えていなかったと推測もしている。 自己、自分という境界線は実に曖昧で、...
彼によれば、個性や、自己の確立というものは、西洋世界から来たものであって、根本的に日本人の性質になじむものではないと、彼は、主張している。さらに、もともと日本人は、「自己」とか「個性」をさほど大切なものだとは考えていなかったと推測もしている。 自己、自分という境界線は実に曖昧で、明確にとらえられないものでる。人間の意識は自分をえこひいきしていて、例えば、自分の口の中にある唾液を汚いとは思わないのに、それが自分の外に出たとたんに汚いものとみなされる。つまり、人間はの脳は、ここまでが自分でここまでは、自分のものではないと境界をつけていて、人間の脳、意識は「ここからここまでが自分だ」と自己の範囲を決めている。 彼曰く、生物学的な「自分」とは、地図の中の矢印に過ぎない。そして、社会的に見ても、日本において「自分」を立てることが、そう重要だとも思わない。それよりも世間と折り合うことの大切さを教えたほうがはるかにましだと言っている。 また、彼は、本当の自分というものは、最後に残ったものだと言っている。人間はだれしも世間と折り合いをつけられない部分が出てくる。そして、世間と自分は争うことになってくるが、その結果残った自分というものが「本当の自分」のはずだと言っている。「本当の自分」というのは徹底的に争ったあとに残り、またそれはそういう過程を踏まないと見えてこないという面がある、と彼は主張している。 本当の自分というのは、せいぜい現在位置の矢印だと考えてみる。べつにふらふらと動いても構わない、なぜなら現在位置は動くものだからだそう。 また、自然環境や人間が生きている地球の生態系を見れば、個性というものは、あまり現実味がないことともいえる。人間を含めすべての生き物は地球上で相互作用的に生きていて、また、人間の身体も様々な生物、生命の集合体でもある。生物は、体内に菌などの別の生物を持っていることは珍しくない。なので、すべての生き物は運命共同体であり、共生している。そういう在り方が自然的である。よって、確固とした個性をもって、確固とした自分をもって独立して生きるということは、不自然なことであり、生物としての本質から離れてしまっている。 田んぼは私とたとえられるように、私は環境の一部である。 *アイヌの熊送り
Posted by
自己を大切にすることは周りとの境界がはっきりすること メタメッセージ 行きすぎると疲れてしまう 自分を縛らず自然に触れること
Posted by
体調が上向く布石となった価値ある本。自分なんて分からなくて当たり前との記述が目から鱗でした。 『自分探しなんてムダなこと』 『自分とは地図の中の矢印である』 『自分以外の存在を意識せよ』 本文中のこれらの意見に浸るうちに、脳みそが柔軟体操をしてるかのごとく、グニャっとして楽になり...
体調が上向く布石となった価値ある本。自分なんて分からなくて当たり前との記述が目から鱗でした。 『自分探しなんてムダなこと』 『自分とは地図の中の矢印である』 『自分以外の存在を意識せよ』 本文中のこれらの意見に浸るうちに、脳みそが柔軟体操をしてるかのごとく、グニャっとして楽になります。 養老孟司さんの本は大好きでたくさん読んでます。文章力が確かで柔らかくて癒されます。 ただ、この本は興味のない箇所も多いので減点1。
Posted by
GDPが高い方が自殺率高くなるのは初知り。 格差が広がることが原因になるって見栄やお金を稼いだら幸せと疑わない人が一定数いるってことだよな。 エジプトは日本より豊かではないけどみんな似たような状況だから自殺者がいないとか。 今は簡単になんでも調べられるから調べすぎることでアイデア...
GDPが高い方が自殺率高くなるのは初知り。 格差が広がることが原因になるって見栄やお金を稼いだら幸せと疑わない人が一定数いるってことだよな。 エジプトは日本より豊かではないけどみんな似たような状況だから自殺者がいないとか。 今は簡単になんでも調べられるから調べすぎることでアイデアが出にくくなるというのは同意できた。 やっぱり自分自身で問題を定義することが重要だな。 自然の中で15分過ごすと認知能力や活力、熟考力が増すらしいから試そうと思った。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
養老孟司氏の本はサラッと読める。 そして、「死」の壁等、他の本と内容が重複しているところもあり、私にとっては復習がてら丁度良い。 日本では戦後「個性」「自己主張」という考え方が増幅した、というところはなるほどなと思った。 細胞や細菌の話はすごく興味深く、自分という存在や意識というのはどこからくるのだろうと考えさせられる。
Posted by
『バカの壁』『超バカの壁』『死の壁』と、養老さんの壁シリーズは都度読んで参りました。毎度毎度あ〜分かるぅ〜、納得ぅ〜っと言う記憶だけあって内容は全く覚えておりませんので、偶に読み返すのも必要だと思いますね。あ、『人の壁』は未読か。 特に年齢を重ねる毎に壁シリーズの面白さと言うか...
『バカの壁』『超バカの壁』『死の壁』と、養老さんの壁シリーズは都度読んで参りました。毎度毎度あ〜分かるぅ〜、納得ぅ〜っと言う記憶だけあって内容は全く覚えておりませんので、偶に読み返すのも必要だと思いますね。あ、『人の壁』は未読か。 特に年齢を重ねる毎に壁シリーズの面白さと言うか、筆者の捉え所の良さを実感します。 脳、人生、医療、死、情報、仕事について筆者の考えが方が相変わらず面白い、いや、そうなって欲しいと思いますが、経営者の立場としては仕事については些か賛成出来ない事もありました。 ま、昆虫好きの学者さんですから浮世離れしている所も散見できすし、それがまたいいんでしょうか。 この猛暑の中、クーラーの効いた部屋で昼寝を狙って読むには最高の本ですね。 次の壁は何でしょうか。私としては『信用取引の壁』と言うのを一筆お願いしたい、そうです、今年信用取引で大損した私です。株は現物に限ります、そこテストに出ますからね。Twitterの煽りに乗せられてんじゃねーよ、このバカ、バカは私か。やはりバカの壁を越えられない私です。
Posted by
「自己」についての意識について考えさせられた。 西欧の「個性」「自己主張」が善とされ、それを日本にも取り入れようと教育や社会で「自分らしさ」が叫ばれているけれど、日本には自己をなくし共同体で生きる文化が根付いているという文化的背景を無視したまま他の文化から来た価値観を取り入れる...
「自己」についての意識について考えさせられた。 西欧の「個性」「自己主張」が善とされ、それを日本にも取り入れようと教育や社会で「自分らしさ」が叫ばれているけれど、日本には自己をなくし共同体で生きる文化が根付いているという文化的背景を無視したまま他の文化から来た価値観を取り入れるのは、一旦ちょっと待ったをかけてもいいのかもしれない。 自然との触れ合いについて何が分かるのかは「やってみればわかる」としか記述されていなかったので気になってしまった。
Posted by