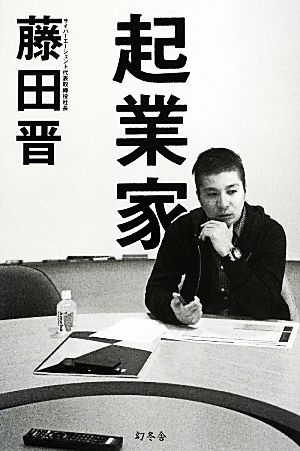起業家 の商品レビュー
この方の著書は初めて読んだ。とにかく、まじめな人柄というか、起業家、社長「らしく」ないんじゃないか?という感想をずっと抱き続けながら読了。最後に、アメーバという事業を立ち上げ、如何に成功に導くことができたか、という話になり、急に山場が来るような全体構成。それまでの内容は実は正直、...
この方の著書は初めて読んだ。とにかく、まじめな人柄というか、起業家、社長「らしく」ないんじゃないか?という感想をずっと抱き続けながら読了。最後に、アメーバという事業を立ち上げ、如何に成功に導くことができたか、という話になり、急に山場が来るような全体構成。それまでの内容は実は正直、退屈というか、盛り上がりがないように感じられ、読み進めるのに必要な刺激というものが少なかったという気がする。淡々としているというか、まじめで、温厚な人柄なんだなあ....とひたすらそれを感じ続けながら、最後のアメーバ事業のくだりになった途端、ページをめくるスピードが一気にあがり、そして、普通の本だったら、後書きに謝辞として定型的に書かれるような、お世話になった方のお礼も本文内容に含まれていて、ま、それも、まじめな人柄の表れなのかな...と思わせられたり。 この方のマネジメントスタイルは、本書にも語られているように、任せて後は口出しせず、というもの。それが敗因として、最後はそれと決別し、長年夢見ていた事業の成功を達成することが出来た、ということが、繰り返し失敗を失敗として、くどいくらい反省調で語っている。自分の仕事スタイルと比べても、そりゃ任せて口出しせずってのは、リーダーシップとは違うし、最後に上手く事業を成功させるまでの、それまでとは違うマネジメントスタイルの方が、リーダーシップとしてはあるべき姿なんじゃないの?と思ったりはするが、あとから言うことはいくらでもできるわけで、フェアじゃないのは分かってるわけで、まあ、それに気づくまでものすごく時間がかかって、ものすごく悩んで、失敗をいっぱいして、それにたどり着きました、という告白は、ダサいかも知れないが、やっぱりずっとさっきから言って(書いて)いるように、ほんとにまじめで、温厚な性格の方なんだろうな、と伝わってくる。 ビジネス本として読むには、やや冗長で、この方の性格みたいなものに、延々付会うことになり、最後、リーダーシップってそうだよね、という点ぐらいが読んで得られるぐらい、という感じだが、一人の起業家の、10年以上に渡る心の内がどんなもんだったのか、というノンフィクションとして読むのは、同じ起業家や、企業人には面白いだろうと思う。 ということで、いちおうやっぱりお薦めはします。
Posted by
サイバーエージェントがどのような経緯で今があるかを分かる本。 アメーバブログに取り組むときの藤田社長の姿が印象的。 買収の問題や黒字化までの踏ん張りについて印象に残っている。
Posted by
啓太さんのアワードの話を聞き読む。 サイバーが広告代理店から、メディア事業に以下に転換をしていったのかについて、経緯と共に書かれている本。 ・最初はホリエモンとの交流からしったブログの可能性。 ・そのサービスを立ち上げる際に、売上市場主義から、顧客目線に徹底的にこだわりサービスへ...
啓太さんのアワードの話を聞き読む。 サイバーが広告代理店から、メディア事業に以下に転換をしていったのかについて、経緯と共に書かれている本。 ・最初はホリエモンとの交流からしったブログの可能性。 ・そのサービスを立ち上げる際に、売上市場主義から、顧客目線に徹底的にこだわりサービスへ、という採算意識からの脱却という転換点。 ・人に任せるというスタンスから、自らが介入していくことの重要性 ・結果的に成功ラインを超えた時点で、売上が倍々と伸びていくメディア事業の面白さ という展開性は非常に面白い。 特にネットの中で、強いサービスを作るということに従事されている人にとっては共感するところも多いのでは、感じます。 以下抜粋 『経営者が現場に違和感を感じたら、そこは口を出してもいいというシグナル』
Posted by
「ユーザー視点」という言葉は、当時のアメーバでも皆が一応は口にしていました。 しかし、本当にそうだとは私には感じられませんでした。 最初はユーザー視点を大事にして開発を始めても、さまざまな利害関係、リソース調整、技術的な制約、スケジュールなどに振り回されて、最後は全く違ったものに...
「ユーザー視点」という言葉は、当時のアメーバでも皆が一応は口にしていました。 しかし、本当にそうだとは私には感じられませんでした。 最初はユーザー視点を大事にして開発を始めても、さまざまな利害関係、リソース調整、技術的な制約、スケジュールなどに振り回されて、最後は全く違ったものになっていました。 雑音に惑わされず、ユーザー視点を貫く強いリーダーが必要でした。 経営者として長年「メディア事業」に取り組みながらも、それまで取り組んでいたのは「事業」であって、「メディア」や「コンテンツ」ではありませんでした。 なぜ今までのアメーバのサービスはこけてばかりだったのか。 ネットの場合、テレビでの視聴率にあたる「ページビュー数」を伸ばすためには、仮にコンテンツの力が3割くらいだとすると、残り7割は技術力なのです。 快適な「サーバレスポンス」や、画面推移やレイアウトやデザインなどの「UI」といった技術力がページビューを伸ばすのです。 テレビ局もプロデューサーが視聴率を稼ぐためにコンテンツを強化しようと考えるのと同様に、我々はページビュー数を稼ぐために、何より技術力を強化しなくてはなりませんでした。 「何がアメーバの転換点になったのか?」 「全ての創造はたった1人の『熱狂』から始まる。」 「新しいことを生み出すのは、1人の孤独な『熱狂』である。」 不可能を可能にするのが起業家です。 「絶望しきって死ぬために、今を熱狂して生きろ」
Posted by
<企業理念> ・「21世紀を代表する会社を創る」を理念として掲げ、事業領域は極端な話、伸びている市場であればどこでも良かった。 <戦略> ・広告代理店業からメディア事業に転換することを考え、多くの新規事業を立ち上げ ・一方、投資家からのプレッシャーで短期的な売上を求め、広告代理...
<企業理念> ・「21世紀を代表する会社を創る」を理念として掲げ、事業領域は極端な話、伸びている市場であればどこでも良かった。 <戦略> ・広告代理店業からメディア事業に転換することを考え、多くの新規事業を立ち上げ ・一方、投資家からのプレッシャーで短期的な売上を求め、広告代理店事業に注力 ⇒メディア事業への転換という想いと実際の注力事業が異なる結果に ・サイバーエージェントやリクルートのように強烈なカルチャーを有する企業は、買収先・買収候補先の企業が引いてしまって、買収が上手くいかないことが多い ⇒事業、人材を一から育てる方針に ・一方、ライブドアは積極的に買収を仕掛けていたが、リスク管理の甘さの一因になったのかもしれない? ・メディア事業はもの凄いアクセス数を稼ぐことができ、知名度向上に繋がる ⇒ライブドアがTBSや球団を買収しようとしたのも知名度が欲しかったから。結局、買収に成功せずとも、名乗りを上げるだけで知名度を上げることができた ・結果、メディア事業の責任者3名を更迭、社長自ら「2年で黒字化できなければ社長退任」と自らのクビを賭け、メディア事業に取り組む ←これまではグループ経営を掲げ、事業責任者に委ねていたところ、社長自らが推進 ←新規事業の撤退に関する基準からアメーバ事業を例外的に取り外す →社内の誰よりもアメーバブログを使用していたので、ユーザーの立場から見た改善個所が分かる →IRや会食等の社長としての仕事を最大限に減らし、アメーバ事業に注力する →秋元康が、AKBのブログをアメーバで実施することに快諾 ・ブログ事業でUI含めた利便性を高めるためには技術力が不可欠。サイバーエージェントは技術を外注していたから苦労した ・目標をページビュー一本に絞り込む。売上は見ず、ページビューが一定程度を超えれば売上もついてくると信じる。事業部の社員にもその方針を徹底 ・「孤独、憂鬱、怒り、それを3つ足してもはるかに上回る希望」 ・「たった一人の熱狂」から全ての創作活動は始まる <人材面> ・伸びている市場においては、高度経済成長期の日本型人事制度が機能するのではないかという仮説 ・成果主義、実力主義かつ終身雇用制度を打ち出す。長く在籍する社員を奨励する ・会社が社員を大切にすれば、社員も(自分のキャリアだけではなく、)会社に報いようという気持ちになる ・会社への愛社精神が高まると、社内結婚が増える ・自社カルチャーに染まりやすい新卒を大事にする ・インターネット業界は特殊なため、他業界の中途が即戦力として活躍しづらい ・中途で優秀な人が参画しても、まずは現場から始めてもらう <その他> ・「MADE IN JAPAN -わが体験的国際戦略」(盛田昭夫) ・睡眠以外の全ての時間を仕事に充てる。これだけ仕事をすれば失敗しても仕方がないと思えるところまで追い込む
Posted by
主審雇用、買収をしないという方針での経営を決定。 日本型雇用は右肩上がりの社会で通用する。ネットはあと30年は右肩上がりという見通しのため、そのような方針とした。 アメーバを成功させるためにそれまでは社員の意思を尊重する経営方法だったが、アメーバは自らが取り組む方針とした。
Posted by
2015/05/19 サイバーエージェントが、現在のような1大企業になるまでの道のりを示したもの。渋谷で働く社長の告白の続きのようなものである。この本では、特に堀江さんとの関係や、アメーバブログが普及するまでの苦労などを描いている。順風満帆に育ってきた合えばエージェントだと思って...
2015/05/19 サイバーエージェントが、現在のような1大企業になるまでの道のりを示したもの。渋谷で働く社長の告白の続きのようなものである。この本では、特に堀江さんとの関係や、アメーバブログが普及するまでの苦労などを描いている。順風満帆に育ってきた合えばエージェントだと思っていたが、実はそうではなく、様々な苦労があったのだとうかがえる。特に何を制す者が成功するのかという、不確定な物を信念を持って育てる事は難しいものなのだなと感じた。周りの反対や不安に打ち勝ち、自分の信じるものを育てていき、成功収めるのはほんの一握りの人なのかもしれない。
Posted by
今まで読もうと思っていたが読めずにいた1時間くらいで一気に読み終えた。 起業家ってこういうことなんだなと思った。 これだけ愚直にしっかりと経営していることを知らなかったし、今まで、短期的なことしか見ていなかった自分に反省した。 今、スタートアップ界はバブルだけど、先日藤田さん...
今まで読もうと思っていたが読めずにいた1時間くらいで一気に読み終えた。 起業家ってこういうことなんだなと思った。 これだけ愚直にしっかりと経営していることを知らなかったし、今まで、短期的なことしか見ていなかった自分に反省した。 今、スタートアップ界はバブルだけど、先日藤田さんが言っていたこの状況はおかしいということが身にしみてわかった。 起業家として、何を大切にするべきか、現代の起業家が考えるべきことがしっかりと詰まっている本だった。
Posted by
今や日本を代表する起業家藤田社長の本を初めて読ませていただいた。 最年少でマザーズ上場という輝かしい経歴を持つにもかかわらず、新規事業を軌道に乗せるのに苦労されているのには驚かされた。 『新しいことを生み出すのは、一人の孤独な『熱狂』である』と、『孤独、憂鬱、怒り、それを3つ足し...
今や日本を代表する起業家藤田社長の本を初めて読ませていただいた。 最年少でマザーズ上場という輝かしい経歴を持つにもかかわらず、新規事業を軌道に乗せるのに苦労されているのには驚かされた。 『新しいことを生み出すのは、一人の孤独な『熱狂』である』と、『孤独、憂鬱、怒り、それを3つ足してもはるかに上回る希望』は心に響いた。 あと、営業の会社でありプログラマーを軽視している社風に対してプログラマーが嫌気をさしているという点については経営者は注意が必要だと思う。
Posted by
ブックオフで360円で購入 ライブドア 堀江の逮捕の時とかそれからの奮闘などがオープンに書かれてあるのでおもしろかった。 「全ての創造はたった一人の熱狂から始まる」には感動を覚える。
Posted by