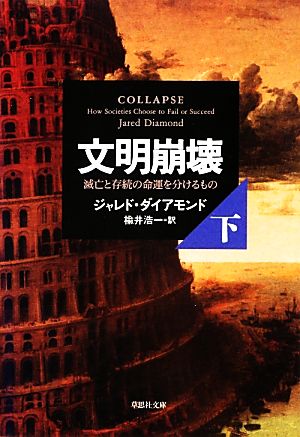文明崩壊(下) の商品レビュー
ホテル・ルワンダで有名なツチ族80万人(ツチ族の4分の3)の大虐殺は、単にフツ族との民族紛争でなく、過密になった人口圧力と飢餓によって同じ民族同士で殺しあったという。 アフリカで人口が急増したのは、北米原産のトウモロコシ、豆、サツマイモなどがアフリカにも取り入れられ、食料生産が飛...
ホテル・ルワンダで有名なツチ族80万人(ツチ族の4分の3)の大虐殺は、単にフツ族との民族紛争でなく、過密になった人口圧力と飢餓によって同じ民族同士で殺しあったという。 アフリカで人口が急増したのは、北米原産のトウモロコシ、豆、サツマイモなどがアフリカにも取り入れられ、食料生産が飛躍的に拡大したことがあげられる。 ところが、足し算でしか伸びない食料生産の増加は、掛け算で伸びる人口増加のスピードに追いついていない。 衛生状態が改善されて、抗生物質や予防接種が乳児死亡率を低下させたこと、マラリアなどの風土病も抑止されたこと、国家が統一され、国境が定まったことによりこれまで無人地帯だったところも居住可能になったことなどから、ケニアなど人口が毎年4%も伸び、17年で人口が倍増している。 過密になった人口が農地開拓や森林伐採によって環境を破壊したことが、イースター島や、古代マヤ文明、ノルウェー領グリーンランドの文明が崩壊した原因だった。 「世界はひとつの干拓地」だ。 環境破壊による文明の衰退は現在のオーストラリアや中国、ハイチとドミニカ共和国でも静かに進行している。
Posted by
時代や国を縦横無尽に駆け巡り、知性と感性に訴えかけつつ現代への警鐘を鳴らす。 久しぶりに、本当に、読むに値する本に出会った気がする。
Posted by
自分たちの文明が崩壊しないためにできることはあるのか、最後に著者が問いかける。 考えさせられる本の一つでした。
Posted by
話題となった著作『銃・病原菌・鉄』で、「人類の歴史をこんな形でとらえることが出来るのか」と、目を開かせてもらった学者、ジャレド・ダイアモンド。 その後続となる著作が文庫化されていたので、取り組んでみることにしました。 「文明」について、その興隆と滅亡を分ける要因とはなにか。 イー...
話題となった著作『銃・病原菌・鉄』で、「人類の歴史をこんな形でとらえることが出来るのか」と、目を開かせてもらった学者、ジャレド・ダイアモンド。 その後続となる著作が文庫化されていたので、取り組んでみることにしました。 「文明」について、その興隆と滅亡を分ける要因とはなにか。 イースター島など、滅亡した文明や、厳しい環境のなかで存続している文明を分析することで、その答えを模索しています。 もともと、「環境破壊と文明の繁栄」についての研究というのが始まりだったようなので、その面での考察に多くのページが割かれています。 上下間合わせて1100ページに及ぶ大著。 論点も多岐に渡るため、簡単にまとめるべきではないとは思いますが、全体を通じて僕が受け取ったのは以下のようなことです。 ・人間が生きていく上で、衣食住に関わる資源は、間違いなく必要なものである。 ・かたや、文明が繁栄すると、人口は増える。 ・人口の増加に対して、資源の調達が追いつかなくなると、その文明は滅びる。 文明存続に成功した事例として、江戸時代の政策によって高い森林占有率を保っている日本も、挙げられています。 物流の発達により、世界的に資源のやりとりができるようになった現在の世界では、上記の考え方に加えて、経済的な優位性と安全保障という切り口が加わるのかな、などということも考えました。 ひとつひとつの事例も興味深く、膨大な知識をもって書かれた著作なのだなあと感じる力作でした。 この後の著作も発表されているようなので、文庫化を待って読んでみたいと思います。
Posted by
「〜文明は滅びて、〜文明が栄えました」を、詳細に多角的に推測。 歴史の副読本に! かつ、現代の諸都市にもフォーカスをあてるので、ちょっと怖くもなる。 ゲンダイブンメイは滅びました。。。って言われたくないなぁ。
Posted by
上下巻を読み終えて…。 唸るほどに面白い。 2005年に書かれたものだが、古さは感じない。 現状を言い当てられているようだ。 『ある社会(文明)は、何故崩壊したのか』、滅びのメカニズムを分析して、そこに普遍性を見いだし、将来進むべき道を模索していく。 特に、下巻の第3部、第4...
上下巻を読み終えて…。 唸るほどに面白い。 2005年に書かれたものだが、古さは感じない。 現状を言い当てられているようだ。 『ある社会(文明)は、何故崩壊したのか』、滅びのメカニズムを分析して、そこに普遍性を見いだし、将来進むべき道を模索していく。 特に、下巻の第3部、第4部は興味深い。 【第3部 現代の社会】 第10章(アフリカ ルワンダ) 第11章(ドミニカ、ハイチ) 第12章(中国) ※最近ニュースで取り上げられている大気汚染についても書かれている。 第13章(オーストラリア) 【第4部 将来に向けて】 第14~16章は、本書を際立たせている。 『先進国の住民が現在享受しているライフスタイルを、あらゆる人が切望した場合、世界にどのような影響が及ぶのか?』 我々がとるべき行動とは何かを問いかけてくれた。
Posted by
歴史上、文明崩壊の危機は多々訪れているし、崩壊した文明も少なくない、ということを再認識。(特にこの本で触れられてはいないけど、日本の大和政権以前や中世戦乱期も崩壊の危機だったのか) その文明の歴史自体が続いて当然、と思って過去を眺めていたことに気がついた。現在の立場からの知識で見...
歴史上、文明崩壊の危機は多々訪れているし、崩壊した文明も少なくない、ということを再認識。(特にこの本で触れられてはいないけど、日本の大和政権以前や中世戦乱期も崩壊の危機だったのか) その文明の歴史自体が続いて当然、と思って過去を眺めていたことに気がついた。現在の立場からの知識で見ていてはいけないな。 また環境面や経済的な問題にも目を配る必要性も感じさせられた。 価値観の転換、という部分がとても興味深い。 価値観をどうするか(守り続けるか捨てるか)でその社会の将来が決まる。 その選択の理由もまた探れるのではないのか。選択の主体は個人ではないから、全く自由に選べるわけではないはず。 少なくとも先進国では、教育は広まっているし、現在は過去の社会よりも正しい選択が行われる可能性は高いのではないかな。
Posted by