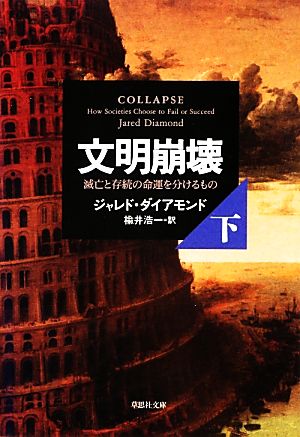文明崩壊(下) の商品レビュー
下巻は人間が文明崩壊に至らず、存続した過去の社会や、文明崩壊の要因と密接に絡み合っている現代社会、そして今後人間社会が存続するために出来ることが詳細に書いてある。例えば、日本は江戸時代に森林破壊が進んでいたが、トップダウン型の政治組織をうまく活用してこれを食い止めた。現代社会にお...
下巻は人間が文明崩壊に至らず、存続した過去の社会や、文明崩壊の要因と密接に絡み合っている現代社会、そして今後人間社会が存続するために出来ることが詳細に書いてある。例えば、日本は江戸時代に森林破壊が進んでいたが、トップダウン型の政治組織をうまく活用してこれを食い止めた。現代社会における転換の発想の面白い例としてはオーストリアである。生産性の低い土地で農作物を作るより、そこをレジャーや研究開発に回した方がいいという考えである。
Posted by
過去の事例を紐解き、現代に警鐘を鳴らす良書。かなりのボリュームで読むには根気がいるが、後世への負の遺産を残すことなく、この世の永続は環境との共存と人類の謙虚さ、慎ましやかさが必要だ。意思決定システムのエラーは人類の最も恥ずべき行為である。三人寄れば文殊の知恵ではない集団心理を構造...
過去の事例を紐解き、現代に警鐘を鳴らす良書。かなりのボリュームで読むには根気がいるが、後世への負の遺産を残すことなく、この世の永続は環境との共存と人類の謙虚さ、慎ましやかさが必要だ。意思決定システムのエラーは人類の最も恥ずべき行為である。三人寄れば文殊の知恵ではない集団心理を構造的に抉るには様々な知見が必要だろう。
Posted by
環境問題に関しては気が滅入るような内容が多いが、分析力や情報量が多く非常に勉強になる。 江戸時代の森林保護などは全く知らなかった事例だった。博士が自然エネルギー技術の進展に期待を寄せていないのは少し残念な気がした。 環境問題のキーとなるのは大企業を中心とする経済活動にあり、環境へ...
環境問題に関しては気が滅入るような内容が多いが、分析力や情報量が多く非常に勉強になる。 江戸時代の森林保護などは全く知らなかった事例だった。博士が自然エネルギー技術の進展に期待を寄せていないのは少し残念な気がした。 環境問題のキーとなるのは大企業を中心とする経済活動にあり、環境への取り組みが評価を得て会社の利益にとってもプラスとなる方向性に今後も進んで行くことを期待したい。 広く危機意識を持ってもらうためには、身近に環境問題由来の災害などが作用しなければダメなのか… より先見の明を持たせる啓蒙が急務と感じた。 日本の国会で環境問題について議論されることはあるのか?聞いたことがない… トランプ政権の方向性について見てもアメリカがどれだけ愚かな国かと呆れるばかりで、文明の将来に暗い影を落としている。 ゴアのような人物がまた出てきてほしいと願うばかり
Posted by
マヤ文明とかエスキモーとかの話含めて、人が生きるには何が必要か?サステナビリティとはなぜ必要か?それが綺麗事でなくわかる本。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
いろいろ示唆に富んでいて、得たものは多かったのだが、特に一つ言えるのは、『土壌』が消耗される資源だという認識はコレを読むまで一切無かった。 オーストラリアが食料(主に小麦)輸出国なのは当たり前だと思っていたが、かなり無理矢理な形なのか(そして、であるからこそ、いつまでも続くものではないのか)
Posted by
前作の銃・病原菌・鉄ほどのインパクトはないが、環境の持続可能性という視点も含めて、人が環境に適合することの困難さを多数の事例を上げて説明しており示唆に富むところが多い。 環境破壊と文明崩壊が、すべての事例においてそこまで直截に関連していたかはさておき、100年後の世界のためにいま...
前作の銃・病原菌・鉄ほどのインパクトはないが、環境の持続可能性という視点も含めて、人が環境に適合することの困難さを多数の事例を上げて説明しており示唆に富むところが多い。 環境破壊と文明崩壊が、すべての事例においてそこまで直截に関連していたかはさておき、100年後の世界のためにいま何ができるのか、もう一度考える機会を与えてくれる。 とはいえ、他の方のレビューにもあるとおりやや冗長ではある。
Posted by
「文明崩壊(下)」(ジャレド・ダイアモンド:楡井浩一 訳)を読んだ。 『イースター島の最後に残った一本のヤシの木を前にした島民が、それを切り倒しながらどういう言葉を吐いたのか』(本文より) 我々人類は今その時の彼よりもより多くの情報に接しているのだ。希望はまだあるはずだと思いたい...
「文明崩壊(下)」(ジャレド・ダイアモンド:楡井浩一 訳)を読んだ。 『イースター島の最後に残った一本のヤシの木を前にした島民が、それを切り倒しながらどういう言葉を吐いたのか』(本文より) 我々人類は今その時の彼よりもより多くの情報に接しているのだ。希望はまだあるはずだと思いたい。
Posted by
章テーマの問題もあるが上巻より面白い。但し全体で1,200ページ超の大作の価値があるかは読む人によるだろう。私にとっては冗長的な内容と明確ではない主張にやや不満があった。 とはいえ個別の事例は面白い。特に一島を東西に隔てるドミニカ共和国とハイチは興味深く、類する位置の2国が(現...
章テーマの問題もあるが上巻より面白い。但し全体で1,200ページ超の大作の価値があるかは読む人によるだろう。私にとっては冗長的な内容と明確ではない主張にやや不満があった。 とはいえ個別の事例は面白い。特に一島を東西に隔てるドミニカ共和国とハイチは興味深く、類する位置の2国が(現にハイチのほうが豊かな時代もあった)が、人種や文化、環境の微妙な相違が累積し、ドミニカ共和国は持続的社会を築き、ハイチは崩壊へ向かっている事実は、文明維持に相当の努力を要することを示す。 ルワンダなど人類の愚かな歴史といった新しい視点はあるものの、興味あるなしが出やすい本だと思うので、下巻まで読むかは上巻の第1章(モンタナ州の事例)を読んで判断するのがよろしい。
Posted by
環境保護運動にとって、象徴的な事例であるイースター島のことは上巻で扱われている。 私もそれを期待して読んだクチなので、下巻は、もういいか、と思っていたが、手に入ったので一通り目を通しておこうか、という低めのテンションで読み始めた。 確かに、分量が分量なので、一気に読み進めることは...
環境保護運動にとって、象徴的な事例であるイースター島のことは上巻で扱われている。 私もそれを期待して読んだクチなので、下巻は、もういいか、と思っていたが、手に入ったので一通り目を通しておこうか、という低めのテンションで読み始めた。 確かに、分量が分量なので、一気に読み進めることはできなかったが、最後まで読みたくさせる本だった。 最初に、森林破壊が進んで一時は文明が崩壊する危険があったにもかかわらず、その危機を切り抜けた二つの事例が紹介される。 それがニューギニアのティコピア島と、江戸時代の日本だ。 共通点は外部から閉ざされた社会だったこと。 違いは社会と国土の大きさ。 小さな社会だったティコピア島は、島民皆が島のことを把握できるサイズだったため、ボトムアップで社会と環境のコントロールをした。 一方、日本は、幕府や大名が自分たちと子孫が得られる恩恵を損なわないために、トップダウンで厳しい山林や木材の流通管理を徹底させた。 読んでいると、ダイアモンド教授は江戸時代も現在も日本は外部に環境破壊や資源の枯渇を転嫁していると見ているようだ。 耳が痛い話だ。 「第14章 社会が破滅的な決断を下すのはなぜか?」は、四つの失敗のロードマップを示している。 問題の予期への失敗、(予期はできても)問題の感知の失敗、(感知はできても)解決を試みられないという失敗、(解決を試みても)解決に失敗する、ということらしい。 それぞれについて、本書の中で検討されてきた事例が例に挙がっている。 共有地の悲劇や、囚人のジレンマとして分析される、短期的な利己的な行動の優先は、解決の試みに失敗する事例だそうだ。 そして、その解決方法も、本書には提案されている。 消費者が共通の利益を認識し、利用のルールを決めていくことだという。 そうだな、と思いつつも、温暖化対策の国際会議が難航しているのを見ると、これから行くべき道はまだまだ遠いな、と思ってしまう。 こんな風に、既にあきらめモードに入った私に、ダイヤモンド教授は、最後の檄をくれる。 「第16章 世界はひとつの干拓地」は、環境保護を批判する「よくある言説」を10パターンほど取り上げて、反駁していく。 私には「個人での取り組みに何の意味があるのか」が一番陥りやすいところだったが、これは何と、参考文献リストの中で、普通の人ができる6つの方法が挙げられている。 投票と、不買/購買運動、企業の環境対策をを批判/称賛する、宗教団体を通じて活動する、地元の環境保護活動に参加する、自然保護団体に寄付する、の6つだ。 う~ん…。これさえできるかなあ、と思っていると、すかさず「すぐに変化を期待するな」、「生涯を通じ、根気よく、複数の行動を続けなくてはいけない。」とある。 すっかり見透かされてる?
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
徳川時代の裕福な農民が普通に想定し、もっと貧しい村人も希望したのは、自分の土地を何自分の後継に譲ることだった。そういう理由などから、日本の森林管理は、しだいに森林の長期的な既得権を持つ国民の手に委ねられるようになった。なぜなら、それによって人々が自分の子どもに森林の利用権を継がせることを期待するから、あるいは、さまざまな形での長期の賃貸や契約が可能になるからだ。(p.69) ルワンダの大量虐殺の根源を理解することは、たいへん重要なのだ。殺人者に責任逃れをさせたいからではなく、ルワンダや、他の場所であのようなことがふたたび起こる危険性を減らすために、その知識を利用したいからだ。同じような目的から、ナチのホロコーストの根源を理解すること、あるいは連続殺人犯と強姦犯の心理を理解することに生涯を捧げる決意をした人々もいる。彼らがそういう決意をしたのは、ヒットラーや連続殺人犯や強姦犯の責任を軽減するためではなく、ああいう恐ろしいことがなぜ現実となったのか、再発を防ぐ最善の方法とは何かを探るためだ。(p.107) 先進国の住民が現在享受しているライフスタイルを、あらゆる人が切望した場合、世界にどのような影響が及ぶのかについては、中国がよい具体例を示してくれる。中国は、世界最大の人口と、最も急速に成長する経済を併せ持っているからだ。(中略)中国が先進国の基準に達すれば、全世界の人間による資源利用と環境侵害がほぼ倍増するのだ。ところが、現在の世界の資源利用と環境侵害でさえ、このまま維持できるとは考えにくい。どこかで歯止めが必要だろう。中国の問題がそのまま世界の問題になる最も強い理由は、そこにある。(pp.188-189) 基本的価値観の一部が生存と両立しえなくなってなってきたと感じるとき、それを捨て去るかどうかを決断することは、痛ましいほどの困難を伴う。どの時点で、わたしたちは個人として、妥協して生きるより死ぬことを選ぶのだろうか?現代世界では、実際に何百万もの人々が、自分の命を守るために、友人や親戚を裏切るか、堕落した独裁政権に黙って従うか、事実上の奴隷として生きるか、故国を捨てるかという判断を迫られている。国家や社会も、ときに集団として同様の決断を下さなければならない。 おそらく、一社会としての成功と失敗を分ける肝心な点は、時代が変化したとき、どの基本的価値観を保持し、どの基本的価値観を捨てて新しい価値観と置き換えるべきかを知ることだろう。過去60年で、世界のほとんどの峡谷は、古くから尊重され、かつての国家イメージの中心だった価値観を捨て去る一方で、その他の価値観を保持した。(pp.296-297) 世の中は妥協という土台の上に立った苦渋の選択に充ち満ちているが、これはわたしたちが迫られている最も過酷な妥協だと言っていい。全世界の人々がより高い生活水準を達成できるよう励まし助けながら、同時に、地球の資源に過度の負担をかけてその水準を崩してしまわないよう努めなくてはならないのだ。(pp.408-409) 例えば、ニューギニアでは、葬儀の際、死者に敬意を表するために親族がその肉を分け合って食べるという。「ところが、多くの、もしくはほとんどの欧米の考古学者は、自身の社会において、人肉食は忌避すべきものだと刷り込まれているので、自分の敬愛と研究の対象となる人々がそんな風習を身につけているという考えにも強い忌避感を覚え、事実にふたをして、そういう指摘を人種差別主義者の中傷とみなす」(上巻305~306ページ)(p.409)
Posted by