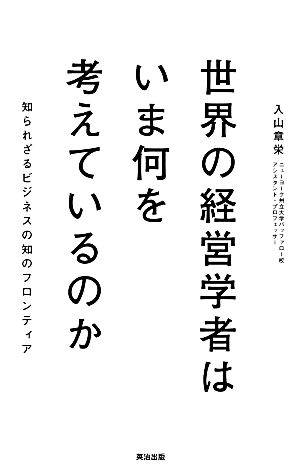世界の経営学者はいま何を考えているのか の商品レビュー
枕元に積んでありましたがようやく読みました。 経営学がまだ若い学問であり発展途上という事がよくわかりました。組織の記憶力の考え方が非常に面白かった。
Posted by
組織の全員が同じ情報を持っていればいいわけではなく、他の人が何を知っているかを知っているか、who knows whatが重要。 ウェグナーの実験にあるように、人は交流を深めれば自然にトランザクティブメモリーを形成するものです。しかし、大きな企業では社員の全員が深い交流をするこ...
組織の全員が同じ情報を持っていればいいわけではなく、他の人が何を知っているかを知っているか、who knows whatが重要。 ウェグナーの実験にあるように、人は交流を深めれば自然にトランザクティブメモリーを形成するものです。しかし、大きな企業では社員の全員が深い交流をすることは難しいため、その形成が難しくなります。 だからと言って、もし中途半端にトランザクティブメモリーができている組織に制度的に記憶の分担の枠組みを与えると、ウェグナーの実験がしめしたように、むしろ両者が軋轢を起こして、組織全体の記憶効率がいちじるしく低下する可能性もあります。 したがって大事なことは、制度的な枠にはめずとも、社員同士が自然にwho knows whatを意識できているような組織を作っていくことではないでしょうか? リアルオプションの考え方 不確実が高い市場では、一気に投資をおこなうのではなく、段階的に投資をしていく。 下振れのリスクと上振れを逃す可能性を下げることができる。 まずは小さくやってみる。 当初の仮定とマイルストーンを記録。 定期的なフィードバックをおこなう。
Posted by
大変勉強になりました。 もっと早く読むべきだったと思うが、遅すぎることはないかと。 アメリカの経営学者はドラッカーを読まない。 大半がケーススタディではなく、統計分析。 経営学の3大流派、経済学ディシプリン、認知心理学ディシプリン、社会学ディシプリン。 ポーター(1980年代...
大変勉強になりました。 もっと早く読むべきだったと思うが、遅すぎることはないかと。 アメリカの経営学者はドラッカーを読まない。 大半がケーススタディではなく、統計分析。 経営学の3大流派、経済学ディシプリン、認知心理学ディシプリン、社会学ディシプリン。 ポーター(1980年代)の戦略だけでは通用しない。持続的競争優位は2〜5%、競争優位を実現できる期間は短くなっている。一旦競争優位を失っても再び獲得できる企業が増えている。一時的な競争優位を連続して作り出せる。ダヴェニ、からの、ウィギンズ、ルエフリ、2000年代初頭。 ハイパーコンペティション、competitive ダイナミクス、より多く競争的行動をとる、長期間競争行動をとる方が市場シェア伸びる。 組織の記憶力は、組織全体が覚えてるのではなく、誰が何を知っているか?を知っておく。 イノベーションに必要な両利きの経営。知と知の組み合わせ、ほどほどに幅広く。知の探索と、知の深化。両利きの企業文化、3Mの15%ルール。 産業によっても異なる、鉄鋼は深く、半導体では弱い結びつき。変化の激しさ、 ストラクチャール・ホール。 海外進出、4つのフレームワーク。 CAGE、カルチャー、administrative、ジオグラフィック、economic(所得格差)、 不確実性の高い時代の事業計画。綿密に? リアルオプション、段階的な計画。最初からDCFではなく。不確実性はチャンス(但しリターンも高いか?) 買収額の払い過ぎについて。 CVC、双方にメリットある(特にベンチャーは、活用できる資産が増える)が、警戒感も。信頼構築が大事。 RBV、経営理論? 経営学は役立つか?理論に偏りすぎ?実証研究をするべき?
Posted by
読み始めたら、一気に読めるほど興味深く、かつ噛み砕いて書かれています。 論文を貪り読みたくなりました。
Posted by
この時点ですでに「両利きの経営(深化と探索)」を唱えていたのか。 これだけ情報が伝播するのが一瞬という時代にも関わらず、人の心に言葉が根付くのには逆に時間がかかっているような気がしてしまう。 2021年の今でこそ、社内のみならず各所で「両利きの経営」の話を聞く。 しかもこの著作、...
この時点ですでに「両利きの経営(深化と探索)」を唱えていたのか。 これだけ情報が伝播するのが一瞬という時代にも関わらず、人の心に言葉が根付くのには逆に時間がかかっているような気がしてしまう。 2021年の今でこそ、社内のみならず各所で「両利きの経営」の話を聞く。 しかもこの著作、約10年前に発行であるが、この10年間で両利きを達成して業績をV字回復した会社はほとんどないということか? それだけ「両利き」が根付いてないということか。 この10年で両利きを意識していれば、必ず業績は回復しているはず。 「『両利き』なんて10年前の理論じゃないか」で切り捨ててもいい話だ。 しかし10年経った今でもこれらが実現できていないことは何を示唆しているのだろう。 本書でも書かれているが、ドラッカーもポーターも今の経営学者は研究していない。 学問にも栄枯盛衰はつきものと思うが、それではこの10年間でどの部分がどう進化していったのかが知りたいところだ。 ビジネスは確かに大きく変化している。 個人的な考えだが、日々の技術進歩、科学の進歩があって、それがビジネスに転用されて変化していっているように感じる。 理想的な経営理論があって、それに合わせて後追いでビジネス自体が変化するということはないと思う。 やっぱりテクノロジー起点と考えるのだが、それは偏った考えだろうか。 一方で最近は人事組織についてもテクノロジーを活用するようになっている。 経営は「戦略」という言葉が一般化したくらい、戦争・競争と切っても切り離させない。 どういう組織が強いのか。どういう人材がいれば勝負に勝てるのか。 ライバル企業に打ち勝つために、この辺をHRテックとして効果的に管理する方法も流行っている。 本書を読むと「必ず勝つ戦略」がどこにもないことに気が付いてしまう。 それは当然であって、もし必ず勝つ戦略が体系化されていて、誰でも真似が出来たらどうなるだろうか。 どの企業もその必ず勝つ戦略を使ったらどこが勝つのだろうか。 そう考えると「どうすれば勝てる組織を作れるか」という点に集約されていくのだということが見えてくる。 なぜ成功した経営者ほど、M&Aでオプションを多めに積み上げてしまうのか。 日本人は集団主義と言われるが本当なのだろうか。 やはり企業は人と組織で左右される。 究極の経営とは、実は人事なのではないだろうか。 そんなことすら本書を読んで考えてしまった。 (2021/12/21)
Posted by
2012年に書かれているので、「いまなにを考えているか」という観点ではちょっと古くなっているのかもしれないが、平易な文章でアカデミアの経営学と実学を連結させようという筆者の意図が伝わってくる。読みやすい。総花的になっているため、結局何だったのかという感想になる可能性は高いが、ざっ...
2012年に書かれているので、「いまなにを考えているか」という観点ではちょっと古くなっているのかもしれないが、平易な文章でアカデミアの経営学と実学を連結させようという筆者の意図が伝わってくる。読みやすい。総花的になっているため、結局何だったのかという感想になる可能性は高いが、ざっくりと2010年代前半までの経営学の研究潮流をとらえる(計量的な分析が多くなっているが、定性的な分析も有効性あるよね)のには良い。
Posted by
経営学は科学である、まだまだ発展途上の学問。 ということを知らなかったので、読んでいて大変新鮮。 明記はなかったが登場する企業は上場企業相当の規模感の印象。逆に述べると中小企業向けではない?? 気になったキーワード 内生性 モデレーティング効果 イノベーションは新たな組み合わ...
経営学は科学である、まだまだ発展途上の学問。 ということを知らなかったので、読んでいて大変新鮮。 明記はなかったが登場する企業は上場企業相当の規模感の印象。逆に述べると中小企業向けではない?? 気になったキーワード 内生性 モデレーティング効果 イノベーションは新たな組み合わせ 知の範囲はほどほどに who know whatが重要 CVCはリアルオプション 等。
Posted by
思ったよりも読みやすかった。 ドラッカーは世界の(アメリカの)経済学の主流ではないのですね。 知の進化も大事、それ以上に知の探索も大事。 経営戦略は単純な表向き、見せかけに騙されるな。 本当に“その”戦略を取ったから業績が上向き、下向きとなったのか改めて考えよ。
Posted by
10%の人員入れ替えのあるチームの方がイノベーションが生まれやすい(コミュニケーションの質が下がらないことが前提)。 多様なバックグラウンドのクリエーターが集まった企画の方が爆発力高い(良い方も悪い方も) 誰が何を知っているかを双方知っていることが資本になる、weak tieによ...
10%の人員入れ替えのあるチームの方がイノベーションが生まれやすい(コミュニケーションの質が下がらないことが前提)。 多様なバックグラウンドのクリエーターが集まった企画の方が爆発力高い(良い方も悪い方も) 誰が何を知っているかを双方知っていることが資本になる、weak tieによる情報伝播の効率の良さ(誰と組むのか、社内知識の集合のヒントになる?)
Posted by
◎購入動機 会社からお勧めの本と共有を受け、興味を持ったため。 ◎所感 アメリカで経営学を研究している入山氏が、世界最先端の経営理論をエッセイ形式で綴っている。 その中でもいくつか興味をそそられたトピックについての要約・感想を述べる。 ⚪︎トランザクティブ・メモリー トラン...
◎購入動機 会社からお勧めの本と共有を受け、興味を持ったため。 ◎所感 アメリカで経営学を研究している入山氏が、世界最先端の経営理論をエッセイ形式で綴っている。 その中でもいくつか興味をそそられたトピックについての要約・感想を述べる。 ⚪︎トランザクティブ・メモリー トランザクティブ・メモリー →組織の記憶力に重要なことは、組織全体が何を覚えているかではなく、組織の各メンバーが他メンバーの“何が誰を知っているか”を知っておくことである、という考え方。 これを自分の環境に置き換えると、例えば自分が何かしらの業界で案件を持った時、同業界の導入の事例を当然把握したくなる。そのために全てのビジネスモデルの導入事例を完璧に記憶していれば良いのだが、現実的ではない上、組織内の記憶力最適化の面で考えれば適切とは言えないだろう。 やはり全ての内容を自身で把握するのではなく、この手の企業であれば“誰に相談すれば良いのか”を知っておくことが大切である。 皆さんがどんな企業とのやり取りがあるのかを把握しておくことが非常に大切である。そのために日々自分以外の方の日報を読む癖をつけたい。 ⚪︎知の探索と知の深化 知の探索 →企業が知の範囲を広げるために新しい知を探す行動のこと。 知の深化 →すでに持っている知識や同質の知に改良を重ね、それらを深めて活用すること。 2つのバランスを取ることが重要。 私自身、やはり刺激の多い“知の探索”ばかりを求めてしまう節がある。 得た知識をいかに実務に活用していくか、浅く広い知識ではなく一歩踏み込んだ深い知識にも真摯に向き合っていきたい。 ⚪︎国民性を数値化する 通常の業務にはあまり関わりがないが、個人的に面白かったトピック。 ざっくりと違うんだろうなと思っていた各国の“国民性”を数値化した研究。 私自身、海外旅行に行っても言葉の壁よりも文化の壁を感じてしまい、その壁をなかなか楽しめないタイプである。 海外市場に進出する際にはあまり懸念されていないとのことだが、軽く見ていると痛い目を見そうな領域。 ◎まとめ 本書に出てくる様々な理論は知らないものばかりだったが、研究手法と結果を学ぶと納得感のいくものばかりだった。 全ての経営学者は企業の経営に貢献したいと考えているはすだが、自分の成果を残すことや自分の理論に反対する勢力を論破することが正義になっている節もあると感じた。 其々の学者が様々な理論が発表し、他の研究者に 立証されることのないままSafariのように乱立される。 学者のビジネスモデルや評価基準を考えれば仕方のないことだし、それも経営学の面白みの一つかもしれないと思った。 経営学がどこまで実際の企業に貢献できるかはわからないが、知の探索の観点からこれからも学び続けていく。
Posted by