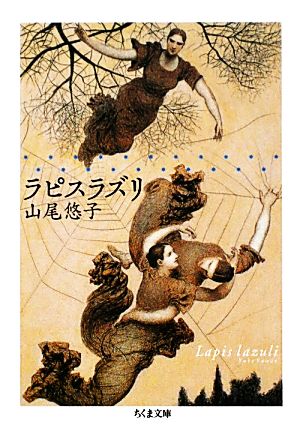ラピスラズリ の商品レビュー
綺麗な作品だとは思うのですが、内容が難解。 登場人物が次々に変わるので、読んでいるうちに「今誰の話をやってるの?」となりました。 冬眠者、使用人、人形、ゴースト、春の目覚め。 寒々しいイメージが重なりあい、絡み合い、幻想的な美しさを醸し出しています。
Posted by
『歪み真珠』から読んでしまったのだけど、『ラピスラズリ』から読めばよかったかな…と思いつつ、でもそれほど違和感なく読めたから、これでよかったのだと思う。難解です。一度読んだくらいではちょっと分からない。特に3つ目の「竈の秋」は人物が多く出てくるし、視点がころころ変わるので日本古典...
『歪み真珠』から読んでしまったのだけど、『ラピスラズリ』から読めばよかったかな…と思いつつ、でもそれほど違和感なく読めたから、これでよかったのだと思う。難解です。一度読んだくらいではちょっと分からない。特に3つ目の「竈の秋」は人物が多く出てくるし、視点がころころ変わるので日本古典文学のようだと思った。私は「閑日」が好きだった。時間を置いてからまた読みたい。ただ、冬眠者たちの物語を冬から春にかけて読めたことは、ベストだったかもしれない。
Posted by
千野帽子さんの解説を読むまで迷路に迷い込んだような気持ちでいた。中世の冬眠者が存在するディストピア小説だと感じていたが、自分の集中力が欠如して、誰の言葉なのか?どこにいるのか?場面が違うのか?と自問して迷子になることが頻繁に起こった。 不思議な世界観。読者を迷路に導く構成。独特な...
千野帽子さんの解説を読むまで迷路に迷い込んだような気持ちでいた。中世の冬眠者が存在するディストピア小説だと感じていたが、自分の集中力が欠如して、誰の言葉なのか?どこにいるのか?場面が違うのか?と自問して迷子になることが頻繁に起こった。 不思議な世界観。読者を迷路に導く構成。独特な言葉選び。闇へ、冬へ、死へと誘う小説から聖フランチェスコの再生へと。記憶に残る不思議な小説だった。
Posted by
Boschの絵画のような人の群れにズームインしり俯瞰したり。非常にビジュアルを喚起させる作品だった。時間軸もも同時に存在していて、文字から喚起される場面があふれかえりそうになりながらも収束するさまは、風で舞い上がる枯葉の只中にいる様だった。
Posted by
最初に3枚の銅版画の話が出てきますが、読んで行くとその絵を連想させる部分が他の各章で出てきます。あれはこういう意味やったのか、と腑に落ちる。何回読んでも飽きない作品。
Posted by
美しい文章で綴られる幻想的なお話。冒頭の「銅版」の話がいい。深夜営業している画廊という時点で現実離れしている。冬寝室と名付けられた銅版の絵のルーツを推測していく件に魅せられる。 その後のエピソードはぼんやりと読んでしまったので、ぼんやりとした印象しかない。
Posted by
循環する物語。冬は生き物が静まる季節。しかし、やがて春が来る。夜になると、人は眠る。しかし、やがて朝を迎える。人も犬も、生きて死ぬ。しかし、やがて新たな生命が産まれる。死も夜も冬も永遠ではなく、いつか明けていく。眠りについた者たちの思いとともに、明日を生きよう。
Posted by
山尾悠子が2003年に発表した2作目の書き下ろし長編小説の文庫版。旅の途中、深夜に訪れた画廊で見かけた銅版画から始まる物語です。極限までそぎ落とした文章で、おいそれと簡単には物語に近づくことのできません。じっくりと考えながら咀嚼して味わうことを要求されます。日本にも、こんなに素晴...
山尾悠子が2003年に発表した2作目の書き下ろし長編小説の文庫版。旅の途中、深夜に訪れた画廊で見かけた銅版画から始まる物語です。極限までそぎ落とした文章で、おいそれと簡単には物語に近づくことのできません。じっくりと考えながら咀嚼して味わうことを要求されます。日本にも、こんなに素晴らしい幻想文学が存在するのかと驚きました。
Posted by
ディストピアみのある幻想文学連作集。 日本が舞台らしき部分をもうちょっとくわしく!って感じに惹かれました。
Posted by
幻想小説の大家、山尾悠子の連作長編。 山奥の館に住む冬眠者と使用人の破滅と再生を描く。 時系列や空間が絶えず移り変わり、「意識の流れ」のような物語の流動性を感じさせる美しい文章。 この作品を簡潔明瞭に批評できる語彙と論理的思考を身につけたい。
Posted by