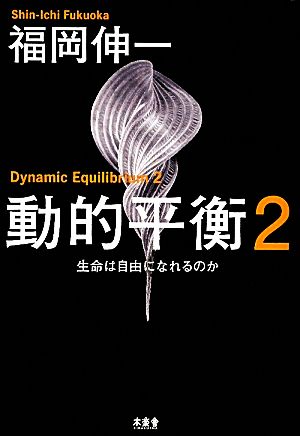動的平衡(2) の商品レビュー
(2012/6/7) この人は、普通に書けば面白くない遺伝子の話を、実に生き生きと、楽しいものに描いてくれる。 文才のある化学者。貴重な存在。見た目はぱっとしないのだけれど、、失礼。おたくであることを自認しながら、我々に、ふだんイメージできない世界をわかりやすく説明してくれるあり...
(2012/6/7) この人は、普通に書けば面白くない遺伝子の話を、実に生き生きと、楽しいものに描いてくれる。 文才のある化学者。貴重な存在。見た目はぱっとしないのだけれど、、失礼。おたくであることを自認しながら、我々に、ふだんイメージできない世界をわかりやすく説明してくれるありがたい存在だ。 動的平衡の第二弾もその文才を遺憾なく発揮してくれている。 いくら鍛えてもそれはRNAのみでDNAには反映されないとか、二酸化炭素が増えて地球が大変といっても、木を見て森を見ず、人間が影響を与えるのはごくごく限られた容量であるとか、覚めた化学の目で、鋭く世相も一緒に切っている。 生理が伝染る という微妙な話からフェロモンを上手に説明したり。 こないだのマラソンで私がお世話になったBCAAを取り上げたり。 読んでいて楽しいから不思議。 副題は「生命は自由になれるのか」あまり上手な副題ではない。読み終わってこの副題をみてもぴんとこない。 目次は 第1章 「自由であれ」という命令 ――遺伝子は生命の楽譜にすぎない 生命体は遺伝子の乗り物か 働きアリにみる「パレートの法則」 ホモ・ルーデンスかロボット機械か サブシステムは自然選択の対象にならない 生命の律動こそ音楽の起源 生命を動かしている遺伝子以外の何か 遺伝子は音楽における楽譜 卵環境は子孫に受け継がれる 第2章 なぜ、多様性が必要か――「分際」を知ることが長持ちの秘訣 子孫を残せないソメイヨシノ 植物は不死である 進化で重要なのは「負ける」こと センス・オブ・ワンダーを追いかけて なぜ、蝶は頑ななまでに食性を守るか 動的だからこそ、恒常性が保たれる 多様性が動的平衡の強靭さを支えている 第3章 植物が動物になった日――動物の必須アミノ酸は何を意味しているか なぜ食べ続けなければならないか なぜ、動物が誕生したか グルタミン酸においしさを感じる理由 「うま味」を探り当てた日本人 地球を支配しているのはトウモロコシ アミノ酸の桶の理論 運動、老化にはBCAAが効果的 第4章 時間を止めて何が見えるか――世界のあらゆる要素は繋がりあっている 昆虫少年の夢 日本最大の甲虫ヤンバルテナガコガネ ファーブルの言明 人間は時間を止めようとする この世界に因果関係は存在しない 第5章 バイオテクノロジーの恩人たち――大腸菌の驚くべき遺伝子交換能力 タンパク質研究の最大の困難さ 大腸菌が遺伝子組み換え技術を可能に 大腸菌とヒトの共生 風土に合ったものを食べる知恵 大腸菌の驚くべきパワー 細菌たちのリベンジ――腸管出血性大腸菌O104 遺伝情報の水平的に伝達するプラスミッド 第6章 生命は宇宙からやって来た――パンスペルミア説の根拠 地球外生命体の証し DNAが先かタンパク質が先か チェック博士のRNAワールド 「生命誕生までに八億年」はあまりにも短い パンスペルミア説 第7章 ヒトフェロモンを探して――異性を惹き付ける物質とその感知器官 ファーブルが探した誘引物質 ブーテナントとシェーンハイマー なぜ「生理は伝染る」か ヒトにもあるフェロモン感知器官 フェロモン香水を作った人たち 第8章 遺伝は本当に遺伝子の仕業か?――エピジェネティクスが開く遺伝学の新時代 トリプレット暗号とは何か なぜ、生命の起源は単一だと言えるか 生物は不変ではなく、動的なものだ/ダーウィンの予言 第9章 木を見て森を見ず――私たちは錯覚に陥っていないか 花粉症は、薬では治らない 生命は水でエントロピーを捨てている 達成できそうにないCO2削減目標 排出権取引の胡乱さ 気楽に読む本。
Posted by
小田原の地球博物館に行った時に記念に買った本 ちょうどこの本を読み終える頃に、死にまつわる経験をした。死んでも、炭素という形で循環する。その循環を感じられるだけで救われる気がしました。 放っておけばエントロピーは増大する。それに抗うために、生命は積極的に壊して、再生を繰り返す...
小田原の地球博物館に行った時に記念に買った本 ちょうどこの本を読み終える頃に、死にまつわる経験をした。死んでも、炭素という形で循環する。その循環を感じられるだけで救われる気がしました。 放っておけばエントロピーは増大する。それに抗うために、生命は積極的に壊して、再生を繰り返す。膨大なエネルギーとコストをかけて。コントロールできる範囲で積極的に壊し作り変える、というのはものづくりの観点で真剣に向き合ってみたい。決して使い捨てでゴミを増やすことではなく、循環のために、そして長く平衡を保つために。 生命は常に動的に平衡を保とうとする。ある一側面の現象を変えると、また全体の平衡を保とうと全体が調整される。病気になる、筋肉が衰える、いろんなことが起こるけど、長い目を見てどう平衡させたいかは念頭に置いておきたい。 そして、生命も社会システムも同じなんだろうな。一つを調整すると全体が調整されていく。 一現象にとらわれず、全体を見ていきたい 自然農でその訓練をして、システム思考を持って社会と対話する
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本屋で動的平衡3が出ているのを見かけたので、まずは読んでいない2を読んでみた。これは2と呼んでいいのか正直微妙なところで、1作目の圧倒的な完成度と比較すると寄せ集め感が強かった。一部は媒体の原稿を集めて編集したものなので仕方ないのだけど、逆に1作目の凄さを際立たせる結果になっていた。 ただ一つ一つの原稿は当然ハズレなし。著者の作品を読むのは4冊目だが、サイエンティストかつエッセイストとして右に出るものはいない。身近な生命の現象をこれだけ豊かに描くことができるのは圧倒的な読書量と頭脳の明晰さによることを本作でも例に漏れず思い知らされた。個人的にはエントロピーをめぐる議論が興味深かった。物事は自然と発散の方向へ向かうようになっているが、生命はそれを見越して自らを破壊・再構築を繰り返し動的平衡を維持、エントロピーの影響を逃がしている。ここからもう一歩踏み込んで「水を飲むことでエントロピーを捨てている」という話になるあたりが他のサイエンティストと違うところだと思う。あとは遺伝子上に発生するミスとしてのガンを考察しながら、どうしてミスが起こるような設計になっているかの話も興味深かった。ミスが発生する、つまりそこに進化の可能性を残しているということらしい。そこに遊びがないと皆共倒れになるというのは人生の教訓のよう。自分とは縁遠い生物の世界をアナロジーとして捉える面白さもあるのでジャンルにとらわれず色んな本を読みたい。
Posted by
いいです。エントロピーの排出としての水の役割とか。大腸菌は20分で複製するとか。窒素固定の話とか。このタイミングでこの本を読むシンクロニシティが。
Posted by
「動的平衡」概念にもとづくエッセイ集のようなものの第二弾。相変わらず、生物学の話の説明としては、非常にわかりやすい。 これを読むことで、生物・生命に関するテーマを大方洗い出すことができそう。 ・美は動的平衡に宿る ・「自由であれ」という命令 ・なぜ、多様性が必要か ・植物...
「動的平衡」概念にもとづくエッセイ集のようなものの第二弾。相変わらず、生物学の話の説明としては、非常にわかりやすい。 これを読むことで、生物・生命に関するテーマを大方洗い出すことができそう。 ・美は動的平衡に宿る ・「自由であれ」という命令 ・なぜ、多様性が必要か ・植物が動物になった日 ・時間を止めて何が見えるか ・バイオテクノロジーの恩人 ・生命は宇宙からやって来たか ・ヒトフェロモンを探して ・遺伝は本当に遺伝子の仕業か ・木を見て森を見ず
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
生命を構成している要素としての細胞やDNAレベルのミクロな世界では、合成と崩壊が凄い速さで繰り返されつつ、生命体としての構成要素の臓器、皮膚、骨等の各モジュールの現状を維持している。エントロピーの増大法則はあらゆる事象を包括しているので、形が有るものは崩壊していくことが避けられませんが、崩壊と合成を繰り返すことで、エントロピーの増大の法則に反して、各モジュールは維持され、従って生命活動が続くと言うことについて、様々な視点から説明がされています。その説明は、素人にも解り易く殆ど違和感を感じずに、読むことが出来ました。「地球上の全てのものを構成している元素の総量は昔から変わらずほぼ一定の中で、絶え間なく結びつきを変えながら循環している。」とのこと。これは、方丈記の「ゆく河の流れは絶えして、しかも、もとの水にあらず。」や仏教の輪廻転生の現代科学による解釈とも言えるかと思いました。様々な説明がなされる中で、ミクロな世界の動的平衡と、例えば人間活動を起点とした世界の有り様としての動的平衡と言う視点は、相似形に見えてきます。その後、量子論の中では全ての事象で因果関係が無いと言う最近の研究が紹介され、人間の活動にも因果関係が無いと言う解釈の説明が出ますが、その考えがスッと入ってきました。読み終わった後に気持ちが軽くなる良書だと思います。
Posted by
ブグログの良いところは、過去自分が読んだ本を検索できることだ。検索をしてみると、私が最初に読んだ福岡伸一の本は、「生物と無生物のあいだ」であり、その感想を書いたのは2008年2月のことであった。評価は5点満点で、「最近読んだ本の中ではベスト」と言い切っている。 福岡伸一は生物学者...
ブグログの良いところは、過去自分が読んだ本を検索できることだ。検索をしてみると、私が最初に読んだ福岡伸一の本は、「生物と無生物のあいだ」であり、その感想を書いたのは2008年2月のことであった。評価は5点満点で、「最近読んだ本の中ではベスト」と言い切っている。 福岡伸一は生物学者であり、青山学院大学の教授である。著作は多く、生物学者としての科学的な著作が多いが、その他にも「フェルメール 光の王国」のような美術や歴史に題材をとったものも書いている。 「生物と無生物の間」、そして、この「動的平衡2」は、科学的な本。ただ、私にとっては、「動的平衡」シリーズの方が、ついていくのが大変であった。注意深く読めば何とか話の筋についていけるけれども、少し集中を切らすと話の筋が分からなくなる。「生物と無生物のあいだ」では、そういうことはなかったようなので、記述されている科学的な内容の難易度が少し違うのだろう。 福岡伸一は科学者であるが、美文家だと思う。いくら美文で書かれていても、難しいものは難しいのであるが、それでも、文系の私に科学的な内容の本を読んでみる気にさせるくらいの効果はある。
Posted by
飛ぶためには軽いほど有利。カゲロウ、ホタル、峨などは成虫になってからはほとんど食べない。 働きアリの一部は、常に働かない。生物学的にはあらかじめ予定して準備しておくことはできない。なぜならその戦略は自然選択の対象にはならないはずだから。 ランダムに起こる異変のうち、環境に適合し...
飛ぶためには軽いほど有利。カゲロウ、ホタル、峨などは成虫になってからはほとんど食べない。 働きアリの一部は、常に働かない。生物学的にはあらかじめ予定して準備しておくことはできない。なぜならその戦略は自然選択の対象にはならないはずだから。 ランダムに起こる異変のうち、環境に適合したものだけが、生き残る。ある方向性をもって進化しているわけではない。 生物の進化では、負ける、ということが変化に生き延びる力を生み出す。絶滅の危機のときに生き延びることができる力を持つものだけが生き延びる。 鳥は、体を軽くするために膀胱と大腸のほとんどをなくした。ペニスもなく、総排泄口があるだけ。 センスオブワンダー、を大人になっても失わない。自然に畏敬の念を持ち続けること。 人はたんぱく質をたんぱく質としては吸収せず、わざわざ分解と合成を繰り返すのか。生命は一直線に死に向かうことに抵抗している。 20種のアミノ酸に分解される。そのうち11種は体内で作れる非必須アミノ酸。 あえて必須アミノ酸の合成能力を捨てた。必須になったとき、植物から動物になった。自ら動き回って求める必要ができた。=食べる。食べられれば、作る機能はいらない。 グルタミン酸が最も多く含まれるアミノ酸。美味しさを求めれば、手に入る。 トウモロコシには、リジンが含まれていない。リジンが含まれているのは肉や乳製品。 鶏卵はバランスがいい。 運動、老化にはBCAAが効果的。 「志賀昆虫普及社」 腸内細菌は胎児には存在しない。人間の消化管は体の外側。内側には免疫システムがあり、細菌は入り込めない。腸内は細菌にとって居心地がいい。 細菌は、色がない。グラム染色法を使う。 ペニシリンの耐性菌が、他の細菌にも伝達された。プラスミッドが重要な役割を果たした。 プラスミッドを使った遺伝子交換で、新しい大腸菌が生まれた。O104は、O157のプラスミッドの影響で強毒化した可能性がある。 DNAが先か、タンパク質が先か。 鶏は、もともと赤色野鶏の生んだ卵から変異種が生まれたもの。卵が先。 RNAが先にあった。DNAが生まれてRNAは必要なくなった。 フェロモンは、排卵期はアクセル、排卵後はブレーキの役を果たす。 人にも、レセプターであるヤコブソン器官がHタラいている。 キリンは高いところの葉っぱを食べようとして首が延びた、わけではない。たまたま首が長いものが生き残っただけ。 チンパンジーの成熟のタイミングが遅れ、子供時代が長くなって、人間ができたのではないか。子供の特徴を残したままゆっくり性成熟することは、進化上有利だった。恐れを知らず、好奇心に満ち、探索行動が長続きする。 抗ヒスタミン剤を飲み続けると、より過敏な花粉症体質を招く可能性がある。薬の作用はこれと同じ。 腎臓が人間のエントロピーを輩出している。尿で水を捨てるのではなく、エントロピーを捨てている。 二酸化炭素濃度と気温上昇には因果関係のなら、気温は下がるかもしれない。しかし因果関係があれば、取り返しのつかないことになる。 遺伝子のミスコピーがガンの原因。しかし、進化の可能性を失う。 人間は分解と合成を繰り返しつつ、自らを作り替える。しかしやがてエントロピー増大に追いつかれてしまう。 常に分解していることが大切。 アレルギーとは、エントロピーそのもの。下げるために消化という仕組みがある。
Posted by
科学者でありながらやたら文章がうまい著者であるが、章ごとに生命の不思議を説いているが、最終的に生命とは何かが結局わからない、現在の科学で解き明かすことはできないということだろうか、最終章では量子力学が出てきて、量子力学が解き明かされない限り生命とは何かも結局分かりそうもないのかも...
科学者でありながらやたら文章がうまい著者であるが、章ごとに生命の不思議を説いているが、最終的に生命とは何かが結局わからない、現在の科学で解き明かすことはできないということだろうか、最終章では量子力学が出てきて、量子力学が解き明かされない限り生命とは何かも結局分かりそうもないのかもしれない。
Posted by
RNAからタンパク質とDNAの循環というバランスを達成したことが、動的平衡としてセントラルドグマの形を作った。様々な動的平衡が我々の成り立ちの中に存在することを教えてくれる。それが複雑系の上にあることも。
Posted by