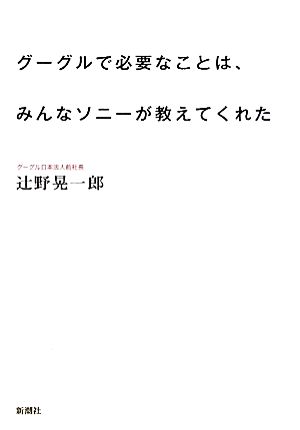グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた の商品レビュー
正月休みに大阪で読んだ本。2012年初の読了本である。 「グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた」 この本のタイトルが意味するところは、今のグーグルは、昔のソニーそのものであるということだ。カルチャー、ベンチャースピリット、少数精鋭etc。 著者は、グーグル日本法人...
正月休みに大阪で読んだ本。2012年初の読了本である。 「グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた」 この本のタイトルが意味するところは、今のグーグルは、昔のソニーそのものであるということだ。カルチャー、ベンチャースピリット、少数精鋭etc。 著者は、グーグル日本法人の社長になったわけだが、その前は、ソニーで22年間勤務していた。グーグルのカルチャーは昔のソニーそのものなので、22年間のソニーでの経験をそのままグーグルに生かせることができたということだ。ソニーの凋落ぶりを本書ではどうどうと批判しており、元社員だけあって生々しく臨場感がある。 (メモ:Googleについて) ---------------------------------------------------------------------------- ①「グーグルの異色な点は、全世界のユーザーがまだ具体的にイメージしていないニーズを予測して製品やサービスを開発し、新たなスタンダードを作り出すこと。」 →市場調査等では絶対に出てこない、ユーザーの潜在的ニーズを掘り起こし、それを起点に新たなライフスタイルを作り上げている。 ②グーグルの売上げの98%はオンライン広告である。(検索連動型・コンテンツ連動型)グーグル全般の活動資金は、オンライン広告という収入源に任せていて、ストリートビュー、アンドロイド、グーグルマップなど新たな活動は、特にビジネスモデルは存在せず、細かな採算の心配をする必要がない組織運営となっている。収益をあげることに特化した活動とそれ以外の活動というように区分けすることで、インターネット・クラウドの進化のために、大胆な戦略が可能となっている。 →もし、一般企業のように事業部制(ストリートビュー部・アンドロイド部etc)であるならば、限られた時間の中で採算を求められる。グーグルのように徹底的に技術を追い求める等の活動ができなくなる。グーグルは営利企業でもあるが、アカデミックな公共機関のような面も併せ持つことが理解できる。 ③グーグル社員の20%ルール 人間は、あまりに忙しくなると自分がやっている仕事の本質的な意味を忘れてしまう傾向がある。(一日スケジュールがパンパンになると、目先のスケジュールを守ることが優先されて、目標やそれ自体の意味を考えなくなる)忙しいということは、難しいことや余計なことは考えたくないということに対する自分自身や周囲に対する積極的な口実としても機能してしまう。 →創造的な仕事をするには、忙しすぎることはよくないことである。
Posted by
ソニーを駆け抜けてグーグルの幹部にもなった人の言うことには、説得力があります。 いいものを作り上げるということは、何もかも忘れてバカになって没頭しなければならない。企業でも研究でも一緒なんですね。 でも、それを続けなければ生き抜けないというのは、大変だなぁ。
Posted by
褒める人だけ実名。読む人が読んだら悪口が誰に対してだか分かるんだから,悪口も実名で書いて欲しかったな。 ○○したのはSONYが先だと言われてもね。 2011/12/23図書館から借用; 12/31の午後だけで読了
Posted by
ソニーで22年、その後Googleで3年勤めた経験を書いた本。タイトルが気になり手にとった。当時のソニーとGoogleの共通点から、現代のIT産業、ビジネスの状況、今後の在り方に至るまでわかりやすく説明されている。わかりやすさは著者の実体験によるところが大きいと思う。 ソニーの...
ソニーで22年、その後Googleで3年勤めた経験を書いた本。タイトルが気になり手にとった。当時のソニーとGoogleの共通点から、現代のIT産業、ビジネスの状況、今後の在り方に至るまでわかりやすく説明されている。わかりやすさは著者の実体験によるところが大きいと思う。 ソニーの話で印象的だったのは、ソニー創業者の一人である盛田昭夫さんの話。新人社員への訓示で「人生の大事な時期を過ごす場であるソニーが皆さんにふさわしくないと思えば、時間の無駄だからすぐに去って欲しい」と述べたらしい。企業だけでなく、学校でも、バイト先でも、自分の居場所が自分にとってふさわしい場所かどうかは常に考えなければならないと感じる。その場所に目的を持って立っているか。人生の大事な時期を過ごす(会社であれば何十年も過ごす)場所という視点から、”自分の居場所”とは何かということを考えさせられた。また、著者も書いているが、我々はシリコンバレーのイノベーションに感嘆する前に、これだけの日本人が存在したことをもう一度認識(学ぶ)必要があると思う。松下幸之助、本田宗一郎、井深大…などなど。我々が学ぶべき日本人は数多くいる。 Googleの話も興味深い。Googleについては他の書籍でも良く目にするが、「20%ルール」には毎回感銘を受ける。「7つの習慣」の時間管理のマトリックスでは第2領域であり、パレートの法則と説明されている。持ち時間の20%を自分の興味があることに使うということが、新しいアイデアの発見など、本業に大きな影響を与えるのはGoogleの成功からも証明されている。週5日働くとして、1日は自分の興味のあるものの研究をする。働く(勉強する)には、そういった余裕が必要なのだろう。それを企業として奨励できるところにGoogleの凄さがあると思う。 著者は全体を通して、インターネットの世界では「やるリスクより、やらないリスクの方が大きい」と述べているが、これはIT産業やビジネスの世界だけに限らず、全てのことに当てはまると思う。オフラインからオンラインに変化する時代に、どう対応するかを常に意識していこうと思う。
Posted by
2011,12,19 TSUTAYAブックカフェ大崎にて読了。 ・多くの人が抱いているであろうソニーに対するイメージが、悪い意味で変わるであろう内容。しかしながら、著者の持つソニーに対する変わらぬ深い愛情もまた感じられる。 ・本書は、著者がソニーに在籍していた時代とグーグル時代...
2011,12,19 TSUTAYAブックカフェ大崎にて読了。 ・多くの人が抱いているであろうソニーに対するイメージが、悪い意味で変わるであろう内容。しかしながら、著者の持つソニーに対する変わらぬ深い愛情もまた感じられる。 ・本書は、著者がソニーに在籍していた時代とグーグル時代の経験との二つに部分に大きく分けられるが、前者では著者が感じた「窮屈さ、落胆」が、また後者では著者の「興奮、刺激、喜び」がとても印象的に描かれている。 ・日本が誇るグローバル企業であるソニーであっても、「異端を敬遠する姿」「ことなかれ主義」「融通が利かない、硬直した組織」としての姿があるという事実に大きなショックを受けた。 「自由闊達にして愉快なる理想工場(井深大)」 「最初の百日が肝心」 「グーグルが急成長しているのは、いろんな面で非常識だから」 ・ネットの世界では「やらないことのリスク」の方が高い。というのも、過剰在庫を抱えてしまうなどの物理的なリスクが無いからである。そのため、素早さが求められる。 「Don't be evil」 「フラットなコミュニケーションからイノベーションは生まれる」 「20%ルール」(持ち時間の20%は本業以外のテーマに使うことを奨励するもの) 「Aクラスの人はAクラスの人と仕事をしたがる。Bクラスの人はCクラスの人と仕事をしたがる。」 「完璧主義が足かせになっている」
Posted by
ソニーで、コクーンやスゴ録等を開発し、その後グーグル日本法人の社長にもなった本人が書き下ろした一冊。自身のその時々の経験をふまえて、ソニー、グーグルの世界企業の内部を筆者がどう捉え、感じたかをまさにそのまま記した本だと言えます。筆者が感じた苦悩の日々や色んな人との出会い、感動。飾...
ソニーで、コクーンやスゴ録等を開発し、その後グーグル日本法人の社長にもなった本人が書き下ろした一冊。自身のその時々の経験をふまえて、ソニー、グーグルの世界企業の内部を筆者がどう捉え、感じたかをまさにそのまま記した本だと言えます。筆者が感じた苦悩の日々や色んな人との出会い、感動。飾らずに書いた文章から、筆者の人物像が想像出来て、各章ごとの出来事が何の疑いも無しに伝わってきます。 大企業の今昔物語を垣間みる事の出来る一冊でしょう。 ネットや大企業に興味がある人、ひょっとしたら、中小企業の経営者にもお薦めの一冊かも。
Posted by
【11/12/02】読了 前半は、Sonyの内部事情が分かる本。 小さい頃はプレイステーションで育ってきたようなもだったので、当時は「Sonyは、すごい!最先端だなー!」と思っていた。が、この本を読むことで2000年代は他社よりも動きだしが遅かったことを知った。その遅れを取り戻す...
【11/12/02】読了 前半は、Sonyの内部事情が分かる本。 小さい頃はプレイステーションで育ってきたようなもだったので、当時は「Sonyは、すごい!最先端だなー!」と思っていた。が、この本を読むことで2000年代は他社よりも動きだしが遅かったことを知った。その遅れを取り戻すために、著者が四苦八苦しながらいろんな事業を立て直すことが書かれてあり読み応えがあった。良い結果に対して、ある上層部の人が「Sony製品だから、そりゃ売れるよね。」なんて発言をしているあたり、Sonyが凋落するのは時間の問題だったように感じる。 後半は、Googleの推進力が分かる。 Googleの10の事実が記載されている章は、とても面白かった。 製品の保守業務や会議などにおいて、数字やコストばかりを追いかけているあまり、「ユーザが製品を使用したことで、どう嬉しいのか」ということが欠けているな、と考えるようになった。
Posted by
一気読み。 コクーンも、ウォークマンAやConnect構想も、 リアルタイムに、ソニーの迷走っぷりを不思議に思っていたので、 その原因となる内部事情が興味深かった。 筆者の持つ信念、人となりが分かる本。 こんなに信念を持った人が近くいないのが残念。 そして、そんな人でも内向きの...
一気読み。 コクーンも、ウォークマンAやConnect構想も、 リアルタイムに、ソニーの迷走っぷりを不思議に思っていたので、 その原因となる内部事情が興味深かった。 筆者の持つ信念、人となりが分かる本。 こんなに信念を持った人が近くいないのが残念。 そして、そんな人でも内向きの抗争でパワーを消耗してしまう。 もったいない。 タイトル先行で内容はソニーでの苦労話が中心。 グーグル部分以降は少なく物足りず。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本の内容はほとんどSony時代のもの。 Sonyは今凋落しているが、それを内部にいた人間が書いているのは非常に興味深い。 とはいえSonyは世界的イノベーションを起こした企業であり、方針さえはっきりさせればまだ戦えると思う。 SONYとGoogleの違いについても書いてあるが、両社はあまりにも違いすぎるので、そこは参考にならないだろう。 ただ、Sonyが時代に追いついていないのは間違いない。
Posted by
すご録/Vaio等の開発を手掛けたソニー⇒グーグル日本法人元社長のお話。 元ソニー社員ということで、ソニーへの愛がありつつもここ十数年のソニーを取り巻く内部/外部環境の変化に関して客観的に批評してる良書だった。 グーグルの経営スピードの速さ、社内の風土とも対比されて書かれてるので...
すご録/Vaio等の開発を手掛けたソニー⇒グーグル日本法人元社長のお話。 元ソニー社員ということで、ソニーへの愛がありつつもここ十数年のソニーを取り巻く内部/外部環境の変化に関して客観的に批評してる良書だった。 グーグルの経営スピードの速さ、社内の風土とも対比されて書かれてるのでなお面白いと思う。 入社する前に自戒を込めて読んでおくべき!
Posted by