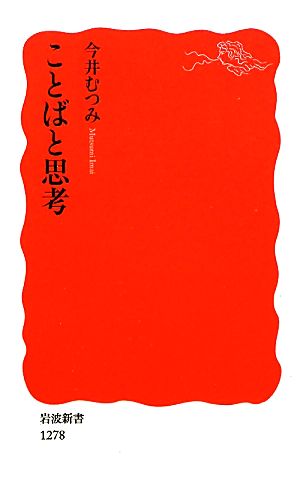ことばと思考 の商品レビュー
「英語独習法」に続く、今井先生2冊目。 「英語〜」はタイトルの通り、英語と日本語の違いを軸に、言語感覚と認知のつながり、言語の違いによる認知の違いを教えてくれた。 この本はもっと幅広く、英語ドイツ語フランス語ロシア語中国語、更にはイヌイット語、ゴドベリ語(どこよ?)、グーグ・イ...
「英語独習法」に続く、今井先生2冊目。 「英語〜」はタイトルの通り、英語と日本語の違いを軸に、言語感覚と認知のつながり、言語の違いによる認知の違いを教えてくれた。 この本はもっと幅広く、英語ドイツ語フランス語ロシア語中国語、更にはイヌイット語、ゴドベリ語(どこよ?)、グーグ・イミディル語(ゆる言語学ラジオで言ってたやつだ!)まで、様々な言語の様々な差異を通して、サピア=ウォーフ仮説を検証する。 イヌイット語では、雪の種類に応じて20以上の独立した単語があるとか。 数の数え方の影響で、一般的にアジア圏のこどもは欧米のこどもより小さいうちに計算ができるようになるとか。 そういうトリビアな雑学だけでも結構楽しい。 個人的に1番面白かったのは、空間認知能力にも、複数の情報を組み合わせて推論することにも、言語が影響していて、だから、「色」情報と「相対位置」情報をヒントに宝探しをさせる実験(たとえば『黒い壁に向かって左側の角』)で、言語野を機能させなくする(ヘッドホンから聞こえてくる文章をどんどん復唱させながら宝探しをさせる)と、成功率が低下するという話。 この実験を考えたのがまず、すごいと思う。 言語がいかに認知に影響するか、人間の言語習得プロセスの面白さ、そして、世界の広さに驚かされる。
Posted by
ゆる言語学ラジオを聴いて興味を持ち手に取った今井むつみ先生本。ラジオ内で語られていた内容がちょくちょく出てきて、相乗効果で楽しめた。 言語によって認識の仕方や思考に影響が出るという話は、非常に興味深い。言語によって世界にそれまで無かった線を引く、ってこととかすごく腑に落ちる。いや...
ゆる言語学ラジオを聴いて興味を持ち手に取った今井むつみ先生本。ラジオ内で語られていた内容がちょくちょく出てきて、相乗効果で楽しめた。 言語によって認識の仕方や思考に影響が出るという話は、非常に興味深い。言語によって世界にそれまで無かった線を引く、ってこととかすごく腑に落ちる。いやー、おもしろいわ。高校生がこれ読んだら言語心理学とか認知科学とかの道に進みたいって思ったりするんじゃなかろうか。文系学問もおもしろいなって改めて思えた1冊。
Posted by
言語が思考を決定するか、 異なる言語の話者が異なる思考をしているか、 というのをいろいろな角度から考察した本。 いろいろな実験結果から話を進めていく。 個々の実験の話はわかりやすいのだが、そこからの考察は私にはちょっと難しかった。
Posted by
私たちの思考は言語の枠組みの影響を受けている。だから異なる言語の話者同士は世界の認識や思考様式がまったく異なるのかもしれない、というある意味有名な仮説に対して最近の言語学がどこまでアプローチしているのかをわかりやすく解説する本。異言語間の差異と共通点だけでなく乳児幼児がどのように...
私たちの思考は言語の枠組みの影響を受けている。だから異なる言語の話者同士は世界の認識や思考様式がまったく異なるのかもしれない、というある意味有名な仮説に対して最近の言語学がどこまでアプローチしているのかをわかりやすく解説する本。異言語間の差異と共通点だけでなく乳児幼児がどのように言語を習得していくのか、言語習得以前の認識のあり方に対して言語はどのように影響しているのかなど基本的な事柄を初心者向けに丁寧に解説していて良かった。さすが岩波新書と言うべきかとても新書らしい新書で安心して読めました。
Posted by
今井むつみさんの本はこれで3冊目ですが、この本は分けてもインパクトが大きいものでした。言葉を通じて世界を見たり、ものごとを考えるのですが、言葉が違うと、認識、思考のありようが違うのか、それにより相互理解はできないのかといった問題に認知心理学の成果を踏まえて分け入っていきます。外国...
今井むつみさんの本はこれで3冊目ですが、この本は分けてもインパクトが大きいものでした。言葉を通じて世界を見たり、ものごとを考えるのですが、言葉が違うと、認識、思考のありようが違うのか、それにより相互理解はできないのかといった問題に認知心理学の成果を踏まえて分け入っていきます。外国語を学ぶことで認識の多様性への気づきといった思考の変容が得られるとか、言語が異なっても相互に分かり合えるとか、ある意味、感動的な知見の連続でした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
言語が違うと認識や思考は異なるのか。言語に影響され、記憶が歪められることはあるようだが、思考が異なるとは断言できなと読んだ。すなわち、言語というものは思考の道具に過ぎないからか。言語学習や他言語の人と接する際の前提となる知識。
Posted by
"われわれは、生まれつき身につけた言語の規定する線にそって自然を分割する" "世界が自分自身を分割し、名前をつけられるべく待っている" 先達のことばを引きつつ、ご自身の研究も紹介しながら、どうヒトは思考しているかを考えさせられる、良い本でし...
"われわれは、生まれつき身につけた言語の規定する線にそって自然を分割する" "世界が自分自身を分割し、名前をつけられるべく待っている" 先達のことばを引きつつ、ご自身の研究も紹介しながら、どうヒトは思考しているかを考えさせられる、良い本でした。
Posted by
『#ことばと思考』 ほぼ日書評 Day596 Day591で上げた認知科学書の推薦本より。 世の中には、左右を示す言葉のない言語があるのだそうだ。左右がないから、位置関係を絶対関係で捉える、つまりAはBの北にあるという具合。時間軸についても左から右でなく、東から西のように並...
『#ことばと思考』 ほぼ日書評 Day596 Day591で上げた認知科学書の推薦本より。 世の中には、左右を示す言葉のない言語があるのだそうだ。左右がないから、位置関係を絶対関係で捉える、つまりAはBの北にあるという具合。時間軸についても左から右でなく、東から西のように並べる。 そのような言語を母語とする人たちは、我々なら容易に迷ってしまいそうな曲がりくねった道をかなりの距離進んだ後でも、出発地の方向を5度以内という驚くべき精度で指し示すことができる。 では、こうした能力は使用する言語によって後天的に獲得されるのか? 端的に言えば、どうもそうではないらしい。 むしろ、赤ん坊の時に誰でも持っている能力が、言語能力の獲得と共に徐々に失われる(というか寧ろ歪められると言う方が妥当に感じられた)。欧州言語に多い男性女性名詞の区別や冠詞・序数詞に認識が引っ張られる現象、あるいは日本人の苦手なLとRの区別等、すべて後天的な作用であることが、様々な実験で判明したという。 もちろん逆に、言語を獲得すること(言い換えれば抽象化すること)で、長く記憶に留められるといった側面が人類の文明発展に大きく寄与したことは言うまでもない。 即物的に役に立つというよりは、いわゆる教養書に属する本だが、「異文化コミュニケーション」が当たり前になった世界では、そうした教養を持っておくのも意味のあることだろう。 https://amzn.to/38EmDaw
Posted by
母国語が、ものの見方にいかに影響を与えるものであるか。衝撃的でした。一方で、異言語使用者間でも、共通する見方があるとのこと。非常に興味深いテーマでした。
Posted by
これは面白い。最初のうちは「それって必ずしも因果関係と言えないんじゃ?」とモヤモヤしたが、中盤に入って著者の専門分野である子供の言語習得のテーマになると俄然説得力が増して本質を掴むことができる。結論だけを見れば当たり前のことしか書かれていないが、それに至るまでの道筋が良く考えられ...
これは面白い。最初のうちは「それって必ずしも因果関係と言えないんじゃ?」とモヤモヤしたが、中盤に入って著者の専門分野である子供の言語習得のテーマになると俄然説得力が増して本質を掴むことができる。結論だけを見れば当たり前のことしか書かれていないが、それに至るまでの道筋が良く考えられていて自然と腑に落ちるようになっているのはさすが。
Posted by