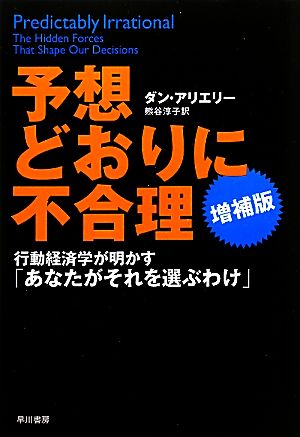予想どおりに不合理 増補版 の商品レビュー
目から鱗が落ちるとはまさにこの本を読んだ感想を的確に表した言葉である。少なくとも自分にとっては。 朗読を聞くことにお金を払う意識ともらう意識が恣意的に作り出せることや、ものの値段に対する感覚がいとも簡単に操作されてしまうことなど、人がいかに論理的ではない生き物かということが、実験...
目から鱗が落ちるとはまさにこの本を読んだ感想を的確に表した言葉である。少なくとも自分にとっては。 朗読を聞くことにお金を払う意識ともらう意識が恣意的に作り出せることや、ものの値段に対する感覚がいとも簡単に操作されてしまうことなど、人がいかに論理的ではない生き物かということが、実験結果とその考察により説得力を持って書かれている。 図書館で借りて読んだけど、買ってしまいたい!
Posted by
私たちは自分の行動や意志を自分でコントロール出来ていると信じている。でも実際は簡単に不合理な行動をとってしまう。 この本でとりあげられている様々な例は悔しいが自分にも覚えがあった。自分含め人間にはそういう側面があると認めることで、世界の見方が少し変わると思った。 この本の中では数...
私たちは自分の行動や意志を自分でコントロール出来ていると信じている。でも実際は簡単に不合理な行動をとってしまう。 この本でとりあげられている様々な例は悔しいが自分にも覚えがあった。自分含め人間にはそういう側面があると認めることで、世界の見方が少し変わると思った。 この本の中では数々の実験がとりあげられているがどの結果も非常に興味深く、これによって行動経済学に対しての興味も大きくなった。 2023.07.30 読了
Posted by
人間の行動の不合理性が、実験や論拠に裏付けされて証明されていく論法は気持ちがよいし、身近な事例が列挙されるので堅苦しくなくてよい。経済学の至上とする合理性が市場経済という世界での行動をベースとしている一方で、、本書の「行動経済学」では人間の社会規範ベースの世界における別のロジック...
人間の行動の不合理性が、実験や論拠に裏付けされて証明されていく論法は気持ちがよいし、身近な事例が列挙されるので堅苦しくなくてよい。経済学の至上とする合理性が市場経済という世界での行動をベースとしている一方で、、本書の「行動経済学」では人間の社会規範ベースの世界における別のロジックに由来する行動の解明は面白かった。その二つの世界を介在する人間の行動の非合理的な要素を掘り下げることは人生のTipsになるのかもしれない。
Posted by
画像はないが、実験が多くしかも大学のキャンパスを中心としたものである。したがって、学生が卒論でじっけんするための十分な方法を提供する。しかも結果が面白い。心理学の教科書としても使える。
Posted by
単に主張とか結果だけがまとめられているのではなく、オリジナルの実験と共に解釈がまとめられている。 心理実験をやる機会はないだろうけど、やり方が詳しく書いてあるのでそういうことをやる人にもおすすめ。
Posted by
タイトル通り、いやな予想した通り、人は不合理、不条理な行動を選択してしまう、というお話。 どこかの本で読んだことのある例題が多々あったけど、それは逆で、ここに載っていたものがわかりやすいために他で引用されていたのね。 内容が分かった反面、モヤモヤする結果だな。。 306冊目読了。...
タイトル通り、いやな予想した通り、人は不合理、不条理な行動を選択してしまう、というお話。 どこかの本で読んだことのある例題が多々あったけど、それは逆で、ここに載っていたものがわかりやすいために他で引用されていたのね。 内容が分かった反面、モヤモヤする結果だな。。 306冊目読了。
Posted by
世界は二つの規範で出来ている。社会規範と市場規範。二つは別々のもので、混同すると痛い目を見る(例: 交際とセックスにかかる費用の折り合いをつけようとする=社会規範と市場規範の混同) 人は無料(社会規範)なら喜んで働くし、相応の賃金(市場規範)を出しても喜んで働く、しかしほんの少...
世界は二つの規範で出来ている。社会規範と市場規範。二つは別々のもので、混同すると痛い目を見る(例: 交際とセックスにかかる費用の折り合いをつけようとする=社会規範と市場規範の混同) 人は無料(社会規範)なら喜んで働くし、相応の賃金(市場規範)を出しても喜んで働く、しかしほんの少額では誰も働かない。 市場規範が台頭するには、お金のことを口にするだけで(お金のやりとりが全くなくても)十分。 社会規範が市場規範と衝突すると、社会規範が長い間どこかへ消えてしまう。社会的な人間関係はな簡単には修復できない。 市場規範が少なめで社会規範が多めの生活の方が、気持ちよく有意義に充実感をもって楽しく暮らせる。 飛行機で隣になった人との会話で、何故仕事の話をするのか?飛行機を降りる直前まで、名前さえろくに知らないのに? 大半の人が自分の仕事をとても誇りに思っているからでは?多くの人にとって職場は単なる収入源ではなく、意欲や自己定義の源でもある。 助産婦の助言: 出産の痛み=氷を入れたバケツに両手を2分間浸す 人は先延ばしをする、それには自由を厳しく制限する(限られた選択肢を示す、選択の余地を与えないなど)ことがもっとも効果がある。また、締め切りを自ら決意表明させることでいい結果を出す助けになること。
Posted by
行動経済学ブームに火をつけたと言われる一冊。著者はニューヨークで生まれ、イスラエルで育った。イスラエル軍にいた18歳のとき、訓練中に全身の7割に重い火傷を負い、3年間病院で過ごす。その間に看護師をはじめとする人の行動を観察、それについて深く考えるようになったという。退院後、いろい...
行動経済学ブームに火をつけたと言われる一冊。著者はニューヨークで生まれ、イスラエルで育った。イスラエル軍にいた18歳のとき、訓練中に全身の7割に重い火傷を負い、3年間病院で過ごす。その間に看護師をはじめとする人の行動を観察、それについて深く考えるようになったという。退院後、いろいろな大学で心理学や経営学を学び、その後も研究を続けて、今や行動経済学の第一人者と呼ばれるまでになった。 この本は、長年にわたり研究仲間とともに行ってきた多数の実験に基づいて、人間の不合理な行動の数々を紹介、分かりやすく解説するという内容になっている。 印象に残った幾つかを列挙しておく。 ・自分より劣る容姿や能力を持つ友人を連れていき、自分を魅力的に見せる「おとり効果」 ・給料や所有物の高望みから脱するには、他人を羨み嫉妬する「相対性の連鎖」を断つこと。 ・新製品に遭遇すると最初の価格をすんなり受け入れてしまう。「アンカリング」 ・「無料!」につられ、欲しいものとは違うものを選んでしまったり、損をしてしまう合理的でない選択をする「ゼロコストのコスト」 ・社交性や共同体が重んじられる「社会規範」と、対価を払って利益を受ける「市場規範」を混同してはいけない。例えば、好意に対してお金で返すのではなくプレゼントで返す、企業が、「社会規範」を重視すれば、従業員の忠誠心ややる気を促すことになる等 ・事前の決意表明という仕組みが先伸ばしの問題の解決につながることがある。健康診断の先伸ばしに対して、保証金を医者に前もって払い、検査に行くと返金される仕組みの紹介もあった。 ・値段の高い薬や栄養ドリンクが効くと認識される「プラセボ効果」 ・誰かが利己的になるとすべての人が損をする「共有地(コモン)の悲劇」 著者が伝えたかった「人がいつも合理的に行動するわけではなく、誤った決断をすることも多い」という点は多くの実験例でよくわかった。ただ、紹介されている実験や事例がアメリカ人の行動様式や、文化に基づいているせいか、もうひとつなじめず、奇抜に感じられたり、違和感のある翻訳があったりしたのも事実。また、実験や事例は豊富に紹介され考察も示されているものの、実社会ですぐに役立つ手段、つまり実践的なナッジに関してはほとんど言及されていない。その点については、この本を基に読者がそれぞれの現場で考えてくださいということかもしれない。
Posted by
我々は常に合理的に行動しようと心がけている。しかし本書(行動経済学)によれば、知らず知らずのうちに、多くの不合理な行動を行っている。本書では全て実験から得られた、それらの原理を非常にわかりやすく解説している。 これらの原理は、マーケティングなどにも活用されていて、我々はコントロー...
我々は常に合理的に行動しようと心がけている。しかし本書(行動経済学)によれば、知らず知らずのうちに、多くの不合理な行動を行っている。本書では全て実験から得られた、それらの原理を非常にわかりやすく解説している。 これらの原理は、マーケティングなどにも活用されていて、我々はコントロールされてしまっているのである。 全ての原理を意識してコントロールされないようにすることは難しいが、そういう原理が働いていることを意識するだけでも意味のあることだと思う。 本書で扱っている原理。 ・常に比較する(比較しにくいものは無視する) ・三択では真ん中を選ぶ ・恣意の一貫性(最初の価格が「恣意」的でも一度意識に定着すると、アンカーとしてその価格を基準に比較する) ・自分の決断が合理的だと正当化する ・出費の痛み(自分のものを手放すときの不快さ)のため「無料」の力はすごい ・社会規範(モラルで判断すると市場規範(お金で判断する) ・社会規範の中に金銭が加わると市場規範に従ってしまう ・性的な興奮状態では適切な判断が出来なくなる ・自分の所有物を過大評価する ・予測した通りに感じ取る(高級レストランでは何でも美味しく感じる) ・価格と効果は比例関係(効果な薬ほどよく効く=プラセボ効果) ・みんなが信用し協力すれば社会全体の価値は最大化するが、短期的には信用を裏切ることで個人が利益を得られてしまい、不信が連鎖してしまう。 ・チャンスがあれば不正をしてしまうが、誘惑の直前に宣誓や規則など正直さを思い出させると不正を止める。 ・人は選択する際に他人の選んだものに影響されてしまう
Posted by
人間は合理的な選択をするという前提で成り立つ従来の経済学とは対照的に、人間は"不"合理な選択をしがちという前提に立つ行動経済学。本書では人間がいかに不合理な選択を無意識のうちにしてしまうのか、15章に分けて様々な実験データを基に解説していく。
Posted by