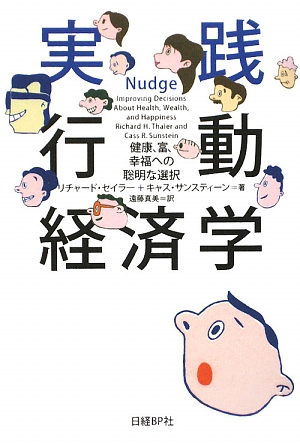実践行動経済学 の商品レビュー
Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness ― http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/P47470.html
Posted by
http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2009/07/post-d938.html
Posted by
前に読んだっけ?と思うような聞いたことのある話が多い。 具体例がアメリカのものなので理解の手助けにならない。 全体に「ヤバ経」などの類書に比べて知的刺激を得られない。
Posted by
卒論の参考文献でした。行動経済学のトピックが網羅されてる感じで大いに使わせてもらいました。エイミングフライの例とか、実際の例を挙げて説明されているので理解しやすかった。長いけどすらすら読める!
Posted by
リバタリアニズム(自由至上主義)とパターナリズム(父権主義)とを結合した「リバタリアン・パターナリズム」を提唱している。 個人の選択の自由を侵害することなく、可能な限り社会善とされるような利益へ誘導する制度設計を目指す。 タイトルに「行動経済学」とあるが、その誘導の仕方が行動...
リバタリアニズム(自由至上主義)とパターナリズム(父権主義)とを結合した「リバタリアン・パターナリズム」を提唱している。 個人の選択の自由を侵害することなく、可能な限り社会善とされるような利益へ誘導する制度設計を目指す。 タイトルに「行動経済学」とあるが、その誘導の仕方が行動経済学的な発想で制度設計しようと訴えるためである。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
社会全般の良識と判断をいかに経済的に結びつけながら実践行動していくか? アメリカのブッシュ時代の国内情勢への批判及び評価をしている点が読みづらかった。
Posted by
この本を行動経済学の本と思って読むのは、いろいろと取りこぼしてしまうと思う。この本にとって、人間が合理的に行動しないことは明らかにすべき事実ではなく、与件でしかない。ここで主張されるのは、そうした与件を前提として制度をつくること。それこそが原題のNudge。 そして、そこからさ...
この本を行動経済学の本と思って読むのは、いろいろと取りこぼしてしまうと思う。この本にとって、人間が合理的に行動しないことは明らかにすべき事実ではなく、与件でしかない。ここで主張されるのは、そうした与件を前提として制度をつくること。それこそが原題のNudge。 そして、そこからさらに進んで、著者はリバタリアン・パターナリズムを提唱する。個人の選択権を残しつつ、社会的に望ましい方向へ誘導するよう制度を設計しようとするそれは、単なる技術論にとどまらずイデオロギーといってもいい。 一見、科学的見地から演繹された技術論のようだし、極端なリバタリアニズムでも極端なパターナリズムでもない穏当な政策にもみえる。が、アーキテクトによる利益誘導の危険性は常に存在し、一定の価値判断が潜り込むことも避けられない。著者もそうした批判への一応の反論を用意しているが、読み手としても留意する必要がある。 とはいえ、技術論としてのリバタリアン・パターナリズムには十分な魅力があることも事実。一つの可能性として注目できるものだと思う。
Posted by
行動経済学が面白い! という話から、もと経済学部生のはしくれとして手をとってみました。 行動経済学・・・、典型的な経済学のように経済人を前提とするのではなく、実際の人間による実験やその観察を重視し、人間がどのように選択・行動し、その結果どうなるかを究明することを目的とした...
行動経済学が面白い! という話から、もと経済学部生のはしくれとして手をとってみました。 行動経済学・・・、典型的な経済学のように経済人を前提とするのではなく、実際の人間による実験やその観察を重視し、人間がどのように選択・行動し、その結果どうなるかを究明することを目的とした経済学の総称である。 簡単に言うと経済学が前提としている完璧に合理的な人間なんて実際は存在しない、人間の非合理な面を明らかにすることで、 経済事象を捉えていこうという学問というイメージ。 本書の前半部分は行動経済学のエッセンスの説明となっていて、経済学うんぬんではなく面白い。 「ボールとバットをかったら110円だった。 バットはボールより100円高い。 ではボールはいくらでしたか?」 →ボールは10円ではなく、これは直感思考の誤り。 「結婚したカップルの離婚率は5割(アメリカの場合?)だが、 結婚式前後ではほとんどすべてのカップルは自分たちが離婚する可能性はゼロに等しいと信じている。 運転者の9割は自分の運転能力は平均以上だと考えている。」 →これらは自信過剰の誤り。 本書の後半部分ではこうした人間の誤りを前提とすると、 どのような選択設計が望ましいのか?が書かれていたり、 より解釈を拡大して、年金制度や環境問題への対処党、 より現実的な社会制度設計の提言についてまとめられている。 が、 一介のサラリーマンとしては直接関わることのない領域なのかなぁという気がした。 結婚制度の見直しの提言は身近で面白かったけど、これも海外を例にしているので、 もう一歩リアリティが薄かったかも。 最後に、本書ではがっつり批判されているけど、 どうしても僕がこんな本なんか読むと、 人間の誤りやバイアスを利用して、 てっとりばやくなんか儲かる方法ないかなぁ。 とか考えてしまう。。。 そんな本があれば売れるかもなぁ。
Posted by
■心理 1.ものを失う痛みは得る喜びの2倍。 2.人はあなたが思っているほど、あなたを注意してみていない。
Posted by
結構、誘導されて物事決めてるかも。何かを決断する際、よく考えて判断してると思いきや、些細なことに影響されているということ。でも怖い話ではなく、ちょいとしたこと、ナッジをするだけでみんながいい方向にいくと教えてくれます。 仕事でも他でも何かをするとき、こういう気を配っていこう。
Posted by