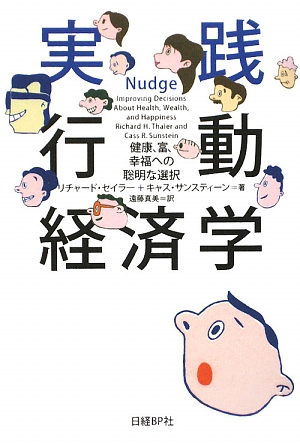実践行動経済学 の商品レビュー
■ナッジが必要な場合 ・選択の結果が遅れて現れる場合 コストがすぐに発生して、便益が後から生じる場合(運動、ダイエット) 便益をすぐに得て、ツケを後で払う場合(アルコール、間食) ・選択するのが難しい場合 (多数の複雑な保険商品や住宅ローンの中から適切に選択する) ・まれに...
■ナッジが必要な場合 ・選択の結果が遅れて現れる場合 コストがすぐに発生して、便益が後から生じる場合(運動、ダイエット) 便益をすぐに得て、ツケを後で払う場合(アルコール、間食) ・選択するのが難しい場合 (多数の複雑な保険商品や住宅ローンの中から適切に選択する) ・まれにしか起こらない選択をする場合 逆に、問題の発生頻度が高ければ、練習することで対応が上手になる。 (大学を選ぶ、配偶者を選ぶ、退職資金を貯める、車を買う) ・すぐに明確なフィードバックが返ってこない場合 (保険商品を購入したとき、消費者は良いリターンを得られているのか?) ・選択と結果の対応関係=マッピングが不明瞭な場合 (保険商品を購入したとき、消費者は何を買って何を得ているのか?) ■Tips ・アンカリング: 優秀な交渉人は、最初に極端に高い提示額を突きつける。 ・プライミング:いつ、どのルートで予防接種を受けるかを 学生に決めさせたら、摂取率が大幅に向上した。 ・スウェーデンの社会保障民営化の教訓: 選択肢が増えれば増えるほど、意思決定を手助けする必要性が高まる。 デフォルトを適切に選定するなど。
Posted by
◯内容は、まさしく実践的ではあるが、株式における利用の部分は難解に感じた。予想どおりに不合理と類似する一冊。 ◯しかし、結局ナッジとは何かと考えると、中々説明が難しい。今まで無意識に行なっていた強制ではなく、示唆的な促しをナッジと認識するくらいにしか理解が及ばなかった。 ◯経済学...
◯内容は、まさしく実践的ではあるが、株式における利用の部分は難解に感じた。予想どおりに不合理と類似する一冊。 ◯しかし、結局ナッジとは何かと考えると、中々説明が難しい。今まで無意識に行なっていた強制ではなく、示唆的な促しをナッジと認識するくらいにしか理解が及ばなかった。 ◯経済学における議論ではあるが、本書にもあるとおり、より政策に活かすべき技術なのではないか。
Posted by
もちろん勉強にはなったのだけど、ユーモア少なめでけっこう読むのに苦労した。 行動経済学の逆襲、のノリを期待して嬉々として読み始め第一部はそんな箇所も多かったが、第二部以降は至極真面目なトーン。ゆえに、ちょっとがっかり。 でも、これがバイアスに縛られたヒューマンだからこそ、なんです...
もちろん勉強にはなったのだけど、ユーモア少なめでけっこう読むのに苦労した。 行動経済学の逆襲、のノリを期待して嬉々として読み始め第一部はそんな箇所も多かったが、第二部以降は至極真面目なトーン。ゆえに、ちょっとがっかり。 でも、これがバイアスに縛られたヒューマンだからこそ、なんですよね。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本屋で流し読み。 行動経済学の本ということで、読んだことある内容もちらほら。ファスト&スローで見たことある内容がいくつかありました。 マーケターやデザイナーは行動経済学を学ぶべきだなと改めて認識。以下メモ。 ----------------------------------------- リバタリアン・パターナリズム 拒絶の選択をする自由を与えられるべき 誘惑にほだされるホットな状態と冷静なコールド状態 先を見通す力がある計画者と狭量な実行者という半独立的な二つの自己がある
Posted by
リバタリアン・パターナリズムという考え方を元に、どのようなナッジを与えれば人々の選択をより良い方向に導けるか?を説いた本 貯蓄や投資だけでなく、医療や婚姻制度など、選択アーキテクトを提供する側からの提案をしている。 貯蓄や投資の項は、自分にも参考になる点があった。
Posted by
リーマン・ショック直後に著された,行動経済学の視点から政府の望ましい介入のあり方を論じた一冊.エコン(本書ではエコノとしている)と対照したヒューマンの心理的特性を紹介した上で,これらを利用しつつ,同時にそれに伴って不利益を被ることを避けられるように,さりげなく影響力を行使すること...
リーマン・ショック直後に著された,行動経済学の視点から政府の望ましい介入のあり方を論じた一冊.エコン(本書ではエコノとしている)と対照したヒューマンの心理的特性を紹介した上で,これらを利用しつつ,同時にそれに伴って不利益を被ることを避けられるように,さりげなく影響力を行使することで,多くの人々をより望ましい方向に導く「ナッジ」を政策に取り入れることを提案する.選択の自由を重んじながら,万人にとって望ましい方向へ他者を促すというあり方には,私自身も大いに賛同するところ.一部,年金やローンなど金融商品についての説明が多く,理解が進まないところもあったが,同じ内容を言葉を変えて説明したり,選択肢を工夫したり,望ましくない選択に対してちょっとした警告を出したりすることで,統計的に見て多くの人々の行動を変化させられるというのは恐ろしくもあるが興味深く,様々な形で研究・試行されるべきものだと思った.婚姻制度の民営化という話は目新しかったが,離婚に対する法制化という部分と今一つ整合性が見えずもやっとしている.何か他に彼が書いている論文などがあれば探して読んでみたい.
Posted by
『行動経済学の逆襲』を先に読んでいたのだが、こちらの本は、第1部が良かった。 この本を読もうと思ったきっかけは、ナッジという言葉だったが、その背景には、「リバタリアン・パターナリズム」という思想(政治的な文脈で使われることが多そう)がある。自由主義かつ干渉主義というちょっと悩ま...
『行動経済学の逆襲』を先に読んでいたのだが、こちらの本は、第1部が良かった。 この本を読もうと思ったきっかけは、ナッジという言葉だったが、その背景には、「リバタリアン・パターナリズム」という思想(政治的な文脈で使われることが多そう)がある。自由主義かつ干渉主義というちょっと悩ましい概念だが、本の中で出てくるのは、年金の為の積み立ての話。401k制度は個人がやっても良いしやらなくても良いが、デフォルト設定を「やる」にしておいて、「やめる」を選択できるようにと言ったものらしい。やるにした方が効果が高いのだが、やらないも選べる。 なんで、こんなことしてるのかと言うと、経済的に正しい振る舞いと言われる行動を人間は必ず取るとは限らないという現象の分析から発生している。 経済学では、経済完璧人間を設定して概念が形成されてきたが、現実世界のホモ・サピエンスが起こす行動の矛盾を研究対象にしたのが筆者であるリチャード・セイラー氏。 この本を読むと役に立つ人ってどう言う人だろう?と考えてみると、政治家のみならず、何かしら設計に携わる人は、知っていて損はないだろうし、事務の企画などをしている人も参考になると思う。 目次は以下の通り。 第1部の「ヒューマンの世界とエコノの世界」 ・バイアスと誤謬 ・誘惑の先回りをする ・言動は群れに従う ・ナッジはいつ必要なのか ・選択アーキテクチャー 第2部の「個人における貯蓄、投資、借金」 ・意志力を問わない貯蓄戦略 ・オメデタすぎる投資法 ・借金市場に油断は禁物 第3部の「社会における医療、環境、婚姻制度」 ・社会保障制度の民営化ービュッフェ方式 ・複雑きわまりない薬剤給付プログラム ・臓器提供者を増やす方法 ・われわれの地球を救え ・結婚を民営化する 第4部の「ナッジの拡張と想定される異論」 ・12のミニナッジ ・異論に答えよう ・真の第三の道へ
Posted by
ナッジ(nudge)の本。第1部はわりと概念とか心理メカニズムの話,第2部以降は実際の社会問題と関連づけた話。ああ,(心理学者でなく)経済学者が書いてる本だなあ,という印象(実験とか調査とかの話がほとんとないので)。それがダメという意味ではなく,感慨として。 原書が2008年なの...
ナッジ(nudge)の本。第1部はわりと概念とか心理メカニズムの話,第2部以降は実際の社会問題と関連づけた話。ああ,(心理学者でなく)経済学者が書いてる本だなあ,という印象(実験とか調査とかの話がほとんとないので)。それがダメという意味ではなく,感慨として。 原書が2008年なので,話題に出てくる世界情勢がやや古い。リーマンショック前後だもんなあ。これも,だからダメというわけでなく,今この話をするとしたら別の例を考えないとだよなあ,というくらいの感想。あとアメリカの税のしくみとかよくわかんないといまいちわかりにくくて(自分の知識のなさが)残念。
Posted by
原題のままでよかったと思う。これは行動経済学の本ではなくて、行動経済学を応用した「ナッジ」の本なので。まぁ実践編と言われればそうなんだけど。
Posted by
ナッジで有名なこの本もサービスデザインの考え方(の一部)として読むと、理解しやすいのではないかと思います。
Posted by