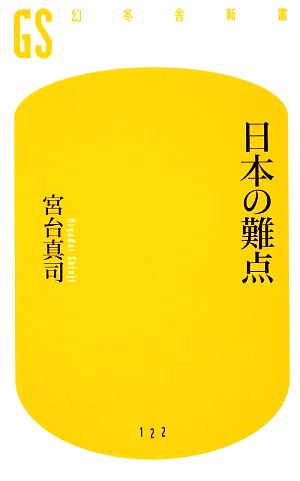日本の難点 の商品レビュー
現代社会は共同体が崩壊したことで表面的な承認欲求を満たす活動が蔓延していると嘆く。それはわかるが、対処法が特に明確には示されていない。格差をなくすのではなく格差が生じることを前提に敗者を包摂する仕組みが重要と主張するが、そんなことはみんなわかっていることで、そのためにどういう仕組...
現代社会は共同体が崩壊したことで表面的な承認欲求を満たす活動が蔓延していると嘆く。それはわかるが、対処法が特に明確には示されていない。格差をなくすのではなく格差が生じることを前提に敗者を包摂する仕組みが重要と主張するが、そんなことはみんなわかっていることで、そのためにどういう仕組みなら(あるいはどういう仕組みの決め方なら)多くが納得しつつ、敗者の生活の安定も尊厳も守られるのかについての提示がない。 まあ、本書は問題提起の書という位置付けということか。
Posted by
本書は2009年出版で時代と共に一部劣化した情報もあり割愛した。「この社会」をどう読み、どう国民は考えるべきかを問う本書だ。その中で気になる内容は当時から「防衛は重装備+対米中立」を掲げ「農業は農協+農水省+自民党水族を解体し農業の抜本的な改革」と主張している事だ。現実米国は防衛...
本書は2009年出版で時代と共に一部劣化した情報もあり割愛した。「この社会」をどう読み、どう国民は考えるべきかを問う本書だ。その中で気になる内容は当時から「防衛は重装備+対米中立」を掲げ「農業は農協+農水省+自民党水族を解体し農業の抜本的な改革」と主張している事だ。現実米国は防衛費の増額を毎年要求し、米国武器の購入、日本の駐留部隊への補助を求めているが、2025年には見直すべき項目でありEU諸国が対米国で動き出したように、いつまでも米国頼りではなく、日本独自開発の重装備が必須であり、米国とは中立的な立場(貿易含め)での交渉が必須となった。また農業に関する「2025年の米不足問題」は農協+農水省+自民党農水族の悪巧みが暴露され、更に「自給自足不可能」の現状から農業改革を即刻実行に移さなければならないと実感しているのは私だけだろうか。
Posted by
題名につられて入手したが、とても難しい本だった。「いじめ」を「尊厳」を回復不能なまでに傷つけることで以前と同じ生活を送れないようにしてしまうこと、と定義したり、米国大統領選が南北戦争における「分裂」と「再統合」の模擬演習だと言ったり。こういうところはまさに目からウロコ。結局日本は...
題名につられて入手したが、とても難しい本だった。「いじめ」を「尊厳」を回復不能なまでに傷つけることで以前と同じ生活を送れないようにしてしまうこと、と定義したり、米国大統領選が南北戦争における「分裂」と「再統合」の模擬演習だと言ったり。こういうところはまさに目からウロコ。結局日本は難点ばかりで少しも良くなっていく気配は無い。教育にしても、政治、各種制度にしてもそう。
Posted by
「部分的」「断片的」な読みしかできていないことを断りつつ書くなら、宮台真司が「スゴイ人」に「感染」することの重要性を説いていることを興味深く思う。ここまで堅牢に社会学内外の成果・精華を吸収しアウトプットできたのも、彼がニクラス・ルーマンや小室直樹といった「スゴイ人」に「感染」しえ...
「部分的」「断片的」な読みしかできていないことを断りつつ書くなら、宮台真司が「スゴイ人」に「感染」することの重要性を説いていることを興味深く思う。ここまで堅牢に社会学内外の成果・精華を吸収しアウトプットできたのも、彼がニクラス・ルーマンや小室直樹といった「スゴイ人」に「感染」しえたからだろう。つまり、人の中に深遠さ・神秘を認めてその世界の不思議さにひれ伏し、同時に深くそのインパクトを受容して自分自身を積極的に組み替えていくことか。その果敢な冒険精神をあらためて尊敬し、毀誉褒貶あれどあなどれない人と認識した
Posted by
私たちが抱えているものについてを時代ごとの事象と意味づけながら記述している。 表題にもある通り「日本の難点」はそれが課題なのか問題点なのかを明示できない側面がある。複雑に絡み合うものを一つずつ解くことで私たちの社会がより透明になりうるだろう。これからどうあるべきかの思考ができる準...
私たちが抱えているものについてを時代ごとの事象と意味づけながら記述している。 表題にもある通り「日本の難点」はそれが課題なのか問題点なのかを明示できない側面がある。複雑に絡み合うものを一つずつ解くことで私たちの社会がより透明になりうるだろう。これからどうあるべきかの思考ができる準備段階に入ることが重要なのかもしれない。その手段としては歴史の理解(把握)が必要だ。 本章は 人間関係、教育、幸福、アメリカのこと、日本のこと、の順で進んでいく。 最終的には私たちの住む国がどうなっていくことで個々の幸福度が高まるのか にもっていく。 教育のシステムと場所の喪失について私は面白く感じた。 ゆとり教育、さとり教育と世代が区別されてしまうことで過去を生きた人はそれらに属する若者を冷淡な目でみることがある。それは単に人間性の問題ではなく教育指針による結果なのだから大人は考慮すべき、といつも思う。 また団欒できる場所がなくなっている現代では深く語ったり何かを観て共有する時間が圧倒的に少なくなっている。ネット社会の問題点は文字。言葉だけが先行してしまい些細な一言を懐疑的に受けて人間不信になってしまうことは誰にでもありうる悩み 私はこの現代社会を割と問題寄りに解釈するが、逆に今の社会が良いと感じることもある。オンライン化によってこれまでになかった関係性がうまれたり、長々やっていた授業が簡素化されて受け身の時間が減ったり。最近では低学年次から英語やプログラミングの導入を行い、よりグローバルな知見を広げる機会も増えたらしい。 どちらが良い悪いと断定するのではなく時代と傾向を把握することで今後より良い社会を想像してみることが良いのかなー。 知った上で結局は自分自身がどうするべきか。 そう考える人の母数が増えることが未来の明るい日本を創りあげていくのではないでしょうか。
Posted by
アングラな部分を含めて様々なフィールドワークを通して積み上げられてきた著者の視点は、社会学のアカデミックなラインとは一線を画した揺るぎなさがある。 現代の社会学は何かと悲観的な論調になりがちだが、著者は「本当にスゴい奴は利他的だ」と述べ、最後のところで希望を持っている。
Posted by
社会の底が抜けた時代、相対主義の時代も終わり、境界線があやふやで恣意的な時代になっています。最先端の人文知の成果を総動員した日本という国の論点です。
Posted by
若者論や教育、安全保障、政治など様々な分野を横断して論じていて面白かった。他者に承認して欲しいけど自分は承認できない問題や、周りを感染させるようなレベルの高い人はどの人も利己的で公共に関心があるというのは、自分に自信があって周りのために頑張りたいとか思える人なのかなと思った。 そ...
若者論や教育、安全保障、政治など様々な分野を横断して論じていて面白かった。他者に承認して欲しいけど自分は承認できない問題や、周りを感染させるようなレベルの高い人はどの人も利己的で公共に関心があるというのは、自分に自信があって周りのために頑張りたいとか思える人なのかなと思った。 そういう人になるには様々な経験値を積んだり、ガリ勉じゃなくて豊かな感情を学ぶことが大切というのも共感できた。 環境問題についても、温暖化懐疑論を、本当に温暖化が起こっているかは問題ではもうなくて、世界の流れが変わらないなら、それにのって先行者利益を取るべきというのは新しい学びだった。 また社会が変わるになる合理性を越えるための感情による感染力と、いいことをしないことが社会で生き残れないようになる仕組みづくりが必要というのも共感できた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
著者をYouTubeで見かけたのをきっかけに図書館で借りて読んでみた。 可能な限り平易に書いたということだが、自分にとってはひと通り読んで理解できるものでもなく、やはり本著としっかり向き合って読むことが望まれる。 社会学や著者の洞察力等のフィルターを通して見た世界は、世の中の移ろいに何か必然性を与えてくれているようで興味深いものがある。 「本当にスゴイ奴に利己的な輩はいない」、 なるほど、その信念のもと後進の教育を続けている著者に敬意を表したい。
Posted by
問題提起の一冊。 【処方箋】かと言われると違和感があるが、誰でも目にすることができ、誰にでもなんでも言えてしまう「今の日本」を抽象度を上げたもの。このような入門書はなかなかないと思う。 でもターゲットは社会学を学ぼうとする学生向け。 一見とっつきやすそうな目次だが、基本的な社会学...
問題提起の一冊。 【処方箋】かと言われると違和感があるが、誰でも目にすることができ、誰にでもなんでも言えてしまう「今の日本」を抽象度を上げたもの。このような入門書はなかなかないと思う。 でもターゲットは社会学を学ぼうとする学生向け。 一見とっつきやすそうな目次だが、基本的な社会学の素養がない人には勧めない。 一応社会学士の私ですが、もうちょっと基礎を学ばないとダメだなと反省しきりです。(2010.8)
Posted by