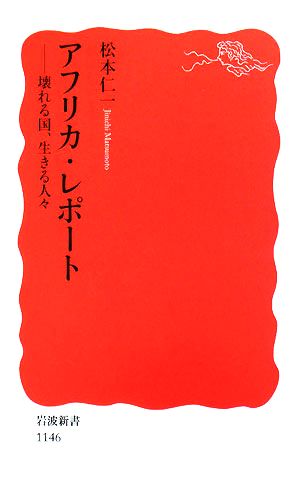アフリカ・レポート の商品レビュー
知っているようで、まったく知らないアフリカのこと。 想像を絶する状況だった…… ただ貧しいだけではなく、命が脅かされている。 少し古い本だが、状況はどれほど変わっているのだろうか。 希望を持てる章があるのが救い。 自分には何ができるのか。
Posted by
アフリカの2000年代当時までの現状がよくわかる一冊でした。書かれた頃から15年経ったアフリカはどう変わってるのか、最近状況を知りたくなります。 本書に出てくるような腐敗する政治、苦しむ国民を他所にチャンスとばなりに目をつけて利権を奪いにくる外国人、母国を諦めて移住する国民。 ...
アフリカの2000年代当時までの現状がよくわかる一冊でした。書かれた頃から15年経ったアフリカはどう変わってるのか、最近状況を知りたくなります。 本書に出てくるような腐敗する政治、苦しむ国民を他所にチャンスとばなりに目をつけて利権を奪いにくる外国人、母国を諦めて移住する国民。 日本も同じ運命をたどる日は近い? あるいはもうすでに起きているかも?
Posted by
アフリカの国々が今ある状況を認識できるようになる本。適切な統治、開発を行って飢餓や旱魃の問題を解決するケース、腐敗した政府による独裁により国民が苦しみに喘いでいるケースなどが紹介される。地獄がなぜ地獄になるのか、その実態が少しわかるようになる。
Posted by
30年以上の取材の成果がまとまっています。2018年、南アフリカに行った後に本書を読んだのですが、現地で見てきたことと本書の内容が見事に一致していました。南部アフリカの概要や真実を知りたい人におすすめです。
Posted by
「アフリカでは政府は自らの敵を作り出すことで自らの立場を強めることが多い」 政治家も同様に、批判対象を作ることで自らの地位を確保することが多々ある。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
豊かなジンバブエの農業を一〇年で壊滅させ、アパルトへイトを克服した南ア共和国を犯罪の多発に悩む国にしたのは誰か。中国の進出、逆に国を脱出するアフリカ人の増加などの新しい動きを追い、同時に、腐敗した権力には頼らず自立の道を求めて健闘する人々の姿も伝える。三〇年近いアフリカ取材経験に基づく、人間をみつめた報告。 ①政府が順調に国づくりを進めている国家 ボツワナ ②政府の国づくりの意欲はあるが、運営手腕が未熟なため進度が遅い国家 ガーナ、ウガンダ、マラウィ等10ケ国程度 ③政府幹部が利権を追い求め、国づくりが遅れている国家 ケニア、南アフリカ等アフリカでは最も一般的 ④指導者が利権にしか関心を持たず、国づくりなど初めから考えていない国家 ジンバブエ、アンゴラ、スーダン、ナイジェリア、赤道ギニア等 この本が出版されたのが2008年。 今、少しでもいいから状況が改善されていることを祈る。 そして、私たちに出来ることは何かを考える。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
普段あまり意識しないけど、国民国家や民主主義といった一見あたりまえと思えるシステムがどれほど大事か痛感する。 読みかけで中断してる「国家はなず衰退するか」にも書いてあったけど、包括的で民主的なシステムが発展の肝だと思う。関係ないけどその半分しかない中国が今後どうなるか興味深いが。たまたま逮捕された某自動車会社の社長ともダブって見える。 あと中国と日本の民間の活動の対比は非常に興味深かった。 たまたまNHKでみたタスマニアの華僑の活動もそうだけど、中国人のやり方は恐ろしいくらい徹底していると思う。 そんななかで現地の発展を促す日本のやり方が頑張ってほしいと本当に思う。 いずれにせよ未熟だからこそ、詳細に無ることで国に必要なものが何かがわかる優れたレポートであった。最後に書かれた希望にほっとする。
Posted by
本書が書かれたのが2008年。読んだのが2017年。10年の時差があるが、果たして、その間に本書で述べられたアフリカの情勢はどうなったのだろうか。 ジンバブエはムガベ大統領の交代はあったが、与党内のコップの嵐に終わりそうだし、南アに住み着いた人たちが帰る気配はない。南アの犯罪...
本書が書かれたのが2008年。読んだのが2017年。10年の時差があるが、果たして、その間に本書で述べられたアフリカの情勢はどうなったのだろうか。 ジンバブエはムガベ大統領の交代はあったが、与党内のコップの嵐に終わりそうだし、南アに住み着いた人たちが帰る気配はない。南アの犯罪はワールドカップを挟んでも高止まりのままだし、カージャックは相変わらずである。スーダンは分離独立したが泥沼のまま。ナイジェリアはISといった新しいファクターを取り込みつつ更に不安定要素が増している。 中国は、本書の頃よりも現地化を進めるなどの工夫をしていると思うが、プレゼンスは依然増す一方だ。 そして、政府ではなく、NGOや商業ベースの民間活動に未来への期待が集まる、というのも変わらない。 本書を読んで、事象は進化しているが、基本構造に変化なし、という印象を改めて持った。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
指導者が「敵」をつくり出すことで自分への不満をすりかえる。アフリカでよく見られる構図だ。それは国内の対立を激化させることであり、国家的統一とは逆の方向に国民を駆り立てる。へたをすると国の将来が崩壊してしまう危険さえある。しかし権力者は将来のことなど考えていない。目の前の責任を回避し、権力の延命を図る。それだけなのだ。ルワンダの大虐殺もジンバブエの経済崩壊も、まさにそうして起きた。p42 ヨハネスブルク市警「フライング・スクォッド」(空飛ぶ部隊)と呼ばれる特別機動捜査隊。車の操縦や射撃の特別訓練を受けた警官が、二人一組でパトカーに乗り、市内を一晩中巡回して凶悪犯罪に対応する。p55 明治維新直後の日本政府指導部には、早く国づくりをして近代化を達成しないと、西欧やロシアにのみこまれるという恐怖と危機感があった。アヘン戦争で西欧列強の食い物にされた中国を、彼らは目の当たりにしていた。 いつまでも薩摩だの会津だのといっておられず、国民すべてが帰属感を持つ国家、国民国家を形成しなければならない。その危機感が国家形成を急がせた。p75 【国民の中から生まれた新しい動き】p200 ジンバブエの農業NGOのORAP。国際社会非公認のソマリランド新政府。シエラレオネ内戦の兵士たちが始めたバイクタクシー。セネガルの漁民が経営するアフリカ最西端の生ガキ屋台...。
Posted by
これがアフリカのリアルな姿か。 日本人が静かに内にこもっているうちに、行動力のある中国人がアフリカを支配している。 こういう本をもっと皆に読んでもらいたい。
Posted by