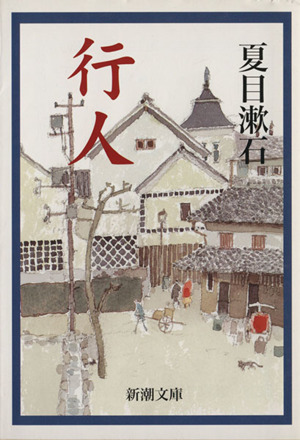行人 の商品レビュー
何事も考えに考え抜いて、それでも行動を起こさない一郎と、 「女は鉢植えのようなもの。誰か来て動かしてくれない以上、立枯れになるまで じっとしている外ない」 と言う感情主義で情熱的な直。 そんな彼女がストレートな愛情表現をしない一郎に満足するはずもなく、 捻れた態度をとるばかり。...
何事も考えに考え抜いて、それでも行動を起こさない一郎と、 「女は鉢植えのようなもの。誰か来て動かしてくれない以上、立枯れになるまで じっとしている外ない」 と言う感情主義で情熱的な直。 そんな彼女がストレートな愛情表現をしない一郎に満足するはずもなく、 捻れた態度をとるばかり。 直が二郎と一夜を共にしたのに、何も行動を起こさない彼に焦れて、 暗闇の中わざと帯を解く音など聞かせて誘惑したのは、 鉢植えのような自分をどこか遠くへ連れ出して欲しかっただけで、 別段二郎でなくてもよかったのだろう。 ともあれ、これほど相性の悪い女を妻にしたことが、 一郎にとってそもそもの不幸の始まりだった。 思索ばかりで実行力のないことが、自分の不幸の根源だと一郎は分かっているが、 (実行に伴う)自意識を捨てることができない。 そして、ぐるぐると思考の螺旋に迷い込み、とうとう狂気の淵へと辿り着く。 心が体を支配するのではなく、体が脳(心)を支配しているということが 近年明らかになってきたようだが、 そのような人間の本質を見抜いていた漱石はさすが。 それにしても「何か大変なことが起こるぞ」という餌をしじゅうちらつかせ、 読者にぞくぞくする期待を持たせるのが上手い書き手である。
Posted by
ブクログ再開します、と自分に戒めるために書いておきます。 夫婦像というのは、みんな自分の理想を持ってて、しかもそれが普通だと信じている面があるけど、実の夫婦関係って夫婦の数だけ違うよね、と思いながら読みました。 三角関係♪という読み方はしませんでした。その方が下世話に面白いけど...
ブクログ再開します、と自分に戒めるために書いておきます。 夫婦像というのは、みんな自分の理想を持ってて、しかもそれが普通だと信じている面があるけど、実の夫婦関係って夫婦の数だけ違うよね、と思いながら読みました。 三角関係♪という読み方はしませんでした。その方が下世話に面白いけど、うがちすぎかと。
Posted by
2014年11月【東京月曜会5周年記念】修善寺温泉旅行の課題本です。 http://www.nekomachi-club.com/report/15768
Posted by
漱石の結論はいつも先進的な答えだな。聖書も読んでみるかな。 一番ハッとさせられたのが↓ 『あなた方は兄さんが傍のものを不愉快にすると云って、気の毒な兄さんに多少非難の意味を持たせているようですが、自分が幸福でないものに、他を幸福にする力があるはずがありません』
Posted by
最後のどんでん返しが凄かった。 兄の様子が兄の友人の手紙からどんどんわかっていく。 すべてを手にしても、落ち着かなかったり、疑心暗鬼になってしまう。 人間とはそんなものかもしれない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
20140205読了。漱石先生、後期三部作の二作目。長くて捉えどころがないな、というのが印象の本。中心となる人物は一郎とその弟、二郎。一郎は結婚をしているが妻の自分に対する気持ちを信じることが出来ず、果ては妻が「弟に気があるのではないか?」と疑心暗鬼に陥り、弟の二郎に妻の気持ちを確かめるために一晩二人っきりで過ごしてほしい、とまで詰め寄る。一種パラノイア的な神経症を抱える。 そうして、作中には何度か兄と弟が言い争うシーンがあるが、お互いに理解をし合うことはない。この何度かのシーンはどれも迫真生があり、心に迫る。 最後の章は、兄一郎の学生時代からの旧友であるHさんが、兄の神経症緩和のために二人旅をし、その二人旅の様子を弟の二郎へと書いた手紙の内容で物語が終わる。余談だが、手紙という手段をもって人の心の真相を読者に伝える、という手法は次の作品である『こころ』に繋がる序章となっているような気がする。 この手紙の中では、兄一郎はそのこころに迂闊と矛盾を抱えながら苦しみ自分の現状をHさんに吐露する。どうして自ら生きづらくするのか、と思ってしまうがそうようにしか生きられない一郎のこころに同情せざるを得ない。 この作品を読んで、どこまで漱石先生の精神性が作品中に込められているのかが分からないけれども、夏目漱石という人は、その時代を客観的に冷静にある種の危惧をもって、つまり明晰な頭脳で批判的に世の中をみた人だけれども、その一方で何の根拠もなく何の利害もなく、“ただ人を信じる“、ということに強く憧れた人なのではないかと思う。 信じることができずに、考えるしかないその苦しみをこの作品は伝えていると思う。
Posted by
何度も読み返しています。人の内面をこんな風に文書に表せるのは流石だと思います。読むことで、自分の中のもやもやして表現しがたいことが、すっーと整っていきます。
Posted by
漱石の内面の心情を流れるような文章で表現する能力が素晴らしい。 本作品は漱石の傑作のひとつだと思う。 一郎の持つ精神的な悩み、鬱状況は漱石自身が悩んでいたことでもあり、故にその描写に迫りくるものを感じる。 宗教への葛藤、哲学的な遣り取りは、知識人としての価値観のぶつかり合い、苦...
漱石の内面の心情を流れるような文章で表現する能力が素晴らしい。 本作品は漱石の傑作のひとつだと思う。 一郎の持つ精神的な悩み、鬱状況は漱石自身が悩んでいたことでもあり、故にその描写に迫りくるものを感じる。 宗教への葛藤、哲学的な遣り取りは、知識人としての価値観のぶつかり合い、苦悩を表現しているともいえる。 本小説内で展開が幾つかに分かれるが、纏まりに欠けるとの批判となるのか、多様なテーマが織り込まれているので愉しめる、と評価するのか。 夫婦、男女、兄弟、親子、友情と様々な人間関係のテーマが散りばめられており、ストーリーに飽きがこない。 特に漱石が得意とする「女性の謎」、そしてそれに苦悩する男性、にも触れることができる。 以下引用~ ・「考えるだけで誰が宗教心に近づける。宗教は考えるものじゃない、信じるものだ」 ・「道徳に加勢するものは一時の勝利者に違いないが、永久の敗北者だ。自然に従うものは、一時の敗北者だけれども永久の勝利者だ・・・」
Posted by
ダンテの「神曲」地獄篇の挿話"パオロとフランチェスカ"を題材に、二人を殺すジョバンニに当たる人物の自意識を描く。そんなに気になるなら本人に直接聞けよ!と思うことは現代生活でもよくある。バレバレなのに自分が気にしていると悟られたくない馬鹿馬鹿しさこそ自意識の本性...
ダンテの「神曲」地獄篇の挿話"パオロとフランチェスカ"を題材に、二人を殺すジョバンニに当たる人物の自意識を描く。そんなに気になるなら本人に直接聞けよ!と思うことは現代生活でもよくある。バレバレなのに自分が気にしていると悟られたくない馬鹿馬鹿しさこそ自意識の本性なわけで、植え付けられた鉢植えのように立ち枯れになるまで、そこに居続けるしかないと語る嫂が哀れ。独りぼっちで書斎に籠ってばかりいると僻んだ観察ばかりする、と肉親に言われる主人もまた然り。現代の僕たちが教科書で読む「こころ」はここから繋がっているんだ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
最初、二郎が主人公だと思っていたら、兄の一郎が主人公だった。一郎の研究したら人の心を理解できるのではないかと真面目さ、研究すればするほど妻も家族が離れて、深まる孤立と狂気。この作品のタイトルの方が『こころ』でも良い気がする…。 一郎の家の中で花嫁修業している純粋な乙女だったお貞さんを幸福な人といい、嫁いだお貞さんは「もう夫にスポイルされてしまっている」と夫のために女は邪に変わる存在なのだという。確かに女は男によって変わりやすい生き物なんだろうなと思った。寝ているところで終わるのが、少し勿体無いなと思うのだけど、これが現代なら精神病院へ連れていかれるだろうから、この時代そう終わらせるのが妥当なのかもしれない。結婚生活で男女で女が変わるというのなら、今の時代の同性婚はどうなのだろう。夏目漱石が現代に生きていたら同性婚についてどう思うか聞いてみたいところ。
Posted by