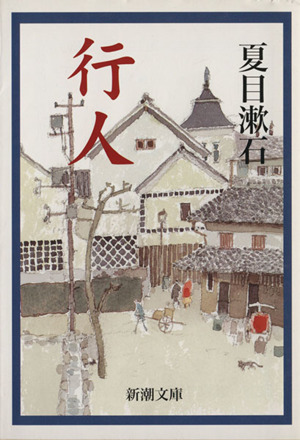行人 の商品レビュー
漱石さんの小説は、どうしようもないほど救えない登場人物がいる。こんなに厭世的な人は、小説の中で存在はしてもいいが、実際の世の中に存在するとややこしくなる。
Posted by
登場人物長兄一郎を通し漱石の孤独を描いている。生まれつき学業や宗教に入っているでもない天真な性分に生まれた妹が則天去私に到達しているように見え、対称に自身の投影である一郎が自身の我執、エゴイズムに苦しんでいる様が描かれる。読んでいてしんどくなった。 生きるが、そのまま行人に直結...
登場人物長兄一郎を通し漱石の孤独を描いている。生まれつき学業や宗教に入っているでもない天真な性分に生まれた妹が則天去私に到達しているように見え、対称に自身の投影である一郎が自身の我執、エゴイズムに苦しんでいる様が描かれる。読んでいてしんどくなった。 生きるが、そのまま行人に直結するという考え方は、やっぱり思い詰めていて余裕がない。が、家族や友人、関係性はさて置き、同じレベル同じ感度で精神的に何かをある程度シェア出来る瞬間が人生に訪れなければ生きた心地があんまりしない、のはよく理解出来る。そういう機会がないと孤独で寂しくて、堪え難いが、その気持ちをどうにかこうにかやり込めて生かなければならない、のであればその道は一郎同様、ある意味行人であるかもしれない。
Posted by
20180326 漱石晩年の作品の1つ。 神経鋭敏で学者肌であった一郎は、鋭敏な神経ゆえに、他人の心を理解することができなくなる。更に、理知的な頭脳ゆえに、自分の行動理念を他人にも投げかけ、それに従わない普通の人を理解できなくなる。 鷹揚な性格であった二郎は、兄嫁と泊まり行った和...
20180326 漱石晩年の作品の1つ。 神経鋭敏で学者肌であった一郎は、鋭敏な神経ゆえに、他人の心を理解することができなくなる。更に、理知的な頭脳ゆえに、自分の行動理念を他人にも投げかけ、それに従わない普通の人を理解できなくなる。 鷹揚な性格であった二郎は、兄嫁と泊まり行った和歌山の一件を境に、疑心暗鬼で苦しめられる兄と対峙する事になる。 人間の理性を突き詰めていった一郎は、自分一人では理解することができない心理にぶつかり、神経衰弱になる。もちろん、人には理解し得ない、自然の力、他人のこころ等が存在するものだからこれは当然である。もがき苦しんだ挙句、宗教に想いを寄せることは太古からの人の行動心理で正しいのであろう。 自分では計り知れないものがある、ということを窮屈に思うか、あるいは神秘を感じ楽しさを感じるかで生き方は変わると思う。他人の心理全てを理解することはできないし、無論、自分の思うようにコントロールすることもできない。色々な考えを持つ人が行動を起こすから、交流、恋愛、経済、市場が生じ、個性のある文化が生まれるのだろう。私は後者の考えを肯定し突き詰めて生きていきたい。 則天去私 夏目漱石で未だ積読の本。 自分の感情とは、他人の感情とは。人と生きていく上で、漱石が残してくれた心の捉え方を感じたい。 他人に依存したくもないけども、依存する生活もある矛盾に苦しむ主人公。 一般的道徳観念=貞操 vs 自然=純粋なる恋愛 前者は一時の勝者だが、永遠の敗北者 後者は一時の敗者だが、永遠の勝者
Posted by
直感ですけれど、これ傑作ですね。 男女のペアがいくつも現れて、それぞれの綻びというか、綾があったりして、さらにそのそれぞれに並々ならない刺激を受けて鬱屈していく主人公のお兄さんが、真の中心人物です。 単に屈折してしまうのではなくて、その賢さがこじれにこじれてーー。 この手の悩...
直感ですけれど、これ傑作ですね。 男女のペアがいくつも現れて、それぞれの綻びというか、綾があったりして、さらにそのそれぞれに並々ならない刺激を受けて鬱屈していく主人公のお兄さんが、真の中心人物です。 単に屈折してしまうのではなくて、その賢さがこじれにこじれてーー。 この手の悩みって、結構共感できるんです。そして、それがなにかの拍子に螺旋を描くように深く深く落ち込んでしまうと彼のようになってしまいます。 辛いですよ。お兄さん。どうか、快復してほしいです。 映像化されるなんてことがあったら、見応え十分だろうなあ。いつか夏目漱石役を演じられた長谷川博己さんがお兄さんに適役かな。
Posted by
夏目漱石 「行人 」最後の章(塵労)の 一郎とHのやりとりはカラマーゾフの兄弟の大審問官のような思想バトルだった。孤独で病的な不安を持つ一郎は 漱石自身。則天去私へ向かう様子が読み取れる 一郎「何をするのも厭〜何かしなくてはいられない〜この矛盾が苦痛」 Hから一郎へ「君は 批...
夏目漱石 「行人 」最後の章(塵労)の 一郎とHのやりとりはカラマーゾフの兄弟の大審問官のような思想バトルだった。孤独で病的な不安を持つ一郎は 漱石自身。則天去私へ向かう様子が読み取れる 一郎「何をするのも厭〜何かしなくてはいられない〜この矛盾が苦痛」 Hから一郎へ「君は 批判することだけ考える男〜なぜ 山の方へ歩いて行かない」
Posted by
三四郎、それからを読んだのち、門を飛ばして読んだが伊豆の温泉での吐血からか前作ののんびりとした感じとは打って変わって生死人間への鋭さが増してるように感じ、人間の普遍性に対する小説はチャップリンの街の灯と同じ感動だった。
Posted by
男女間の悩みからはじまり、最後はその人(主人公の兄)の人生観、宗教観で終わるというストーリー。 狂人一歩手前の精神状態にあるように思われる兄とその周りの人々の苦悩を描いているのだが、それ程感情移入はできず、明治の知識人とはこういったものかという程度の感想。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
外から見ると単純なのに内側では複雑化している家庭内の人間関係を見ているだけで面白かった。家庭内なのに緊張感がありヒヤヒヤする。 はじめは努力もしないで愛だけ欲しいと喚いているように見えたが、兄の人となりがあばかれていくにつれ、兄の孤独に同情する気持ちが生まれた。 H氏の手紙の兄の言葉にはハッとさせられるものがいくつもあったが、あの家族と兄は相性が良くなく、家族がこれを読んでもよりギクシャクするだけだろうなと思う。それが分かっているからまた深く孤独を感じるのだろうと想像した。
Posted by
一郎、女性に劣等感抱き過ぎではないか。気持ちは分からなくはないけど。並の人間なら出来る人間関係の初期治療を、我が強いために出来なかったんだろう。もしかしたら一郎もその点に気づいていたかもしれないけれど、我を押し通して修復不能にしてしまった、と言う傍から見た感想。 偉そうな感想だっ...
一郎、女性に劣等感抱き過ぎではないか。気持ちは分からなくはないけど。並の人間なら出来る人間関係の初期治療を、我が強いために出来なかったんだろう。もしかしたら一郎もその点に気づいていたかもしれないけれど、我を押し通して修復不能にしてしまった、と言う傍から見た感想。 偉そうな感想だったけど、僕自身、女性の本音をどう引き出すかなんて知らないから、この点では一郎とどっこいではある。兎に角、直の本音をどうにかして一郎が知ることができれば、少なくとも「所有」だの「絶対」だの小難しい問題まで悪化しなかったのではないか。 今回は一郎と直の不和の原因が曖昧なまま終わってしまった。「門」で宗助と御米が不倫した原因が明らかにされないように、一番俗っぽい点を省くのはなんだか狡いなと思いつつ、逆に「こころ」は先生の一番俗っぽい感情を描写しきったから凄く面白く読めてしまうんだろうなと思った。
Posted by
学問だけを生きがいとしている一郎は、妻に理解されないばかりでなく、両親や親族からも敬遠されている。孤独に苦しみながらも、我を棄てることができない彼は、妻を愛しながらも、妻を信じることができず、弟・二郎に対する妻の愛情を疑い、弟に自分の妻とひと晩よそで泊まってくれとまで頼む……。「...
学問だけを生きがいとしている一郎は、妻に理解されないばかりでなく、両親や親族からも敬遠されている。孤独に苦しみながらも、我を棄てることができない彼は、妻を愛しながらも、妻を信じることができず、弟・二郎に対する妻の愛情を疑い、弟に自分の妻とひと晩よそで泊まってくれとまで頼む……。「他の心」をつかめなくなった人間の寂寞とした姿を追究して『こころ』につながる作品
Posted by