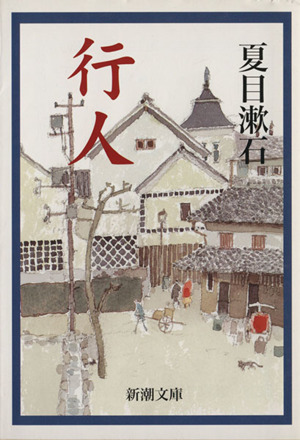行人 の商品レビュー
「ゆくひと」、ではなく「こうじん」と呼ぶのか、と最初にちょっとした驚きが。 妻、身内を信じられなくなった一郎の苦悩、葛藤、孤独が綴られている本作、決して他人事のように感じられない。 ただ、「もう誰も信じることが出来ない」と打ち明けることが出来る友人を持っている点には救いを感じ...
「ゆくひと」、ではなく「こうじん」と呼ぶのか、と最初にちょっとした驚きが。 妻、身内を信じられなくなった一郎の苦悩、葛藤、孤独が綴られている本作、決して他人事のように感じられない。 ただ、「もう誰も信じることが出来ない」と打ち明けることが出来る友人を持っている点には救いを感じる。自分の中で肥大化していく自意識や被害者妄想を少しずつ他人に吐き出しながら生きていくしかないのだ、この世の中。 以下、引用。 行人 p66 其処に自分たちの心付かない暗闘があった。其処に持って生まれた人間の我儘と嫉妬があった。 其処に調和にも衝突にも発展し得ない、中心を欠いた興味があった。要するに其処には性の争いがあったのである。そうして両方ともそれを露骨に言うことが出来なかったのである。 けれども浅間しい人間である以上、これから先何年交際を重ねても、この卑怯を抜くことは到底出来ないんだという自覚があった。自分はその時非常に心細くなった。かつ悲しくなった。 p293 そうして自己と周囲と全く遮断された人の寂しさを独り感じた。 p253 人間の作った夫婦という関係よりも、自然が醸した恋愛の方が、実際神聖だから、それで時を経るに従って、狭い社会の作った窮屈な道徳を脱ぎ捨て、大きな自然の法則を嘆美する声だけが、我々の耳を刺激するように残るのではなかろうか。
Posted by
深く深く考えることが懐疑を深め、孤独を招き、そしていつか自我崩壊につながっていく。何も考えずに生きるのがいいことかというとそうではないし、近代知識人のエゴ、苦しみ、心の葛藤を描いた作品だろう。
Posted by
現在では、精神的不具合は病気として扱われるが、医学が未発達のときはまだそれを性格的なこととか考え方の修正と捉えていた。その精神的不具合は、薬などで治るという意味では病気であり、それが今の考え方であるが、以前は治るにしても、環境を変えてみたり、当人の考え方を変えるしかなかったのだろ...
現在では、精神的不具合は病気として扱われるが、医学が未発達のときはまだそれを性格的なこととか考え方の修正と捉えていた。その精神的不具合は、薬などで治るという意味では病気であり、それが今の考え方であるが、以前は治るにしても、環境を変えてみたり、当人の考え方を変えるしかなかったのだろう。しかし、いつの世にも共通しているのは、周りにいる知人がそれをしっかり理解して行くことが肝心であるという事だろう。そして、この病気の発見の難しさは、傍で寄り添うべき人がいかに客観的になれるかにかかっている、というところにあるのかもしれない。それをこの小説は教えてくれる。 しかし、本筋はというと、絶対と相対の関係をどう処理するかという事だろう。本人は絶対を信じたいが、そのように行動すると相対的にできている社会から弾き飛ばされ、馴染めなくなってしまう。しからばと、相対的な社会で相対的な行動を取れる人間はいいが、それをできない人間はどうしたらよいのだろうか?これがこの本のテーマだろう。結論の一歩手前での解決策は、そのような人間には、死、気違いそして宗教があると提示されるが、そのどれをも選択できない人間には、苦悩の日々しか残されないという悲劇が待っている。
Posted by
結構面白く読めました。嫂と和歌山で一晩過ごす羽目になるのも、はわはわしながら読んでました。停電の中で義姉が帯を解くのもすんごい興奮しながら読んでました(笑) それから穏やかに過ぎる日々の中で、少しずつひずんでゆく兄との関係や嫂との妙な距離、母の視線なんかも、なかなかスリリングで中...
結構面白く読めました。嫂と和歌山で一晩過ごす羽目になるのも、はわはわしながら読んでました。停電の中で義姉が帯を解くのもすんごい興奮しながら読んでました(笑) それから穏やかに過ぎる日々の中で、少しずつひずんでゆく兄との関係や嫂との妙な距離、母の視線なんかも、なかなかスリリングで中盤からは一息で読んでしまいました。 「宗教は考えるものじゃない、信じるものだ」 兄はさも忌々しそうにこう云い放った。そうしておいて、「ああおれはどうしても信じられない。どうしても信じられない。ただ考えて、 考えて、考えるだけだ。二郎、 どうかおれを信じられるようにしてくれ」 この兄さんの叫びは何とも切なかったです。 こんな頭のいい兄さんに対しておこがましいですが、よくわかるんですよ。これって宗教だけじゃないんですよね。恋愛もそうだし、幸福さえそうだと思います。 昔、幸せについて考えた時に「そんなものはどこにもない。幸せはその人がそう思い込んでいるだけだ」ってところに行き着いて、何も考えず幸せそうな人を少し馬鹿にさえしていたけれど、今はそれが出来る人がとても羨ましいんです。 その人がそれを幸福だと信じれば、たとえどんな状況であったとしても、誰に否定されようともそれを侵すことは出来ないんです。 幸福の正体について考えることなど、なんて無意味なことでしょう。信じられることのなんと強く難しく潔いことでしょう。 私も兄さんと一緒で、もしかしたら一生疑うことしか出来ない気がしているのです。 だから、あの結末は永遠に眠る時まで安らぐことなどできないとでもいうようで、真理であったとしても、切なかった。 それとも、そんな孤独が自分だけではないと思えば少しは救われるのかな。
Posted by
これは読了に結構時間がかかってしまった。 おそらく自分にとって、主人公=兄の一郎を客観的に描く文体にうまく馴染めなかったからではないか。 正直、裏の説明文を読まなければこの作品が兄に関してのものであるということを理解するのに、半分くらい読み終えてようやく気づく、という感じであろ...
これは読了に結構時間がかかってしまった。 おそらく自分にとって、主人公=兄の一郎を客観的に描く文体にうまく馴染めなかったからではないか。 正直、裏の説明文を読まなければこの作品が兄に関してのものであるということを理解するのに、半分くらい読み終えてようやく気づく、という感じであろう。 主人公をあくまで客観的に描くというやり方は非常に面白いが同時に面白くなくもある。他の作品も割と客観的に淡々と描くものが多く感じるが、この作品は特に顕著だと思う。 まだ自分にはこの時期の作品を理解することが出来ないかとなると若干悔しさもこみ上げてくるが、めげずに他の作品も鑑賞するとする。
Posted by
一郎の苦悩が壮絶で痛々しい。幸せになる方法を追求しながら、実際は理想とする幸せから離れていくという矛盾。また、その矛盾をも良くわかっているのに追求をやめられない。いい加減=良い加減 やっぱ これに尽きるんだろうなと。 次はラスト、こころ。
Posted by
漱石に限らず、この時代の文章は 「語らずに語り、語るが語れず」 という感じがする。 隠微な空気や 胸がやけつくような愚直さ 友人の手紙は長すぎる気がするも、 最後の文がやさしくて じんとした。
Posted by
いかにも夏目漱石らしい、美しい文章で、淡々と、ただ静かに物語は流れる。何と言うか、この人の小説は水を思わせる。穏やかな海、川、曇りの日の湖。この小説もまさにそんな感じで、暑い夏の描写の中でも、どこか涼しげな冷たさがある。一人称のはずの小説なのに、何と言うかことごとく冷淡に進む。 ...
いかにも夏目漱石らしい、美しい文章で、淡々と、ただ静かに物語は流れる。何と言うか、この人の小説は水を思わせる。穏やかな海、川、曇りの日の湖。この小説もまさにそんな感じで、暑い夏の描写の中でも、どこか涼しげな冷たさがある。一人称のはずの小説なのに、何と言うかことごとく冷淡に進む。 妻が弟を愛しているのではないかと苦悩する兄。その苦悩によって兄は妻を疑うことしか出来ず、ますます関係は悪化する。それを、他人事のように眺める弟。 小説を読み終えた時、心をいっぱいにしていたのはお兄さんの子どものように美しい苦悩だった。静かに、しかし正直に妻を愛するお兄さんの悲しさが切なかった。
Posted by
こころ、につながる佳作。ダークトーンな夏目節が冴える。 追記。 佳作、などと書いているが、しばらく時間が経ってみると、強烈な印象として蘇ってくる。
Posted by