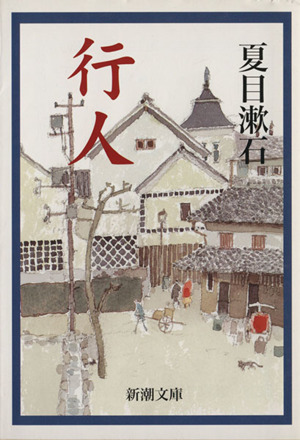行人 の商品レビュー
「彼岸過迄」に続き「こゝろ」に繋がる後期3部作の2作目。一郎が惚けるように蟹をいつまでも眺める場面は切なかった。自分はお貞さん寄りの人間で良かった‥‥
Posted by
理想を追い求めるあまり、周りとうまくいかない男の苦悩の話。 語り手は二郎くん(弟)なんだけど、主人公は一郎さん(兄)。このお兄ちゃんがなんかめっちゃ考え過ぎてて、「崇高な俺の考えが理解されない。低俗な人間どもに馬鹿にされる!」って周りに(特に奥さんに)当たり散らしてる印象。お兄...
理想を追い求めるあまり、周りとうまくいかない男の苦悩の話。 語り手は二郎くん(弟)なんだけど、主人公は一郎さん(兄)。このお兄ちゃんがなんかめっちゃ考え過ぎてて、「崇高な俺の考えが理解されない。低俗な人間どもに馬鹿にされる!」って周りに(特に奥さんに)当たり散らしてる印象。お兄ちゃんだけ異質なんだよなあ。周りはお兄ちゃんに敬意を払ってると思うんだけど。一郎さんの考えは高尚だと思うけど、生きていくってそんなことばかりでなくて、一郎さんは自分で自分を苦しめてて、そのせいで周りも引っ掻き回されて、何だかなあ…って感じの話でした。
Posted by
家族との関係、結婚についてや、夫婦関係、友達などが描かれていて読み応えがあった。 生きていく上で、人間関係は外せないけど、不器用でうまく人と関われない人もいる。私も得意ではない。 この本の登場人物の兄さんは、不器用で真面目で知識人だ。頭はいいけど、人との付き合いが苦手。考えすぎて...
家族との関係、結婚についてや、夫婦関係、友達などが描かれていて読み応えがあった。 生きていく上で、人間関係は外せないけど、不器用でうまく人と関われない人もいる。私も得意ではない。 この本の登場人物の兄さんは、不器用で真面目で知識人だ。頭はいいけど、人との付き合いが苦手。考えすぎてしまって不安になってしまう。1+1=2のように答えの出るものや予測がつくことはいいけど、人のこころなんてわからない。こうしたらこうするだろうって、期待するから裏切られる。むしろ何も考えないで、期待しないで、意外な答えが返ってきても、あー、そうきましたか。ぐらいに柔軟に考えた方が人付き合いってしやすい。
Posted by
のつこつと読んだ。 昔いっぺん読んだことがあって、浜寺の料亭の場面だけが印象に残ってて、そこを確認したくって読んだら、かなり前の方にでてきてほんの数行だけやった。あとはほとんど忘れていてまるで初めて読む気分。 病院の場面が面白いっていうか映像として想像つかない。病室は畳張りで布団...
のつこつと読んだ。 昔いっぺん読んだことがあって、浜寺の料亭の場面だけが印象に残ってて、そこを確認したくって読んだら、かなり前の方にでてきてほんの数行だけやった。あとはほとんど忘れていてまるで初めて読む気分。 病院の場面が面白いっていうか映像として想像つかない。病室は畳張りで布団やったんやろうか。それやったら靴は何処で脱いでたんやろうかとか。どうも看護婦さんはそれぞれ専属で部屋の前の廊下で待機してるみたいな。声がかかるまで柱にもたれて本を読んで時間潰してる表現があったり、その看護婦さんに病人のこと聞いたら何でも教えてくれてプライバシーダダ漏れやったり。 その上病人の都合で入院したり退院したり。胃潰瘍の人にはお腹の上に氷嚢乗せてたり。今では想像もつかないことばかり。 漢字の使い方もええ加減なような気がする。ページによって送り仮名が変わってたり「初」と「始」の使い方も違うかったり。昔は手書きやったからそんなこともあり得たって感じかな。ある意味自由やな。でも、ま、この小説で描こうとしたことは、そんなことではない。兄一郎の苦悩を描いたんやろうが、そこに至るまでがのつこつのつこつ。
Posted by
【多知多解の一郎が向かう先は、行人?】 一郎は理智で聡明であるが故に人を信じることができない。また周囲も、彼が優秀であるが故に理解を示せない。故に彼は孤独に苦しみ、この負の循環から抜け出す方法を模索する。おそらく彼が最終的に行き着くのは宗教家であり、行人である。(宗教家は信じる...
【多知多解の一郎が向かう先は、行人?】 一郎は理智で聡明であるが故に人を信じることができない。また周囲も、彼が優秀であるが故に理解を示せない。故に彼は孤独に苦しみ、この負の循環から抜け出す方法を模索する。おそらく彼が最終的に行き着くのは宗教家であり、行人である。(宗教家は信じることができるため) なかなかの長編小説で中盤まではやや退屈に感じてしまったが、最後のHの手紙で怒涛の巻き返しが図られ、兄の心情が明らかにされる。 読み応えがあり、共感の多い一冊だった。
Posted by
知識人の幸せは難しいなぁ。漱石をずっと順を追って読んでるけど、男と女、古い価値観と新しい価値観といった単純な二項対立じゃなくて、行人は肉親の家族や夫婦でありながら理解できない他人の精神の作用と苦悩みたいなものが書かれていて、文学として重厚に感じる。昔の交流と他人への影響力があると...
知識人の幸せは難しいなぁ。漱石をずっと順を追って読んでるけど、男と女、古い価値観と新しい価値観といった単純な二項対立じゃなくて、行人は肉親の家族や夫婦でありながら理解できない他人の精神の作用と苦悩みたいなものが書かれていて、文学として重厚に感じる。昔の交流と他人への影響力があると思っていて、でも深くは考えられない父、現代的だけど鉢植えの木である嫂の直、気難し屋なだけでなく、碁を打つのは苦痛だが逆に碁を打たずにはいられない、漠然と苦しくもがき続ける兄、といった人間の性格と考えが本当に冷静に正確な目で書き表されている。 こういうのを読める歳になったのかなと思いました。
Posted by
1912年から1913年 朝日新聞 学問を生きがいとして、余りに理知的すぎる主人公・兄・一郎。 そんな兄を尊敬し、家族を大切にしているエセ主人公・弟・二郎。 「友人」「兄」「帰ってから」「塵労」の4章からなる。彼岸過迄の様に、短編を重ねているわけでない。兄一郎が、神経質的...
1912年から1913年 朝日新聞 学問を生きがいとして、余りに理知的すぎる主人公・兄・一郎。 そんな兄を尊敬し、家族を大切にしているエセ主人公・弟・二郎。 「友人」「兄」「帰ってから」「塵労」の4章からなる。彼岸過迄の様に、短編を重ねているわけでない。兄一郎が、神経質的な素養から、妻を、弟を、家族を疑い、疎外感と孤立感に苛まれていく。それに、悩まされる家族の葛藤。 連載半ばで、治療のため、半年程休載していたそうだ。「友人」から「塵労」へのつながりが、どうもね。時折描かれるエピソードの幾つかは面白いが、 妻を殴りさえした一郎の、追い詰められた精神と言われても、受け入れ難い。殴られた方が、痛いよねえ。平静を装って、殴られているんだよねえ。 まあ、合わない作品も、あります。
Posted by
私は、色々読んで、漱石の妻が嫌いだ。 この本を読んでいくにつれて、漱石が自分の妻と(浮気という観点ではないが)、心がちっとも通じている気がしなくて苦しかったんのかなーと同情を感じてきた。 この話は、後期三部作と言われる彼岸過迄から確かに続いている。彼岸過迄の須永と今回の行人の兄...
私は、色々読んで、漱石の妻が嫌いだ。 この本を読んでいくにつれて、漱石が自分の妻と(浮気という観点ではないが)、心がちっとも通じている気がしなくて苦しかったんのかなーと同情を感じてきた。 この話は、後期三部作と言われる彼岸過迄から確かに続いている。彼岸過迄の須永と今回の行人の兄さんが似ている。 二人とも、最も身近な存在の女性の”本当の気持ち”を求めて、袋小路に迷い込む。 しかし、1作目の須永はが悩むのは少し複雑な事情がある関係の二人の恋愛関係が軸で、それ以外の要素もあるが、細かい気持ちの描写を読むと、それは恋だねとかわいく思える部分もあった。 ところが、今回の兄さんは、気持ちの読みにくい妻への疑いを通して、家族、ひいては長年の親友に対しても疑いの心を持ってしまって、もっと重症だ。 とはいえ、気持ちは分かるので、読んでいて悲しく切なくなる。 それに、兄さんが決して、悪い人なわけではなく、ただまじめで、ものをいい加減にすませることができなくて、人間関係が不器用なだけで、程度の違いはあれ、誰にでも身につまされるところはあると思うので、より救われない気がする。 行人というタイトルの意味も調べた。勝手に、行動する人という意味かと思ったが、修行者などの意味もある単語らしい。 奥が深い。 また、引用したが、兄さんは人の心を解ろうとして、弟の僕は分かるもんかと使っている漢字が違うのも興味深い。 すでにここからして、同じわかるという認識であろうと会話しているが、実のところか分かり合えていないということを伝えているんだろうか? 兄さんの使う解るは解剖して細かいとこまでの解る、弟の分かるはあぁ、悲しいんだなーとかそういったレベルの分かるを意味しているのではないだろうかと思った。 これがさらに進行したのが、こころで。こちらへ向けて、3部作はどんどんと不幸度が増していく。 こういった心の襞を解剖して、たくさんの人生の出来事をわかりやすく例として示してくれるのが、暗くてしんどいが、読める作品として仕上がっていて、さすが文豪だと思った。
Posted by
漱石の作品を丹念に読んでいくと、教科書的文学史的知識を通り越してやはり文豪だ、天才だと実感する。100年前にこんなすごい文学を書いた天才が日本にいた、という誇りが湧いてくる。 『行人』 人間と人間の関係を、心理の奥深くに探求してやまない作者の彷徨は、苦しくも胸を打つ。 前...
漱石の作品を丹念に読んでいくと、教科書的文学史的知識を通り越してやはり文豪だ、天才だと実感する。100年前にこんなすごい文学を書いた天才が日本にいた、という誇りが湧いてくる。 『行人』 人間と人間の関係を、心理の奥深くに探求してやまない作者の彷徨は、苦しくも胸を打つ。 前半、二郎は兄一郎のストイックな性格に翻弄され、兄の家族(妻、両親、妹)まで巻き込んで起こってくる葛藤を語る。兄嫁との三角関係まで疑われ、微妙な立場になる。あげく後半、兄の友人Hにも世話をかけ、手紙で描写される兄の性格とは。 「ひとのこころはわからない」と人を信じられない。いえ、いい加減なところで妥協できない性格なのだ。 そんな性格の人はめんどくさいからほっとこう、というわけにはいかない。 誰でも本当はそこが知りたい。 人を愛しながらも人を信じられず、こころが病んでいく。近代、現代のこころの病といえるこのテーマは、古くない。
Posted by
漱石の、いわゆる「後期」作品達の中で、僕の「一番好き」な作品です。 未読の方、是非、味わってください。
Posted by