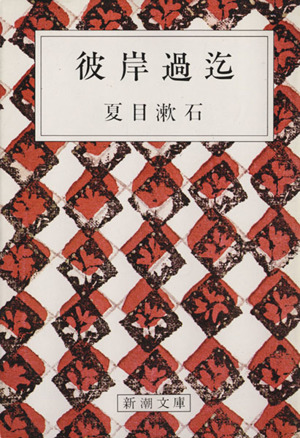彼岸過迄 の商品レビュー
バブル期のトレンディドラマのような、どうでもいい男女の空騒ぎがいつまでも続く。けれど普段から自分の仕事、事業、実績、学業などがどの様に評価されているかが気になって仕方ない現代人の小市民性と、その気もないのに千代子のことでイチイチ嫉妬する市蔵の自意識が重なる。世の中と接触する度に内...
バブル期のトレンディドラマのような、どうでもいい男女の空騒ぎがいつまでも続く。けれど普段から自分の仕事、事業、実績、学業などがどの様に評価されているかが気になって仕方ない現代人の小市民性と、その気もないのに千代子のことでイチイチ嫉妬する市蔵の自意識が重なる。世の中と接触する度に内へとぐろを捲き込み、刺激が心の奥に食い込む性質というのは鬱陶しいが、巷説の新型「うつ」だと原因を外に求めて、これっぽちも自分の責任を考えないという点で全く違うし、流石の漱石もそこまで現代の病魔が進むとは考え及ばなかったに違いない。
Posted by
なんかイマイチまとまりのなさそうな話が続いて、特に山場とかなくフワフワしたまま終わった感がある。唯一惹かれたのは市蔵と千代子の絡みだろうか。まあ、それもなんだかなあという感じでスカッとする内容ではないです。
Posted by
気づけばすっかり須永に感情移入してしまう作品でした。タイトルもちっと何とかならなかったのか(笑)と思いつつ、なんというか本人が考えてることと第三者から見た本人像ってどっかずれてたりするよなぁと思いました。敬太郎視点の話では須永とかいう高等遊民甘ったれたこと言うなよー家が裕福だから...
気づけばすっかり須永に感情移入してしまう作品でした。タイトルもちっと何とかならなかったのか(笑)と思いつつ、なんというか本人が考えてることと第三者から見た本人像ってどっかずれてたりするよなぁと思いました。敬太郎視点の話では須永とかいう高等遊民甘ったれたこと言うなよー家が裕福だから退嬰主義気取れるんだろうがって印象でしたが、須永視点に話が変わると、彼のじめじめネバネバした思考(ほんとに思うだけ思って考え尽くすけど行動には決して移さない)に虜になっていました。千代子に対する一言じゃ表白しきれない気持ち、自分でも原因がわかるような判らないような嫉妬心、多分好きなんだけど、結婚することはお互いにとっていい方向に行かないと理解しちゃってるところ、自分なんかより男らしくて爽やかな高木のほうが絶対千代子にとってお似合いだ〜でもむかつく〜みたいな心のなかで繰り返す矛盾。 個人的に一番ドキッとしたのは、須永が、松本叔父さんに自分で考えみなよと言われて泣く場面です。どうにかしたいのに誰も何も言ってくれない、そもそも自分でもどうしたらいいのか判らない、気持ちを言葉にしきれない時って感情的になってしまうよなと思いました。とにかく須永がいじらしくて……。 こころでも感じたけど、この作者が書くモノローグがとても好きです。物語に出てくる高等遊民が先生とか須永みたいなキャラクターばっかだったら私は読み漁りまくるぞ。
Posted by
本書名は著者が最初に記すように、元日から書き始めて、彼岸過迄に書き終えるぞ!という決意をそのまま書名にしたとのことで(笑)、本人いわく「実は空しい標題」であるとのこと。しかし、一方で「自然派」でも「象徴派」でも「ネオ浪漫派」でもなく、そうした色分けではなく「自分は自分である」とい...
本書名は著者が最初に記すように、元日から書き始めて、彼岸過迄に書き終えるぞ!という決意をそのまま書名にしたとのことで(笑)、本人いわく「実は空しい標題」であるとのこと。しかし、一方で「自然派」でも「象徴派」でも「ネオ浪漫派」でもなく、そうした色分けではなく「自分は自分である」という孤高宣言をした上で、明治知識人を対象とした小説を書くのだという気概も謳い上げられている。短編を紡いで長編にするという構想の下に、当時の朝日新聞に連載されたものとのこと。 最後に著者は、敬太郎という主人公に「世間」を「聴く」だけという役割を与え、彼を取り巻く人々の諸相を描いたとしているが、むしろ、前半は敬太郎が主人公そのものになって、就活中の身の上ながらも冒険心を内に秘めた性格として描かれ、隣人との関係のこと、占いをしてもらう話、知らない人の尾行を依頼されての任務経緯などお気楽な話が続きます。(笑)新聞紙上での連載ということもあって、テンポの良い1章1章の流れにのって割とスラスラ(そしてダラダラ)物語が進んでいく感じです。 しかし、後半から一転、尾行した家の娘の死の話から始まって次第に物語が重くなり、本書の後3分の1頃からは、実主人公が敬太郎の友人の須永に変わった上で、従妹の千代子との結婚問題に苦悩する心理描写が重たく描かれることになる。知識が逆に内向・深読み化する方向へ向かいがちな須永が、母と千代子との板挟みに苦しむ姿の描写は漱石ならではの展開でとても秀逸。千代子が須永へ、愛してもいない自分に何故嫉妬するのかと罵倒するシーンはボルテージ満開で最高のシーンでした。(笑)そして、須永に千代子を強いる母のプレッシャーとその想いの根源にも重圧感どっしりです。 読者をその共感に引き込む巧みな描写力でなかなかの深い感慨が残る後半と、前半のお気楽さの差には驚きました。(笑)これは2冊の本に分けても良かったのではないかな・・・。途中からの路線変更ですが、過去を語る須永の話は敬太郎とともに読者は現在をわかっているので、ある意味、安心して読めてしまいますしね。それぞれの短編物語に明確な結末がないのは、経緯そのものを読者への印象として強く残すことになっている。
Posted by
著述の主体に変化が見られる点が私にとっては非常に新鮮であった。 ある意味醒めたようにも捉えられるが、醒めているようで肉薄した感じを端々に感じられるのが作品を読んでいてわくわくしたとこであった。
Posted by
気楽に再読したものの、読み終えてみると、なんだかとんでもない連作に着手してしまったという感じ。この内容を全く覚えていなかったことも納得。 須永と松本の似て比なる性質を持った人間、興味深いけど、やっぱり須永は気の毒だなと思った。内へとぐろを巻いて巻いて昇華する術を持たないって悲劇...
気楽に再読したものの、読み終えてみると、なんだかとんでもない連作に着手してしまったという感じ。この内容を全く覚えていなかったことも納得。 須永と松本の似て比なる性質を持った人間、興味深いけど、やっぱり須永は気の毒だなと思った。内へとぐろを巻いて巻いて昇華する術を持たないって悲劇以外の何物でもないよなと。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
須永の物事を何でも、頭で考えて自らを動けなくしてしまう性質には、共感を覚えた。そして、高木の出現により、ハートよりヘッドを重んじていた須永の性質、自分のハート、心または、自我が脅かされることを凄くおそれていた。なぜ、そのような性質になってしまったのか。由来を辿っていくと、自分は不義の子だったからである。 それを知る敬太郎は、はじめはロマンティックなことを求めて自己の好奇心を満足させるために、探偵をし、外面的なことしか見抜くことが出来なかったのだけれども、須永の話、松本の話を聞くことによって、内面的な部分に触れて初めて、人の性質を理解することが出来たのであった。漱石の小説には、必ず無知な若い青年が主人公として出てきて、話を聞くうちに、内面的に成長をする段階に移行するのである。
Posted by
須永と千代子の距離感に終始やきもきさせられる小説。 でも電話の件は、素直にほほえましい。それ故に…ね。 主題を恋愛に置きながら、安い青春マンガチックに陥らないところが、 漱石先生の凄いところ。
Posted by
ようやく『彼岸過迄』を読んだ。読もうと思ってから一年以上過ぎていた。 感想を一言でまとめれば、ネガティブな単語を含むのでまとめない。 だから他の作品との比較を言えば、エンターテイナーとしての漱石の面目が光ってると思った。 笑いを主題にするなら、『猫』や『坊っちゃん』があるけども、...
ようやく『彼岸過迄』を読んだ。読もうと思ってから一年以上過ぎていた。 感想を一言でまとめれば、ネガティブな単語を含むのでまとめない。 だから他の作品との比較を言えば、エンターテイナーとしての漱石の面目が光ってると思った。 笑いを主題にするなら、『猫』や『坊っちゃん』があるけども、語りを主題にするのは本作が一番優れてる気がする。 例えば、冒頭の森本との軽妙なやり取りや敬太郎の探偵行為など、読者わ楽しませる手法が沢山使われてる。 けれども、他の作品と比較してわかるのは(というか他を先に読んで、これを最後に読んだ感想を書けば)、作品内に見えるテーマが他の作品と重複してる。また、重複してる上に他の作品以上には踏み込まれてない。 例えば、両親に対する不信から生じる実存的不安や原因不明の人間不信など。 だから、見所が特にない→駄作 という感想を持つ人が出てくるのだろうけど、それは肯定的に言えば、漱石の文学的エッセンスがつまってるとも言える。 とはいえ、柄谷行人が解説(平成二十二年改版)で言うように、これは写生文なので、普通の「小説」とは違って話の筋を一番に優先しないから、普通の読者はびっくりするか退屈に感じるだろうから、やっぱりあまりオススメはできないと思った。
Posted by
敬太郎が主人公のようで、いつの間にか須永が主人公に変わっていた。しかし敬太郎の存在が、須永や千代子らに起こった様々の出来事に一枚膜を張って、読者が傍観者の位置から奥に入り込めないようになっている。この感じは『こころ』の遺書の部分にも似ているような気がした。 須永は神経質すぎる...
敬太郎が主人公のようで、いつの間にか須永が主人公に変わっていた。しかし敬太郎の存在が、須永や千代子らに起こった様々の出来事に一枚膜を張って、読者が傍観者の位置から奥に入り込めないようになっている。この感じは『こころ』の遺書の部分にも似ているような気がした。 須永は神経質すぎるとは思うけど、気持ちは分からなくもないな、と思う。 「写生文」という言葉が解説にあったが、作者から何の解釈も与えずにただあるものをあるがままに書いたような文章だ。私はそこが好きだ。作中には漱石の実体験に基づいている部分も多く、特に松本の幼い娘の死にまつわる描写は凄まじくリアルでぞっとする。 以下余談 こないだツイッターで、「文学研究は出版社の都合とか表現上の規制とか締切とか、そういうものは全く斟酌されていなくて、作家は自分の書きたいように書いたという前提でなされているということを知った」的なRTを見たんだけど、「そんなことないよ、漱石の連載小説はよく『さっさと終わらせろ』と朝日新聞から言われてみたいだし……」と思っていた。そんなときにこの本を読んでいた。 『彼岸過迄』は、まさにそんな感じで、どこかから「さっさと連載終わらせろ」という圧力がかかったとしか思われないような、煮え切らない終わり方をしている。そんな圧力のために、やむなく駆け足でまとめざるを得なかったのではないだろうか。 だとすると、ここに文学のジレンマを見ることもできるかもしれない。たくさんの人に面白く読まれることは必須条件だけど、読まれるためには出版社の意向等諸々の都合に合わせなければならず、自らの価値を貶めることさえある、という意味で。 ただ、何の制限もなく自由に書けるということが、文学作品において、私はさほど重要だと思っていない。それは漱石の言葉を引用すると「小説は建築家の図面と違って、いくら下手でも活動と発展を含まない訳に行かないので、たとい自分が作るとは云いながら、自分の計画通りに進行しかねる場合がよく起って来る」からで、つまり作者が自由に小説を書くと言っても、自力では如何ともしがたい謎めいた力がそこに働いているように思うのだ。
Posted by