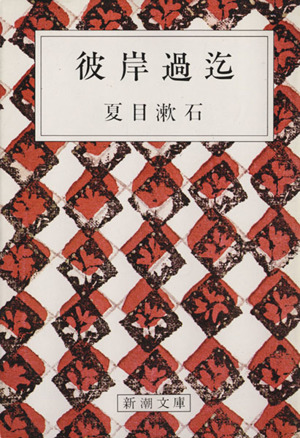彼岸過迄 の商品レビュー
語り手が変わっていく独特のスタイル。 語り手であり聞き手にもまわる主人公がいますが、ストーリーやテーマの中心になるのは、その友人だと思います。 夏目漱石好きなだなあ、と私が感じるポイントが存分に表れています。人間の内面が本当によく描かれています。そしてそのいちいちに、そういう気...
語り手が変わっていく独特のスタイル。 語り手であり聞き手にもまわる主人公がいますが、ストーリーやテーマの中心になるのは、その友人だと思います。 夏目漱石好きなだなあ、と私が感じるポイントが存分に表れています。人間の内面が本当によく描かれています。そしてそのいちいちに、そういう気持ちわかるよ、と言ってしまいそうになるのです。 この時代は美しい。 個人の内面が、他者あるいは世間にいまほど影響されることはなかったでしょう。それだからこそ、内面を変容させることは困難で、彼らのように自分でどうにかするしかなかった。そこに苦しさと美しさがあるように、私には思えました。
Posted by
彼岸って言っても今どきいつ頃のことだか良く分からんし、むしろ島なのか?丸太は持ったのか?って感じになるし、彼岸島迄?って思う人もいるしいないしで、まぁでも吸血鬼は出てこない平和な話だった。 でもっていつもの昔の文学に出てくる、ぶつぶつと面倒くさい事ばっかり言って何もしないニートが...
彼岸って言っても今どきいつ頃のことだか良く分からんし、むしろ島なのか?丸太は持ったのか?って感じになるし、彼岸島迄?って思う人もいるしいないしで、まぁでも吸血鬼は出てこない平和な話だった。 でもっていつもの昔の文学に出てくる、ぶつぶつと面倒くさい事ばっかり言って何もしないニートがぶつぶつ言ってるわけなんだけども、そんなぶつぶつ言ってるだけなのに、女の子がしっかりついてくるという、またこれか!って言わずにはいられない展開。そしてその展開がどうなったのか分からないまま終わってしまうという、このモヤモヤをどうしてくれようか。 あと鎌倉在住者として、鎌倉近辺がめっさ田舎というか、スラム漁師村的に語られてたのがなかなか良かった。調子に乗ってる住民に是非とも読ませるべき書ではないか。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
印象に残っているのは宵子の死の場面。漂う線香の煙が見えるようだった。骨を拾う時の、もうこれは人じゃないという感じがリアルで、市蔵の言葉があまりに冷淡で少し気になる。 読み進めていくうちに市蔵に対するイメージが変わり、次第に共感を覚えるようになっていった。空虚な努力に疲れていた、という一文が刺さった。
Posted by
高校生の頃に読んだ。終いまで鉛筆で手書きのルビがふってあった。でも内容が全然頭に残っていない。今読み返すと、須永が千代子に対して抱く嫉妬も含めた思いと、行動には移せない態度が我がことのように感じられた。宵子の亡くなる場面を描いた場面は、漱石の実体験を基にしたものだけに切なさが伝わ...
高校生の頃に読んだ。終いまで鉛筆で手書きのルビがふってあった。でも内容が全然頭に残っていない。今読み返すと、須永が千代子に対して抱く嫉妬も含めた思いと、行動には移せない態度が我がことのように感じられた。宵子の亡くなる場面を描いた場面は、漱石の実体験を基にしたものだけに切なさが伝わってくる。序盤の敬太郎のエピソード、須永の長い独り語り、松本の締めくくりの話というのは、推理小説の謎解きのようで構成そのものを楽しめた。
Posted by
2017年33冊目。 夏目漱石の作品を読むのは、小さい頃に「こころ」を読んで以来。 内容はほとんど覚えていないけど、割と悪戦苦闘しながら読んでいた記憶がある。 ので、この作品をこんなにストレスなく読めるとは思っていなかった。 深刻になり過ぎず、それでいて退屈もなく、全体的な重さ...
2017年33冊目。 夏目漱石の作品を読むのは、小さい頃に「こころ」を読んで以来。 内容はほとんど覚えていないけど、割と悪戦苦闘しながら読んでいた記憶がある。 ので、この作品をこんなにストレスなく読めるとは思っていなかった。 深刻になり過ぎず、それでいて退屈もなく、全体的な重さが自分にはちょうどよかった。 啓太郎の観察眼に唸ったが、それを描いた作者のそれはもっとすごいと思う。 好奇心は人一倍強いくせに、その対象に付き合った先々を皮算用すると恐れをなしてしまう性格が、自分とよく重なって笑ってしまった。 前書きも秀逸。
Posted by
敬太郎という大学を出たばかりの男が主人公。敬太郎の目線から様々な周りの人々の様子が描かれている。「恐れない女と恐れる男」の解釈が自分には難しい… タイトルの『彼岸過迄』は元旦から彼岸過迄書く予定だからこのタイトルにしたっていうのははじめて知った。大ざっぱだなぁ…
Posted by
漱石が巻頭で述べているように、短編を繋げた連作のようなものなので統一感が今一つの長編。題名も正月から開始してお彼岸の頃までの新聞連載という意味。中盤の探偵小説風の尾行話は面白いが他は印象が薄い。
Posted by
読書のやる気が起きずにこれで相当の時間を費やしてしまった。 敬太郎を取り巻く人々の話が伝聞形式で進んでいく、一種のオムニバス形式のような小説。 気だるい空気がひたすら続く。 個人的には前期三部作の方が好きやなあ。 引き続き行人も読みたいけど、しんどかったのでちょっと休憩。
Posted by
読み終わって、こういう流れなのね…ってびっくり。 最初は敬太郎を主軸に回るお話かなと思ってのですが、なるほどなあ…と。 相変わらず通勤中に少しずつ読んでたのですが、面白かったです。一気に読んだ方が良かったかな。 漱石の書く女性って瑞々しく生々しいですよね。なんともいえない魅力が...
読み終わって、こういう流れなのね…ってびっくり。 最初は敬太郎を主軸に回るお話かなと思ってのですが、なるほどなあ…と。 相変わらず通勤中に少しずつ読んでたのですが、面白かったです。一気に読んだ方が良かったかな。 漱石の書く女性って瑞々しく生々しいですよね。なんともいえない魅力があります。
Posted by
あらすじに出てくる登場人物がぜんぜん登場しないし、話に脈絡がなく、この場面になぜこんなに頁を割くのか、など色々思いましたが、聞き手としての敬太郎の人物造形と須永の自己心情に対する詳細すぎる分析、二人の性格の対比が面白かったです。私は敬太郎が主役だと思っています。漱石の表題作の要素...
あらすじに出てくる登場人物がぜんぜん登場しないし、話に脈絡がなく、この場面になぜこんなに頁を割くのか、など色々思いましたが、聞き手としての敬太郎の人物造形と須永の自己心情に対する詳細すぎる分析、二人の性格の対比が面白かったです。私は敬太郎が主役だと思っています。漱石の表題作の要素が全て散りばめられたような作品です。 やっぱり、心情を考えすぎだろうというくらいだらだらと語る話は面白い。
Posted by