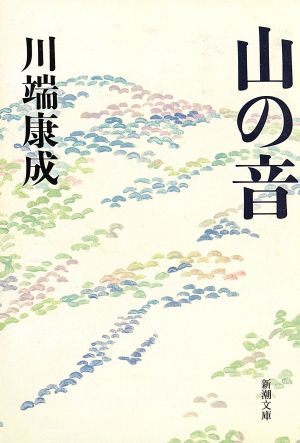山の音 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
一昔前の日本を舞台にしている小説である。 90年代生まれの私としては、女性を軽視している!と思える描写に反応してしまう。 しかし、本書の本質はそんなところではないので、読み流した。 ウィキペディアによれば、本書は下記のことが特徴のようだ。 “繊細冷静に捕えられた複雑な諸相の中、敗戦の傷跡が色濃く残る時代を背景に〈日本古来の悲しみ〉〈あはれな日本の美しさ〉が表現されている。” 〈日本古来の悲しみ〉とはなんだろうか。 読了して、ずいぶんと時間が経っているからかもしれないが、まったく思い当たらない。 また、ウィキペディアからの引用となるが、このように評価されている。 “日本の敗戦とそれに続く戦後とが、日本の「家庭」に何をもたらしたかを表現している作品として文壇で高評価を得た。” そう言われてみれば、なんとなく分かるような場面も思い起こされるが、はっきりと「ここ」とは言えない。 私の読解能力の低さが露呈してしまったが、本書は場所を指定して「ここに何が表現されている」と言うよりも、全体を通しての表現を感じるもののような気がする。 本来、本とはそういうものだろうか? 最近読んでいた本は、どちらかというと、「ここに何が表現されている」という本であったので、本書は新鮮だった。 日本文学を読むと寝てしまいがちな私にとって、眠らずに読了できたことも、本書の魅力である。 ※駄文すぎるレビューで申し訳ありません・・・
Posted by
戦後の一般的な家庭を描いている。ただそこに描かれている中で心地よい関係を築いているのは舅の信吾とと息子の嫁の菊子だけだった。信吾は若いころ、妻の姉にあこがれを抱いていた。娘の房子は二人の子供を連れて離婚して出戻ってきた。息子の修一は菊子がいながら戦争未亡人の絹子と不倫をし、子供ま...
戦後の一般的な家庭を描いている。ただそこに描かれている中で心地よい関係を築いているのは舅の信吾とと息子の嫁の菊子だけだった。信吾は若いころ、妻の姉にあこがれを抱いていた。娘の房子は二人の子供を連れて離婚して出戻ってきた。息子の修一は菊子がいながら戦争未亡人の絹子と不倫をし、子供まで作った。信吾は菊子の可愛さに、菊子は信吾の優しさに癒されていた。 家族とは何なのかと考えさせられる作品だった。
Posted by
その他の著作と同様に淡々と進みこれがどうなるんだろう…と、ながらダラダラ読みしていたらしっぺ返しをくらう。夢のくだりやお面のくだりが印象的。
Posted by
初めての川端康成。老いと男女がテーマであるが、燃え上がるようなものではなくて、主人公の老いを描写しながら、それを取り巻く環境と関係の中で男女を描く。人生をきりもみしながら進む中で、灰汁のように浮かび縁にたまった感情を救い上げたような、とってもセンシティブな小説。淡々と進む、主人公...
初めての川端康成。老いと男女がテーマであるが、燃え上がるようなものではなくて、主人公の老いを描写しながら、それを取り巻く環境と関係の中で男女を描く。人生をきりもみしながら進む中で、灰汁のように浮かび縁にたまった感情を救い上げたような、とってもセンシティブな小説。淡々と進む、主人公の感情を中心とした物語の展開だが、山も谷もない。しかし人間そのものをよく描いている傑作であると思う。山の音とはいったい何だったんだろうか。老いとほのかな恋慕の間のギャップがある。それはかすかな低音を響かせる大きな穴のようだ。だが目立ちはしない、自身の事情でありながらも自身でも気づかぬほどに目立たない。山の音は虚しさをたたえている。焦りをたたえている。 主人公はよく夢を見る。老いの現れであろうか。ネクタイの結び方を忘れた、いろいろして思い出した、というところだけ恣意的なものを感じ、違和感があった。それ以外は素晴らしかった。 14/12/30
Posted by
2014.12.28 読了 戦後の中流家庭の内情を描いた物語。内容、文章、言葉のひとつひとつから時代を感じると共に登場人物の感情や背景を繊細に表現されている事に感動した。
Posted by
川端康成の作品の中で特に一番大好きな話。 信吾の菊子への感情については、色恋の印象無しで読んだ。 舅から嫁への愛情、泣ける。
Posted by
死、老いを意識させる山の音を聴くように静かに話が流れていく。「夫婦というものは、おたがいの悪行を果てしなく吸い込んでしまう不気味な沼のようでもある」が印象に残った。
Posted by
戦後日本の鎌倉を背景に、息子夫婦と同居する老紳士の家で次々と巻き起こる家族の問題。しみじみとした会話と物語進行だったのに加え、鎌倉の自然とともに生きる穏やかな性格の夫であり父であり舅である主人公の信吾と嫁の菊子の心の交流を主軸に描いているものと思いきや、豈図らんや、次第に昼ドラや...
戦後日本の鎌倉を背景に、息子夫婦と同居する老紳士の家で次々と巻き起こる家族の問題。しみじみとした会話と物語進行だったのに加え、鎌倉の自然とともに生きる穏やかな性格の夫であり父であり舅である主人公の信吾と嫁の菊子の心の交流を主軸に描いているものと思いきや、豈図らんや、次第に昼ドラや渡鬼顔負けのドロドロ愛憎劇の様相を呈してきて、展開が気になり一気に読み進めてしまった。(笑)いや、舅と嫁の交流が主軸なのは間違いないんですけどね。 死というものを感じるようになった老境の主人公の、未だ幼い嫁に「女」を感じる眼差しと、かつて自分が恋した妻の亡き美人姉への忘れ難い想いが、老紳士の哀愁を引き立てている。だが、「老人」と「少女」という川端ならではの対比と相関がそこはかとないシンボリックな描写に止まり、逆に想いだけを胸に秘めた旧き家長像を設定することで、ドロドロとした物語展開にもかかわらず、読者へ安心感を与えているようにも思える。物語は次第に不倫、DV、離婚、エトセトラと重たい話になっていくのだが、主人公の女性に対する抑制とほんわかな老紳士ぶりをみていると、どの重たい出来事も優しく包まれているような感じになってくるので不思議だ。シンボリックといえば、主人公がみる夢の話が随所にみられるが、これも抑制した主人公の心理状態や予兆をうまく物語の表面へ浮き上がらせる話のタネとして面白い手法であった。 この物語で登場する主要男性は実は主人公の信吾と息子の修一のみで、その周りを彩る女性が多いのも特徴だ。信吾の妻・保子、修一の妻・菊子にはじまり、信吾の娘・房子、その子どもの里子と国子、信吾の秘書・英子、修一の不倫相手・絹子などなどで、それぞれの個性が対極な相手によって対比させられているのも設定の妙である。何気ない女性らしさの描写をみるにつけ、細やかな観察眼には敬服するとともに、やはり川端先生、女好きなんですね。(笑) 会話は考え抜かれて選ばれたであろう言葉が多くみられ、たおやかな表現が心地よいのだが、自分には意味が捉えずらい会話も少なからずあり、途中で何度か会話の前後を読み返してしまった。(笑)しかし、それだけに心理と感情のあやが繊細に伝わってくるので、この物語全般に流れる穏やかな関係性を一層印象付けているといえる。 あと余計な話だが、やはりこの物語の展開自体はかなりのドロドロ劇であるので、昼ドラになってもかなり面白いのではないかな。(笑)
Posted by
雪国と同じように、短編からなる。 短い部分を書き継いでいくスタイルのせいか、19世紀ヨーロッパ小説の流れをくむものというか「世界小説」というかとは、かなり違うように感じる。 舞台は刊行年の1954年よりは古いようで、主人公の息子は戦争体験があり、冷蔵庫、電気掃除機あたりも普及し...
雪国と同じように、短編からなる。 短い部分を書き継いでいくスタイルのせいか、19世紀ヨーロッパ小説の流れをくむものというか「世界小説」というかとは、かなり違うように感じる。 舞台は刊行年の1954年よりは古いようで、主人公の息子は戦争体験があり、冷蔵庫、電気掃除機あたりも普及しきっていない。 主人公一家の経済状況も良くわからない。横須賀線で鎌倉から東京に通っているようでそこまで裕福ではないようだけれど、別な登場人物からは身分が上のように言われている。 戦前の日本から高度成長を迎える前の、変わっていく日本を予感させるような雰囲気がある。主人公や菊子の自然や文化への感受性も何処か懐かしいものがある。 うまくいっていない子供夫婦×2、自身や友人の老い、若くして死んでしまった美しかった妻の姉への未練など、全体的に陰鬱な空気だが、主人公と菊子の交流は微かに暖かいものを感じさせる。
Posted by
どの登場人物に対してもイライラして、なんでそうなのよもっとちゃんと生きなさいよ、と思ってしまうのに最後まできちんと読んでしまった。 とにかくイライラするので面白いという表現はしっくりこないけど、やっぱり引き込まれる。
Posted by