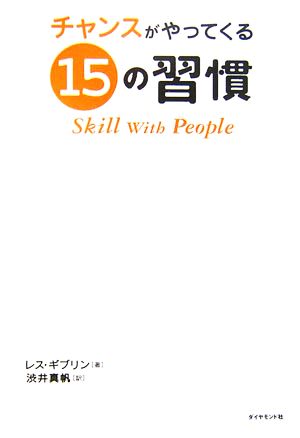チャンスがやってくる15の習慣 の商品レビュー
-短いから一気に読めます.わかりやすいです. -書いてあることは”至極当然”なのですが,それがなかなか難しいからこういう本が出てるんでしょうね. -忘れた頃に読み返すのが良いかと. 【15の法則】 ・人間は自分にしか興味がない、と知っておく ・相手のことだけ話題にする ・認めら...
-短いから一気に読めます.わかりやすいです. -書いてあることは”至極当然”なのですが,それがなかなか難しいからこういう本が出てるんでしょうね. -忘れた頃に読み返すのが良いかと. 【15の法則】 ・人間は自分にしか興味がない、と知っておく ・相手のことだけ話題にする ・認められている、と相手に感じさせる ・とにかく、同意する ・聞き役に徹する ・相手の求めているものを見つける ・あなたの意見は「ある人の意見」として語る ・「ノー」とは言わせない状況にする ・会った瞬間に笑顔を向ける ・1日に3人、ほめ言葉をかける ・相手のミスに、怒りで反応しない ・「ありがとう」と、声に出す ・自分には価値がある、と信じる ・5つのルールを守って話す ・この習慣を実践する -「おれがおれが」ではなく相手のことを考えること. --それは「優しくする」というのとは違って「相手の思考をhackしてactionする」ってことなのかな? ---それが後々自分のためになる。。。ってことか。。。? 【実践】 -普段の会話において”私”から始まる発言を”あなた(○○さん)”に置き換えた場合を考えてみる. -普段の会話において”聞く”というスタイルに重点を置く. --その中で5W1Hを意識する. --途中で割り込みたくなっても堪え,相手の話にひと段落がつくまでは頭の中で話の整理をする. ---応答はまず”確認(つまり○○ってことだよね?)”をして,その後に”発言”する. -目を見て微笑む. --特に初めて会う人などはfirst impressionがその後を大きく左右する. --一瞬で,爽やかに,さりげなく. -相手の良いところを常に意識する. --見つけたらその点について具体的に褒める,しかしあくまで軽く. ---感謝すべきことであったならば,素直にその意を述べる,具体的に. -相手の悪いところは見えても外に出さない. --それでも注意すべきところは,公然とするのではなく,相手を傷つけないレベルで行う. -自信を持つ. --謙遜と卑下は違う. 【注意】 -”ヨイショすればよいのではない”ということを忘れずに. -”ただ聞く”だけでなく”相手を良く把握するために聞く”のであり,そこから”より有意義な会話を生む”ことが大事.
Posted by
◆著者はコミニュケーション・スキルを教える専門家で、クライアントは、GE、メリルリンチ、アムウェイ、モービルなど。書いてある内容は、シンプルで的を射たものばかり。コミュニケーションの教科書。 ◇人間は何を考えているかではなく、どう行動したかでしか判断してもらえない ◇あなたの...
◆著者はコミニュケーション・スキルを教える専門家で、クライアントは、GE、メリルリンチ、アムウェイ、モービルなど。書いてある内容は、シンプルで的を射たものばかり。コミュニケーションの教科書。 ◇人間は何を考えているかではなく、どう行動したかでしか判断してもらえない ◇あなたの印象は最終的には、あなた自身が決めるのではなく、相手が決める ◇15の習慣 1.人間は自分にしか、興味がないと知っておく 2.相手のことだけを話題にする 3.認められていると、相手に感じさせる 4.とにかく、同意する 5.聞き役に徹する 6.相手の求めているものを見つける 7.あなたの意見は「ある人の意見」として語る 8.「ノー」とは言わせない状況にする 9.会った瞬間に笑顔を向ける 10.1日に3人、ほめ言葉をかける 11.相手のミスに、怒りで反応しない 12.「ありがとう」と、声に出す 13.自分には価値がある、と信じる 14.5つのルールを守って話す 15.この習慣を実践する
Posted by
アメリカのトップセールスたちに読み継がれている本らしい。 「Skill With People」という原題がなぜ「チャンスがやってくる15の習慣」になってしまったのかは謎。 非常に薄い本で、しかも字数も少ないレイアウト。 1時間もあれば読めてしまう。 この本の根底にあるのは「...
アメリカのトップセールスたちに読み継がれている本らしい。 「Skill With People」という原題がなぜ「チャンスがやってくる15の習慣」になってしまったのかは謎。 非常に薄い本で、しかも字数も少ないレイアウト。 1時間もあれば読めてしまう。 この本の根底にあるのは「人は自分のことにしか興味がない」ということだけ。 だから、相手の話を聴き、自分の話を聞いて欲しいときこそ相手の話に耳を傾け、相手のことを褒め、自分が話すときは短めに、と。 すべては「人は自分のことにしか興味がない」から。 それにしてもなんで「直訳風」の翻訳なんだろう。 演出? アメリカっぽさを出すため?
Posted by
当たり前のことだけど、やれていない。でもやることでコミュニケーションがうまくいき、成功に結びつくという内容。 この本を出版するにあたってのきっかけが面白い。それをかいてある前書きも面白い。
Posted by
多少なり 聞きの心得があり 一読の後 既知のことだと 思っていました やれていると思っていたけれど 人との会話 本を片手に 思い出してみると できていないこと その事の大きさを感じました 聞き上手 への一歩として 外せない感じです。
Posted by
「1.人間は自分にしか興味がない、と知っておく」ということは、 今後さらに意識していきたいものだ。
Posted by
特にセールスの方には、得るものが多そう。人間関係、中でも人との会話における良き習慣が書かれています。
Posted by
080205 30分くらいで読めます。ビジネスで相手を動かしたいときのコミュニケーションのコツが書かれています。著者はこのコツが仕事でもプライベートでも応用できると言ってますが、私やったら友達がこんなこと考えながら喋ってたら怖いなぁと思いました。社会人になる前に参考程度に読むくら...
080205 30分くらいで読めます。ビジネスで相手を動かしたいときのコミュニケーションのコツが書かれています。著者はこのコツが仕事でもプライベートでも応用できると言ってますが、私やったら友達がこんなこと考えながら喋ってたら怖いなぁと思いました。社会人になる前に参考程度に読むくらいなら、シンプルでわかりやすいとは思います。
Posted by
『この15の習慣は、とても小さな習慣ですが、あなたの生活をよりよくし、より多くの友人を得、成功と幸福を呼びこむ鍵です。しかし、覚えただけでは価値はありません。くれぐれも実践です。』『人間は自分にしか興味がない、と知っておく』『相手のことだけ話題にする』『同意する習慣がみにつくよう...
『この15の習慣は、とても小さな習慣ですが、あなたの生活をよりよくし、より多くの友人を得、成功と幸福を呼びこむ鍵です。しかし、覚えただけでは価値はありません。くれぐれも実践です。』『人間は自分にしか興味がない、と知っておく』『相手のことだけ話題にする』『同意する習慣がみにつくよう努力する』『聞き役に徹する』『会った瞬間に笑顔を向ける』『1日に3人、ほめ言葉をかける』『感謝する訓練をする』『人や物を悪く言わない』『言いたいことを言い終わったら、すぐに終わる』『聞き手が聞きたがっていることを話す』『この習慣を実践する』 Oh! No!自分のこと話すの大好きな私にとって、なんとムズカシイことでしょう!!!でも、ココロから納得できます☆
Posted by
兎に角実践が大事、人間は自分中心に行動する、「私」という言葉を削除し「あなた」という言葉を使ってみる、人と話す時は「相手のことを話題にする」「相手に話してもらう」、よい人間関係を築くには「あなたがその人の価値を認めている」と相手に知らせることが肝心、人とうまく接するには相手に同意...
兎に角実践が大事、人間は自分中心に行動する、「私」という言葉を削除し「あなた」という言葉を使ってみる、人と話す時は「相手のことを話題にする」「相手に話してもらう」、よい人間関係を築くには「あなたがその人の価値を認めている」と相手に知らせることが肝心、人とうまく接するには相手に同意すること、自分の話をちゃんと聞く人に好感を持つもの、相手が何を求め何を好きかを見つけ出す、求めているものを手に入れるためにはあなたがやって欲しい事をそればいいのだと相手に示す、他人の言葉として聞くと疑いを持たない(ある人の意見として語る)、イエスとしか答えられない質問をしイエスと答える雰囲気を作る→相手の有利に働き相手に利益がある理由が必要、どちらの答えもイエスとなる質問をする、会った瞬間に笑顔を向ける→最初の数秒でその後の雰囲気が決まる・相手の態度を見てそれと同じ行動をする傾向、褒め言葉は出し惜しみしない(1日3人)、ミスを指摘して納得させる7つのルール−誰もいない場所・指摘前に労いの言葉を・行動を批判・解決策を示す・命令ではなく協力を求める・1回のミスに批判は1度まで・なごやかな雰囲気でしめる、ありがとうと言葉にだす、自分がどういう人間でどんな事をしているかに自信を持つ(自惚れは×)、人や物を悪く言わない、5つのルールを守って話す−話す内容をきちんと知っておく・言い終わったらすぐ終わる・顔を見ながら話す・聞きたがっている事を話す・普通に話す(演説×)、この習慣を実践する
Posted by