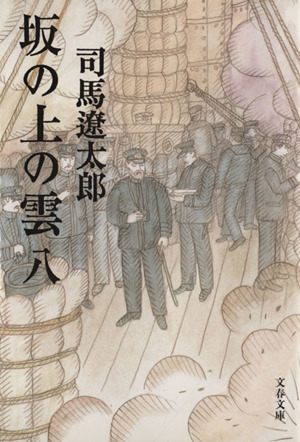坂の上の雲 新装版(八) の商品レビュー
完結巻。嗚呼、長かった物語もこれで終わりか。戦争の終結に至る過程はなんとも言えぬ思いで読んだ——ロジェストヴェンスキーが主将だったから露は負けたのだ。他の軍人だったならここまでの大敗はしなかっただろう。本当にどうしようもないヤツだ…。何があそこまでの強者を演出していたのか、不思議...
完結巻。嗚呼、長かった物語もこれで終わりか。戦争の終結に至る過程はなんとも言えぬ思いで読んだ——ロジェストヴェンスキーが主将だったから露は負けたのだ。他の軍人だったならここまでの大敗はしなかっただろう。本当にどうしようもないヤツだ…。何があそこまでの強者を演出していたのか、不思議なくらいだ。 ・・で、反対に日本のトップこと東郷であるが、故・野村克也みたいなひとだなぁ、と。 秋山兄弟を通して、日露戦争…いや"戦争"の何たるかをよーく学べた気がします。 (※後に、この快勝が太平洋戦争へと駆り立て、敗北へと導く原因のひとつなのですね…。) 愛媛旅行がきっかけで、ほぼ一年くらい掛けましたが、読んで良かったなぁと心から思いました。星三つ半。
Posted by
5巻を読んでいる頃、根岸にある子規庵を訪ねました。小さな日本家屋と季節の草花が植る庭から、子規の創作活動と家族3人での暮らしが想像できます。 日本海海戦から帰った真之は、この子規のいなくなった家を訪ねます。しかし、家の前まで行っても、戸を叩き、子規の母と妹に会うことはありませんで...
5巻を読んでいる頃、根岸にある子規庵を訪ねました。小さな日本家屋と季節の草花が植る庭から、子規の創作活動と家族3人での暮らしが想像できます。 日本海海戦から帰った真之は、この子規のいなくなった家を訪ねます。しかし、家の前まで行っても、戸を叩き、子規の母と妹に会うことはありませんでした。 真之は子規の家の前で何を思ったのでしょう。あの静かな路地にある真之の後ろ姿を想像すると、なんだかとても切ない気持ちになりました。
Posted by
クライマックスが一番スピード感あって面白かったから7巻は数ヶ月かかったのに最終巻は2週間半で読み終えました!とはいえ本編だけなので残すところ50ページ近くあるあとがき集を読み切ろうと思います。あとがきは筆者の考えなど当時の事情に寄り添っていたので考察の参考になりそう。
Posted by
ロジェストウェンスキーはなかなか考えさせられた。指揮することをまともに考えていない指揮官は戦いにおいている意味のない人に成り下がっている。けれど、皇帝の専制で戦争が行われているという意味ではこの指揮官も気の毒な被害者だとも言える。それらをひっくるめて?戦いあった同士?として敵国軍...
ロジェストウェンスキーはなかなか考えさせられた。指揮することをまともに考えていない指揮官は戦いにおいている意味のない人に成り下がっている。けれど、皇帝の専制で戦争が行われているという意味ではこの指揮官も気の毒な被害者だとも言える。それらをひっくるめて?戦いあった同士?として敵国軍人に敬意を払う日本の軍人の姿は(いいことなのかそうでないのかわからないけど)なかなかかっこいいと思ってしまった。 またその一方で、勝って嬉しいわけではまったくなく多くの殺戮に苦悩し始めた真之の様子も印象深い。 戦争がもたらす苦悩とか虚しさを感じた。 全体を通して、維新でリセットされた日本社会とか、初めて国民とか国家を意識し始めた日本や世界とか、国民主権と専制君主の組織の力の強さの違いとか、いろいろ雰囲気を知ることができて有意義だった。 恐らく多分に司馬さんの好みや主観的な解釈が盛り込まれていると思われるが、一つの歴史の解釈を物語として追体験できた。
Posted by
坂の上の雲の最終巻。 完全勝利と言って良いバルチック艦隊との戦いを描く。 しかし、その勝利は日本軍の強さのみではなく、突き詰めるとロシアの政体自体の問題でさえあった。 これらをわかりやすく、かつスピーディーに描き切っており、読了後の満腹感がすごい。 なぜか勝利したものの、手...
坂の上の雲の最終巻。 完全勝利と言って良いバルチック艦隊との戦いを描く。 しかし、その勝利は日本軍の強さのみではなく、突き詰めるとロシアの政体自体の問題でさえあった。 これらをわかりやすく、かつスピーディーに描き切っており、読了後の満腹感がすごい。 なぜか勝利したものの、手放しに喜べない戦争の切なさも感じた。 歴史好きの方にはぜひ読んでいただきたい一冊。
Posted by
第1巻から一気読み。面白いは面白いけど、理屈っぽいのと、漢字仮名の選択が今どきと違うので読みにくいのが難点。頭でっかちだったり視野狭窄になると、ろくなことにならないなぁ...とは分かっているけど、果たして当事者だったらどう振る舞えるだろうか。後世の学士さんたちが研究・解釈して、著...
第1巻から一気読み。面白いは面白いけど、理屈っぽいのと、漢字仮名の選択が今どきと違うので読みにくいのが難点。頭でっかちだったり視野狭窄になると、ろくなことにならないなぁ...とは分かっているけど、果たして当事者だったらどう振る舞えるだろうか。後世の学士さんたちが研究・解釈して、著者が小説という形に整えたから俯瞰できるけど、実際のところ天才のようには振る舞えないんだろうなぁ。
Posted by
▼エンタメと考えれば、この小説は(日露戦争は)いろいろあっても最後が日本海海戦で圧勝して終わるので、溜飲が下げられて素晴らしい。その、苦しい辛い中で最後スッキリというヤクザ映画的な語り口がこれまた上手い。海戦でも、まずは三笠が被弾しまくる描写も延々とやる。その次にロシア側の(日本...
▼エンタメと考えれば、この小説は(日露戦争は)いろいろあっても最後が日本海海戦で圧勝して終わるので、溜飲が下げられて素晴らしい。その、苦しい辛い中で最後スッキリというヤクザ映画的な語り口がこれまた上手い。海戦でも、まずは三笠が被弾しまくる描写も延々とやる。その次にロシア側の(日本軍と比べ物にならない)被弾を描く。そういう順番構成とか。上手い。 ▼一つ勘違いしていたことがあって。ポーツマスの和平のあとで、日比谷焼き討ち事件がある。つまり民衆が「より戦争を、戦果を」と暴動を起こした。その戦慄の描写があって。そして、日本海海戦の完勝、その成果であるポーツマス条約。だがその中から昭和の戦争と完敗に向けた胎動が始まっている…というドロドロした思いが湧き上がって終わる。・・・と思っていたら、間違っていて、全然その描写は無かった。恐らく、同じ司馬遼太郎さんの「明治という国家」か、「昭和という国家」か、あるいは吉村昭さんの「ポーツマスの旗」か、どれかと記憶が混同していました。 ▼今、個人的な興味関心で、「第一次世界大戦とは」というテーマに向けた読書の旅を続けていて、実は「明治日本と帝国主義先行国家とのせめぎあい」を畫いた坂の上の雲は、このテーマの流れとしてもとても良かった。
Posted by
日露戦争は日本の勝利と知っていたが、この本を読む事によって多くの両国の犠牲があった上でのことだと再認識させられる。 最後の章の、真之が子規庵に行った場面は海上での戦いとのコントラストを強く感じた。他愛ない日常も、戦争のもとでの日々も同じ人間の生活の一部なんだと思った。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
いよいよクライマックスで、この巻を読むためにここまで来たのだと思う。 日本海海戦がここまで圧勝とは知らなかったので、清々しさも感じた。 終わり方があっさりしているのは、この本についてはそれが良いと思った。それにしても超大作だった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「すでに述べた」を何度読んだことか。 数えながら読めばよかった。 なかなか辿りつかないバルチック艦隊がやっと来たと思ったら、こんな戦闘だったのか。 やっと終わった。
Posted by