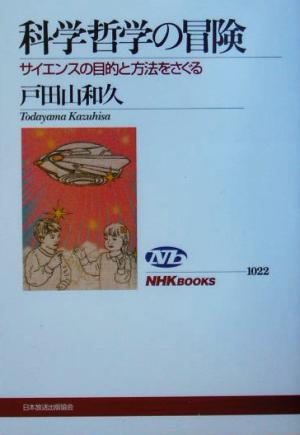科学哲学の冒険 の商品レビュー
■細目次 https://gyazo.com/487aa8e45c028a561617052d9c08cd89 https://gyazo.com/0913b40013014c722959538c69f3ebe4
Posted by
私には非常に難解でした。 文系だからって言い訳するつもりもないです、理解できないから低評価っていうのも良くないですが… 帰納と演繹の部分だけかろうじて理解できました。 私達は日常の中でも無意識に帰納と演繹を使ってるんですね。
Posted by
科学哲学の入門書。科学哲学を専門にしている大学教師の「センセイ」と二人の学生(つまりリケジョのリカさんと現代思想オタクのテツオくん)の三人による対話形式。まず科学哲学の歴史から入り、現在でも未だ解決していない科学哲学の難問に対する「センセイ」=筆者の解答が示される。 一口に「...
科学哲学の入門書。科学哲学を専門にしている大学教師の「センセイ」と二人の学生(つまりリケジョのリカさんと現代思想オタクのテツオくん)の三人による対話形式。まず科学哲学の歴史から入り、現在でも未だ解決していない科学哲学の難問に対する「センセイ」=筆者の解答が示される。 一口に「科学」とは言っても、その捉え方は様々である。本書を読むと、自分が如何に色々な立場の考えをごちゃ混ぜにしていたかを突きつけられる。直観的には、科学の対象には確かに実体があって科学はその姿を少しずつ明らかにしていく営みだと思っているのだが(科学的実在論)、中途半端な聞きかじりの社会科学の知識も持っているので科学は結局科学者の間の社会的合意に過ぎないという主張も分かるし(社会構成主義)、科学理論が世界についての真理を語っているとは限らないという考えも理解できる(反実在論)。例えば、量子力学には正準量子化という重要な手法があるのだが、この手法が何故上手くいくのかは、少なくとも今は、経験上上手くいっているからとしか説明しようがない(清水『量子論の基礎』)。こういうことを知ると、最も直観的に思われた科学的実在論は俄かに怪しく思われ、現象をうまく説明できさえすればそれで良いという反実在論になってしまう。筆者は科学的実在論を擁護する立場に立っており、彼の、社会構成主義や反実在論といった他の陣営からの批判に耐え得るような理論の構築の試みを、本書の後半で見ることができる。 最近関心があることとの関連で言えば、「帰納」というのは論理的に言えば飛躍のある推論方法である訳だが、それが科学の方法として正当化されるのは何故かというとそれはまさにこの世界が帰納がうまくいく世界だからだというのが、人間原理に近いと思った。「帰納を使って科学をやってよさそうな究極の理由は、宇宙のわれわれがいる場所が、帰納が役に立つような場所だからだ。われわれのいる場所が、ありとあらゆるものがもっとカオス的で、最初の状態がちょっと違っただけで、そのあとどうなるかが劇的に違ってしまうような現象に満ちあふれているのだったら、帰納という情報処理をやる生き物は進化してこなかっただろう。(略)それどころか、そんな太陽系では安定した軌道を回る惑星が存在できなくなるから、そもそも科学をやるような知的生命が進化してきたかどうかも分かりませんよね。ということは、わたしたちの科学の方法がうまく当てはまるようになっているということが、同時に科学という営みが生じてくる条件でもあるってことかしら。」(p.266-267)岩井克人の、「貨幣が貨幣なのはそれが貨幣だからだ」ともロジックが似ている? たまに見る論法なので、何か名前が付いていそうな気もする。 Ⅰ 科学哲学をはじめよう—理系と文系をつなぐ視点 1 科学哲学って何?それは何のためにあるの? 2 まずは、科学の方法について考えてみよう 3 ヒュームの呪い—帰納と法則についての悩ましい問題 4 科学的説明って何をすること? Ⅱ 「電子は実在する」って言うのがこんなにも難しいとは—科学的実在論をめぐる果てしなき戦い 5 強敵登場!—反実在論と社会構成主義 6 科学的実在論vs.反実在論 Ⅲ それでも科学は実在を捉えている—世界をまるごと理解するために 7 理論の実在論と対象の実在論を区別しよう 8 そもそも、科学理論って何なのさ 9 自然主義の方へ
Posted by
★図書館だよりNo.67 「一手指南」 紀ノ定保礼 先生(情報デザイン学科)紹介図書 コラムを読む https://www.sist.ac.jp/media/letter_No.67.pdf 【所在・貸出状況を見る】 https://sistlb.sist.ac.jp/op...
★図書館だよりNo.67 「一手指南」 紀ノ定保礼 先生(情報デザイン学科)紹介図書 コラムを読む https://www.sist.ac.jp/media/letter_No.67.pdf 【所在・貸出状況を見る】 https://sistlb.sist.ac.jp/opac/volume/58004
Posted by
この本がどうこうということではないのだが、 科学哲学に限らず哲学全般って、やってる時(考えてる時)はすごく面白いんだけど、結論出した時のがっかり感というか腑抜け感でちょっと虚しくなる。笑あまりに当たり前で常識的な答えが出てくると…。納得できるだけに尚更。 とりあえず今は、科学哲...
この本がどうこうということではないのだが、 科学哲学に限らず哲学全般って、やってる時(考えてる時)はすごく面白いんだけど、結論出した時のがっかり感というか腑抜け感でちょっと虚しくなる。笑あまりに当たり前で常識的な答えが出てくると…。納得できるだけに尚更。 とりあえず今は、科学哲学の存在意義をもっと強く正当化したいな、という気持ち。紹介されてる科学哲学界隈の論争は自分もいっしょに考えてとても面白かった。特に実在論vs反実在論のとことか。でも、、「科学をまるごと理解する」ことの功績をもっと知りたい、強調してほしい、というのは欲張りでしょうか…。利益云々ではなく面白い学問だというのはわかりますがね。 というわけで科学哲学をやる目的ってなんなんだろ、と思ってしまいました。もはや「哲学の哲学」をしたい。 終盤の意味論的捉え方の話がまだよくわかってないから、それがわかれば虚しいだけで終わらなくなるかな? 本としては楽しく読めました。センセイとリカとテツオの軽快なやりとりが好きです。 * 言ってることわかる人はいいね、わかるけど意見ある人、よくわからない人はコメントください。
Posted by
科学哲学の基本的な問題と理論を説明しながら、著者の支持する立場の擁護を目指しています。 基本概念の説明が明晰で、例も分かりやすい。
Posted by
対象や理論の実在性、科学の目的、科学の方法の妥当性、等、ふだん考えることのなかった問題について考えることができた。かなりややこしい問題を順を追って説明しており、なんとか読み進めることができる。演繹と帰納についての議論も勉強になった。
Posted by
科学哲学ってのはなんだろうか?という素朴な疑問への回答とその意義の伝達を試みた一冊。 「帰納法vsヒューム」の辺りはおもしろい。ただ他の箇所は読み飛ばしがちだったので、もうちょっと時間をかけて読むべきだったと反省。 なぜかヒュームへの理解が深まったのでよかった。
Posted by
大変良く出来た『科学哲学』の入門書であった。これを最初 に読めば良かったかな(苦笑)。最終的に、科学哲学に対する 著者自身の考え方が前面に押し出されるのだが、前もって 自ら断りを入れているので問題はない。その誠実な態度と 対話形式という読みやすさも手伝い、とても上質な入門書と い...
大変良く出来た『科学哲学』の入門書であった。これを最初 に読めば良かったかな(苦笑)。最終的に、科学哲学に対する 著者自身の考え方が前面に押し出されるのだが、前もって 自ら断りを入れているので問題はない。その誠実な態度と 対話形式という読みやすさも手伝い、とても上質な入門書と いう印象が強く残った。 科学哲学の難しいところから初めて逆向きに進み、やっと 振り出しに戻った感じ(笑)。ここから再び先へ進もうと思い ます。
Posted by
慣れない用語も多く、行きつ戻りつしながらゆっくりと読んだ。対話調でやさしく書かれてあったので、リカちゃんとテツオくんほど理解が早い生徒にはなれなかったけど、ちゃんと読めば議論を追っていくことはできた。
Posted by