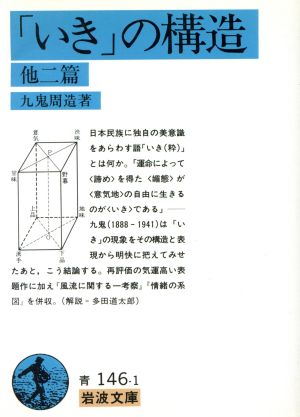「いき」の構造 他二篇 の商品レビュー
二元論をベースに対立項間の緊張関係に注目する思想。おおむね面白かったけど、「自由な芸術的表現」を論じる第4章の論理は強引すぎて引いた。
Posted by
大学の講義(一般教養)中に紹介されたので購入した書物。 当時読了したものでレビューは今しています。 当時は雑誌でいうところのCanCamのえびちゃんなんかが流行っていたりして、今でこそ浅草上野両国好きですが…まだ文章をサラっと撫でたような読み方をしていた。「確かに江戸千代紙は縞...
大学の講義(一般教養)中に紹介されたので購入した書物。 当時読了したものでレビューは今しています。 当時は雑誌でいうところのCanCamのえびちゃんなんかが流行っていたりして、今でこそ浅草上野両国好きですが…まだ文章をサラっと撫でたような読み方をしていた。「確かに江戸千代紙は縞が多くてボーダーはないですね」くらいの感覚でした。 なるほど、いきとは異性への媚態であり、意地と諦めの絶妙なバランス…確かに吉原発祥の「見栄」という言葉もそうですよね。 著者は「いき」という概念は消えつつあると嘆いているものの、最近の流行を見ると、根底には日本人は「『いき』というもの」が好きなんじゃないかな、という気がしますね。 →くだらないと言われそうだけど、最近流行した中村アンちゃんの「無造作ヘア」とか、森エリカさんが雑誌arでよく載っていた「イガリメイク」は異性への媚態がありつつも素っぽく作りこみすぎないことに重点を置いています。 (だからなんだと言われたらそれまでですが)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「いき」という概念を、内在的意味と対外的な区別との観点から論じる。 その枠組みはわかったけど、各論の議論の内容はいまいち理解不十分。 わび・さび・萌えとともに、日本固有の概念なんだろうか。 半分くらいで投げました…。
Posted by
「いき」という日本人(主に江戸時代の江戸の人)独特の感覚についての解説本。著者によると「諦め」と「媚態」と「意気地」である。著者はパリに10年以上滞在しているが、そこで日本人の特徴をアピールするのに「いき」を使ったというのは「いき」である。
Posted by
・九鬼周造は、江戸の美意識であった「粋(いき)」の意味を哲学的に探り、恋愛にある緊張感や儚さ、近松や西鶴の描く、心の交情。その本質的なところに「いき」があると云っています。 「いきの第一の徴表は、相手に対する媚態である。 関係が、いきの原本的存在を形成していることは、い...
・九鬼周造は、江戸の美意識であった「粋(いき)」の意味を哲学的に探り、恋愛にある緊張感や儚さ、近松や西鶴の描く、心の交情。その本質的なところに「いき」があると云っています。 「いきの第一の徴表は、相手に対する媚態である。 関係が、いきの原本的存在を形成していることは、いきごとが、いろごと、を意味するのでも分かる。 媚態の要は、距離を出来得る限り接近せしめつつ、距離の差が、極限に達せざることである。 いきは媚態でありながら、なお相手に対して、一種の反抗を示す強みを持った意識である」 (九鬼周造) まず第一に、「いき」には「媚態」があり、相手を惹き付けようとする色気こそが、いきの大前提なのだそうです。 そして、恋愛には、緊張感が大切で、いざ深い仲になってしまうと、その媚態は消え去り、いきではなくなってしまうのだそうです。 近づきたいから生まれるのが、いき。しかし、近づきすぎてもだめ……。この微妙な距離感でないと、いきにはなりません。そこで、生まれたのが、意気地(いきじ)という反抗的な態度です。たとえば、武士は食わねど高楊枝、宵越しの金は持たぬ、というどこか突き放したやり方も、いきといわれる所以です。 また、運命を受け入れる、諦めの気持ちもいきには必要といいます。 恋愛においては、相手を好きになっても構わないけれど、そのことで束縛や、未練があるなら、それは断つ(諦める)のだそうです。好きだとしても、相手に縛られるということは、「いき」ではなくなってしまう。好きでありながらも、その支配下には入らない、のが良いそうです。 この、媚態、意気地、諦観、の三位一体がいきの定義としていて、成る程と興味深いのですが、ここで、九鬼自身が実例として挙げているのを見ると、いき特有の複雑さが分かります。 (九鬼の女性観に対するいき) 「只、まっすぐ立っているのではなく、 少し姿勢を崩し、姿はほっそり柳腰。丸顔よりも、細面が宜しい。 目は、流し目。過去の憂いを感じさせる光沢。軽やかな諦めと、凛とした張りがあること。 口は、緊張と緩みの絶妙なところが好い。憂いを感じさせて、厚化粧は野暮である。 髪形は、きちっとさせないつぶし島田など、少し崩したものがいきである。 着物は揺れる物で、襟足を見せるように引き下げた抜衣紋(ぬきえもん)が色っぽい。 湯上がりのような上気した肌に浴衣を羽織って解れ髪。こういうのがいきである……」 個人的に思うのは、アメリカなどでは、胸が大きければ大きいほど良いというのがアメリカ人のエロスの考え方ですが、うなじがなんとなく、見えたり見えなかったりするのが色っぽい、エロスだ、というのは、アメリカ人の感覚にはないです。 「いいな」「いきだな」、と思う日本人の振るまい、生き方に蓄積されていったものを知れると同時に、国際的な第三者の考えでいうと、あまり意味のない「一体なにしているんだろう」、とも思ってしまいます。 直接的すぎてはいけないし、直接的じゃなくてもいけない。 かっこいいだけではなくて、けれどかっこ悪くてもいけない。そのあいだの微妙なところを歩いていくのが、「いき」であり、日本人の美徳だと九鬼は述べています。 江戸時代、江戸っ子が蕎麦の汁をちょっとしか浸けないで食べるのは、いきなことだと云われていましたが、それは確かにかっこよくもあり、また変な人だとおかしくもあります。 つまり、江戸時代の人たちのメンタリティは、外からの敵がいない状況のなか、かっこよさとおかしさが、複雑に、そして独特に絡み合い、しかもその絡み合いの概念が、「いき」と人々の間で共有されてしまっていました。それは、異分子(諸外国)から見ると、考えられない光景でした。 九鬼は、いきをさらに明らかにしようと、他のさまざまな言葉と、どんな関係にあるのかを探り続けました。 「この時のいきは何かである」と言わないで、その「何か」というのは、常に他のものとの関係性で、はじめて出てくるいきであり、曖昧なものでも、曖昧なもののまま、追求はできるのだということを、一手に引き受けて論じてくれました。 好む、や好奇心を持つなどの、「好き」は、髪を梳く、紙を漉く、土を鋤く、風がすく、透き通る、ということの「数寄」に由来していますが、この「いき」も、何となく曖昧に揺れ動く「好き」に近いです。 現代のいきは、決して日本人だけのものではなくて、色々なところに伝わって語っていける、いきな、恋心であり、いきな、かっこよさになっていけたらいいなと思いました。
Posted by
「いき」の核にあるのは、見た目でもなく振る舞いでもなく二元性。 江戸のいきな人たちと同じような生活はできないけれど、現代の日本人の中にも「いき」の精神は生き続けることができる いきでありたい
Posted by
『「いき」の構造』 日本文化論として、その枢軸の概念に「いき」を位置づけている。 いきを中心に、差異を作ることで、いきの直方体的構造が現れてきている。 いきの内包的構造としての、三つの契機は、時間論に沿うもの。ここには、ドゥルーズとの近親性があるように思う。時間の三つの総合と、近...
『「いき」の構造』 日本文化論として、その枢軸の概念に「いき」を位置づけている。 いきを中心に、差異を作ることで、いきの直方体的構造が現れてきている。 いきの内包的構造としての、三つの契機は、時間論に沿うもの。ここには、ドゥルーズとの近親性があるように思う。時間の三つの総合と、近しい時間の見方だった。ただ、未来に目的を置くあたりは、カントとの距離の取り方の違いかもしれない。 最後に、いきの概念を単に西洋の文化に適用することはできないとされてるなど、いきの概念が個別的なものにとどまっていることへ注意がされる点は興味深い。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 日本民族に独自の美意識をあらわす語「いき(粋)」とは何か。 「運命によって“諦め”を得た“媚態”が“意気地”の自由に生きるのが“いき”である」―九鬼(1888‐1941)は「いき」の現象をその構造と表現から明快に把えてみせたあと、こう結論する。 再評価の気運高い表題作に加え『風流に関する一考察』『情緒の系図』を併収。 [ 目次 ] 「いき」の構造 風流に関する一考察 情緒の系図 [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by
最初は、そのものすごく論文的な文体に若干の疎ましさと、なんとも、言えない違和感を感じながらの読書だった。 おそらく、自分の中で予想していた、「いき」というものを論じるリズムや語彙、文体とあまりにもかけ離れていたからだと思う。 でも、しばらく読み進むうちに、だんだん、面白くなって...
最初は、そのものすごく論文的な文体に若干の疎ましさと、なんとも、言えない違和感を感じながらの読書だった。 おそらく、自分の中で予想していた、「いき」というものを論じるリズムや語彙、文体とあまりにもかけ離れていたからだと思う。 でも、しばらく読み進むうちに、だんだん、面白くなって来た。 何が面白いかというと、「いき」というある種情緒的な内容を、それとは全く異なるような次元での論調との二元性に可笑しみを感じたのだ。 書いている内容はとてもわかりすく、興味深い。 でも、その語彙や文体が、それを自虐的に妨げる節もある。 と、こうしてレビューを、まとめていて、あることに気づいた。 著者が、あらゆる角度から、「いき」に着いて論じているその要旨を一言で現せば、まさに 「二元性の同居」 なわけである。 なるほど、有る意味、この本も、「いき」なのかもしれない。
Posted by
「いき」とは「媚態」を根本として、それに「意気地」と「諦め」が加わった様子のことをいう。 日本独特の美意識を、哲学の言葉で明快に書き表している。 とはいえ、どんな言葉を使っても、こういう美意識をニュアンスまで完全に言い表すことはできない。このことを筆者自らはっきりと言っていると...
「いき」とは「媚態」を根本として、それに「意気地」と「諦め」が加わった様子のことをいう。 日本独特の美意識を、哲学の言葉で明快に書き表している。 とはいえ、どんな言葉を使っても、こういう美意識をニュアンスまで完全に言い表すことはできない。このことを筆者自らはっきりと言っているところに、九鬼周造の哲学者としての覚悟のようなものが感じられる。 残念ながら現代人の私には、現実で「いき」な人やものに出会う機会がないが、これを読むとなんとなく分かる気がするのは日本人だからなのか。 ただ、本当に「いき」を理解するには、やはり自分には人生経験が全然足りていない。
Posted by