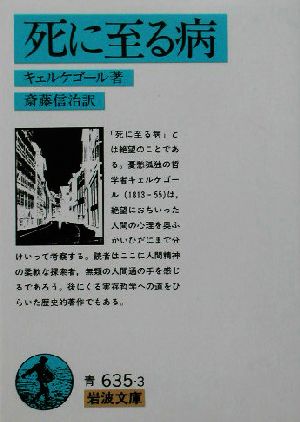死に至る病 の商品レビュー
「死」について、キリ…
「死」について、キリスト教も絡んだ哲学書。難しいですが良書です。
文庫OFF
有神論的実存主義の祖…
有神論的実存主義の祖、キリケゴールの著書。正直に言えば思想も文章も難解です。しかも読むだけではなく実践する事を目的とした書です。困難。
文庫OFF
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
いやあ~これはキリスト教のことを理解していないと、なおさら理解できないですね。 真実のキリスト者として生きることがキェルケゴールの生涯の念願だったそうなので。 というわけで、さーっと流し読みしてしまいました。延々と「絶望」について描かれており、感心するフレーズや持論があっても、その理由を理解するには、私がキリスト教のことが分からないと、ホントに分かったことにはならないと思いましたので、断念しました。
Posted by
2025/03/21 死に至る病とは絶望のことである。 キェルケゴールの言う「絶望」の定義が理解できない。 ここでいう「絶望」とは、自分が求める望みが一切叶わない状態ということで合っているのかな。すみません、よーわからんです。
Posted by
過去課題本。文句なしの名著だが。キリスト教に興味のない人や、キリスト教に悪イメージを持っている人には、無意味な本でもある。
Posted by
実存主義の創設者と言われる哲学者キェルケゴールの主著。 死に至る病とは、要するに絶望(死にたくても死ねない状態)のことで、これを解決するには信仰しかないとのこと。 読み始めて、早速このような難解な書を読むためにはどうすれば良いかという問題に直面したので、無理矢理にでも自分自身...
実存主義の創設者と言われる哲学者キェルケゴールの主著。 死に至る病とは、要するに絶望(死にたくても死ねない状態)のことで、これを解決するには信仰しかないとのこと。 読み始めて、早速このような難解な書を読むためにはどうすれば良いかという問題に直面したので、無理矢理にでも自分自身の問題に置き換えるという方法で読み進めた。 まずは第一編の以下の冒頭は「自己」に別の言葉を入れることで、読者各々の実存(生きるとはどういうことか)を取り出すことが可能だと思った。 「人間とは精神である。精神とは〇〇である。〇〇とは〇〇自身に関係するところの関係である」 (私は〇〇に「運命」や「笑い」を当てはめて読み進めてみた) また、絶望は以下の4パターンに区分されるとのことだが、自身はどれに当てはまるか考えながら読んだ。 ※念のためパターンを記載しますが、これだけでは意味不明。 ①無限性の絶望は有限性の欠乏に存する。 ②有限性の絶望は無限性の欠乏に存する。 ③可能性の絶望は必然性の欠乏に存する。 ④必然性の絶望は可能性の欠乏に存する。 私は③だったが、③は現実を生きておらず夢想ばかりしている人向けである。 夢想している人間が現実に戻ってくる時に現実に必然性を持ち合わせていなければ、生きることができず、また夢想へと向かうのである。 最後に最も重要だと思うことは、本著を書いた当のキェルケゴールが絶望していたということである。 彼の父親は子供達は若くして死ぬと信じており、キェルケゴールに「可愛そうな子よ、お前はやがて絶望のなかに陥る」と言い放ち、幼く柔らかい心に呪いをかけた。 (実際に7人兄弟の5人は早死にし、1人は精神病で入院した、キェルケゴールは街中で倒れ死ぬ) またキェルケゴールは突然に愛していたレギーネとの婚約を破棄し、レギーネは思い留まるように彼に泣きついたが、結果絶縁した。 そして怠慢なデンマーク教会に改革を求め、教会闘争中に道ばたで倒れて42歳で死んだ。 元来の自意識、父親の呪い、愛する人との絶縁、腐敗した教会。彼はこの絶望から救われたのだろうか。幸せだったのであろうか。 少なくとも彼は自殺していない。精神病で寝床に伏してもいない。(それは決して悪いことではないが) 彼は背後に存在する絶望を決して人生に連れて行こうとせずに、むしろ周り右して、信仰とその知性を持ってして絶望に突進しに行った。 その凄まじい程の衝突は意図せず、キリスト教から実存主義を生んだ。(キリストが意図せず、ユダヤ教からキリスト教を生んだように) ここで、ミラン・クンデラの小説「存在の耐えらない軽さ」の言葉を引用したい。 「悲しみは形態であり、幸福は内容であった」 「絶望は形態であり、幸福は内容であった」という現象もあり得るのではないか。そして、その幸福とは「生き抜いた幸せ」ではないだろうか。(キェルケゴールはそれを信仰と呼ぶだろう) 読者の私自身、物心ついた頃から現在に至るまで希死念慮と友達だが、そういう意味ではキェルケゴールは絶望の大先輩である。 しかし、私は知性も信仰もない。 どうすれば良いのだろうか。 ただ、確かに分かっていることは自分より遥かに絶望した人間が、この世界には間違いなく存在したということである。 それが分かっただけでも、だいぶ良い。 ★追記 本書には次のような文章が出てくる。 「罪は無知である。これが周知のようにソクラテス的な定義である。」 無知は罪?ソクラテス、こんなこと言っていたっけ?と調べてみると、案の定キェルケゴールのお手製だった。やってるな、キェルケゴール(笑)
Posted by
なぜそこまでキリスト教を信じ切れるのかが私にはわからないだけに、思索の根幹に疑問を持ってしまう。結局は神を否定したら意味を失うのではないか、と。 後半は神とキリスト者をどれだけ賞賛したいのかという感じだったけど、思慕だったのかな?
Posted by
宗教観を前提にしているところは宗教だなあと思うだけなのだけれど、自身らをまさに擁護するために対比せられる世間や異教徒への眼差しがなんというか思いのほか俗っぽくて、それのほかにもたとえば自己喪失のくだりなんかも書かれていることがあまりにも当たり前で、まあそのあたりはエッセイでも読む...
宗教観を前提にしているところは宗教だなあと思うだけなのだけれど、自身らをまさに擁護するために対比せられる世間や異教徒への眼差しがなんというか思いのほか俗っぽくて、それのほかにもたとえば自己喪失のくだりなんかも書かれていることがあまりにも当たり前で、まあそのあたりはエッセイでも読むような気で読み進めたけれども、第二編にはいっていよいよ宗教色が強くなるとさすがにどうでもよくなってきてしまった。
Posted by
さて、読み終わったが、かなり分からなかった。キリスト教的価値観についてはこれまでかなり勉強してきた筈だったがそれでもこの本には分からない表現が多かったし、哲学書としてはニーチェのツァラトゥストラのように詩的表現をされている訳でもないにも関わらずそれ以上に難解だった。 かろうじて...
さて、読み終わったが、かなり分からなかった。キリスト教的価値観についてはこれまでかなり勉強してきた筈だったがそれでもこの本には分からない表現が多かったし、哲学書としてはニーチェのツァラトゥストラのように詩的表現をされている訳でもないにも関わらずそれ以上に難解だった。 かろうじて私が受け取れた表現で面白かったところをいくつか。 ◎想像力とは無限化するところの反省である→→自己とは反省である→→想像力とは反省であり、即ち自己の再現であり、したがって自己の可能性である。 …想像力(ファンタジー)を巡らせることとはつまり自分について反省することであり、逆説的に自分とは反省によって形成されているという考え。直感的にこれはかなり真理に近づいた考え方に思える。 ◎彼は自己自身であろうと欲しないことを仕事として時間をすごしているのであるが、それでいてその自己自身を愛しているほどに十分に自己なのである。 …これはとてもアイロニックな考え方で好きだ。人は理想の自分を求める故に今の自分ではないものになりたい、変わりたいと欲して生きているが同時にそれは自己愛であり、十分に利己的な考え方なのだ。 ◎何故なら異教徒は自分の自己を神の前にもっていないからである→→異教徒は最厳密な意味では罪を犯したことがないというのもまた真なのである、なぜというに彼は神の前で罪を犯したのではないのであり、そしてあらゆる罪は神の前で起こるものだからである。 …宗教学的にはこの部分が一番興味深かった。ダンテのキリスト教観でいうと異教徒は全員罪人であり決して天国にはいけない。しかし実存主義的キェルケゴールの立場から見た宗教観では、罪という概念そのものが神の前で起こるものであり、(キリスト教的)神の存在しない異教徒にとっては罪という概念そのものがないのである。これはとてもキリスト教主体の考え方で実際には宗教ごとにそれぞれの「罪」が存在するだろう。しかし、罪という概念そのものが何らかの社会的な相対によって生じるもので、本質的に突き詰めてしまうとこの世に存在し得ないのだという考えはザ・実存主義って感じでおもろい。 今回の読書で読み解けなかった部分もいずれ再読して理解を深めてみたい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
むかし読んだ。たぶん。いや、たしかに目は通した。根拠のない甘ったれた希死念慮から逃げきるために藁をもつかむ思いだった。死が答えではない、という事だけは本能的に分かっていたので、いろんな宗教に答えを求めていた時期。仏教に人の致死率は100%だよね、とサクッと言われて「そうだけどさ、ひゃー」という気分で。イスラム教にはあなたの生存率は神のみぞ知るよね、と言われて「そうだけどさ、ひゃー」となって。そしてキリスト教関連(キリスト教では自殺を宗教として禁じてる)の本書、、、ケムに巻かれた(笑)。とりあえずめっちゃ頭の良い過去の哲学者たちがこんなに真剣に考え尽くして資料残しているんだから、バカな自分が何考えてもだから何なのさー、っていう諦めはついた。人には絶対に勧めない本だけど、必要なひとが必要なときに出会ってしまう未来永劫に必要な本だろうと勝手に思う。 ちなみに星2つなのは、自分の苦しみを考えるヒマがあったら生きることを考えよ、苦しんでる誰かを支えることを考えよ、と世界中のヒーローたちが悪と戦っている姿をいつも見せてくれているから、だ。しかし世界中の誰も信じられないとき、(それは自分自身を信じられないのと同義だが)この本に出会えたならば、それはなにか大きな力が投げた最後の蜘蛛の糸だと信じ怯まず掴んでいいと思う。
Posted by