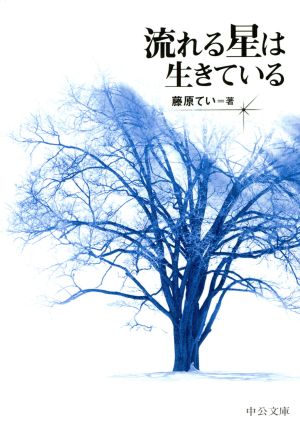流れる星は生きている 改版6版 の商品レビュー
作家新田次郎の妻、数学者藤原正彦の母の藤原ていさん。満洲から幼子3人を連れた脱出行。極限状態での人のエゴと母の本能が素晴らしい筆致で描かれる。昭和史に遺る1冊だろう。 昭和20年8月9日ソ連の突然の参戦。その時満州の新京観象台勤務だった後の作家新田次郎、その妻が本書の筆者。 ...
作家新田次郎の妻、数学者藤原正彦の母の藤原ていさん。満洲から幼子3人を連れた脱出行。極限状態での人のエゴと母の本能が素晴らしい筆致で描かれる。昭和史に遺る1冊だろう。 昭和20年8月9日ソ連の突然の参戦。その時満州の新京観象台勤務だった後の作家新田次郎、その妻が本書の筆者。 子供三人を連れて朝鮮半島を経由し1年以上かけた脱出行。出版当時かなりベストセラーになったらしい。自分の母も当たり前のように読んでいた。 現在の史観的にはそもそも、日本が満州や朝鮮半島に進出したことが問題のように思われるような気もする。だが多少の反発はあるが、決して掌返しをしていない朝鮮半島の人たちについては日本人として記憶した方がいいかも。 既に歴史となりつつあるが、中国残留日本人孤児、藤原家の逃避行のような境遇から、孤児が発生したのだろう。当時多くあった悲劇なのだと思われる。 とにかく「母は強し」というフレーズを想起させる作品。今となってからこそ日本人の記録として貴重であるように思う。
Posted by
終戦時、満州駐在だった夫と三人の子供。敗戦となり、満州から北朝鮮、韓国を通って日本に引き揚げ、故郷へ戻るまでの記録。夫は強制収容所送りとなり、一緒に働いていた日本人からも子供を邪魔者扱いされ、瀕死の状態で逃避行を続ける。食べ物も着るものもなく、雨風を防ぐものもないなか、日本に帰る...
終戦時、満州駐在だった夫と三人の子供。敗戦となり、満州から北朝鮮、韓国を通って日本に引き揚げ、故郷へ戻るまでの記録。夫は強制収容所送りとなり、一緒に働いていた日本人からも子供を邪魔者扱いされ、瀕死の状態で逃避行を続ける。食べ物も着るものもなく、雨風を防ぐものもないなか、日本に帰る一心で歩き続ける。こういったノンフィクションは数多くあるが、今読んで感じるのは、この悲惨な出来事や人の非道な振る舞いと、東日本大震災などの後の整列や譲り合いの心の差。同じように生き死にがかかった状態で、こうも人々の言動が変わるのはなぜか。民度の成熟などでは説明しきれないと感じるし、もしかして極限状態になると、自分も綺麗事では済まされない行動をとるのかと思うと恐ろしい。
Posted by
終戦時満州にいた一家が夫と離れ、母1人、子3人で朝鮮経由で帰国するまでを描く。 想像以上に過酷な生活、そして逃亡時の悲惨な状況。シベリア抑留も大変な惨事だが、その裏でもこのような苦難の歴史があったことを知ることができた。 子持ちに対する世間の冷たい仕打ちは、現代ともそう変わら...
終戦時満州にいた一家が夫と離れ、母1人、子3人で朝鮮経由で帰国するまでを描く。 想像以上に過酷な生活、そして逃亡時の悲惨な状況。シベリア抑留も大変な惨事だが、その裏でもこのような苦難の歴史があったことを知ることができた。 子持ちに対する世間の冷たい仕打ちは、現代ともそう変わらないと感じた。日本国民、特に若い世代は、本書をぜひ読んで欲しいと強く思う。
Posted by
いわた書店一万円選書 満州からの引き揚げ関連作品として2016年本屋大賞第3位の『世界の果てのこどもたち』(中脇初枝)がある。 (自分の中では大賞にイチ押しだったが、大賞は『羊と鋼の森』(宮下奈都)だった) 『世界の果てのこどもたち』と共通するのは最初に守るべきものは子供である...
いわた書店一万円選書 満州からの引き揚げ関連作品として2016年本屋大賞第3位の『世界の果てのこどもたち』(中脇初枝)がある。 (自分の中では大賞にイチ押しだったが、大賞は『羊と鋼の森』(宮下奈都)だった) 『世界の果てのこどもたち』と共通するのは最初に守るべきものは子供であるということ。 母と子3人の引き揚げの様子が手記のような形で進行していく。平壌までの母親はまるで良いところのお嬢様のようで読んでいて歯痒かったが後半は生死の瀬戸際に母親としての強さが前面に出てくる。 長男の振る舞いに心打たれた。
Posted by
涙が止まらない場面が幾つもあった。自分の姿を鏡で見た場面からは、涙で文字が読めなかった。 強い母の姿がここにある。
Posted by
息を詰めて読んだ。呼吸が浅くなった。 まず読み始めてすぐに脱出開始の場面。子ども3人(6歳、3歳、1ヶ月)連れて新京から脱出するというので、絶対この子どもたち死んでしまうよ・・・と胸が苦しくなったので、あわてて藤原ていさんをググったら真ん中の3歳の子と一番下の女の子(逃げ始めは1...
息を詰めて読んだ。呼吸が浅くなった。 まず読み始めてすぐに脱出開始の場面。子ども3人(6歳、3歳、1ヶ月)連れて新京から脱出するというので、絶対この子どもたち死んでしまうよ・・・と胸が苦しくなったので、あわてて藤原ていさんをググったら真ん中の3歳の子と一番下の女の子(逃げ始めは1ヶ月の赤ちゃん)は大人になるまで育っていることがチラチラと確認できたので(しかも次男は藤原正彦さん!)、とりあえず一安心して、やっと読み進めることができた。 戦争物は胸が潰れる思いだけど、知っておくべきだし読んだほうがいいと思っているが、今回の出だしはその思いをひっくり返して、絶対つらいことが書いてあるんだから読み進めるのやめようかくらいのインパクトだった。 読み進んでいくと、文章が平易で使っている言葉も昔っぽくないことに驚いた。さらに藤原ていさんの芯の強いところや、女性だからといって黙っていただけの時代じゃなくて、ちゃんと言いたいことは言えるような世の中だった(それが戦後の混乱で、主張しなければやっていけなかったという特殊事情なのかもしれないが)んだなというのがわかった。男の人がほとんどいない状況だったからかもしれないが。。 でもこんな混乱して食べ物もない、寒いっていうところで子どもたちを守らなくちゃいけないのは、なんという悲劇だろうと思う。夜中、雨の降っている中、子どもに歩け、歩かないと死ぬぞ!と叱り飛ばしながら歩かせて、子どもは靴も脱げてしまって裸足で一晩歩いて!そんなの考えられない。そして、きているものも脱げて濡れて寒くて紫色になって死にそうになってしまって・・・なんて本当に悲劇だ。私がその場にいたら、子どもたちを守ってあげられただろうか。死ぬまで歩かせられるだろうか。どうせどこかで死んでしまうんならばいっそ一思いに(というのは藤原ていさんも本文中で度々考えていたようだが)、本当に私は子どもと一緒にさっさと死んでしまうことを選んだかもしれない。裸足で山道を歩き足の皮は破れて小石が入って膿む。川を、子どもを引きずりながら渡り、自分も限界なので、子どもを水につけると浮力で軽くなるので、たまに子どもを水につけながら進む。怯えてしがみついて泣く子に、泣くと死ぬぞ!と脅しながら渡っていく。こんなことができるだろうか。 この本は、子どもたちへの遺書として書いたので、もっとえげつないことは書けなかったそうだ。それがどうも、「旅路」という本に藤原ていさんは書いたらしい。目を背けたくなるような話かもしれないけど、読もう(もう少し時間を開けよう)。そして、この、流れる星は生きているは、子どもたちにもいつか読んでもらおう。ずっと先になると思うけど。
Posted by
このレポが恐らく私のラストレポでしょう。 手元にある未読の本などの順番から最後に残しておきました。 作者である藤原ていさんは作家の新田次郎さんの妻です。 この作品は、藤原ていさんが、1945-46年にかけて、 子供3人をつれて敗戦直後の満州から引き揚げたときの実話です。 てい...
このレポが恐らく私のラストレポでしょう。 手元にある未読の本などの順番から最後に残しておきました。 作者である藤原ていさんは作家の新田次郎さんの妻です。 この作品は、藤原ていさんが、1945-46年にかけて、 子供3人をつれて敗戦直後の満州から引き揚げたときの実話です。 ていさんの夫・新田次郎氏は新京の観象台(気象台)に務めていました。 1945年(昭和20年)8月9日の夜、ていさんは、 観象台から帰って来た夫からすぐに移動を始めるように言われます。 その時、子供たちは 長男の正広さんは6歳、次男の正彦さんは3歳、 長女の咲子さんは生後1か月でした。 ていさんらを含む観象台の家族たちは「観象台疎開団」と自らを名づけ、 集団行動を取りながら日本をめざしました。 満州に近い北朝鮮北部の学校校舎に収容されたとき、 8月15日の終戦を迎えます。 ていさんの夫を含む18歳から40歳までの日本人男子が 汽車で平壌へ送られることになり、夫と離れ離れになりました。 男たちがいない疎開団での生活は、悲惨なもの。 少しでも早く日本へ引き上げようとする人たちもあらわれ、 各疎開団が浮き足立ちました。 ていさんも、やむにやまれず、 3人の幼子を連れて平壌へ向かう汽車に乗りました。 平壌に着き、そこからまた、貨車で新幕まで移動。 貨車を降りると、夜中でしたが、 危険があるため明かりをつけることもできずに歩き始め、 苦難の旅が始まったのです。 やっとの思いで引き揚げ船に乗って故郷に辿り着いたとき、 ていさんは「もう死んでもいい」とつぶやいた、と書いてありました。 いかにそれまでの道のりが大変だったのかわかります。 大陸からの引き揚げの旅は、 自分ひとりでも逃げるのは大変だったと思われます。 命がかかっていますから、自分勝手にならざるを得ない過酷な境遇の中、 3人の子供を抱えて、よくぞ生き延びた!と思わずにいられません。 「母は強し」といいますが、それ以前に 「生きなきゃ」という強い信念がないと出来ないことでしょう。 悲惨な戦争は軍人ばかりか、 生きている普通の人々までも巻き込んでしまいます。 戦争をすると、いったい誰が得をするというのでしょう。 ボロボロになっても生きて故郷へ帰ること。 これこそが、真の勇気ある者であり、 戦争への精一杯の抵抗の姿だと思いました。 苦難も辛抱強く乗り越える精神的な強さが 日本人として誇りを持ってもいいことなのでしょう。 生きるためにエゴになりがちですが、 子供たちを守りながら生きて故郷へ帰りついたていさん。 日本人の真の強さを持った方だと感心しました。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ※ 私のラストレポ…。自分で書いて切なくなりました。 これまでレポを書いたこともなく、ただ本を読んだだけで終わっていた私に、感想を書いて読んでもらうという楽しみを教えてくれたのは、ブクレポさんであり、会員の皆様でした。 稚拙な文章を読んでコメントを書いてくださり「あり」までも。他の方のレポで、さまざまな分野の本を知ることもでき、本当に楽しかったです。心から感謝いたします。ありがとうございました。 レポはほそぼそと書いていくつもりですがブクレポのことは忘れません。 ブクレポ! 最高!
Posted by
壮絶。このような苦労をして中国から引き揚げて来たのか。 その過程で、中国残留日本人孤児が誕生した。
Posted by
ちょっと前に「若き数学者のアメリカ」をタイトル買いしたらおもしろくて藤原正彦の本をいろいろ読んでたらこの本の存在を知って、これは読まねば、と。 当時、こういう体験をした人はたくさんいたんだろうけど、文章力がある人がしっかり書いて残してくれてよかった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この時計を1000円で買い取ります。 流星とエネルギー不滅の法則 発疹チフス ジフテリアと血清 愛の確定因子 親子にない場合もある 後発的にもある 今の生活は少しでも虚栄やうぬぼれがあればおしまいになってしまう。 下痢は栄養失調の第二期 女にとって汚いと言われることほど悲しいことはない
Posted by