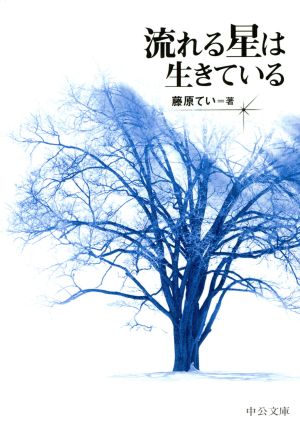流れる星は生きている 改版6版 の商品レビュー
戦争の引き揚げの話をここまでリアルに知れたのは初めて。母親はこんなに強いものなのか。日本人同士、時にお互いに協力したり、裏切ったり、利用したり、されたりと生々しい。藤原ていの別の作品自身の半世紀が書かれている、旅路も読みたいと思う。人はこれだけの経験をした後ど何を思い考え暮らして...
戦争の引き揚げの話をここまでリアルに知れたのは初めて。母親はこんなに強いものなのか。日本人同士、時にお互いに協力したり、裏切ったり、利用したり、されたりと生々しい。藤原ていの別の作品自身の半世紀が書かれている、旅路も読みたいと思う。人はこれだけの経験をした後ど何を思い考え暮らしていったのか想像も出来ない。
Posted by
昭和20年8月9日、ソ連参戦の夜。新京(長春)で夫(藤原寛人33歳)と引き裂かれた妻(藤原てい27歳)が、愛児三人(正弘6歳・正彦3歳・咲子1ヶ月)を引き連れ、敗戦下の満州からの引き揚げを綴った壮絶かつ慟哭の記録です。母子四人が帰国(21年9月)から三ヵ月後、著者の夫(筆名:新田...
昭和20年8月9日、ソ連参戦の夜。新京(長春)で夫(藤原寛人33歳)と引き裂かれた妻(藤原てい27歳)が、愛児三人(正弘6歳・正彦3歳・咲子1ヶ月)を引き連れ、敗戦下の満州からの引き揚げを綴った壮絶かつ慟哭の記録です。母子四人が帰国(21年9月)から三ヵ月後、著者の夫(筆名:新田次郎)はシベリア抑留から解放され帰還、親子の再会が叶いました。艱難辛苦に耐え、幼い子どもたちの成長を見守り続けた母・藤原てい(1918-2016)さんの生涯に敬服し、戦争がもたらす罪過を語り継ぐべしの思いを新たにしました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
藤原ていさんは新田次郎さんの妻であり、数学者の藤原正彦さんのお母さんですね。 終戦の時、夫はシベリアへ送られ、ていさんは幼い子ども3人を抱え、満州から引き揚げてきた。 その時の壮絶な体験をつづったのが本書。 満州から鉄道で朝鮮半島を南下し、38度線を越えるときには何日も、いくつもの山を越えて歩き続けた。 7歳の長男は全てを我慢して自分で歩くしかなかった。 ていさんは二男の手をひき、1歳にもならない娘を背中にくくりつけ、裸足で歩いた。 日本人は日本人同士、助け合ってはいるが、皆それぞれに自分と自分の家族を守るだけで精いっぱい。 時に裏切り、出しぬき、自分以外の人を見殺しにして日本を目指す。 ていさんも何度も裏切られ、悔し涙を流す。 でも時には、同じ日本人に、そして朝鮮人に助けられ、危機を脱する。 そこには人種の壁などはなく、日本人でも意地悪い人は意地悪いし、親切な人は親切だ。 朝鮮人でも意地悪い人は意地悪く、親切な人は親切だが、命からがら引き揚げていく日本人に対して皆同情の目を向ける。 日本人が物乞いにいくと、皆日本語で受け答え、仕事を与えたり、食料を分けたりする。 ていさん自身も、決してきれいごとでは生きていない。 人と衝突し、恨み事を言い、時には騙し、子どもを守る。 文字通り命がけで子どもを守り抜いた、母の強さを感じる。 故郷へ辿り着く場面には涙があふれます。 母親がどのようにして自分たちを守り、生き抜いてきたかをこのような1冊の本として手に取ることができる息子や娘はどんな気持ちだろう。 ありきたりな感想だけど、今、こんなにも豊かで何不自由ない日本で暮らしながら、政治に対する不平不満ばかりが聞かれる状況は間違っていると思った。 我々は当り前に当たり前のことができていることに感謝しなければならないと思う。 何もかもに批判的な報道しかしないマスコミも問題があると思う。もちろん批判は大事だが・・・、それだけではなく、何かもっと・・・。
Posted by
☑︎どうせ死ぬにしても故郷へ一歩でも近づいて死にたい。 ☑︎パンモグラ、パンモグラ ☑︎日本へ上陸して、無事に故郷に着くまで、否、それからも子持ちという理由で人に嫌われるのかと思うとぞっとした。
Posted by
感動というか、やはりそうなんだ、大変だったんだという気持ち。 ノンフィクションの重要性。こういう記録が大事。 これでも国家公務員の家族だから、一般人よりは恵まれたかたちで引き揚げたのではないかという気がする。 むきだしの自己のぶつかりあい。「個人主義」というのは「利己的」...
感動というか、やはりそうなんだ、大変だったんだという気持ち。 ノンフィクションの重要性。こういう記録が大事。 これでも国家公務員の家族だから、一般人よりは恵まれたかたちで引き揚げたのではないかという気がする。 むきだしの自己のぶつかりあい。「個人主義」というのは「利己的」という意味で使われている。 藤原正彦は当時2歳で、こんな目にあいながら引き揚げてきたのだ。
Posted by
終盤涙が出そうになった。強い意志から生まれる異常なほどの行動力。お母さんってすごいな。忘れてはいけない、知っておきたい日本の過去の出来事。
Posted by
NHKラジオ「高橋源一郎の飛ぶ教室」の終戦特集で「引き揚げ」をテーマにこの本が取り上げられていたのに触発され十数年ぶりに再読。 敗戦を機に夫と離れ満州から女手一つで三人の幼子を連れて日本に帰還するまでの壮絶な「引き揚げ」の記録。 幼子の手を引いた母親が鬼のような形相で死戦を超...
NHKラジオ「高橋源一郎の飛ぶ教室」の終戦特集で「引き揚げ」をテーマにこの本が取り上げられていたのに触発され十数年ぶりに再読。 敗戦を機に夫と離れ満州から女手一つで三人の幼子を連れて日本に帰還するまでの壮絶な「引き揚げ」の記録。 幼子の手を引いた母親が鬼のような形相で死戦を超えていく絵柄のみが十数年前に読んだ記憶として残っていたが、実際は満州の新京からいったん北朝鮮の宣川に逃れ、ここで1年近くも待機を余儀なくされており、ここでの共同生活にまつわる日々のエピソードがこの小説の過半を占めていたんだと再認識。 私の記憶にあった三十八度線を超えるまでの壮絶な脱出行は後半の三分の一ほどだったが、あたかも天上の蓮池から垂らされた一本の蜘蛛の糸にすがって地獄から這い上がろうとする人(鬼)の群れを想起するほど凄まじい印象を再び残した。 この小説は大きく捉えれば、満州という多国籍の人種から成っていた国が滅びて、そこで暮らしていた日本民族が生き残るために集団で祖国を目指した言わば亡国の民の脱出物語りであるが、そこで詳細に描かれるのは、大きな歴史の荒波に翻弄されながらも、祖国を目指して一日一日を必死に生き抜いた市井の人々の人間ドラマである。 我が国の首相は今年の全国戦没者追悼式典で「今日、私たちが享受している平和と繁栄は、戦没者の皆様の尊い犠牲の上に築かれたもの。。。」と例年どおりの式辞を残しているが、この言葉からいつも空疎な印象を受けるのは、この小説に登場するような過酷な体験を乗り越えて生きて祖国に戻り、戦後復興に尽くした多くの市井の人々 (引揚者)に対する想像力が働いていないからではないか、そんなことを痛切に感じました。
Posted by
戦争がいかにむごいか、悲惨かが分かります。想像力を膨らませすぎると辛すぎるほどです。ただ、戦争の中でも人間の気高きさ、強さがあります。それと同じくらい人間の醜さ、妬みもあります。戦争は心と戦いもあります。ユネスコ憲章に「戦争は心で起きるものだから、心に平和の砦を築かなければならな...
戦争がいかにむごいか、悲惨かが分かります。想像力を膨らませすぎると辛すぎるほどです。ただ、戦争の中でも人間の気高きさ、強さがあります。それと同じくらい人間の醜さ、妬みもあります。戦争は心と戦いもあります。ユネスコ憲章に「戦争は心で起きるものだから、心に平和の砦を築かなければならない」と書いています。
Posted by
2020.4.2 壮絶。追い込まれると人の本性って出てくるんだな。そんな人達も家族や団を守るために純粋に努力してるだけだったりして単純に悪とは思えないし。 自分も守るものがあれば他人を攻撃してでも生きようとするのだろう。 山越えする主人公の変貌ぶりがすごくて、ギリギリ感がよく伝わ...
2020.4.2 壮絶。追い込まれると人の本性って出てくるんだな。そんな人達も家族や団を守るために純粋に努力してるだけだったりして単純に悪とは思えないし。 自分も守るものがあれば他人を攻撃してでも生きようとするのだろう。 山越えする主人公の変貌ぶりがすごくて、ギリギリ感がよく伝わり、母親の強さに感動しました。 この状況で子供三人を守り抜いた藤原ていさんは凄すぎる。 戦争ダメ絶対。
Posted by
中国に取り残された家族の日本になんとか帰国する話。 壮絶な話を詳細に、眼前に情景が浮かぶような話だった。 本人たちのその時の辛さや思い出して言葉に紡いでいくのは、さぞ辛いことだと思う。 ずしんと響く一冊
Posted by